下のような図を描いてみました。
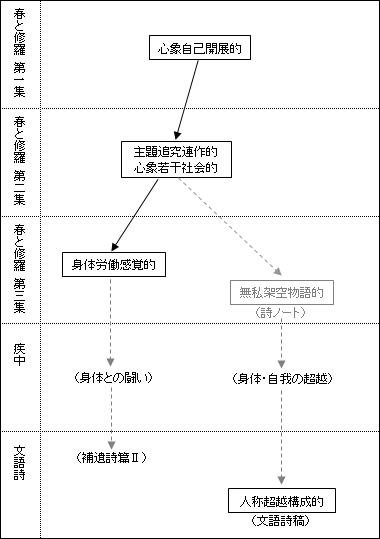
以下では、賢治の詩の推移を私なりに振りかえりながら、この図の説明をしてみます。
1.『第一集』
『春と修羅』は、その「序」に書かれているように、「物質」や「実在」や「本体論」などはただ「こゝろの風物」にすぎず、(一般にはそれらに由来すると思われている)「心象」の「けしき」こそを大切にして、忠実にありのままに「記録」することを、創作上の方法論として生み出されています。これがそもそも、「心象スケッチ」という呼称の意味なのでしょう。
賢治のこのような考え方は、すべての「存在」は仮象であるという仏教的な世界観や、「純粋経験」を基盤としたウィリアム・ジェイムズの哲学の影響も受けていると思われますが、その萌芽は、「心象スケッチ」の誕生よりもっと早い時期にさかのぼることもできます。
高等農林学校時代の、断章群のような短篇「復活の前」において、賢治は「総てはわれに在るがごとくに開展して来る。見事にも見事にも開展してくる。土性調査、兵役、炭焼、しろい空等」と書き、1918年2月の政次郎あて書簡[46]には、「戦争とか病気とか学校も家も山も雪もみな均しき一心の現象に御座候。」と書いています。
すべては、「一心の現象」=心象だというのです。
『春と修羅』の諸作品は、奔流のようにあふれ出てくる、そのような賢治の「心象」の稀有な記録であり、その詩句は、まさに「総てはわれに在るがごとくに開展」してきます。それらは、ある時は天高く駆けある時は地を這い、またしばしば複数の層をなし、常人にとってはその跡を追っていくだけでもやっとのことです。この詩人には「身体」など存在せず、「精神」に翼がついているだけなのではないか、などという気もしてきます。
実際、『第一集』の「序」には、「わたくしといふ現象」について、「ひかりはたもち、その電燈は失はれ」と記されていて、これを書いた人が、電燈――すなわち物質的基盤としての身体――を欠いて、ただ厖大な心象の集合体として明滅しているというような様子まで、目に浮かんできます。
このように、「心象」それ自体が何ものにも束縛されず、どんどんと展開していくのが『第一集』の諸作品の、独特で、天才的で、また難解なところと関係しているわけで、これはまさに「主観的」な叙述の極致とも言えます。
ここではひとまずこのような特徴を、「復活の前」に出てきた言葉を借りて、上図のように「心象自己開展的」と呼んでおくことにします。
2.『第二集』
「春と修羅 第二集」も、基本的には『第一集』と同様の方法によって書きつづけられていった作品群ですが、しかし『第一集』と比べると、若干の違いが表れてきているのも事実です。
一つは、天沢退二郎氏も指摘しているように、『第二集』の世界には「連作詩群」と言うべきものがかなり見られるようになり、それぞれの詩群ごとに何らかのテーマが多面的に追究されるようになっていることです。例えば、「≪五輪峠≫詩群では認識論・物質論の問題が、≪外山詩群≫では欲望の超克の問題が、≪業の花びら≫詩群では信仰の暗たんとした未来が、≪旅程幻想≫詩群では重層する≪旅≫のさなかに宙吊りにされた詩人の不安の根源が、それぞれに、複数のテクストのそれぞれの複数性の織物が織られてゆく過程で追求されている」(天沢退二郎「≪宮澤賢治≫作品史の試み」,『≪宮澤賢治≫鑑』所収)のです。
いま一つ、『第一集』から『第二集』に至る変化を挙げるとすれば、作者は作品中に登場するさまざまな「他者」と現実的な関わりを持つようになり、徐々に社会的な視点を持つようになっていったことです。中村稔氏は、「第二集の時期において宮沢賢治が自覚したものは、社会的存在としての自己であり、彼が獲得したものは、外界に対する客観的な眼であった。」(『宮沢賢治ふたたび』)と書いています。
『第二集』の中でも後期に属する「渇水と座禅」において、賢治は農業実習担当教官として、切実な感情移入を持って渇水に悩む農民を描いており、これは『第一集』において、「ことなくひとのかたちのもの」をとる農夫に、「ほんたうにおれが見えるのか」と、思いを投げつける態度(「春と修羅」)とは、大きく異なっています。
しかしその「渇水と座禅」においてさえ、賢治は農民を「外から見る」という立ち位置にいるわけで、それは次の『第三集』の世界とは、まだ大きな違いがあります。
3.『第三集』
『第一集』→『第二集』の変化よりも、『第二集』→『第三集』の変化は、段違いに大きい感があります。これはもちろん、賢治が農学校教師を辞めて、「羅須地人協会」を名乗り、独居自炊生活を始めたという生活の激変によるところが大きいでしょう。大半の作品は、農作業と並行して書かれるようになります。
この『第三集』の評価としては、「より現実生活に根ざした詩」として肯定的にとらえる向きもなくはありませんが、「「第一集」「第二集」に比べたら詩的燃焼力はいかんともしがたく落ちている。あれだけ自在だった翼は、もう傷だらけである。」(佐藤通雅「<農民>と<百姓>の狭間」)というコメントに見るように、「詩」としての力は全体的に落ちていると見なす人の方が多いようです。天沢退二郎氏は、「この詩集をつらぬく自己追放と自己消去、地べたにより近いところに自分の視点を置いて、労働と連帯の詩句をつらねながら、自らはいよいよ孤独に、あたかも死を先取りした死者のいっときのまぼろしのように≪みんな≫の中へ自らを消去して行く。」と書いています(前掲書)。
しかし私としては、『第三集』の注目すべき独自の特徴としては、賢治が農業労働を通して、自らの「身体」と出会っていったということがあると思います。
その好例はたとえば、「水汲み」という作品です。これは、砂地の畑に何度も何度も水を汲んでかけるという労働行為を題材としていて、その実体である「……水を汲んで砂へかけて……」というリフレインに挟まれた本文では、周囲の情景や自身の身体感覚が描写されます。その描写は順に一行ずつ減っていき、景色も近景から遠景へと移っていくという構造になっていき、最後のリフレインは、「……水を汲んで水を汲んで……」という単純な反復に変わります。
この作品を読んだ時に感じられるのは、単調な反復作業の持つ独特の麻痺的な感覚、それとともに身体が覚える疲労、そしてその疲労とともにあたかも何かが「浄化」されていくような印象です。木嶋孝法氏は『宮沢賢治論』において、この作品について、「もしかすると、労働の苦痛であるとか、逆に愉悦であるとかを伝えようとしているのではないか」と指摘して、「まさに≪芸術をもてあの灰色の労働を燃せ≫(「農民芸術論」ノート)なのである。」と書いていますが、その通りだと思います。
『第三集』において、同様に労働を通じた身体感覚を描いている作品としては、「井戸」、「疲労」、「休息」、「〔青いけむりで唐黍を焼き〕」、「圃道」、「開墾」、「燕麦播き」などが挙げられます。
前述のように、『第一集』の頃には、「身体」を欠いた「透明な幽霊の複合体」のようであった詩人は、ここにおいて自らの「身体性」を再確認するのです。それは、フッサールに始まった「現象学」が、メルロ=ポンティにおいて「身体」を発見したという経過を見るようでもあります。
ところで、このように「身体を取り戻す」ということは、同時にまた「身体に束縛される」ということでもあります。賢治はこの時期に、一人の農民としての自分の能力の限界を思い知らされるとともに、「科学や芸術によって農民の生活を改善する」という構想も、現実的には困難であることを、骨身に感じます。
詩作品が、身体や現実によって拘束されていくとともに、一方でこの時期には、『第一集』にも『第二集』にも見られなかったような、「おとぎ話」のような「説話」のような詩が現れてくるのも、一つの特徴です。入沢康夫氏が、ちくま文庫版全集の解説において「フィクショナル」あるいは「ロマネスク」と呼んでいる作品群がそれで、天沢退二郎氏は、「『詩ノート』の中にいくつも見られる物語的な詩はその(自己消去の―引用者註)あらわれであろう」(前掲書)と触れています。
具体的には、「〔わたくしどもは〕」、「ローマンス」、「〔桃いろの〕」などがその群に属しますし、「基督再臨」も含めてよいかもしれません。また、「〔古びた水いろの薄明穹のなかに〕」は、その説話的な形態から、この群に含めるべき作品と思いますが、その内容には、賢治自身がおそらく1920年頃に友人の阿部孝と西公園を散策した時の記憶(短篇「ラジウムの雁」にも作品化)が部分的に織り込まれています。
天沢氏が「自己消去」と関連づけているように、これらの作品群は、たとえ一人称で語られていても、基本的には作者自身とは切り離された「フィクション」の様相を呈しているのですが、「〔古びた水いろの…〕」のように、どこかで作者の現実体験が素材となっている場合もあるようです。
これらの「架空物語的」な作品群は、労働をする「わたくし」に根ざした作品群とはまさに対極にあるものですが、この時期の賢治が身体とともに現実に縛られつつ詩を書く過程において、彼の心に本質的に備わるファンタジー性が、どうしても生み出さざるをえなかったものなのかもしれません。
これらの作品は、いずれも「春と修羅 第三集」に採用されずに「詩ノート」の段階にとどまっており、この時期の賢治にとっては、地下の伏流にすぎなかったのかとも思われます。しかし私としては、ここに現れている、しだいに「私性」を離れ、「主観」よりも「客観」的な語り口になっていく傾向は、その後の賢治の作品の変化の先駆けではないかとも思っています。
4.「疾中」
現在、「疾中」として分類されている作品が書かれたのは、おおむね賢治が1928年8月に結核に倒れてから、1930年にいったん回復するまでの、第一回目の療養期間の病臥期です(「結核療養期間」参照)。
『第三集』の時期に、「身体性」の新たな自覚に至った賢治でしたが、今度は他ならぬその「身体」が、結核という深刻な病魔によって侵されるという悲劇に見舞われたのです。
そこでこの時期の作品を、やはり「自己の身体に対する態度」という視点で見てみると、あくまで病を負った自らの身体を引き受けつつ、作者が身体的苦痛と闘う有り様を描いた作品と、逆に、そのような身体を超越した立場から、何かを書きとめた作品とに分けてみることができます。
前者の方が、数としては多く存在しますが、「〔丁丁丁丁丁〕」、「病」、「〔こんなにも切なく〕」、「病中」などは、その代表的なものでしょう。
一方、身体などというものを超越した視点を感じさせる作品としては、「たけにぐさに風が吹いてゐるといふことである…」で始まる「病床」、「〔美しき夕陽の色なして〕」などがそうですし、有名な「眼にて云ふ」も、自らの病状にも触れてはいますが、そのような身体を超えたところから、彼は客観的に世界を見ています。
このような二つの系列は、「身体」という観点から見れば、『第三集』の時代に枝分かれした二つの流れの、だいたいの延長線上に置くことができるのではないかと思われたので、上図のように表しました。
5.文語詩
「疾中」の時代、すなわち第一回目の療養期間が終わると、ふたたび屋外で活動できるようになった賢治は、1931年1月から「東北砕石工場」の技師として働きはじめます。この時期から、同年9月にまた結核が悪化して倒れてしまい、第二回目の療養期間を経て、1933年9月の死に至るまでの間に、彼は厖大な文語詩を創作し推敲を重ねていきます。もちろん、この時期にも並行して、以前の口語詩の推敲は行われていたのですが、新たな詩作は文語詩に限られていて、詩の分野の活動の重心が文語詩に置かれていたのは事実でしょう。
そのような賢治の文語詩の中心をなすのは、「文語詩稿 五十篇」「文語詩稿 一百篇」「文語詩未定稿」と呼ばれる、一連の作品群です。
これら「文語詩稿」をどう見るかということについては様々な議論があり、「病床の手すさみ」(中村稔)という評価がある一方で、「彼の最高の併も最も彼の独自性の現はれた作品」(吉本隆明)という見解もありました。
意味を理解するのが困難なほどまで凝縮され、観照的な態度で叙事に徹したその独特な作品群の本質を、最も適確に衝いていると私が思うのは、小沢俊郎氏の次の言葉です(小沢俊郎「「疾中」と<文語詩>」)。
結論をいってしまえば、詠嘆や抒情とは反対の方向へ<文語詩>は進んでいったのだ。虚構も自在に用いて、現実世界とは別の世界を構想する方向へ、即物的具体的叙事的な表現によって迫ろうとした。
「文語詩稿」の作品群は、彼の若い頃の作品や、自らの人生における現実の体験を土台にしているものがほとんどであるため、「自分史の試み」と評される場合もありますが、推敲の途中では人称を入れ替えたり、素材を様々に変化させることによって、結局は賢治という一個人の体験としての「私性」は消去され、非常に客観的な印象のある構築物として造形されます。
ここで思い起こされるのは、「詩ノート」の「〔古びた水いろの薄明穹のなかに〕」においても、作者自らの体験を素材としながら、それをあたかもフィクションのように加工するという方法がとられていたことです。詩の形式としてはまったく異なるものの、創作の方法としては、ここには後の「文語詩稿」の諸作品に通ずるものがあったとも言えるのではないでしょうか。
『春と修羅』が、独我論と紙一重の「主観性の極致」から出発したことを思えば、「文語詩稿」は、その対極である「客観性の極致」を目ざしていたと考えてみることもできます。
あと、全集において「補遺詩篇 II 」として分類されている作品の中には、東北砕石工場技師時代に、賢治が営業活動のかたわら自由な文語詩の形式で手帳に書きつけたものが、一部含まれています。たとえば、「〔雲影滑れる山のこなた〕」や「〔朝は北海道の拓殖博覧会へ送るとて〕」などがそれで、口語と文語の違いはあるものの、これらは「春と修羅 第三集」の系列を引きつぐものと思われます。しかしこの系列も、賢治が二度目に病床に臥したことによって、途絶えてしまいました。
結局、私性や主観性や身体性に基礎を置いた作品はこれ以後新たには作られなくなり、反対に、自我や身体を超越して、不思議な客観性を帯びた作品が、晩年の「文語詩稿」の中心となります。
なぜそうなったのかということは、とりあえず私にはわかりません。それが詩人としての賢治の本質的・内在的な変化だったのかもしれませんが、病気によって「身体」を損なってしまったという現実が、賢治を否応なくその方向へと向かわせた面があったのかもしれません。
最後に、賢治の詩作品が、途中から「日付」や「作品番号」を喪失していったということについて、少し考えておきたいと思います。
『春と修羅』の各作品には、「作品番号」は付けられていないものの、最初のスケッチが行われたと思われる「日付」がすべてに付いています。『第二集』と『第三集』の作品は、原則的に「作品番号」と「日付」の両方を持っているのですが、推敲されるうちに、それらを喪失する場合もあります(それぞれの「集」の「補遺」の作品群)。また『第三集』と並行して、詩稿用紙に書かれた段階から、すでに「日付」も「作品番号」も伴っていない作品も出現してきます(「口語詩稿」)。
「疾中」やその後の文語詩は、基本的にはもはや「日付」も「作品番号」も伴っていません。
今回振りかえってみたように、賢治の詩作品は、強い「主観性」「私性」から出発しながらも、ある時期からはその対極である「客観性」「普遍性」を志向するようになったと、言うことができます。
ここで、作品に付けられる「日付」や「作品番号」というものは、まさに個人的な「私性」の表徴と言えるものですから、作品の性質が上述のように変化していったとすれば、「日付」や「作品番号」が不要になるのも、当然なのかもしれません。
「いつのことだったのか」「誰が書いたのか」ということなど超越した、それこそ「説話」のように普遍的で、なおかつ美しい構築物を作ることを、最終的に賢治は目ざしていたのかもしれません。
つめくさ
連休も後半ですが、いかがお過ごしですか。
賢治詩の変容過程について明快なご説明をいただきました。なるほど、文語詩の「無視架空物語的」な世界が、ご説明のような一定の潜伏期を経て一挙に開花した、という見方はとてもクリアです。
タイトル・バックも「変容」したのですね。旅情に誘われます。
私はこの季節、毎年のように、♪「緑の町に舞い降りて」を聴きながら(連休どこへやら)オフィスに出かける日々です。桜はいよいよ来週開花のようです。
hamagaki
つめくさ様、いつもお読みいただいてありがとうございます。
「緑の街に舞い降りて」・・・。 飛行機が花巻空港に着陸するところから始まる歌は、まさに旅情を誘いますね。また、「MORIOKA というその響きが ロシア語みたいだった」という感性は、なんか賢治に通じるところがあるように思えて・・・。
じつは私は、明日と明後日だけですが、ちょっと苫小牧→小樽あたりにうかがう予定です。
連休というのにお忙しそうで、一方こちらは旅の空で、恐縮です。
どうかお身体を大切にして下さい。
またお会いできる日を楽しみにしています。