「空明と傷痍」は、「春と修羅 第二集」の冒頭を飾る作品です。
二
空明と傷痍
一九二四、二、二〇、顥気の海の青びかりする底に立ち
いかにもさういふ敬虔な風に
一きれ白い紙巻煙草(シガーレット)を燃すことは
月のあかりやらんかんの陰画
つめたい空明への貢献である
……ところがおれの右掌(て)の傷は
鋼青いろの等寒線に
わくわくわくわく囲まれてゐる……
しかればきみはピアノを獲るの企画をやめて
かの中型のヴァイオルをこそ弾くべきである
燦々として析出される氷晶を
総身浴びるその謙虚なる直立は
営利の社団 賞を懸けての広告などに
きほひ出づるにふさはしからぬ
……ところがおれのてのひらからは
血がまっ青に垂れてゐる……
月をかすめる鳥の影
電信ばしらのオルゴール
泥岩を噛む水瓦斯と
一列黒いみをつくし
……てのひらの血は
ぽけっとのなかで凍りながら
たぶんぼんやり燐光をだす……
しかも結局きみがこれらの忠言を
気軽に採択できぬとすれば
その厳粛な教会風の直立も
気海の底の一つの焦慮の工場に過ぎぬ
月賦で買った緑青いろの外套に
しめったルビーの火をともし
かすかな青いけむりをあげる
一つの焦慮の工場に過ぎぬ
この作品は、賢治が自ら『文芸プランニング』という雑誌にも発表していることから、それなりの自負を持っていたものだったのでしょう。
何となく難しい言葉が使われていて、一見とっつきにくそうな詩ですが、その内容については小沢俊郎氏が『薄明穹を行く 賢治詩私読』(学藝書林)において、古典的で思い入れたっぷりの解釈を示してくれています。
まず、ここに登場する「きみ」が、賢治の親友で音楽教師の藤原嘉藤治であり、場所は北上川に架かる朝日橋の上であることを推定した後、小沢氏は次のように書きます。
満月の明るい、といっても北国の身に沁みる寒さの二月、友人嘉菟治との話に熱中した賢治は、寒さも忘れて橋の上に来ていた。嘉菟治は熱心に自分の夢を語りつづけた。某社のコンクールに応じ、入賞し、ピアノを貰う夢を。古いヴァイオルでは彼の楽才が満足できないのである。ピアノが欲しい、新しいピアノが、と、月賦の外套を着たこの貧しい音楽教師はいう。もちろん、ピアノとともに楽才が認められ名声を得ることも彼にとって魅力でなかろうはずはない......。
ことばになって発したのか、あるいは控え目にしか言えなかったのか。少くも心の中では激しく賢治は否定せずにはいられない。
この町で芸術を語り合える数少ない貴重な友の嘉菟治よ。その君がそんなことを夢みるのか。君は今、やっとのことでその夢を打明けてくれる緊張からか、厳粛なまでに黙りこくって突っ立っているね。ぼくは、やっぱり反対だ。名声、賞品。そんなものに目もくれず進まなければいけない。もっと純粋に音楽だけを追求すべきだ。ピアノがなければあのヴァイオルみたいな古い楽器だっていいではないか。君の心いっぱいに引き鳴らせ。焦ってはいけない。君は君を大切にしなければいけない。(後略)
これは、「ピアノが欲しい」という親友の野心と、賢治の求道的な思想との相違に重点を置いた解釈です。一方、榊昌子氏はより審美的な観点から、賢治は嘉藤治の企画に反対していたととらえます(『宮沢賢治 「春と修羅 第二集」の風景』無明舎)。
「空明と傷痍」の「きみ」も、敬虔に直立し、紙巻煙草をくゆらして、青い二月の月夜の景に貢献した人物である。こういう人物には、当然、相応の行為とそうでない行為とがある。ふさわしいのは“中型のヴァイオルを弾くこと”、ふさわしくないのは、「営利の社団 賞を懸けての広告などに」かかわって“ピアノを獲得すること”である。後者はむろん、ピアノそのものが悪いと言っているわけではない。「燦々として析出される氷晶を/総身浴びるその謙虚なる直立」の姿勢と精神には、あさましく賞をねらったり、金もうけに腐心するような行為は似付かわしくないというのである。
「定稿」においては、懸賞の「ピアノ」か、ちょっと謎の「中型のヴァイオル」か、という楽器選択がどうしても葛藤の中心になっているように見えますが、不思議なことにこの作品の「下書稿(一)第一形態」には、まったく楽器は登場しないんですね。最初期の段階のテクストでは、終わりの方に
何だいきなり足踏みをする
こいつも結局
緑青いろの外套を着て
しめった緑宝石の火をともし
かすかな青いけむりをあげる
一つの焦慮の工場に過ぎぬ
という形で作者の「反発」は表現されていて、友人が「直立不動」だったのが「足踏み」をしただけで非難されているわけです。これには榊昌子氏も、次のように解釈します。
けれども、時は二月の夜。橋の上なら寒いに決まっているから、足踏みくらいしてもいいじゃないかと誰でも思う。作者もあんまりだと思ったのか、やがてピアノかヴァイオルかという、ソフトな音楽路線に改作されていった。
しかしこの「改作」の過程も一筋縄ではいきません。作者はまず「下書稿(一)第一形態」を、
[然→(削)] [そんなら→然れば]君はセロを〔?〕る企画をやめ[る→て]
ビオラダガムバを買ふべきである
といったん書き直してから、さらに、
然れば君は[セロ→ピアノ]を[〔?〕る企画→買ひ得ぬ焦燥→[[求める→借るの]]企画]をやめ[て→(削)→て]
ビオラダガムバを[買ふ→借る→買ふ]べきである
と、手入れしています。
すなわち、賢治が異を唱えた楽器は、最初には「セロ」だったようで、それが2回目の手入れ途中から「ピアノ」になったのです。一方、賢治が推奨する楽器は、当初は「ビオラダガムバ」だったのです。
 「ヴィオラ・ダ・ガンバ」とは、一般にはなじみが薄いかもしれませんが、西欧バロック期まで宮廷などで流行し、その後は廃れた弦楽器の一種です。大きさや雰囲気はチェロに似ていますが、「ヴァイオリン属」に属するチェロとは、系統的に異なる楽器です。1754年に描かれた右の絵(ジャン・マルク・ナエティエ「王女アンリエットの肖像」)で、王女が手にしているのがヴィオラ・ダ・ガンバです。ヴァイオリン属と比べて「なで肩」であること、指板に「フレット」があること、弓の持ち方が異なることなどの違いがあります。
「ヴィオラ・ダ・ガンバ」とは、一般にはなじみが薄いかもしれませんが、西欧バロック期まで宮廷などで流行し、その後は廃れた弦楽器の一種です。大きさや雰囲気はチェロに似ていますが、「ヴァイオリン属」に属するチェロとは、系統的に異なる楽器です。1754年に描かれた右の絵(ジャン・マルク・ナエティエ「王女アンリエットの肖像」)で、王女が手にしているのがヴィオラ・ダ・ガンバです。ヴァイオリン属と比べて「なで肩」であること、指板に「フレット」があること、弓の持ち方が異なることなどの違いがあります。
ヴィオラ・ダ・ガンバは、典雅な音色に魅力があるものの音量が小さく、よりダイナミックな表現が可能なチェロなどヴァイオリン属の楽器に、取って代わられていきます。J.S.バッハが「ブランデンブルグ協奏曲」の第6番で使ったり、「ヴィオラ・ダ・ガンバ・ソナタ」を残したのを最後あたりにして、モーツァルトの時代以降は全く使用されなくなりました。
「下書稿(二)」あるいは「雑誌発表形」以降は、賢治が推奨する楽器は「中型のヴァイオル」となりますが、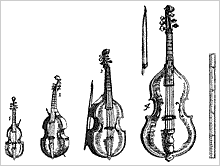 英語形の「ヴァイオル」、フランス語では「ヴィオール」とは、ヴィオラ・ダ・ガンバそのものを指すこともあれば、ヴィオラ・ダ・ガンバと同型の一群の弦楽器=「ヴィオール属」を指すこともあります。賢治がこれに、わざわざ「中型の」という限定的な形容を付けていることからすると、この「ヴァイオル」とは、「ヴィオール属」(右図)のことを意味していると考えられます。
英語形の「ヴァイオル」、フランス語では「ヴィオール」とは、ヴィオラ・ダ・ガンバそのものを指すこともあれば、ヴィオラ・ダ・ガンバと同型の一群の弦楽器=「ヴィオール属」を指すこともあります。賢治がこれに、わざわざ「中型の」という限定的な形容を付けていることからすると、この「ヴァイオル」とは、「ヴィオール属」(右図)のことを意味していると考えられます。
しかしそれにしても、なぜこんな馴染みの薄い古楽器が、ここに登場するのでしょうか。
榊昌子氏は、「下書稿(一)」における推敲過程で、「君」がじっと立っている様子について、
さういふ敬虔な直立は
むしろ中世風の冬の会堂の中にしばしばあった
と描写されていることを指摘し、さらに次のように論じます。
最後の一行は、「中生(ママ)信仰的の姿態である」とか、「中古ゴシック風の信仰である」などと書き替えられていくが、要するに、冬の青い月夜に直立している「きみ」の様子が、中世の教会でのそれを連想させ、一方また、「きみ」が音楽家であるらしいところから、中世の楽器であるヴァイオルやビオラダガムバが登場し、そこから、「中世風の冬の会堂」に敬虔にたたずんでいるような「きみ」には、ピアノよりもヴァイオルがふさわしい、という、結論が引き出されるわけである。
ということで、「ビオラダガムバ」や「ヴァイオル」がこの作品に登場する趣旨まではわかる気がしますし、その名前を知っていた賢治の博識には驚きますが、いったい当時の大正時代の日本に、ヴィオラ・ダ・ガンバなどという楽器の実物が存在していたのでしょうか。
「かの中型のヴァイオル」というふうに形容していることからすると、ひょっとしたら賢治と嘉藤治の二人は、この珍しい古楽器をどこかで一緒に目にする機会があったのかもしれません。しかしかりにこれが入手可能であったとしても、まだ現代のような古楽器ブームも到来していない時代、海外で好事家的にごく少数手作りされたような楽器を輸入したとしたら、それはとんでもない高価なものになったでしょう。そのことを賢治も多少は考慮してか、「下書稿(一)」上では「ビオラダガムバを[買ふ→借る→買ふ]べきである」という風に、一時は「借る」という方法も考慮しています。
しかし、さらにもしこの楽器を借りられたとしても、当時ヴィオラ・ダ・ガンバなどという珍品など持ったところで、合奏にも使えないし、人に教えることもできないし、音楽教師として全く役に立ちそうではありません。いくら「中世的な雰囲気に合わせるため」と言っても、これは嘉藤治に対して「西欧中世貴族のようなカツラを付けてタイツを履くように」求めると同じくらい、非現実的な要求のように感じます。
まあ、この辺の賢治の主張は、まじめくさった一種のジョークであって、榊昌子氏が指摘するように、その「諧謔的な見立てがこの作品の魅力の一つだろう」と考えるべきなのかもしれません。
一方、中村三春氏は、『修辞的モダニズム』(ひつじ書房)の中で、この作品全体を次のように解釈しています。
さて、この詩の中心が、あくまでも「空明への貢献」となる「謙虚な直立」にあるとすれば、次のように解釈できるだろう。「きみ」が「敬虔」な風景を完成するためには、「教会風の直立」が必要であり、またその風景の中で演奏するならば、近代のピアノよりも古風なヴァイオルがふさわしい。ところが、「おれ」は手を負傷しているので、風景を完成することができず、また二つの楽器のいずれも弾けない。二箇所の「ところが」は、これで容易に説明できる。つまりこのテクストにおいて音楽や音楽家は、「謙虚なる直立」に比べて本質的な問題ではない。風景を補完し風景と一体となる「直立」こそ、≪美学型≫語り手の欲するところである。だが、傷痍を帯びた身体を持つ≪独白型≫語り手自身には、「謙虚なる直立」を持続することは困難なのである。これは人間と風景との≪統合≫に関わるところの、透明と障害との形象である。
すなわち、作品全体としては「きみ」が音楽家であることや、楽器の是非などは本質的な問題ではなく、「人間と風景との≪統合≫」がテーマとなっているのだというわけです。さらに、「「焦慮」の語句は、「きみ」の感情以上に、自然・人間・人工の一体調和を求めて果たしえない「おれ」の心情が大きく投影されている」として、
つまり、「おれ」は自らのネガティヴな素質において、むしろ「きみ」へ同一化する志向を帯びている。もはや「きみ」と「おれ」とを別物と考える必要はないだろう。端的に言って、これは同一人格たる主体を、内部的・外部的な「すべて二重の風景」にほいて描き出したものにほかならないのである。
という興味深い視点を提示します。
ちなみに、上記で「≪美学型≫語り手」とは、作品の地の部分の主体、「≪独白型≫語り手」とは、「……」記号とともに字下げされた箇所の主体です。
◇ ◇
 と、いうような作品そのものの深い読みがあるとして、一方で私としては、藤原嘉藤治が「ピアノが欲しい」と切に願い、そのためには作品に出てくるように「懸賞?」または「コンクール?」に応募しようというような意思を、賢治に明かすことが実際にあったのではないか、と思うのです。
と、いうような作品そのものの深い読みがあるとして、一方で私としては、藤原嘉藤治が「ピアノが欲しい」と切に願い、そのためには作品に出てくるように「懸賞?」または「コンクール?」に応募しようというような意思を、賢治に明かすことが実際にあったのではないか、と思うのです。
その理由の一つは、当時の藤原嘉藤治が、中等学校音楽教員の資格を取ろうと何度も挑戦しては、おそらくピアノの実技のために不合格になるということを繰り返していたということです。
紫波町の「どっこ舎」による「かとうじ物語」というページには、次のように記されています。
藤原嘉藤治は、中等学校音楽教員の免許をとるため、東京まで出かけて勉強していますがなかなか試験に合格出来ません。
大人になってはじめたピアノの実技が障害になっていたようです。
諦めかけていた嘉藤治に、賢治は「おれが履歴書を書いてやるからがんばれ」と丁寧な文字で代筆しています。
しかし、また不合格。嘉藤治はすっかり落ち込んでしまいました。
そんな嘉藤治を元気にするために賢治のとった最後の手段が嫁の世話だったのです。
嘉藤治は岩手県師範学校在学中に、盛岡幼稚園の園長をしていたタッピング夫人の好意で、盛岡に初めてお目見えしたというピアノを借りて、早朝から練習をしていたということですが、やはり年長になってからの練習では、どうしても技術的な限界があったのでしょう。
嘉藤治の勤務先である花巻高等女学校にはピアノはありましたが、できることなら嘉藤治もあのゴーシュのように、自宅でも自由にピアノの猛練習をしたかったはずだと思います。そのためには、どうしてもピアノが欲しかったのではないかというのが、私の一つの推測です。
それからもう一つ、藤原嘉藤治の長兄で、嘉藤治と同じく岩手県師範学校で学び、在学中は「音楽の天才」と賞賛された藤原広治(1888-1913)の存在があります。
広治は師範学校を卒業後、地元の不動小学校、日詰小学校、水分小学校に勤務して、それぞれの小学校の校歌を作詞作曲し、合計わずか3年の間でしたが音楽教育に情熱を注ぎました。そして、水分小学校在職中に、結核のため25歳の若さで亡くなります(参考:盛岡タイムス「夭折した音楽の秀才 藤原広治の業績を冊子に」)。
嘉藤治にとって兄の広治は、尊敬すべき音楽の先達でもあり、理想の教師でもあったのですが、師範学校在学中に兄の訃報に接し、「突然心の支えを失って、悲嘆に暮れるばかり」だったということです(「かとうじ物語」より)。
その兄の広治が、生前に書いた次の一文を、嘉藤治も必ずや知っていたはずです。
あゝピアノがほしいピアノがほしい。ピアノがあったなら何物も用はない。新しい楽譜があったらなら弾く印象を作曲紙にならべる。これが僕の最絶頂である。一生単純で華やいで居たいのだ。
僕は、緑したたるりんご畑のなかに小さな音楽堂を建てて一人で響きを絶やさない考えだ。
この文とともに、藤原広治が作詞作曲した「旧校歌」を刻んだ碑は、ピアノをかたどった形で紫波町の水分小学校の近くに建てられています。
かぐら川
賢治の作品のどこかでヴィオラ・ダ・ガンバの名を見た記憶があったのですが、この下書き稿だったのですね。我が田舎都市富山はなぜか古楽アンサンブルのさかんなところで、友人にガンバ奏者がいますので機会があれば聞いてみます。恥ずかしながら私も10年ほど前にその仲間に入っていたこともあり、ガンバと言えばあのマラン・マレのトリオソナタなども演奏したことがあります。そこまで書けば、拙日記の「めぐり逢うことばたち」が、ある映画タイトルのもじりであることもばれてしまいますが。。。
ちょっと検索したところでは、神戸愉樹美さんが「日本のガンバ史――江戸から今日まで――」というタイトルで歴史を追っておられるようですね。
藤原兄弟の音楽に寄せる熱い思いにはほんとうに心動かされます。
hamagaki
かぐら川さま、神戸愉樹美さんによる歴史的概観について、ご教示をありがとうございます。下記ページを拝見しました。
http://vdgsa.org/PPGG/Viols-in-Japan.pdf
このページを見ても、明治・大正期には日本ではヴィオールは使用されておらず、明治以降に初めて出てくる記述は、何と上でも見た賢治の「空明と傷痍」からの引用なのですね。(「空明」の読み方が、?ですが。)
そしてその次の記述は、イギリスに留学していた黒沢某という人が、1929年にバス・ヴィオールを持ち帰ったとのことで、「空明と傷痍」がスケッチされた1924年に、はたして日本にヴィオラ・ダ・ガンバが存在していたのか、やはり可能性が危ぶまれます。
ところで、落ち着いた富山の街に古楽アンサンブル......。なんかしっくりと似合う感じがしますね。
耕生
耕生です。
「空明と傷痍」、春と修羅第二集の冒頭を飾る詩というのに、これまでなんとなくよくわからないまま、見過ごしていました。藤原加藤治が主役だったとはちょっとした驚きした。
藤原嘉藤治のことをこれまで少し過小評価していたようです。調べてみると、賢治と同じ明治29年の生まれです。しかも花巻女学校の音楽教師として赴任したのが大正10年と、賢治が農学校教師になったのと、これまた同じです。この二人が親友になっていくのは自然のことだったでしょう。
賢治の友人というと、保阪嘉内が真っ先に浮かびますが、交流の期間とその深さをとってみると、藤原嘉藤治こそはまさに無二の親友だったのかもしれません。また、東京での嘉内との精神的決別、そして最愛の妹トシの死後、賢治の最大の理解者は嘉藤治だったような気がします。
昭和8年の賢治の死後、嘉藤治も女学校を止め、賢治全集の刊行に奮闘しています。宮沢賢治の名を世に広めた最大の功労者のひとりでもあったわけです。見逃せないのは、戦後、紫波町の開拓地に入植し、死ぬまで一農民として生きたことです。これは賢治のなし得なかった事であり、賢治の実践活動における正統な後継者と考えてもおかしくありません。
保阪嘉内との友人関係には失恋のような心の痛手とほろ苦さがあります。しかし、嘉藤治との友情には青春の明るさがあると感じるのは私だけでしょうか。トシの死後、精神的理解者もなく、周囲の協調も得られないまま、孤独の中で奔走していたという私のイメージは改めなければいけないようです。少なくとも藤原嘉藤治のような友人、そして松田甚次郎のように終生の師と慕う人もいたわけですから(なぜか宮沢賢治語彙辞典には松田甚次郎の項がないのは以前から不思議でした)。
宗教的なことを語る友がいなかったのは賢治の不幸だったのかもしれません(いや、デクノボ-のモデルとされるキリスト者の斎藤宋次郎がいました)。しかし、賢治の青春そして晩年は意外に明るかったのかもしれません。もしそうだったとしたら、藤原嘉藤治の存在はその明るさの大きな原因だったことでしょう。また藤原嘉藤治にとっても賢治の存在は大きな光明だったと思えてなりません。あるいは嘉藤治こそは賢治精神の正統な継承者なのかもしれません。その精神は今、どこかに受け継がれているのでしょうか。もし、受け継がれているのだとしたら、ぜひ会ってみたいと切に思います。
耕生
耕生です。
追加のコメントです。
藤原嘉藤治のピアノへの思いをなにやら後ろめたい思いで読みました。というのは、我が家にもピアノが1台あるのですが、娘たちが家を離れた後はホコリをかぶって、居間の片隅におかれたままになっているからです。時々、キーを触ったりしますが、宝の持ち腐れとはまさにこういう事を言うのですね。
私は下手の横好きでオカリナ演奏が趣味です(ついでに楽器のオカリナの収集も)。といっても楽譜無しで演奏できる曲は極く限られており、「星めぐりの歌」のほか、少ししかありません。
今、「君をのせて」(天空の城ラピュタの主題歌)などを練習中です。また、有名な宮崎駿監督の息子さんの宮崎吾朗監督の初作品の「ゲド戦記」の主題歌「テルーの唄」が気に入ったので、自分で生まれて初めて採譜をし、練習したりもしました。以前、日本エスペラント学会の大会懇親会で飛び入り演奏し、拍手喝采?を浴びたこともあります。そう言えば、宮沢賢治国際研究会のエクスカーションで種山が原へ案内してもらった時にも山頂で「牧歌」を演奏させていただきました。
ピアノはこの年ではもう無理ですが、オカリナは年行ってからでもマスターすることが可能です。普通はC菅(ハ調の音程)とかF菅(ヘ調)とかが多く市販されていると思いますが、息づかいが結構大変なので、最近はピッコロ(1オクターブ高いC調)を愛用しています。これはポケットにも入る大きさなので携帯にも重宝します。
車を運転するとき、信号待ちでイライラすることが多いかと思いますが、そんな時にポケットからオカリナを取り出して演奏するとイライラから解放されます。「ちぇ、もう青か」などと思ったりするから面白いです。一度お試しあれ。
なお、オカリナを購入される時はその辺で売っている数千円の安物ではなく、1万円以上の手作り品を購入されることをお勧めします。大量生産の安物は高音域がうまく出ず、演奏に苦労させられることが多いのです。「安物買いの銭失い」にご注意下さい。個人の演奏技術の問題もあるかもしれませんが・・・(笑)。
hamagaki
耕生さま、こんばんは。
> 保阪嘉内との友人関係には失恋のような心の痛手とほろ苦さがあります。
> しかし、嘉藤治との友情には青春の明るさがあると感じるのは私だけでしょうか。
私も、まさにそんなイメージです。もちろん、嘉内との友情にも輝くばかりの「青春の明るさ」があったはずですが、それはおっしゃるとおり「恋」に近くて、胸が苦しくなるような感じまで伝わってきてしまいます。
以前に見たことのある『わが心の銀河鉄道 宮沢賢治物語』(1996)という映画でも、そんな雰囲気がよく描かれていたような記憶があります。
ところでオカリナは、私もずっと昔にちょっと楽しんでいたことがありますが、やはり「高い方のC調」のでした。小さいし、息の量も少なくてすむし、屋外で吹くには音色もよく通るし、いいですよね。
ただし、恥ずかしながら値段は「数千円」までもいかなかったと思います。(^^)ゞ
石川 朗
『宮澤賢治全集』十字屋書店版の全巻の1/3ほどに藤原嘉藤治の検印がありますがなぜでしょう。お気づきでしたか。調べたことはありませんか。下記に一覧があります。
https://34394792.at.webry.info/201603/article_1.html
石川 朗
上記、石川朗のブログが廃止になり、アドレスが消失しました。
新しいアドレスをが下記です。
『宮澤賢治全集』十字屋書店版の全巻の1/3ほどに藤原嘉藤治の検印がありますがなぜでしょう。お気づきでしたか。調べたことはありませんか。下記に一覧があります。
https://ameblo.jp/kaisizu2019/entry-12532245500.html
なお新しい藤原嘉藤治の本
『賢治さんの人格・芸術を世界へ』瀬川方子編、錄繙堂出版
が出帆されました。良書です。
hamagaki
石川朗様、お知らせをありがとうございました。
『賢治さんの人格・芸術を世界へ』は、私も拝読しておりますが、貴重な内容と存じます。
十字屋版全集の昭和27~28年の検印については、昭和27年11月8日付け宮沢清六から藤原嘉藤治あて書簡A90(『賢治さんの人格・芸術を世界へ』p.79)には、「十字屋書店の不徳義は全く困ったことです。私の方で黙してゐても、世間の目もあり、又自然の制裁もあると思ひますから、どうかこれ以上のひどいことをさせないやうになされて下さい。」とあり、十字屋書店と宮沢家との間に何らかの問題があったようですから、このような事情も関係していたのでしょうか。