賢治は1923年8月に、北海道を縦断してサハリンに至る「オホーツク挽歌」の旅をして、翌1924年5月には、花巻農学校の修学旅行の引率教諭として、再び北海道を訪れています。
前者から後者までの期間は9ヵ月足らずで、同じ北海道を旅したのですから、後者の道中においては前者に関するいろいろな追想があっても不思議ではないと思うのですが、なぜか後者=1924年の修学旅行における作品群には、まったくと言ってよいほど、前年の旅行のことを連想させる記述は出てこないのです。
もちろん、傷心の一人旅と生徒を引率した団体旅行という状況の違いはありますし、二つの旅の間に、賢治の心にそれだけの変化があったと考えることもできます。しかし、賢治はある場所で心象を書きとめる際、しばしば以前にその場所を訪れた時のことに触れる傾向があって、例えば「小岩井農場」「パート一」では、「冬にきたときとはまるでべつだ」と書いて、1月に「屈折率」「くらかけの雪」を書いた時の訪問に言及していますし、また1923年の「津軽海峡」(『春と修羅』補遺)においては、「中学校の四年生のあのときの旅ならば・・・」と、岩手中学の修学旅行で津軽海峡を渡った時のことを回想しています。
したがって、1924年の北海道における作品群に、1923年の北海道の追憶が全く登場しないというのは、やはり不自然だと思うのです。すなわち、1924年の作品群において前年のことが出てこないのは、たんなる偶然ではなくて、賢治は意図的にそれを避けて作品を書いたのではないかと、私は考えてみるのです。
しかし、かりにそのように賢治が意図していたとしても、以前に「若き日の最澄(2)」に書いたように、1924年修学旅行中の「牛」の下書稿(一)の推敲過程においては、トシのことを再び追想しているとしか考えられないような、激しい感情表現や仏教的な言葉が出現しているのを見ました。まだ初期の下書稿においては、作者として抑えきれない記憶が、あふれ出てきていたということかもしれません。
そして、これ以外にも「修学旅行詩群」の中には、前年の旅と関連しているのではないかと気になる表現が、さらに二・三ですが、見られると思うのです。
(1)
その一つは、「〔船首マストの上に来て〕」(補遺詩篇 I)という作品断片です。これは、「春と修羅 第二集」には分類されていませんが、やはり1924年の修学旅行の帰途、青函連絡船で青森港に入る直前の状況と推測されます。無事に生徒たちを引率して本州まで帰ってきたという、教師としての安堵感が感じられる作品です。
この中に、下記のような一節があります。
わたくしはあたらしく marriage を終へた海に
いまいちどわたくしのたましひを投げ
わたくしのまことをちかひ
三十名のわたくしの生徒たちと
けさはやく汽車に乗らうとする
水があんな朱金の波をたゝむのは
海がそれを受けとった証拠だ
ここに出てくる、「(海に)いまいちど私のたましひを投げ・・・」という表現が、ちょっとドキッとしてしまうところです。
「いまいちど」とは、どういう意味でしょうか。賢治は、この修学旅行において、自分の魂を海に投げるようなことを、それまでにもしていたのでしょうか。
それはわかりませんが、ここでどうしても思い出すのは、前年の旅行において賢治は、少なくとも「魂を投げる覚悟で」、トシとの交信を求めていたことです。
例えば「宗谷挽歌」の冒頭は、
こんな誰も居ない夜の甲板で
(雨さへ少し降ってゐるし、)
海峡を越えて行かうとしたら、
(漆黒の闇のうつくしさ。)
私が波に落ち或ひは空に擲げられることがないだらうか。
と始まり、最後は、
さあ、海と陰湿の夜のそらとの鬼神たち
私は試みを受けやう。
で終わります。
1924年に「いまいちどわたくしのたましひを投げ」と言われる前提の、「最初の一度」とは、前年の宗谷海峡の甲板における決死の行動だったのではないだろうか・・・というのが、私の勝手な空想の一つです。

青森港(2006.8.16)
(2)
もう一つは、「〔つめたい海の水銀が〕」の下書稿(二)の最後に出てくる、
そこが島でもなかったとき
そこが陸でもなかったとき
鱗をつけたやさしい妻と
かってあすこにわたしは居た
という一節です。
この作品は、やはり修学旅行の帰途に、青森湾に浮かぶ湯ノ島を眺めつつ書かれたものと推測されますが、上に引用したのは、何とも不思議な賢治の幻想です。
そこが「島でも陸でもなかった」ということは、この島が海底に沈んでいた時代のことかと思われ、作者はそこに、「魚の夫婦として」棲んでいたというのです。輪廻転生における過去生の一つにおいて、そのようなことがあったと、賢治は感じたのでしょうか。
ところで、ここに出てきた「魚になって海中にいる」というテーマですが、私は、賢治がオホーツク挽歌行においても、やはりそのようなことを考えていたふしがあったように感じるのです。
というのは、やはり「宗谷挽歌」において、死んだトシに呼びかける次のような一節があるからです。
われわれが信じわれわれの行かうとするみちが
もしまちがひであったなら
究竟の幸福にいたらないなら
いままっすぐにやって来て
私にそれを知らせて呉れ。
みんなのほんたうの幸福を求めてなら
私たちはこのまゝこのまっくらな
海に封ぜられても悔いてはいけない。
「みんなのほんたうの幸福」のためなら、「私たち=賢治とトシ」は、「海に封ぜられても悔いてはいけない」というわけですが、「海に封ぜられる」とは、すでに死んでいるトシにとっては、そのまま魚に転生すること、賢治はこの場で死んで、やはり魚に転生する、ということになるのではないでしょうか。
さらに、「牛」(下書稿(一))には、
海よしづかに青い魚族の夢をまもれ
……砂丘のなつかしさとやはらかさ
まるでそれはひとりの処女のようだ……
という一節があるのですが、それまではひたすら波が激しく荒れるよう挑戦的に呼びかけておきながら、ここでは急に一転して「海よしづかに青い魚族の夢をまもれ」と言っているのが、不思議に感じられます。
私は、ここで賢治は、トシが魚に転生した可能性をふと思って、「しづかに・・・まもれ」と海に願ったのではないのだろうかとも思ってみているのですが、どうでしょうか。
いずれも、空想的な可能性の積み重ねにしかすぎませんが、「鱗をつけたやさしい妻と/かってあすこにわたしは居た」という不思議に魅力的なイメージは、賢治とトシが「海に封ぜられた」輪廻転生の姿なのかもしれない、などと私は夢想してみるのです。
もちろん、「〔つめたい海の水銀が〕」を書いた時の賢治が、そこまで意識していたとまで考えるわけではありません。ただ、前年に彼が「海に封ぜられて魚になる」可能性について考えていたとすれば、翌年にふと青森で竜宮城のようにかわいい島を見た時、その海底で「鱗をつけたやさしい妻」と暮らすという幻想が湧く、潜在的なきっかけにはなったかもしれないと思うのです。

湯ノ島(2006.8.16)
(3)
あともう一つ私が気になることとして、「凾館港春夜光景」に出てくる、「喜歌劇オルフィウス」があります。
これは、賢治が東京の「浅草オペラ」で、オッフェンバックの喜歌劇「地獄のオルフェ」(一般的な邦題は「天国と地獄」)を見たことがあったとすれば、函館公園の照明から、その喜歌劇の舞台照明を連想したということと解釈できますが、はたしてここで他のオペレッタではなくて「喜歌劇オルフィウス」が登場するのは、偶然なのでしょうか。
そのことについては、また稿をあらためて考えてみたいと思います。
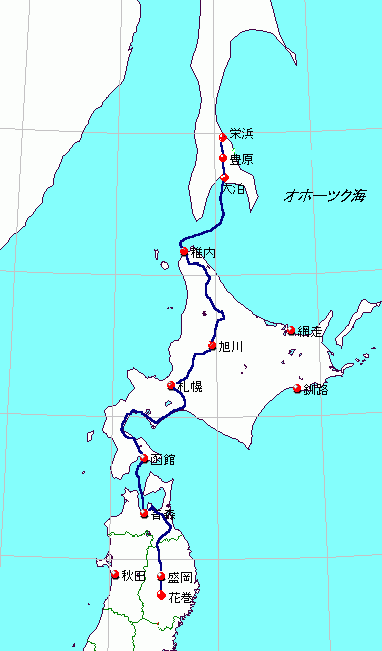
1923年オホーツク挽歌行の旅程
コメント