オホーツク挽歌 詩群
1.対象作品
『春と修羅』
「春と修羅 補遺」
![]()
2.賢治の状況
宮澤賢治は、1923年7月31日から8月12日にかけて、北海道を経由してサハリン(樺太)まで至る一人旅をおこないました。
この旅行の直接の目的は、樺太の王子製紙に勤務している先輩を訪ねて、農学校の教え子の就職を依頼するということでしたが、じつは賢治にとってもっと深いところでは、これは前年の11月に亡くなった妹 とし子 の魂の行方を探そうとする旅でした。
この旅行のあいだに、『春と修羅 〔第一集〕』の「オホーツク挽歌」の章に収められている諸作品と、現在は『同補遺』に分類されている関連草稿がスケッチされました。
以下は、萩原昌好氏の著書『宮沢賢治「銀河鉄道」への旅』を参考にして、この旅行中の賢治の行程を再構成してみたものです。
| 7/31 | 21時59分花巻駅発の、東北本線下り「八〇三号」列車で出発。途中、23時ちょうどに盛岡駅を通過。 |
| 8/1 | 夜半から明け方にかけて、車中で「青森挽歌」「青森挽歌 三」をスケッチ。「けれどもここはいつたいどこの停車場だ」と賢治が呟いたのは、沼崎(3:30)~乙供(通過)~千曳(通過)~野辺地(4:11)の間のいずれかの駅ではないかと推定される。朝5時20分に青森駅着。 午前7時55分、青函連絡船で青森港を発ち、12時55分に函館港着。船上で「津軽海峡」をスケッチ。 13時45分、函館桟橋発の函館本線「網走・根室行」列車に乗り、北へ向かう。車中で「駒ケ岳」をスケッチ。札幌を過ぎたあたりで日付が変わる。 |
| 8/2 | 午前4時55分、旭川駅着。早朝の町を馬車に乗って旭川農事試験場へ行こうと六条十三丁目に向かい、「旭川」をスケッチ。しかし、農事試験場はこの時すでに郊外の永川に移転していた。 午前11時54分、宗谷線急行一号で旭川駅を発ち、21時14分に稚内駅着。 23時30分、稚泊連絡船「対馬丸」に乗船し稚内港を出航。真夜中の宗谷海峡を渡り、「宗谷挽歌」をスケッチ。 |
| 8/3 | 午前7時30分、樺太の大泊港着。午前中、王子製紙会社の細越健氏に会い、農学校生徒の就職を依頼。 13時10分、大泊駅から樺太鉄道に乗り、18時20分、終点栄浜駅着。山口旅館に投宿。 |
| 8/4 | 朝、栄浜の海岸を散策して「オホーツク挽歌」をスケッチ。また、夕方には「樺太鉄道」をスケッチ。 なお、「オホーツク挽歌」文中の「(十一時十五分、その蒼じろく光る盤面)」という一節は、この日の午前11時15分とする解釈が一般的である(【新】校本全集など)。しかし、萩原昌好氏は上記著書において、この作品は前夜半からこの日の朝にかけて、栄浜でスケッチされたものであると考え、11時15分は「午後」すなわち夜中のことであるとしている。この説の眼目は、日本時間のこの日午後11時15分に、「白鳥座」がちょうど天頂に位置し、地上では栄浜に「白鳥湖」という湖があるため、ここで二つの白鳥が重なる、という点にある。 ただ、「オホーツク挽歌」という作品は全体として朝の情景を描いており、ここだけが夜中とすると、やや唐突な感は否めない。 |
| 8/5 | 未詳 |
| 8/6 | 未詳 |
| 8/7 | 日中、豊原近辺で植物採集をおこない、「鈴谷平原」をスケッチ。 21時00分、稚泊連絡船で大泊港を出航し、ふたたび宗谷海峡を渡る。 |
| 8/8 | 午前5時00分、稚内港着。 |
| 8/9 | 未詳 |
| 8/10 | 未詳 |
| 8/11 | 夜明け前頃、室蘭本線~函館本線の車中で「噴火湾(ノクターン)」をスケッチ。車窓から、午前4時森港発室蘭行きの噴火湾汽船を見た。 この列車は、稚内を前日の午前7時25分に発ち、旭川を17時3分、札幌を21時8分にそれぞれ経由して、終点の函館桟橋に至るもので、賢治がこの経路の間のどこで乗車したかは不明である。 函館桟橋に午前6時27分に到着し、7時30分函館港発の青函連絡船急行汽船に乗り、12時00分青森港着。 東北本線上り列車に乗り、夜に盛岡に到着し、ここで下車し、徒歩で花巻へ向かった。 |
| 8/12 | 花巻に到着。 |
1905年に、日露戦争後のポーツマス条約によって南樺太の領有権を得た日本は、1918年のシベリア出兵を機に、さらに北方の足場を固めようとしていました。
1922年11月、旭川-稚内間の宗谷線が開通したのにつづき、1923年5月には、稚内港と樺太の大泊港を結ぶ稚泊連絡船が就航しました。これによって、東京から樺太の栄浜までの経路が、鉄道および連絡船によって、一本に貫通したことになります。
賢治が樺太へ旅立った1923年7月とは、ちょうどこのような時期にあたっていました。
樺太が開発されつつあるからこそ、生徒の就職先の候補にあがって、賢治の出張の必要性が出てきたとも考えられるでしょう。しかし、賢治の個人的な気持ちを推し測ると、まるで上記のような交通手段の完成を待ちかねていたかのように、とにかく口実をつけて北へ向かって飛び出したような感じも受けてしまいます。この樺太旅行の旅費は、賢治が自前で負担したようですが、これも普通の公務としての出張であったら、考えにくいことです。
もともと以前から、北方への志向性を持っていたと思われる賢治ですが、妹 とし子 が亡くなってからというもの、その妹の魂が「われらが上方と呼ぶその不可思議な方角」へ向かったと感じて、北を目ざす衝迫に突き動かされていたかのように見えます。
しかし賢治のこの旅のおかげで、今日の私たちは、日本では他に比類のない、長大な鎮魂の叙事詩群を持つことになりました。
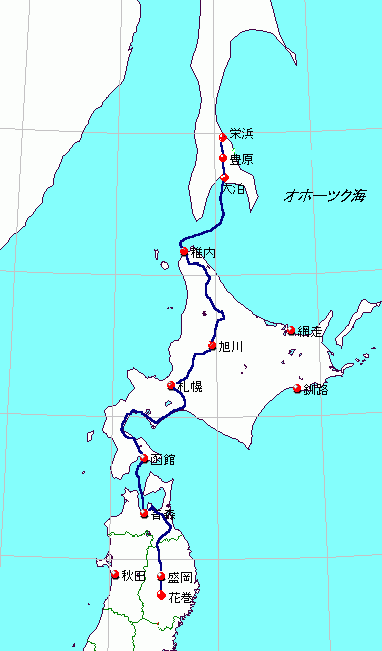
「オホーツク挽歌 詩群」の行程 (萩原氏の著書による)
![]()