以前に、「『春と修羅』第一集ー第三集の各作品の長さ」というエントリにおいて、それぞれの『集』に収録(分類)されている詩作品の字数を比較してみたことがありました。その結果は、作品字数の中間値(メディアン)で見れば、『第二集』の作品が一番長くて、次が『第一集』(=『春と修羅』)、そして一つ一つの作品が最も短いのは、『第三集』ということになりました。
『第三集』においては、『第二集』までのように、野山を歩きまわって自由に空想にひたるという創作スタイルは見られなくなり、農作業の合間に書き付けたというような作品が多くなっていますから、おのずと各作品が短くなる傾向もあったのかと、この時は思っていました。
ただ、当然のことですが、『第三集』に分類されている69篇の作品は、決して同じような性格を持った均質なものではありません。上に述べたような「農作業の合間に書き付けたような」作品もありますが、いろいろと別の状況をスケッチしたものもありますし、それに何よりも、作品が書かれた(発想された)日付に関して、『第三集』には一つの特徴がありました。
『【新】校本全集』において、「春と修羅 第三集」として分類されているのは、(1)主として専用の細罫詩稿用紙に書かれた口語詩のうち、(2)作品番号と日付が記されていて、(3)その日付が、賢治によるメモ「春と修羅 第三集/自昭和元年四月/至 三年七月」の期間に該当するもの、という原則に従っています(全集第四巻「凡例」より)。
ただ、上の「期間」・・・西暦に書き直すと「1926年4月~1928年7月」の間、作品はコンスタントに書かれていたわけではなくて、特に終わりの方、1927年8月20日の「〔何をやっても間に合はない〕」から、次に来る1928年4月12日の「台地」までの間には、8ヵ月ものブランクが空いているのです。(さらに、この「台地」、1928年7月20日の「停留所にてスヰトンを喫す」、7月24日の「穂孕期」という「最後の三作品」には、「作品番号」が付けられていないという、他作品と違った特徴もあります。)
つまり、1927年までの作品と、1928年の作品との間には、ちょっとした「断絶」があるわけですね。
さらに、この1928年という年には、「日付は記入されているが作品番号は付けられていない」という作品が、上の「最後の三作品」の他にも、かなりあるのです。それは、伊豆大島に渡った時の「三原三部」3作(「三原 第一部」、「三原 第二部」、「三原 第三部」)と、大島行きの前後の東京滞在中に書いた作品(「東京」所収の「浮世絵展覧会印象」や「高架線」など)です。「補遺詩篇 I 」に分類されている、「装景家と助手との対話」(1928年6月1日付け)も、ここに含めることが可能です。
そして、上記のようにやはり「日付はあるが作品番号のない」「春と修羅 第三集」の最後の三つの作品も、便宜的にこの一群と一緒に並べてみることができるでしょう。(「口語詩稿」などの中にも、「三月」や「〔澱った光の澱の底〕」のように、内容から明らかに1928年に書かれたと推定できるものもありますが、日付は作品に記入されていないので、ここではこれらは除いておきます。)
そうしてこういった一群の作品を別立てにしてみると、以前に比較した「各作品の長さ(字数)」というのがどうなるのか、というのが今日のテーマです。前回作成してみたグラフから、「春と修羅 第三集」の最後の三作品を除き、新たに「1928年の日付入り作品」というグループを作って棒グラフを書き換えてみると、下のようになりました。
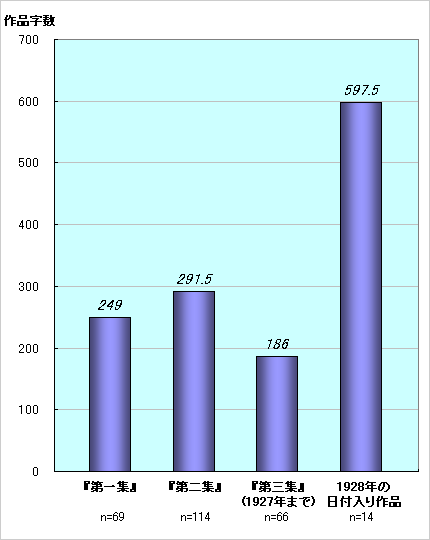
グラフの棒の高さ=添付数字は、その『集』に属する作品の字数の「中間値」を表しています。下に、「n=69」などと書いてあるのは、作品数です。
一目瞭然のごとく、右端の「1928年の日付入り作品」という群は、それ以前の群よりも格段に作品が長い傾向がある、ということがわかります。もちろん、それまでの各集にも、個々に長大な作品はありましたが、1928年のものは総体として長い傾向がある、あるいは逆に言えば、短い作品があまりない、ということが統計的に表れています。サンプル数が少ないので、あまり断定的な言い方はできませんが、それでも2倍以上の違いというのは無視できないと思います。
この所見は、大島や東京における作品を読んでいると、賢治がやけに「饒舌」であるような印象を受けるということの、別の角度からの表現と言えるでしょう。実際、賢治は大島に行くにあたり、かなり気分が高揚していたようですし、その高揚の持続は、花巻帰着直後の作品と思われる「〔澱った光の澱の底〕」からもうかがえます。
しかし、7月下旬の二作品、「停留所にてスヰトンを喫す」、「穂孕期」に至ると、疲労の蓄積と体調の悪化からか、賢治の気持ちはやや下降線に入っているようです。そして、作品の内容もそれまでより感傷的になっていて、これがまた、独特の雰囲気を醸し出しています。
太陽のように輝いていた「賢治の口語詩」が、ついに日暮れを迎えているという感慨を覚えざるをえない、切ない二作品です。
時系列で見ると、羅須地人協会における「青年団」的活動が挫折した後、「肥料相談」「肥料設計」に重点を移すことで農民の役に立とうとした賢治でしたが、1927年8月20日の豪雨で、自分が肥料設計をした田の稲が次々と倒れ(「〔もうはたらくな〕」)、雨の中を農家を訪ね歩き(「〔二時がこんなに暗いのは〕」)、賢治は「〔何をやっても間に合はない〕」と、絶望感にとらわれてしまったように思われます。そして、この「意気消沈」が、その後の8ヶ月間の(日付入り)作品のブランクになって表れたのではないかと、私は思います。
そのブランクの後、翌年4月に久しぶりの日付入り作品が登場し、6月から7月にかけてはそれまでの「意気消沈」の反動でもあるかのように、やや高揚した調子の、長めの作品群が現れるというのが、上に見たところです。
かつて福島章氏は、賢治には「躁うつ」の傾向があったと分析しておられましたが(『宮沢賢治 芸術と病理』, 1970)、作品の時系列推移を見ていても、彼に「気分の波」がありそうなことは、私などでも感じるところです。上記の、1927年8月下旬に始まった「意気消沈」から、1928年春から夏の「気分高揚」へ、というのがその一つの典型例だと思います。
あと一つの例としては、『春と修羅』において、1922年11月27日のトシの死の後、6ヵ月あまりのブランクがありましたが、1923年6月3日付の「風林」で作品が再開すると、6月4日の「白い鳥」、そして8月の「オホーツク挽歌」詩群まで、かなり長い作品群が続くところがあります。「風林」から、8月11日の「噴火湾(ノクターン)」までの7作品で、最長の作品は「青森挽歌」の3852字ですが、7作品の字数の中間値は、824です。
1923年6月から8月までの賢治も、深い悲しみにとらわれてはいましたが、亡き妹との「交信」の可能性を信じて、夜通し甲板に立ってサハリンを目ざすなど、かなり高揚した精神状態にはあったと思います。
福島章氏の意見のとおり、このように「意気消沈」から「高揚」へというのが、賢治の生涯に何度か見られたパターンだったということは、たしかに言えると思います。
コメント