私は2年前に「われらともに歌ひて泯びなんを」という記事で、「〔われらぞやがて泯ぶべき〕」という文語スケッチを読んでみようとしたのですが、そこに賢治が自らの「病気」について記している、非常に深いルサンチマンのような感情には、驚きを禁じ得ませんでした。未来においては何かを「償え」と求めてはいるものの、現世にはもう全く絶望しており、あとはただ同じ苦しみを共有する仲間と「ともに歌ひて泯びなん」ことのみを、賢治は願っているかのようでした。
この救いのなさは、いったい何なのだろうかと思いました。
そこで考えてみると、自らの病気に対するこの根深い感情は、1931年9月に賢治が東京で高熱を出して倒れた際に、生命の危険を冒してまでも、なかなか家にも知らせず帰ろうともしなかったのは何故なのか、という謎にも関わっているように思えました。
それで上の記事の少し後に、「八幡館の八日間(2)」という記事を書きました。
二つの問題を並べてみると、両者に通底する賢治の感情を理解するためには、賢治は結核という病気のために、周囲から陰に陽に侮蔑や差別を受けて、とても深く傷ついていたのだと考えざるを得ないように思われましたので、それを「病気への侮蔑と差別の中で」という記事に書きました。
ところで前述のように、賢治はこのように傷つきながらも、「〔われらぞやがて泯ぶべき〕」では、同じ傷を持つ「仲間」に対して「ともに歌ひて泯びなん」として、「連帯」を呼びかけていたのでした。
このような意味で、「弱者への共感と連帯」を表明する作品が、賢治晩年の文語詩の中にはそれなりに含まれていると思われましたので、その様子を概観しようとしたのが、「弱き者との連帯の歌」という記事でした。
さらに、そのような作品の具体例として、「毘沙門の堂は古びて」や「病める女性とともに(1)」という記事も書きました。
今回の記事は、このような流れに続くものです。
※
賢治晩年の文語詩の中に、「遊女」とか「淫れ女」などと呼ばれる階層の女性たちを描いた作品がかなりあることは、従来から注目されており、栗原敦さんは「うられしをみなごのうた」(『宮沢賢治 透明な軌道の上から』所収)という文章において、「八戸」「歯科医院」「〔せなうち痛み息熱く〕」「〔鉛のいろの冬海の〕」「〔燈を紅き町の家より〕」「〔夜をま青き藺むしろに〕」などの作品を取り上げておられます。
ここで栗原さんは、賢治が「淫れめ」に共感しつつ描写する態度を、「自と他を一瞬にして入れ換えさせ、しかもそれぞれの位置付けの誤差をも正す〈共なる「われ」〉という言葉で表現し、賢治が彼女たちに寄せる思いの深さを指摘しておられます。
また島田隆輔さんは、『宮沢賢治研究 文語詩稿・叙説』の「序章 〈歌ひめ〉の詩系譜を読む」の中で、「〔ちゞれてすがすがしい雲の朝〕」「早池峯山巓」「八戸」「〔燈を紅き町の家より〕」「〔雪とひのきの坂上に〕」「涅槃堂」「〔せなうち痛み息熱く〕」「〔夜をま青き藺むしろに〕」「〔なべてはしけく よそほひて〕」「林館開業」「歯科医院」などを取り上げ、推敲の時間経過に沿って、賢治の「〈歌ひめ〉観」がどのように変化していくかを詳しく跡づけておられます。
なかでも「歯科医院」においては、「たはれめ」がまとう服が、「白き衣」から推敲を経て「浄き衣」となっていくことを指摘し、ここに作者は「あきらけき道」(「〔燈を紅き町の家より〕」の下書稿(一)に現れた言葉)に込められた、潔白さ・清明さ・明潔さ・明浄さを見出しているのではないか、と論じておられます。
私としては、上記のお二人による精緻な論に、これ以上付け加えることは何もありませんが、ここでは「〔せなうち痛み息熱く〕」および「歯科医院」に登場する病気の女性を、「〔われらぞやがて泯ぶべき〕」に歌われた仲間と見る視点から、少しだけ触れておきたいと思います。
※
「文語詩未定稿」の「〔せなうち痛み息熱く〕」は、次のような作品です。
せなうち痛み息熱く
待合室をわが得るや
白き羽せし淫れめの
おごりてまなこうちつむり
かなためぐれるベンチには
かって獅子とも虎とも呼ばれ
いま歯を謝せし村長の
頬明き孫の学生を
侍童のさまに従へて
手袋の手をかさねつゝ
いとつゝましく汽車待てる
外の面俥の往来して
雪もさびしくよごれたる
二月の末のくれちかみ
十貫二十五銭にて
いかんぞ工場立たんなど
そのかみのシャツそのかみの
外套を着て物思ふは
こゝろ形をおしなべて
今日落魄のはてなれや
とは云へなんぞ人人の
なかより来り炉に立てば
遠き海見るさまなして
ひとみやさしくうるめるや
ロイドめがねにはし折りて
丈なすせなの荷をおろし
しばしさびしくつぶやける
その人なにの商人ぞ
はた軍服に剣欠きて
みふゆはややにうら寒き
黄なるりんごの一籠と
布のかばんをたづさえし
この人なにの司ぞや
見よかの美しき淫れめの
いまはかなげにめひらける
その瞳くらくよどみつゝ
かすかに肩のもだゆるは
あはれたまゆらひらめきて
朽ちなんいのちかしこにも
われとひとしくうちなやみ
さびしく汽車を待つなるを
この文語詩の下書稿(一)が記されている「王冠印手帳」は、1931年2月~5月頃に使用していたものと推定されており、東北砕石工場技師時代の初期にあたります。
冒頭ですでに賢治は、「せなうち痛み息熱く」ということで、背中の痛みや発熱の徴候が出ています。苦しい体で何とか駅の待合室に入ってくると、「白き羽せし淫れめ」が座っていました。
女性の衣装は「白き羽」と形容されていますが、下書稿(一)では「セキセイインコいろの白き女」となっていて、とにかく何か「鳥」を連想させるような雰囲気があったのでしょう。「おごりてまなこうちつむり」という描写からすると、何か高慢な態度と感じられて、賢治にとって第一印象はあまり良くなかったようです。
あちらのベンチに座る元村長が、かつては「獅子とも虎とも呼ばれ」る猛者だったのに、今は「いとつゝましく汽車待てる」謙虚な様子とは、好対照を成しています。
この後、待合室にいるさまざまな人々が描写されていきますが、最後に賢治の視線は、再び冒頭の「白き羽せし淫れめ」に戻ります。
さっきは高慢な印象もあった女性ですが、しかし今度の描写は、何と繊細で美しいことでしょう。
「はかなげに」目を開いた彼女の瞳は、なぜか暗く澱んでいます。その原因は、「かすかに肩のもだゆる」──呼吸のたびにその肩が細かく上下する──様子に表れていて、おそらく胸の病気に罹っているのでしょう。
それに気づいた賢治の心は、にわかに強く動かされます。彼女の瞳は暗く澱んでいるけれども、「あそこにも(自分と同じく)ひと時だけ閃いて、消えていく命がある!」と気づき、「彼女も私と同じように、病気で苦しみながら、寂しく汽車を待っているのだ」と思いを寄せ、自らと相手を重ね合わせるのです。
このような「自己と対象の一体化」というのは、賢治の作品における重要な特徴で、それは中学生の短歌の時代から際立っていました。そして晩年の文語詩においては、作品中で三人称と一人称を自在に交替させつつ推敲を重ねていく、という特異なスタイルへとつながっています。
この作品でも、待合室でふと見かけた「淫れめ」に対して、思わず「われとひとしく」と一体化してしまっているところを、栗原敦さんは〈共なる「われ」〉と表現しておられたわけです。
またここでは、「淫れめ」を「白き羽せし」あるいは「セキセイインコ」と形容して、「鳥」に見立てているところも、私には興味深く感じられます。「〔われらぞやがて泯ぶべき〕」においては、この世への別れの歌を、作者は「鳥のごとくに歌はんかな」と記していました。彼女は賢治と一緒に亡びの歌を唱う、鳥の仲間なのです。
あるいはまた、生前のトシは「鳥のやうに栗鼠のやうに」と描写され、亡くなってからは白い鳥の幻影として賢治に現れたことも、ここに遠くつながっているのかもしれません。トシもまた胸の病に罹り、女学校時代には悪意のある噂によって、侮蔑を受けた一員です。
ところでこの「〔せなうち痛み息熱く〕」が、文語詩稿 一百篇」の「歯科医院」と、いくつかのモチーフを共有していることについては、信時哲郎さんが『宮沢賢治「文語詩稿 一百篇」評釈』で、指摘しておられます。
「歯科医院」の定稿は、下記のとおりです。
歯科医院
ま夏は梅の枝青く、 風なき窓を往く蟻や、
碧空の反射のなかにして、 うつつにめぐる鑿ぐるま。
浄き衣せしたはれめの、 ソーファによりてまどろめる、
はてもしらねば磁気嵐、 かぼそき肩ををののかす。
こちらは、駅ではなく歯科医院の待合室が舞台ですが、やはりそこに座っている「たはれめ」が描かれます。
彼女がまとう服は、定稿では「浄き衣」となっていますが、下書稿(二)では「白き衣」で、「〔せなうち痛み息熱く〕」の「白き羽」と共通しています。また、こちらで「かぼそき肩ををののかす」となっているのは、「〔せなうち痛み息熱く〕」では「かすかに肩のもだゆる」となっていました。
この「歯科医院」については、栗原敦さんによるぴんと張りつめた評釈を、引用させていただきます。
風も死に、枝ひとつ揺れぬ中を、音なく蟻が往き来する。診察室では軽い圧迫を思わせる治療器具の音。光の中の小さな黒点というべき蟻の動きと鈍く響くその音のために、かえって永遠をも感じさせる真夏の昼の、時の止まったようなひととき。気圏の大きな拡がりの果てでおこる目には見えない何かを感じたかのごとき一瞬、それが良く捉えられている。まどろみつつ診察の順番を待つ清潔な夏の衣の「たはれめ」。しかもその「かぼそき肩」に着目するのは、「たはれめ」の存在としてのはかなさを、いたわりの視線に包んで描いていることを示すと言ってよい。
(栗原敦『宮沢賢治 透明な軌道の上から』p.328)
こちらの作品には、「〔せなうち痛み息熱く〕」のように、自分と「たはれめ」を一体化させてしまうほどの衝迫はありませんが、上の評のように、作者による温かい「いたわりの視線」が印象的です。
さらに、島田隆輔さんが指摘しておられるように、彼女の衣装を「白き衣」から、あえて「浄き衣」とまで昇華させているのも、注目に値します。「たはれめ」は、当時はまだ一般的には蔑まれる存在であったでしょうが、その衣を「浄き」と形容しているのは、『注文の多い料理店』の「序」の一節、「ひどいぼろぼろのきものが、いちばんすばらしいびろうどや羅紗や、宝石いりのきものに、かはつてゐるのをたびたび見ました」とあることも、連想させます。
ここでは、最も粗末な、蔑まれるものが、その対極にある、最も聖なる、清らかなものに、転化しているのです。
※
この世で抑圧され、差別される者は、己に加えられる圧迫をひたすら耐え忍びつつ、自らが弱き者、虐げられた者であることを、嘆くしかありません。
しかし時に、そのような価値基準を全く転倒させるような、新しい価値基準が登場することがあります。新たな基準では、それまで最も弱かった者が強い者へと、最も貧しかった者が富める者へと、価値の逆転が行われるのです。
たとえば、ローマの圧制下にあったユダヤ人の中から、ナザレのイエスが現れ、「心の貧しい人々は、幸いである、天の国はその人たちのものである(マタイ伝5: 3)」と説いた時、それまで底辺にいると思われていた人々が、最も祝福される存在になったのです。
ニーチェは、キリスト教がこのような価値転倒を成し遂げた原動力は、抑圧されていたユダヤ人が抱いていた「ルサンチマン」にあったと考えました。「道徳における奴隷の叛乱はまず、怨恨の念そのものが創造する力をもつようになり、価値を生みだすことから始まる。」(ニーチェ『道徳の系譜学』光文社古典新訳文庫p.43)
ニーチェはこれを「奴隷の道徳」と呼びましたが、キリスト教とその普遍的な「愛」の教えは、その後現在に至るまで、西洋世界の精神的支柱となってきたのです。
初めに述べたように、「〔われらぞやがて泯ぶべき〕」やその他の作品を読むと、病に対する侮蔑や差別に苦しんだ賢治も、そのような世間に対して、一種のルサンチマンを抱いていたように、私には思えます。彼はそれを、表立って声に出すことはありませんでしたが、一部の作品には上のように記し、また自らと同じような弱き者たちに共感し、慈しみ、連帯を念じていました。
晩年の文語詩に、「遊女」や「淫れ女」が数多く登場する様子からは、「徴税人や娼婦たちのほうが、あなたがたより先に神の国に入る(マタイ伝21: 31)」というイエスの言葉も、連想されます。
そしてまた仏教的な視点からは、栗原敦さんが「うられしをみなごのうた」の最後に記しておられる、下記の文も思い起こされます。
若き日の配布物、「いやしい職業の女」「ビンヅマティー」の奇跡を再話した「〔手紙 二〕」が、時を隔ててこれらの「をみなご」にまでたどりついたとも言ってみたいが、ここではただ指摘しておくだけにとどめる他はない。
(『宮沢賢治 透明な軌道の上から』p.340)
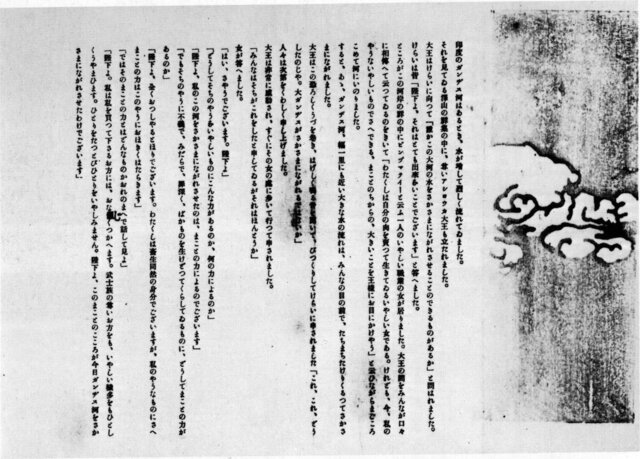
コメント