ほんとうは「『赤光』と『春と修羅』」などという大それたエントリを書いてみたく思ったのですが、到底いきなり手に余るので、とりあえず各々の方法論である(と各々の作者自身が言っている)「写生」と「心象スケッチ」ということについて、考えた事柄を書いてみます。
「写生」は、言うまでもなく正岡子規が、俳句、短歌、散文などの方法論として提唱した概念ですが、近代以降の文学に大きな影響を与えました。その弟子たちによって、「写生」という言葉はさまざまに深められ拡張されていきますが、斎藤茂吉が自らの「写生」の定義を精緻化していくのは、『赤光』の刊行よりも少し後からのことです。
一方、「心象スケッチ」とは、宮澤賢治が独自に考え出し、詩、童話において実践しようとした方法論です。「心象」や「スケッチ」という言葉の各々は、それまでにも使用されていましたが、彼の言うところの「心象スケッチ」は、とりわけ『春と修羅』が世に現れた時には、あまりにも独創的で風変わりなものと思われましたし、もちろんそれを流派として継承する弟子も出ませんでした。
対照的な二つの方法論のようではありますが、この二つの言葉に共通するのは、どちらも「絵画の用語」を文学に輸入したものである、ということです。絵画において、「写生する」ということと「スケッチする」ということは、どちらも対象を忠実に「写す」という行為でしょうが、前者の方がより緻密な作業をイメージさせるのに対して、「スケッチ」というと、より素早く描くという感じはします。賢治が手帳にすごいスピードで文字を書きとめていたという証言を、ちょっと連想させますね。
ただ、文学上の「写生」が、とにかく個人の主観的な歪曲や理屈を排して客観的な記述を推奨したのに対して、賢治の「心象スケッチ」の典型である『春と修羅』を読むと、「客観的」の対極にあるような主観的な描写や、幻想的あるいは超現実的な表現があふれていて、やはり内容も大きく異なったもののように感じられます。
しかしここで面白いのは、宮澤賢治自身は、「心象スケッチ」というのは作者が恣意的に拵えた創作物ではなくて、何らかの対象の「そのとほり」の記録であるということを、繰り返し強調していることです。
彼は、『春と修羅』の「序」においては、
これらは二十二箇月の
過去とかんずる方角から
紙と鉱質インクをつらね
(すべてわたくしと明滅し
みんなが同時に感ずるもの)
ここまでたもちつゞけられた
かげとひかりのひとくさりづつ
そのとほりの心象スケツチです
これらについて人や銀河や修羅や海胆は
宇宙塵をたべ、または空気や塩水を呼吸しながら
それぞれ新鮮な本体論もかんがへませうが
それらも畢竟こゝろのひとつの風物です
たゞたしかに記録されたこれらのけしきは
記録されたそのとほりのこのけしきで
それが虚無ならば虚無自身がこのとほりで
ある程度まではみんなに共通いたします
と書き(強調は引用者)、また『注文の多い料理店』の「序」には、
これらのわたくしのおはなしは、みんな林や野はらや鉄道線路やらで、虹や月あかりからもらつてきたのです。
ほんたうに、かしはばやしの青い夕方を、ひとりで通りかかつたり、十一月の山の風のなかにふるへながら立つたりしますと、もうどうしてもこんな気がしてしかたないのです。ほんたうにもう、どうしてもこんなことがあるやうでしかたないといふことを、わたくしはそのとほり書いたまでです。
と書いています(強調は引用者)。また、岩波茂雄あて書簡(214a)には、『春と修羅』の内容について、
わたくしはあとで勉強するときの仕度にとそれぞれの心もちをそのとほり科学的に記載して置きました。(中略)詩といふことはわたくしも知らないわけではありませんでしたが厳密に事実のとほりに記録したものを何だかいままでのつぎはぎしたものと混ぜられたのは不満でした。
とまで表現しているのです。
すなわち、「写生」も「心象スケッチ」も、絵画における方法論に名を借りつつ、何らかの対象を、「そのとほり」に描写することを目標とするという点で、非常に似ているわけです。
では、似たようなことを標榜しながら、「写生」を旨とする正岡子規やアララギ派の短歌と、「心象スケッチ」による賢治の『春と修羅』の方法論は、どこが違っているのでしょうか。
◇ ◇
まず正岡子規は、「写生」についてたとえば次のように書いています(「叙事文」より)
以上述べし如く実際の有のまゝを写すを仮に写実といふ。又写生ともいふ。写生は画家の語を借りたるなり。又は虚叙(前に概叙といへるに同じ)といふに対して実叙ともいふべきか。更に詳にいはゞ虚叙は抽象的叙述といふべく、実叙は具象的叙述といひて可ならん。要するに虚叙(抽象的)は人の理性に訴ふる事多く、実叙(具象的)は殆んど全く人の感情に訴ふる者なり。虚叙は地図の如く実叙は絵画の如し。地図は大体のの地勢を見るに利あれども或一箇所の景色を詳細に見せ且つ愉快を感ぜしむるは絵画に如く者なし。文章は絵画の如く空間的に精細なる能はざれども、多くの粗画(或は場合には多少の密画をなす)を幾枚となく時間的に連続せしむるは其長所なり。
「理性に訴えるのでなく感情に訴える」ことを目ざす、というわけです。次の文は直接には絵画について述べたものですが、「感情的写生」という言葉が出て来ます(「文学美術評論」より)。
そこで油画が這入つて来ていよいよ写生が完全に出来るやうになつた。此写生は無論感情的写生(理屈的写生といふたのに対していふ)であつて、人が物を見て感ずる度合に従ふて画くから、鯉を画いても鱗を三十六枚画きはせぬ、さりとて東山時代のやうに大きな点を打つて鱗の符牒にして置くのでは無い。それで実物見たやうに出来る。
さらに『俳諧大要』では、次のように述べられます。
主観と客観とを合同して一種非主非客の大文学を製出せざるべからず。主観に偏僻し客観に拘泥するものは、固より其至る者に非ざるなり。(太字部は原文では傍点による強調)
「実際の有のまゝ」と言う一方で、「感情的」であることを肯定し、「主観と客観とを合同」とも言うものですから、子規が亡くなった後に弟子の間でその解釈にニュアンスの相違が出てくるのも無理からぬことに思えます。実際、子規没後3年足らずの1905年に、伊藤左千夫と長塚節の間に起こった「写生をめぐる論争」も、写生において主観はどの程度関与するのかということが中心だったようです。
そんな経過の後、その緻密な論理と、有無を言わせぬほどの実作上の存在感によって、こういった対立を止揚したのが、斎藤茂吉だったと思います。
斎藤茂吉は、1919年「短歌に於ける写生の説」の「第四「短歌と写生」一家言」において、次の有名な写生の定義を記します。
実相に観入して自然・自己一元の生を写す。これが短歌上の写生である。ここの実相は、西洋語で云へば、例へば das Reale ぐらゐに取ればいい。現実の相などと砕いて云つてもいい。自然はロダンなどが生涯遜つてそして力強く云つたあの意味でもいい。この自然の大体の意味を味ふのに和辻氏の文章が有益である。『私はここで自然の語を限定して置く必要を感ずる。ここに用ひる自然は人生と対立せしめた意味の、或は精神・文化などに対立せしめた意味の哲学的用語ではない。むしろ生と同義にさへ解せらる所の(ロダンが好んで用ふる所の)人生自然全体を包括した、我々の対象の世界の名である。(我々の省察の対象となる限り我々自身をも含んでゐる) それは吾々の感覚に訴へる総ての要素を含むと共に、またその奥に活動してゐる生そのものをも含んでゐる』 かう和辻氏は云ふ。予の謂ふ意味の自然もそれでいい。「生」は造化不窮の生気、天地万物生々の「生」で「いのち」の義である。「写」の字は東洋画論では細微の点にまでわたつて論じてゐるが、ここでは表現もしくは実現位でいい。(太字部は原文では傍○)
ここでまず注目すべき点は、「自然・自己一元の生」を写すのが、写生であると定式化しているところです。これは、上に引用した子規の「主観と客観とを合同して一種非主非客の大文学を製出」というところを、より具体的に表現したものとも言えるでしょう。
「写生」だからといって、表現者は対象から距離を隔てた純粋な観察者ではないのですね。「自然・自己一元」となった上での表現だ、というのです。
しかしその際には、いかにすれば表現者が「自然・自己一元」となるのか、ということが問題です。そしてその方法論として茂吉が提示しているのが、「実相に観入して」ということになります。
ここで「実相」というのは、ドイツ語で das Reale と言い換えられていて、これは英語ならば‘reality’として、とりあえず常識的には理解できます。しかし「観入」という言葉が、難しいところですね。
これについて斎藤茂吉自身は、1934年になって書かれた「観入といふ語に就て」という文章の中で、次のように述べています。
なるほど、私の造つた『観入』の熟語は仏典などにある意味その儘ではない。寧ろ独逸の美学や詩論などにある、“Anschauung”といふ語の意味も含んでゐるだらう。併し此の独逸語は、観相とか直観とか翻してゐるものだから、その儘採つて私の歌論に役立たせるには何か足りないところがある。そして、独逸語には“Hineinschauen”といふやうな語もあり、何かさういふところから暗指を得て、私は、『観入』といふ熟語を造つたのであつた。
ここに出てくる“Hineinschauen”とは、日常語としては「のぞき込む」などという意味ですが、“schauen”=「見る」に、“hin-”=「向こうへ」+“ein-”=「中へ」という接頭辞が付加された形になっています。茂吉の文脈で分析的に解釈しなおせば、「自らを対象の方へ向け」・「さらに対象の中に入り」・「見る」、ということになるでしょうか。
この「向こうへ・中へ」ということに関連して、「源実朝雑記」という文章には、次のような箇所があります。
自然を歌ふのは性命を自然に投射するのである。Naturbeseelung である。自然を写生(窪田氏等の用ゐる意味とちがふ)するのは、即ち自己の生を写すのである。
Naturbeseelung とは、「自然に生命を吹き込む」という感じだと思いますが、ここでも自分の生命を「自然に投射する」という、(対象へ向けた)「動き」が重要なようです。そしてこの「動き」こそがさきほどの“hinein-”という接頭辞と対応しており、結局「観入」の「入」という文字に込められているのだと思います。
また斎藤茂吉は、「観入」という行為についてさらに平易に具体的に、次のようにも述べています(「短歌初学門」)。
観入が突嗟にして出来る時があらば、記憶が好い人なら記憶して居るし、記憶の悪い人なら手帳に書きとどめて置く。その時直ぐ表現になる、つまり歌言葉になつたなら、直ちに手帳に書きつけ置く方が便利である。また観入が早く出来ない時には、長いあひだ凝視してゐる。いろいろと視てゐる。さうすると同じ山でもいろいろの処が見えて来る。今まで見えてゐなかつたものがいろいろ様々になつて見えて来る。今までただぼんやりと見えてゐたものが、今度は鮮明に見えて来る、即ち具象化して来る。これが即ち観入である。それだから観入の過程として、集中が必要であるのが無論であるから、人によつては『集中』に主点を置いて、対象集中は即ち自我集中でもあるから、その自我集中体験を以て、観入と同義にいふ人もゐる。それはどちらでも好い。
これを読むと、斎藤茂吉自身は、「観入」とはかなりの程度まで意識的な作業ととらえていたことがわかります。
ここでひとまずまとめると、「実相に観入する」とは、表現者が自らを対象に投げ入れ、そこで「自然・自己一元」の境地を体現しようとする行為のようです。ただし、その「一元」のもとには、和辻哲郎の言葉によれば、「我々の省察の対象となる限り我々自身を含んでいる」のであって、裏を返せば、それを感得し表現する「自己」の別の側面は、ある程度の客観性を持った観察者・表現者として、その外に存在しつづけるということになるのだと思います。
そしてその「観入」の作業は、かなり意識的になされるものだということも、茂吉は言っています。
◇ ◇
さて、それでは賢治の「心象スケッチ」はどうでしょうか。
ここで興味深いことは、賢治もまたその「心象スケッチ」において、茂吉の言葉にいう「自然・自己一元の生」を表現しようとしていたことです。
『春と修羅』の「序」では、
これらについて人や銀河や修羅や海胆は
宇宙塵をたべ、または空気や塩水を呼吸しながら
それぞれ新鮮な本体論もかんがへませうが
それらも畢竟こゝろのひとつの風物です
と述べ、すべてが「こゝろのひとつの風物」であると見なし、また
けだしわれわれがわれわれの感官や
風景や人物をかんずるやうに
そしてたゞ共通に感ずるだけであるやうに
記録や歴史、あるひは地史といふものも
それのいろいろの論料(データ)といつしよに
(因果の時空的制約のもとに)
われわれがかんじてゐるのに過ぎません
として、やはりすべては「われわれがかんじてゐるのに過ぎません」と述べます。ついでにもう一つ例を挙げれば、「銀河鉄道の夜(第三次稿)」でブルカニロ博士が、
ぼくたちはぼくたちのからだだって考だって天の川だって汽車だって歴史だってたゞさう感じてゐるのだから、・・・
と語るところもそうです。
このような世界観は、「すべては仮象である」とする仏教的なそれと共通のもので、もちろん賢治が仏教を信じ学ぶ過程で、このような認識を身につけていった面もあるでしょうが、賢治の成長過程をたどってみると、理屈や信仰によってこういう風に考えるようになったというよりももっと以前から、賢治の中に自然にこういう感じ方が生まれていたように思えます。
いずれにしても、「すべては心象である」と見なすことは、賢治の立場を唯心論的な「一元論」に整理してくれます。
あるいは、佐藤通雅氏は著書『賢治短歌へ』(洋々社)において、賢治の短歌の分析を通じて、短歌においてもやはり「自己と対象の融合」という事態が起こっていることを明らかにしてくれました。(以下強調は引用者)
この転倒が、文学的策略・修辞・技法となるのは、前衛短歌以降である。賢治の場合は、まったく無意識の産物だ。その無意識がどのようにして生じたのか、もういちど75から79へとよみかえしてみると、はじめの段階では作者がいて、岩手山や雲・西火口原・湖などの対象を目の前にしている。しかし77の「あまりに青くかなしかりけり」、78の「みずうみの青の見るにたえねば。」を頂点として、主役は湖自身へと移ってしまう。つまり賢治という主体は後退し、対象との同化がはじまり、ついには両者の境界は視界から消え去ってしまう。(p.83)
赤い傷に痛みをおぼえたのは、なによりも賢治自身だったはずだ。しかし、ほとんど同時に黒板に感情移入してしまっている。その結果、自分と対象との境界はほとんど霧消してしまう。(p.89)
前衛短歌は、近代以後、一人称であるために狭小化した形式を乗り越える方法として、多様な<われ>を設定した。仮構としての、劇としての<われ>を取り込むことによって、格段の自由をえたともいえる。賢治の歌も、そこにいて交叉が可能になった。しかし彼の<われ>の多様性は、方法としてでなく、<われ>そのものを他とおなじ位置に解消させる。(p.180)
賢治の「心象一元論」は、斎藤茂吉が自己を対象の方へ「投入」することによって「自然・自己一元の生」に至ろうとしたことと対照的に、対象を自己の心象の中に「回収」してしまうことによって、結果的に「自然・自己一元の生」となっているわけです。すなわち、二つの方法論はまるで逆を向いたベクトルのようでもあります。
また、佐藤通雅氏の指摘するように、賢治がこのような形で表現活動をしているのは、意識して特異な方法をとろうとしたのではなく、「無意識」のうちにそういう体験をしているところも、茂吉の意識的な「観入」と異なっています。
賢治が「自然・自己一元の生」を、その最も感動的な形で体感し、表現したものとして、「種山ヶ原(下書稿(一))」の中の次の一節があります。
雲が風と水と虚空と光と核の塵とでなりたつときに
風も水も地殻もまたわたくしもそれとひとしく組成され
じつにわたくしは水や風やそれらの核の一部分で
それをわたくしが感ずることは水や光や風ぜんたいがわたくしなのだ
この恍惚とした体験は、「種山ヶ原の情景を詩にしよう」と意識して招来されたものではなく、作者が種山ヶ原を歩いていた時に、どうしようもなく彼を捉えて放さなかった自然との一体感であり、作者にとっては受動的・無意識的に訪れたものだったのでしょう。
◇ ◇
ということで、斎藤茂吉の「写生」=「実相観入」と、宮澤賢治の「心象スケッチ」を検討してみましたが、これをわかりやすくするために(?)、ちょっと図式化してみます。
援用させていただくのは、以前にも「「心象」の体験線モデル」という記事においてご紹介した、安永浩氏の「ファントム空間論」です。
まず、下のような「体験線」と呼ばれる簡単な図が基本となります。
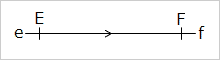
図の左端の「e」は、「自極」と呼ばれ、すべての「私は…」という体験の出発点を表します。これは一つの極限概念で、形もなければ広がりもない、幾何学上の「点」のようなものとされます。またこの点は脳のどこかに定位できるようなものでもなく、あくまで「私」の体験出発点としての、理念的な場所です。
この「e」から右へ矢印が出ていて、これは「自」から「他」へ、「主体」から「対象」へ向かう方向を表しています。おそらくフッサールの現象学における「志向性」という概念はこの矢印に相当し、このことから安永氏は「e」のことを、「現象学的自極」と呼んだりもします。
一方、右端にある「f」は、「対象極」と呼ばれ、ちょうどカントの言う「物自体」に相当します。「他」なるものの理論的な極限点で、これそのものは主体にとって直接に体験できるものではありません。人間は、生物学的に与えられた視覚や聴覚や触覚などの感覚器官を通じて世界を体験できるだけであり、我々が「世界」と思っているのは、そのような特定の体験手段によって構成された世界の「図式」にすぎません。
というわけで、その少し左にある「F」が、そのようにして構成された「対象図式」を表しています。これは「f」よりも少し手前に位置していますが、これはこの場所に、主体が対象を認識する「知覚像」が定位されることを表しています。
また、「e」の少し右には、「E」という記号があります。これは「自我図式」と呼ばれ、対象化された構成物としての「私」です。私は私自身の「感覚」も「感情」も「考え」も「身体」も、それぞれ認識することができ、言い換えれば私は私自身をも一つの対象としてとらえることができます。このように「認識される自己」が定位される場所が、「F=自我図式」であるというわけです。
ウィリアム・ジェイムズは、自らを意識する主体としての「われ」=「主我」と、客体として意識される「われ」=「客我」を区別しました。この用語にあてはめれば、「e」が「主我」、「E」が「客我」ということになります。
以上が、「体験線」というものの一般的な説明ですが、まずこの図式を用いて、斎藤茂吉の言う「写生」=「実相観入」とはどのように表せるかということを、考えてみます。
「観入」とは、自己(の生)を、対象に「投射する」、あるいは、対象に向かい、入り、見るということでした。投げ入れらた結果、自然と一元化する「自己」とは、和辻哲郎の説明によれば「我々の省察の対象となる限り」の「我々自身」ということですから、「体験線」においては「自我図式=E」に相当します。
「E」が「F」に向かって投入され、一体化するというのですから、下のような事態として図式化することができるでしょう。
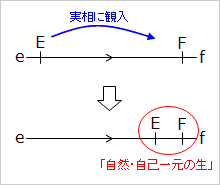
斎藤茂吉も一人の「天才」として、このような「自然・自己一元の生」を、意識的というよりも対象に即して直観的に把握していたのだと思いますが、彼の歌論を見るかぎりは、「実相観入」とはかなり能動的で意識的な営為であるように読めます。
いずれにせよ、観入によって自己(E)と自然(F)が一体となった境地を、表現者である「e」が、「観る」わけです。
一方、賢治の「心象スケッチ」における「自他の融合」は、もっと無意識的で受動的に起こるものだったようです。
融合に至る一つの要素として、「自己の拡大」というべき事態があることは、たとえば「林と思想」(『春と修羅』)という作品から見てとれます。
そら ね ごらん
むかふに霧にぬれてゐる
蕈のかたちのちいさな林があるだらう
あすこのとこへ
わたしのかんがへが
ずゐぶんはやく流れて行つて
みんな
溶け込んでゐるのだよ
こゝいらはふきの花でいつぱいだ
ここでは、作者の「自我図式」の内にあるはずの「わたしのかんがへ」が、「対象図式」に位置する向こうの林に流れて行って溶け込んでいる、というのです。
これに対して、融合を引き起こすもう一つの要素としては、逆に対象図式が自己の方へと迫り近づいてくるという事態もあるようです。
これはたとえば、「小岩井農場」(『春と修羅』)パート九に出てくる、
《幻想が向ふから迫つてくるときは
もうにんげんの壊れるときだ》
という言葉にも表れていると思いますし、また「〔その恐ろしい黒雲が〕」(「疾中」)における、
その恐ろしい黒雲が
またわたくしをとらうと来れば
わたくしは切なく熱くひとりもだえる
北上の河谷を覆ふ
あの雨雲と婚すると云ひ
森と野原をこもごも載せた
その洪積の台地を恋ふと
なかばは戯れに人にも寄せ
なかばは気を負ってほんたうにさうも思ひ
青い山河をさながらに
じぶんじしんと考へた
あゝそのことは私を責める
病の痛みや汗のなか
それらのうづまく黒雲や
紺青の地平線が
またまのあたり近づけば
わたくしは切なく熱くもだえる
という箇所も、自然が自分に迫り、呑み込まれそうになる感覚が描かれています。自然の方から自分に接近してくるという体験は、「わたくしは森やのはらのこひびと」(「一本木野」)として、賢治にかぎりない喜びをもたらしてくれるものでもありましたが、時には恐ろしいものでもありました。
このように、自己の拡大、対象の切迫という二つの要因によって、自己と自然の一体化が起こる状況は、次のように図式化してみることができます。
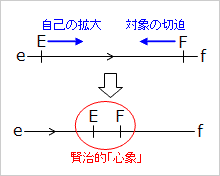
ここでも、結果的には「実相観入」と同様に、「E」と「F」が近接することによって、「自然・自己一元の生」という体験が現れるのです。ただし、これは私の思うところでは賢治の生来の素質によるところが大きく、意図的に行うのではなくて受動的に没入してしまうということだったのではないかと、感じています。
◇ ◇
以上、茂吉の方法論としての「写生=実相観入」と、賢治の方法論としての「心象スケッチ」が、似たようでもありまるで異なっているようでもあるのが興味深かったので、私なりに少し比較検討してみました。
なお、「体験線」という図式については、安永浩氏ご自身による「O.S.ウォーコップの次世代への寄与」という Web ページにおいて触れられていますので、関心がおありの方はご参照下さい。
それとやはりそのうちにいつか、「『赤光』と『春と修羅』」ということについても、考えてみたいと思っています。

斎藤茂吉記念館
rinrin
岩手山の碑のところ
まで行く事が出来ましたので
私のブログに
リンクさせて頂きました
hamagaki
rinrin 様、リンクをありがとうございます。
ブログを拝見しましたが、岩手山の麓はもう美しい紅葉なんですね。
虹も架かって、ご家族の楽しいご旅行の様子が伝わってくるようなお写真でした。
賢治の歌碑は、変わらず健在ですね。