先日ご紹介したように、佐藤通雅氏は『賢治短歌へ』において、賢治の短歌がふつうの<一人称詩>から独特の「ふみはずし」をしているという特徴を指摘し、それを眼球で網膜に像が結ばれない状態などに喩えて説明をしておられました。
この本を読みながら、私はまた別の説明モデルを考えてみました。
安永浩という精神病理学者がおられて、1970年代から1980年代にかけて、「ファントム空間論」などの独自の理論を発表し、注目されていました。(現在 Web 上では、「O.S.ウォーコップの次世代への寄与――「パターン」、「パターン逆転」、「ファントム空間論」――」というページにおいて、その一端を見ることができます。)
こ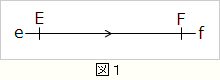 の安永浩氏はかつて、「体験線」と呼ぶところの一本の右向きの矢印(図1)を描いて、人間の体験を説明しました。(この図は上の Web ページでも、「図5」として出てきます。)
の安永浩氏はかつて、「体験線」と呼ぶところの一本の右向きの矢印(図1)を描いて、人間の体験を説明しました。(この図は上の Web ページでも、「図5」として出てきます。)
図の左端の「e」は、「自極」と呼ばれ、「私は~」という体験の出発点を表します。これは一つの極限概念で、形もなければ広がりもない、幾何学上の「点」のようなものとされます。脳のどこかに定位できるようなものではなく、あくまで「私」の体験出発点としての、理念的な場所です。
この「e」から右へ矢印が出ていて、これは「自」から「他」へ、「主体」から「対象」へ向かう方向を表しています。おそらくフッサールの現象学における「志向性」という概念はこの矢印に相当し、このことから安永氏は「e」のことを、「現象学的自極」と呼んだりもします。
一方、右端にある「f」は、「対象極」と呼ばれ、ちょうどカントの言う「物自体」と同じく、「他」なるものの理論的な極限点です。これは、主体にとって直接に体験できるものではなく、その少し左にある「F=対象図式」を通して、はじめて認識が可能となります。私たちは外界を、あくまで視覚・聴覚などの感覚を通じて、各自の神経系が構築した「像」として対象を認識しているわけですが、その「知覚像」が構成される場所が、「F」であるというわけです。
また、「e」の少し右には、「E」という記号があります。これは「自我図式」と呼ばれ、対象化された実体としての「私」です。人間は、自分自身をも対象としてとらえることができるので、ウィリアム・ジェイムズは、自らを意識する主体としての「われ」=「主我」と、客体として意識される「われ」=「客我」を区別しました。これに従えば、主我が「e」、客我が「E」ということになります。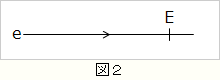
「図1」の左端の部分を拡大すると、「図2」になり、この矢印は、主体(=e)が「自分自身(と感じるもの)=E」を認識するという事態を表していることになります。
「図3」は、通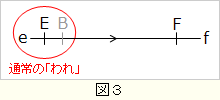 常の場合に一般に「われ」として体験される部分を、赤く囲って示しています。「B」という記号で示しているのは、自らの「身体」です。「体験線」の図で身体は、自我図式 Eよりも外に、すなわち体験線の下流に位置づけられます。「われ」と言う時に、身体を意識して含めている場合とそうでない場合があるかもしれませんので、これは薄いグレーで示してあります。
常の場合に一般に「われ」として体験される部分を、赤く囲って示しています。「B」という記号で示しているのは、自らの「身体」です。「体験線」の図で身体は、自我図式 Eよりも外に、すなわち体験線の下流に位置づけられます。「われ」と言う時に、身体を意識して含めている場合とそうでない場合があるかもしれませんので、これは薄いグレーで示してあります。
さて以上は、安永浩氏が「体験線」というモデルによって述べておられる事柄を、私なりに要約したものでした。
次に、賢治が短歌の一部や「心象スケッチ」において描いている「心象」なるものを、私がこの模式をもとに表してみたのが、「図4」です。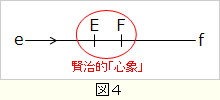 「自我図式 E」は、異様に拡散し、通常よりもかなり右の方に位置しています。一方、「対象図式 F」は、異様に「われ」に接近し、通常よりもそうとう左に位置しています。結果として、E と F が接近してしまい、結局この両者を一括りにして主体 e が体験するのが、賢治的な意味における「心象」であると言えるのではないでしょうか。
「自我図式 E」は、異様に拡散し、通常よりもかなり右の方に位置しています。一方、「対象図式 F」は、異様に「われ」に接近し、通常よりもそうとう左に位置しています。結果として、E と F が接近してしまい、結局この両者を一括りにして主体 e が体験するのが、賢治的な意味における「心象」であると言えるのではないでしょうか。
『賢治短歌へ』において佐藤通雅氏が用いた表現を使えば、「賢治という主体は後退し、対象との同化がはじまり、ついには両者の境界は視界から消え去ってしまう」=「自分と対象との境界はほとんど霧消してしまう」=「<われ>そのものを他とおなじ位置に解消させる」・・・、このような事態は、「体験線」において模式的には、「E と F の接近」として表すことができるでしょう。
もちろん、賢治の多くの作品においても、「自」と「他」がまったく同一化しているわけではなく、上の図のように E と F は一応の距離は保っています。しかし、たとえば短歌で言えば、
299 星群の微光に立ちて
甲斐なさを
なげくはわれとタンクのやぐら。
のように、「われ」と「タンクのやぐら」の感情が並列されたり、口語詩で言えば、
そら、ね、ごらん
むかふに霧にぬれてゐる
蕈のかたちのちいさな林があるだらう
あすこのとこへ
わたしのかんがへが
ずゐぶんはやく流れて行つて
みんな
溶け込んでゐるのだよ
というふうに「わたしのかんがへ」が林に溶け込んだり(「林と思想」)、通常なら自分の内的現象と感じられる事柄と、外的な事柄が接近して、相互の境界があいまいになっているのです。
さらに、
雲が風と水と虚空と光と核の塵とでなりたつときに
風も水も地殻もまたわたくしもそれとひとしく組成され
じつにわたくしは水や風やそれらの核の一部分で
それをわたくしが感ずることは水や光や風ぜんたいがわたくしなのだ
という「種山ヶ原(下書稿(一)」に至っては、E と F はほとんど一体となって溶け合っているとも思えます。
すなわち、E と F の相対的な位置は、賢治においてもさまざまに揺れ動いているようなのです。
最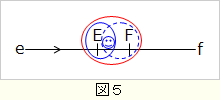 後に、賢治の作品にしばしば現れる「幻聴」というものについても、このモデルをもとにして考えてみることができます。
後に、賢治の作品にしばしば現れる「幻聴」というものについても、このモデルをもとにして考えてみることができます。
「図5」がそれですが、この図で自我図式 E のすぐ右にある ![]() という記号は、主体の心の中における無意識的な考えや言葉を表しているとします。これは、図において青い実線により E と一緒に囲まれているごとく、本来ならば自我図式のもとにあるはずのものです。しかし、賢治的「心象」においては、対象図式 F がすぐ近くまで来ているために、青い点線のように、対象図式に組み込まれて知覚されてしまう可能性が出てきてしまうのです。
という記号は、主体の心の中における無意識的な考えや言葉を表しているとします。これは、図において青い実線により E と一緒に囲まれているごとく、本来ならば自我図式のもとにあるはずのものです。しかし、賢治的「心象」においては、対象図式 F がすぐ近くまで来ているために、青い点線のように、対象図式に組み込まれて知覚されてしまう可能性が出てきてしまうのです。
そうなると、この「考え」や「言葉」は、自分の中からではなくて外部の対象から由来しているように感じられてしまうことになり、すなわち、「幻聴」として体験されるというわけです。
のぶ
おじゃまします。
斉藤環氏の『キャラクター精神分析』という本に安永浩氏のこの図のことが書かれていて、まったく理解できずに困っていたところ、この記事にたどり着きました。
非常にわかりやすく解説されており、理解が深まりとても助かりました。
感謝の言葉を伝えたくてコメントを残します。
ありがとうございました
hamagaki
のぶ様、書き込みをありがとうございます。
安永浩氏の「ファントム空間論」は、統合失調症など種々の精神疾患における認知の歪みを、「幾何学的」に整理しようとした壮大な試みで、ここに私が勝手に引用したのはその「はしり」の部分に過ぎませんが、少しでもお役に立てたのでしたら幸いです。
しかしこのたび、最近でも「ファントム空間論」を論じている本があると教えていただいて、私もうれしかったです。
斉藤環氏の『キャラクター精神分析』、さっそくアマゾンに注文しました。
今後とも、よろしくお願い申し上げます。
さい
客我がよくわかりません。教えて頂けますか?
わたしがわたしを意識する。日常生活でどういう場面で起こるのでしょうか?
hamagaki
さい様、こんばんは。拙文をお読みいただきましてありがとうございます。
これは、認識する主体としての我(主我)が、認識される客体としての我(客我)を認識するということで、ごく日常的な例としては、たとえば自分で自分の状態を振り返ってみて、「今日の自分は何となく集中力が落ちているなあ」と意識する、というようなことです。
英語で言えば、主我が「I」、客我が「me」に相当します。
さい
ご返信ありがとうございます。よく理解できました。
心の哲学を調べていると、こちらのサイトにたどり着きました。ファントム理論とは、興味深い理論ですね。はじめて知りました。
わたしは、哲学、心理学に疎いです。また、質問させていただくことがあるかと思いますが、よろしくお願い致します。
さい
ファントム理論の基礎を理解するために、適当な入門書をご紹介いただけますか?
ウォーコップのものの考え方、でしょうか?
hamagaki
さい様、こんにちは。
安永浩氏によるファントム空間論に関する著作としては、1977年にまず『ファントム空間論―分裂病の論理学的精神病理』が出版されました。
これは、統合失調症の精神病理学として書かれた精神医学専門書ですが、この理論を人間の精神一般に敷衍しつつ、さほど精神医学の専門用語を使わずに書かれたのが、1987年の『精神の幾何学』です。
当初の『ファントム空間論』は絶版となっていましたが、1992年に『安永浩著作集』の第1巻として再刊され、またその後の関連論文が、同著作集の第2巻『ファントム空間論の展開』として出版されました。
上記は、いずれも絶版になっていますが、ネットで古本は手に入ります。
ファントム空間論そのものを理解するためには、やはり『安永浩著作集 第1巻』を読む必要があるでしょうが、一般向けの入門としては、まず『精神の幾何学』がよいのではないかと思います。
なお、ウォーコップの『ものの考え方』は、ファントム空間論の着想の元になった風変わりな哲学書で、私は個人的には大好きなのですが、これにはファントム理論そのものは書かれていません。
さい
ご回答ありがとうございます。
精神の幾何学、図書館で借りてみます。
ところで、ウォーコップの二元論が、たんなる対称的主観-客観図式でないことに、興味を引かれました。心を考察する、良いテキストとなりますか?
はじめて知った哲学者で、これという情報もありません。これも図書館で借りるしかないのですが。
hamagaki
さい様、こんばんは。
ご指摘のように、ウォーコップの哲学の面白いところの一つに、「パターン」という考え方があります。
「右と左」、「男と女」のような「対称的」な対概念とは異なって、たとえば「生/死」、「全体/部分」、「質/量」、「精神/物質」、「主観的/客観的」というような「対」は、実は対称的ではなくて、この例では前者の方が根源的・主導的で、後者の方が従属的な立場にあることをウォーコップは指摘し、彼はこのような対のことを「パターン」と呼びました。
そして、人間も含めた生物の行動を、「生きた行動」(無目的的なエネルギーの発露)と「死を回避する行動」(広い意味で死を避けるために取る行動で、生活のために仕事をしたり受験勉強をしたりすることもこれに入る)に分けてみると、これも彼の言う「パターン」を成していて、しかも「生きた行動」の方が「死を回避する行動」よりも、根源的・本質的なものであるのだと言うところが、彼の面目躍如です。
これが、一つの壮大な「生命観」「人生観」ともなって、私たちに明るい光を投げかけてくれる感じなのです。
安永浩氏の『精神の幾何学』の第一部は、「ウォーコップ註釈」と題されて彼の哲学の簡明な要約になっているので、これを読まれたら、ウォーコップ入門にはほぼ十分だろうと思います。
さい
いろいろお世話になります。
先日、精神の幾何学、図書館にて予約しました。
実存的に行き詰まっており、なんとか乗り超えなければなりません。本当にありがとうございました。
あん
大変勉強になりました。 ありがとうございます。
特に、幻聴の、自我一対象図式の接近により無意識が対象のそれと曖昧に把握されるという説明。これは、ドイツロマン主義などの、自然と人間が無意識を共有しているというような世界観に、分かりやすい図式を与えているものだと思いました。
ありがとうございます
hamagaki
さい様、お久しぶりです。
『精神の幾何学』が、何らかのお力になることを、お祈りしています。
あん様、コメントをありがとうございます。
E(自我図式)が対象の方向へと拡大し、F(対象図式)が自己に接近してくるという状態は、上記のように宮沢賢治にも特徴的だと思いますが、一般的にはロマン主義的な思潮だろうと思います。
まさに「自然と人間が無意識を共有している」という感じですね。
貴重なご意見をありがとうございました。
あん
大変勉強になりました。 ありがとうございます。
特に、幻聴の、自我一対象図式の接近により無意識が対象のそれと曖昧に把握されるという説明。これは、ドイツロマン主義などの、自然と人間が無意識を共有しているというような世界観に、分かりやすい図式を与えているものだと思いました。
ありがとうございます