余命あと1ヵ月となった1933年8月、病床の賢治は「文語詩稿 五十篇」と「文語詩稿 一百篇」の清書を終えました。彼は出来上がった原稿を大事にそれぞれのケースに収め、「なっても駄目でも、これがあるもや」と家族に言い、ケースの表書きには、生涯でただ1度だけ、「定稿」という言葉を書き込みました。
この2束の「定稿」に対する彼の思い入れの在り処に関しては、これまでも研究者によってさまざまに論じられていますが、素人の私などが見てまず外形的に最も目立つ特徴は、ほとんどの作品テクストに共通している、独特の行配置です。
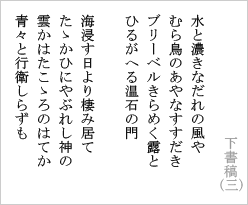 それは、たとえば先月にここで言及した「〔水と濃きなだれの風や〕」という作品を例にとれば、右のようなものです。
それは、たとえば先月にここで言及した「〔水と濃きなだれの風や〕」という作品を例にとれば、右のようなものです。
定稿の直前の「下書稿(三)」では、ふつうのごく一般的な「詩」と同じく、各行は右から左へ、順々に並べられていきます。
これに対して「定稿」では、内容にはさほど大きな変更はないのですが、行の配列の仕方に、大胆な改変がなされます。下書稿において横に並べられて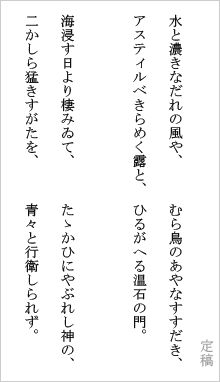 いた1行目と2行目は縦に並べられ、3行目と4行目以下も同様です。(右図)
いた1行目と2行目は縦に並べられ、3行目と4行目以下も同様です。(右図)
この時、もとの偶数行目は、上の詩句から「一定間隔を置いて」書かれるのではなく、すべて「頭を揃えて同じ高さから」書き出されています。
さらに、行と行の間隔に関しても、通常の割り付けとは意識的に区別するかのように、大きな詩稿用紙の一面全体を使って、ゆったりと配置されます。
言ってみれば、下書稿において詩句はただ横方向に、一次元的に配列されるだけだったのに対して、定稿においては、それは縦と横と2つの方向性を持って、二次元的に展開されるのです。その配置の仕方は、たとえば数学の「行列(マトリックス)」を連想させます。
ここにおいて彼の「詩」は、形態的な面においても、より「構造性を高めた」と言えると思います。五・七または七・五の音数律を持った各構成要素は、単純に横に並べられるのではなく、平面上の縦・横に、ある規則性を持って配置されるようになったのです。
たとえば鉱物が結晶化する時、全体の硬度を増すとともに原子の配列は立方体や正八面体など幾何学的な構造をおのずから形づくるように、賢治の文語詩も「定稿」となった時、その内容の比類なき密度とともに、形式においても独特の均整のとれた「型」を獲得したのです。
つねづね私は、賢治の文語詩定稿に見られるこのような「マトリックス型」の詩句配置の由来は、いったいどこにあるのだろうかと、気になっていました。彼が遺した厖大な草稿群を見ても、このような構造は最後の夏の「文語詩稿 五十篇」「文語詩稿 一百篇」において、ほぼ突然に現れます。彼自身がそれまでに試行錯誤を重ね、徐々に形成してきたという様子ではないのです。
すなわち、この「型」は賢治が一人で考え出したというよりも、何らかの下敷きになる原型がすでに存在していて、彼は最後の夏に思い立ってそれを定稿の清書に「採用」したのではないかと、私は感じたりもしていたのです。
その原型の候補として、近代以降の韻文の中では、1882年(明治15年)に刊行された『新体詩抄』のテクストが、まず目につきます。
たとえば、『新体詩抄 初編』の最後に収められている「春夏秋冬」という詩は、賢治の文語詩定稿と同じように、一つの行が前半と後半の2つの節に分かれていて、後半の節は同じ高さから頭を揃えて記され、3行ずつが一まとまりをなすという「構造」になっています。こちらからは、国会図書館の「近代デジタルライブラリー」に収められたその画像が見られますので、ご参照ください。
また、よく似た詩句配置は、大正時代の中勘助の詩の一部にも見られます。しかしいずれにしても、賢治のように2行ずつが組になった定型とは、なかなか一致するものではありません。
そんな折にたまたま私は、瓜生津隆真著『龍樹―空の論理と菩薩の道』(大法輪閣)という本をぼんやりと眺めていて、下のようなテクストを目にしました。
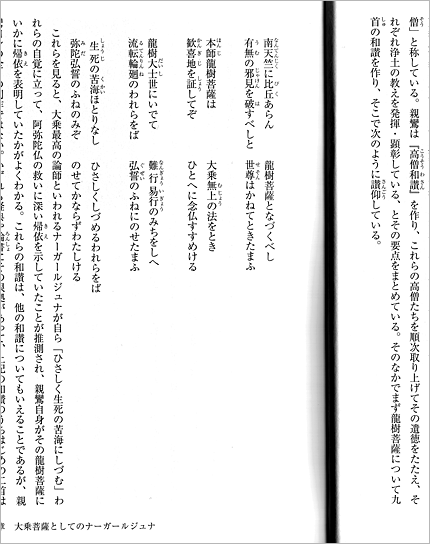
上に引用されている8行の詩句は、親鸞が書いた『高僧和讃』の一部です。それは、「七+五」×2(上下)が1行をなし、それが2行で1組、さらにそれが4組並んでいる、という構成です。これはちょうど、「文語詩稿 五十篇」ならば、「〔月のほのほをかたむけて〕」、「流氷(ザエ)」 、「雪の宿」、「〔川しろじろとまじはりて〕」などの作品と、まったく同じ形になっているではありませんか。
そして、親鸞の書物ならば、父が浄土真宗の篤信家であった賢治の家にはほとんど全てが所蔵されており、彼もきっと物心ついた頃から目にしていたはずなのです。
[次回につづく・・・]
コメント