十代半ばまでの宮澤賢治は、家の宗派であった浄土真宗を深く信仰していて、16歳の時には父あての書簡の中で、「小生はすでに道を得侯。歎異抄の第一頁を以て小生の全信仰と致し侯。」(書簡6)という宣言までしていました。3歳頃には、「正信偈」や「白骨の御文章」を暗誦していたという逸話が残っている賢治ですが、きっと「歎異抄」にも馴れ親しんでいたことでしょう。
そんな賢治が、少なくとも1918年2月には、浄土真宗から離れて完全に法華経にはまり込んでいたことが、父あての「書簡44」や「書簡46」から見てとれます。そして、死の当日に父に伝えたという遺言も、「国訳妙法蓮華経を千部作って配って下さい」というものでしたから、その信仰は死ぬまで変わらなかったと言えるでしょう。
しかし、このように法華経や日蓮に深く帰依し続けていた賢治の信仰心や思想に、実は「浄土真宗的」な要素が分かちがたく結びついていたということを、松岡利夫著『宮沢賢治と法華経 日蓮と親鸞の狭間で』という本は詳しく分析してみせてくれていますし、私自身も以前に「けつしてひとりをいのつてはいけない」という記事などで触れました。
上記の私の記事で取り上げたのは、「青森挽歌」に突如として出現する《みんなむかしからのきやうだいなのだから/けつしてひとりをいのつてはいけない》という命題は、「歎異抄」において親鸞が言ったとされる、次の言葉をルーツに持っているのではないか、ということでした。
親鸞は、父母の孝養のためとて、一返にても念佛まふしたることいまださふらはず。
そのゆへは、一切の有情は、みなもつて世々生々の父母兄弟なり、いづれもいづれも、この順次生に、佛になりて、たすけさふらうべきなり。 (『歎異抄』第五条より)
すなわち、親鸞は父母への孝行のために念仏を唱えたことは一度もない、なぜなら一切の生き物は皆、輪廻転生のうちには自分の父母兄弟だったこともある存在なので、この次の生で(自分が死んで浄土に生まれて)仏になってから、あらためて皆をお救いするべきだからだ、というのです。
ここで親鸞は、父母兄弟のことを「いのつてはいけない」と禁止まではしていませんが、少なくともそれは無意味なことだと見なしています。現代の浄土真宗は、おそらくここまで潔癖な態度はとっておらず、他の宗派と同じように亡くなった方のための「法事」も執り行っているのでしょうが、この親鸞の言葉は今の日本人の感性とは一線を画しているので、とても印象的です。
一方、賢治がこの頃も信じていたはずの日蓮は、近親者を亡くした遺族が故人の死後の幸いを祈るのは当然のことであり、またそれは善いことでもあると言い、大いに行うよう積極的に勧めていました。ですから、「けつしてひとりをいのつてはいけない」という命題は、日蓮の考えとは異なっているのです。
前掲の松岡利夫著『宮沢賢治と法華経 日蓮と親鸞の狭間で』によれば、日蓮にも「六道四生の一切衆生は皆父母也」という言葉があり(「法蓮抄」)、やはりすべての生き物が父母であったということは述べていますが、賢治は「みんなむかしからのきやうだい」と書いているところを、日蓮は「父母」だけを挙げているのに対して、親鸞は上記のように「父母兄弟」としています。したがって松岡利夫氏は、「青森挽歌」のこの箇所は日蓮ではなく親鸞の影響を受けたものであろうと、推断しておられます。
※
そして今日ふと思ったのは、「青森挽歌」の翌日に書かれた「宗谷挽歌」の、次の箇所についてです。
われわれが信じわれわれの行かうとするみちが
もしまちがひであったなら
究竟の幸福にいたらないなら
いままっすぐにやって来て
私にそれを知らせて呉れ。
みんなのほんたうの幸福を求めてなら
私たちはこのまゝこのまっくらな
海に封ぜられても悔いてはいけない。
詩の前半部によれば、稚内からサハリンへ向かう連絡船の甲板に立っている賢治は、もしもトシがどこからか自分を呼ぶ声が聞こえたら、「私はもちろん落ちて行く」という決心を固めています。
何のためにトシが賢治を呼ぶのかというと、トシが死んだ結果、「われわれが信じわれわれが行かうとするみち」、すなわち法華経が、「まちがひ」であったと判明したならば、その事実を「まっすぐにやって来て/知らせて呉れ」というわけです。
この理屈に立つならば、トシが賢治のもとにやって来て再会すること、あるいは会えないまでも二人で通信をかわすことは、「ひとりをいのる」行為に伴うものではなく、現世で法華経を信仰している人すべてにその誤りを伝えるための行いであり、すなわち「みんなのほんたうの幸福を求めて」の行為なのですから、「青森挽歌」でもたらされた上記の啓示には違反しません。
しかし、この「理屈」を皆さんはどう評価されるでしょう。確かに、一応の筋は通っていますが、でもその理屈の皮を一枚めくれば、とにかくトシと会いたい、声を聞きたい、という肉親の愛情に基づいた賢治の本心が、ありありと見えてしまうように、私には感じられます。「ひとりをいのつてはいけない」との制約を自らに課しながら、それでもなおトシと会いたい一心で構築した、綱渡りのごとき論理のように、私には思えるのです。
いずれにせよ、もしもトシが、夜の船上にいる賢治にそのようなことを知らせてくれたら、賢治は「もちろん落ちて行く」という覚悟を決めていて、そして海中に沈む賢治とトシの二人=「私たち」は、「このまゝこのまっくらな/海に封ぜられても悔いてはいけない」と、自らに言い聞かせています。
私がふと感じたのは、この「私たちはこのまゝこのまっくらな/海に封ぜられても悔いてはいけない」という箇所は、これも「歎異抄」の次の部分と、どこか似ているのではないか、ということです。
念仏は、まことに、浄土にむまるるたねにてははんべらん、また、地獄におつべき業にてははんべるらん。惣じてもって存知せざるなり。たとひ、法然聖人にすかされまひらせて、念仏して地獄におちたりとも、さらに後悔すべからずさふらう。 (『歎異抄』第二条より)
念仏というものが、浄土に生まれる契機になるのか地獄に落ちる罪業になるのか知らないが、たとえ法然上人に騙されて地獄に落ちたとしても、何ら後悔すべきではない、と親鸞は言うのです。
賢治が封ぜられるのは、まずは「このまっくらな海」ですが、地獄にいて苦しんでいるトシのもとに行くのですから、最終的にはやはり地獄です。そして、地獄に落ちる理由は、賢治とトシも、法然と親鸞も、どちらも「信仰が間違っていたから」ということで共通しています。
後悔すべきでない理由は、賢治の場合は「みんなの幸福」のためだから、親鸞の場合は「他に方法がないから」、ということで異なっていますが、トシと再会できる賢治と同様に、きっと親鸞は地獄で法然に会えるでしょう。
親鸞が法然から直に教えを受けられたのはわずか6年のことで、承元元年に法然は讃岐へ、親鸞は越後へと流罪になり、これが二人の今生の別れとなりました。「歎異抄」では上の箇所に続いて、「地獄は一定すみかぞかし」という有名な一節が出てきますが、トシのもとへ行く賢治と同じく親鸞にとっても、「お慕いする法然上人と一緒なら、たとえ地獄でも・・・」という気持ちがあったのかもしれません。
ということで、この二つの状況にはある種の共通点を感じ、私としては「青森挽歌」のみならず翌日の「宗谷挽歌」においても、賢治の深層意識からは、むかし親しんだ「歎異抄」の思想や言葉が、思わずにじみ出てきていたのではないか、という気がするのです。
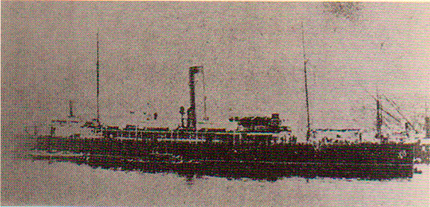
「宗谷挽歌」において賢治が乗船していたと推測される「対馬丸」
(萩原昌好著『宮沢賢治「銀河鉄道の夜」への旅』より)
コメント