先月に私は、「悩みの果てに「いゝこと」と感じる」という変な題名のエントリにおいて、「小岩井農場」や「薤露青」に表れた賢治の思いを、「逆説的で不思議な感情」あるいは「珍しい感じ方」と書きました。
しかし、あらためてゆっくり考えてみると、私自身の奥底にも、この「感じ方」に何となく共鳴できる部分があるんですね。ひょっとしてこれは、さほど「逆説的」で「珍しい」感情ではなくて、どこか人間にとって普遍的な性質も帯びているのではないかとも思ったのですが、皆さんはいかがお感じでしょうか。
とりあえず、それについて考えてみるのが今回の趣旨です。
まず、先日の当該記事で引用した作品部分を再掲しておきます。
一つは、『春と修羅』の「小岩井農場」「パート一」で、賢治が小岩井駅で汽車を降りた後、農場まで馬車に乗ろうかどうしようかと迷う箇所です。
これはあるひは客馬車だ
どうも農場のらしくない
わたくしにも乗れといへばいい
馭者がよこから呼べばいい
乗らなくたつていゝのだが
これから五里もあるくのだし
くらかけ山の下あたりで
ゆつくり時間もほしいのだ
(中略)
そこでゆつくりとどまるために
本部まででも乗つた方がいい
今日ならわたくしだつて
馬車に乗れないわけではない
(あいまいな思惟の蛍光
きつといつでもかうなのだ)
もう馬車がうごいてゐる
(これがじつにいゝことだ
どうしやうか考へてゐるひまに
それが過ぎて滅くなるといふこと)
結局、賢治があれこれ考えているうちに馬車は動き出してしまって、乗ることはできなかったのですが、賢治はここで残念がったりすることもなく、「これがじつにいゝことだ」と受け容れるのです。
そしてもう一つは、「春と修羅 第二集」の「薤露青」です。
声のいゝ製糸場の工女たちが
わたくしをあざけるやうに歌って行けば
そのなかにはわたくしの亡くなった妹の声が
たしかに二つも入ってゐる
(中略)
……あゝ いとしくおもふものが
そのまゝどこへ行ってしまったかわからないことが
なんといふいゝことだらう……
前年には、亡くなった妹を追うようにサハリンまで旅をして、妹がどこへ行ったのかを知ろうと必死になっていた賢治ですが、上の作品では、「いとしくおもふものが/そのまゝどこへ行ってしまったかわからないことが/なんといふいゝことだらう」と述べます。
この二つに共通しているのは、自分の「意思」がかなえられず、それを越えたところで物事が進んでいってしまう時、それを不本意とせず、「いゝこと」として肯定しているところです。
人間というのはある種の「能動性」を持っていて、自らの意思で世界に関わり、それを操作・制御しようとする側面があるでしょう。そして、そのような活動が挫折させられた時には、多少なりともフラストレーションを感じるのが通例だと思うのですが、ここで賢治が表現しているのは、そのような系列とは、また別の感性であるようです。
ここで、分野はまったく離れてしまいますが、立岩真也という社会学者の述べておられるところを、少し引用させていただきます。立岩真也氏は、生命倫理の領域を中心にラディカルな思索を展開しておられる方で、偶然にも私と同年生まれであるにもかかわらず、その著作はいずれも圧巻です。
 |
私的所有論 第2版 立岩 真也 (著) 生活書院; 2版 (2013/5/27) Amazonで詳しく見る |
上の『私的所有論』という著書の中で立岩氏は、ハリスというイギリスの哲学者・倫理学者が提示した「サバイバル・ロッタリー」という思考実験を紹介しています。
すべての人に一種の抽選番号(ロッタリー・ナンバー)を与えておく。医師が臓器移植をすれば助かる二、三人の瀕死の人をかかえているのに、適当な臓器が「自然」死によっては入手できない場合には、医師はいつでもセントラル・コンピューターに適当な臓器移植提供者の供給を依頼することができる。するとコンピューターはアト・ランダムに一人の適当な提供者のナンバーをはじき出し、選ばれた者は他の二人ないし、それ以上の者の生命を救うべく殺される。
まるで冷え冷えとした近未来SFを思わせるような設定ですが、多くの人は、このようなやり方には強い抵抗感を覚えるでしょう。しかし、それはなぜなのでしょうか?
「最大多数の最大幸福」を善とする「功利主義」の立場からは、1人が犠牲になっても何人かの生命が救われるならば、この方法が正当化されることになります。しかし私たちはなぜか、それを実行しません。
かりに他の惑星の知的生命体から見ると、私たち地球人は臓器移植の技術を持っているにもかかわらず、何らかの「感情」のために上のような方法を実施しないことによって、医学的には救えるはずの生命を見殺しにしているわけです。彼らは私たちのことを、何と残酷な生命体だ、と思うかもしれません。
しかし私たちは、彼らにどのように説明すれば、私たちの気持ちをわかってもらえるでしょう?
Wikipedia の「臓器くじ」という項には、この「サバイバル・ロッタリー」に対して想定される様々な反論と、またそれに対する再反論が掲載されています。
そこに書かれているもの以外では例えば、「これは神の領域を侵すことになるから認められない」という意見もあるでしょう。しかし、これまでにも「人工授精」や「遺伝子組み換え」など他の多くの技術が、最初は「神の領域の侵犯」と非難されながらも、しばらくすると普通に実施されるようになりました。「サバイバル・ロッタリー」は、これらと何が違うのでしょうか?
また私たちは、目的は何であれ、単に「人を殺す」ということに抵抗感があるために、「サバイバル・ロッタリー」を認めたくないのかもしれません。では、どこかの映画にあったように、親が我が子に臓器提供するために「自殺」するというのならどうでしょうか。この場合も私たちの多くは、これを「美談」とは見なさずに、自殺しようとする親を止めようとすると思いますが、その理由は何なのでしょうか?
立岩真也氏は上掲書において、「サバイバル・ロッタリー」に対する様々な「反論」を詳細に検討し、そしてこれまで一般に出されている論点だけでは、私たちが抱く抵抗感を説明しきれないことを、明らかにします。そして、次のような新たな考え方を提示します。
私が制御できないもの、精確には私が制御しないものを、「他者」と言うとしよう。その他者は私との違いによって規定される存在ではない。それはただ私ではないもの、私が制御しないものとして在る。私達はこのような意味での他者性を奪ってはならないと考えているのではないか。
(中略)
もっと積極的に言えば、人は、決定しないこと、制御しないことを肯定したいのだ。人は、他者が存在することを認めたいのだと、他者をできる限り決定しない方が私にとってよいのだという感覚を持っているのだと考えたらどうか。自己が制御しないことに積極的な価値を認める、あるいは私達の価値によって測ることをしないことに積極的な価値を認める、そのような部分が私達にあると思う。自己は結局のところ自己の中でしか生きていけない。しかし、その自己がその自己であることを断念する。単に私の及ぶ範囲を断念するのではない。それは別言すれば、他者を「他者」として存在させるということである。自己によって制御不可能であるがゆえに、私達は世界、他者を享受するのではないか。また、制御可能であるとしても、制御しないことにおいて、他者は享受される存在として存在するのではないか。(p.105)
上のような考え方は、「制御すること・できること」に価値を置いてきた、西洋を中心とした近代の思想とは、まったく別の視点を与えてくれます。「制御すること」の価値に関しては、例えば立岩氏も引用しておられるのですが、フレッチャーというアメリカの思想家・倫理学者が、次のように述べています。
人間たるということは、我々がすべてのことをコントロールの手中に置かなければならないということを意味する。このことが、倫理用語のアルファでありオメガである。選択のないところには、倫理的行為の可能性は存在しない。我々が強いられて余儀なく行為することは、すべて非倫理的で道徳とは無関係(amoral)なことである。(「遺伝子操作の倫理学的側面」, 1971)
むろん立岩氏は、上のように「すべてのことをコントロールの手中に」置こうとする人間の性質を、毫も否定しているわけではありません。ただ、人間の感性は、それとは逆の価値に対しても開かれているのではないか、ということを述べているのです。
生命などというたいそうなものについてだけではない。思想・信条を取り下げさせられることや、制服を着ないことや、髭を生やすことをあきらめさせられることを認めないこともまた同じである。それらを奪おうとしないのは、髭を生やすことが何かすばらしいことだから、その人の何かもっともな理由によって選択されたことだからではなく、その人の何かの役に立つというのではないその人の生の様式が許容されるべきだと私達が考えているからではないか。
そのような価値を私達は持っており、多分失うことはないと思う。人は、操作しない部分を残しておこうとするだろう。それは、人間に対する操作が進展していく間にも、あるいはその後にも残るだろう。それは全く素朴な理由からで、他者があることは快楽だと考えるからである。(p.115)
立岩氏の著書では、このような視点をもとに、さらに「能力主義」や「優生学」の検討に進むのですが、その続きは、上掲書そのものを読んでいただくことにしましょう。
それにしても、立岩氏の論を読んだ時、私は目からうろこが落ちる思いがしたものでした。思えば、人が誰かを愛するのも、相手が「私が制御できない他者」だからであり、この感情は得てして「相手を制御したい」という欲求と裏腹になりがちではあるものの、「制御できた」と感じた途端に、愛情が冷めるという人さえあるほどです。(この場合、本当は「相手を制御できる」という思い込みが間違いなのでしょうが。)
あるいは、人から愛されることの喜びも、相手が「制御できない他者」であるからこそ、なのでしょうね。
と、話がだんだん逸れていくので、この辺でそろそろ冒頭の賢治の話に戻らないといけませんが、上のようなことも考えてみた後でもう一度、「小岩井農場」や「薤露青」で賢治が「いゝこと」と感じた状況を見てみると、それはやはり自分が制御できない(あるいは制御しようとない)領域に、その対象があるという場面においてだったことがわかります。
馬車に乗るか乗らないかを自分で選択できず、死んだ妹の行方を知ることができず、そのような状況は、「すべてのことをコントロールの手中に置かなければならない」と考える人にとってはフラストレーションでしかないでしょうが、賢治は、「いゝこと」と言うのです。
これこそ、「(制御されない)他者があることを快楽だと考える」、立岩氏の論と一致した感覚ではないでしょうか。
一見「逆説的な」「不思議な」感覚に見える賢治の反応を、このような大きな枠組みから見ることもできるのではないかと、私は思ったのでした。
あと、蛇足かもしれませんが、もう一歩だけ進めてみます。立岩氏も、上のような考え方を「「文化」の差異や独自性にも還元する必要もない」と述べておられますが(具体的には、「西洋的」なものと「東洋的」なものの対比として論じることには問題もあると指摘しておられますが)、ここで私としてどうしても連想してしまうのは、浄土真宗の開祖・親鸞における、「自力」よりも「他力」に焦点を当てた思想です。
念仏は、行者のために、非行非善なり。
わがはからひにて行ずるにあらざれば、非行といふ。わがはからひにてつくる善にもあらざれば、非善といふ。ひとへに、他力にして、自力をはなれたるゆへに、行者のためには、非行非善なりと云々。(『歎異抄』第八条)
自分自身で何か善いことをしようとさかしらに考えるよりも、阿弥陀如来の本願にすべてを任せてしまう方がよいという考えは、法然や親鸞の当時の日本人にとっても、「逆説的」なものだったでしょう。しかし同時に、大いなる「安心」を与えてくれる教えとして、鎌倉時代の人々の間に爆発的に広まりました。
現代においても親鸞の思想は広く受容されていますが、その要素の一つとして、これが人間の中にある「制御しない(できない)ことの快」(立岩)という感覚を、見事に射抜いてくれるということがあるからなのではないかと、私のような不信心者には思えたりもします。
そして、賢治の場合も、そのような「快」を感じていたのかもしれません。すでに「小岩井農場」に現れていることから明らかなように、賢治が、制御・操作できないことを「いゝこと」と言明したのは、トシの死の後の苦悩よりも以前からのことでした。
ひょっとしたらこのような彼の感覚の基盤には、幼い頃から親しんでいた浄土真宗の教えも、どこか関与しているのではないかと、私は思ったりもしてみるのです。
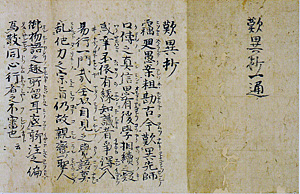
雨三郎
自己放棄、より正確には自己(への過度の拘泥の)放棄という傾向は、日本人、もしくは日本の文化や社会に特徴的なことのように私には思われます。(例えば朝鮮半島や中国の人々は同じ北東アジア人でも、もっと自己への拘泥が強いように思われます)。そしてそのことは、浜垣さんも述べておられるように一概に善や悪と決めつけられるべきものではないと思います。文化や社会がより建設的に展開して行くためには、自己主張と、他者の受け入れ(もしくは自己放棄)という相矛盾した側面の均衡が必要であるように思います。最近のこの国で起きている様々な問題の多くが、当事者の悪しき自己拘泥に由来するような気がするのは、私だけでしょうか?
hamagaki
雨三郎さま、こんにちは。様々なことを考えさせてくれる興味深いご指摘を、ありがとうございます。
あまり私自身は十分な知識はないのですが、たしかに報道映像などを見ていると、朝鮮半島や中国の方々が、不本意な出来事があった際などに怒りや悲しみなどの感情を、日本人よりも強く大きく表現しつつ、理不尽さを訴えておられる情景を目にします。多くの日本人が、家族を殺されたような時にも、TVカメラの前ではできるだけ感情を抑えつつ話をしようとしている様子とは、対照的な感じがします。
ご指摘の、「自己(への過度の拘泥の)放棄」ということの原因が、これまで日本人(先住民族を除くいわゆる「和人」)が他民族による侵略や支配を経験していないために、自己のアイデンティティを抹殺しようとする存在からそれを意識的に守ろうとする必要がなかったことにあるのか、あるいは江戸時代や明治時代の道徳が、「個」を主張することよりも「組織」のために「滅私奉公」することを求めたことにあるのか、また他の理由のためなのか、私にはわかりませんが、ご指摘のとおり、いわゆる「先進国」の中では、日本にかなり特徴的に見られることなのかもしれません。
ただ、私には実例はいま思いつきませんが、世界の様々な民族の中には、この「自己(への過度の拘泥の)放棄」を特徴としている人々も、「先進国」以外では現在もきっとあるのだろうという気はします。過去においても、征服者に滅ぼされたり、「同化」させられたりした民族にはきっと・・・。
それから、日本人が「自己(への過度の拘泥の)放棄」を伝統的に持っていたとすると、最近になってその「逆の」方向性を人々に推奨しようとする動きの一つは、「ほんとうの自分らしさ」を大事にしましょうと言ったり、「自分探し」を提案したりすることに現れているのでしょうね。
これはこれで素晴らしいことではありますが、「自分らしく生きなければいけない」という観念に縛られた若者が、どう生きたらよいのかわからず苦悩する、という皮肉な現象のもとにもなっているようです。
あと、「最近のこの国で起きている様々な問題」には、いろいろな要因が働いているのでしょうが、一般に時代や国境を越えて、犯罪の多くが「利己的」で「自己中心的」な動機に由来するのでしょうから、「問題」の背景に「自己拘泥」が関わっているのは、「最近のこの国」に限らないことなのだろうと思います。
一方で、これも時代や国を越えたことながら、「オウム事件」や「自爆テロ」のように、逆に自己を放棄して、何かそれを越えた価値と信ずるものに自分を溶解させてしまおうとする方向においても、また「様々な問題」が起こっているようにも思います。「戦争」だってそうですね。
やはりご指摘のように、「相矛盾した側面の均衡」が大事なのでしょうね。
雨三郎
やや的外れだったかも知れぬ当方の投稿にまで、わざわざ有益な示唆や補足を頂き、有難うございました。
再び的外れになるかも知れませんが、賢治における主体的な能動性とその抑制という点について、当方なりに考えたことがありましたので、再コメントをお許しください。と言いますのは、外界や他者に対する自らの主体的能動性の走り行きをどこかで抑制したり、無力化したりしようとする傾向は、浜垣さんも捉えておられるように確かに賢治に特徴的なことだろうと私も思うのですが、ただ彼におけるその能動性の抑制の在り方が、私には感性的なものというよりも、より意識的な、あるいはより意志的なものであるような気がするからです。
私としては賢治は基本的に非常に強い、濃密な自我性の持ち主ではなかったか、それゆえその主体的能動性もまた非常に強い人ではなかったかという気がしています。彼の特徴の一つである強い意志的な姿勢や理想主義などは、あくまでも自己実現を目指そうとする濃密な自我の存在なしには生じえないと思うからですし、自らに「修羅」という激しい表現を与えざるを得なかった人が淡白な自己性の持ち主だったとも思えないからです。また、そもそも他人に感動を与えたり、後世に名を残したりするような人は、ほぼ例外なく強い自我の持ち主ではないかと思うからです。
それならば、この強い能動性と正反対のものに見える彼の自己抑制への志向(しかもこの志向は、静的、消極的な段階を超えて、しばしば自己犠牲、自己放棄、自己否定といった極端な形まで取ることがある)をどう考えるべきでしょう?・・私にはこの相反する側面は、ちょうどネガフィルムとその陽画が1セットのものであるように、彼の主体的な能動性の形を変えた現れのように思われるのです。つまり彼の自己抑制は、あくまでも意志的な、あるいは意識的なものであり、それゆえ賢治の強い自己犠牲精神もまた、その激しい、濃密な、能動的な自己性によって初めて生じることができたように思われるのです。小岩井農場で馬車が動いて行ったことに対して「いいことだ」とした賢治の表現は、ただ感じるような本性が彼にもともと備わっていたというよりは、むしろ意識的な、あるいは意志的な要素によるものであるような気がするのです。
それなら彼のこうした特徴的な自我制動への志向、自己実現への志向が自己犠牲という形を取るような価値観をもたらした背景は何かというと、やはり浜垣さんが推測しておられるように、浄土真宗を含めた仏教思想ではないかと思うのです。(仏教の思考は、世界を相対的なものと観ずることによって、自我という煩悩を無力化しようとすることに主眼があるのではないかと思われますので。)
(素人の怖いもの知らずで、勝手なことを書き散らしてしまったかも知れません。どうか悪しからず。)
hamagaki
雨三郎様、コメントをありがとうございます。
まさに、私が言葉足らずでうまく表現できなかったことを、雨三郎様が言い表して下さいました。コメントを拝読して、私の言いたかったことも本当にこのとおり、と感じました。
賢治の人間像に関しても、私も以前からご指摘のごとく感じています。彼は、自分のあり余る才能を十分に自覚していたでしょうし、自信も自負もプライドもあったでしょう。こちらの方が、賢治にとっては生まれ持った「本能的」な感じの性質で、自己抑制的な方向は、父の厳しい教育や、仏教の影響による「後天的」なものだったのだろうと思います。自己表出の欲求が強いほど、現実場面では自己抑制も強くならざるをえず、その葛藤を自らの宿命のように感じて、「修羅」と呼んだのかとも思います。
「自己犠牲」という賢治のテーマは、この二つの相反する方向性を止揚する、根本的な解決方法だったのかと思います。
何か自分の目的を実現するために、自らの意志で自らを殺すという行為は、ある面で「究極の能動性の発現」と言えます。人間に都合がいいように自然を変えようとするグスコーブドリの行為も、その典型です。
一方で「自己犠牲」は、自我を肥大させずに、逆にそれを消滅させてしまうのですから、「我執」を捨てる行為でもあります。
ここにおいて、周囲から見ると非常に辛いかたちでではありますが、矛盾は一挙に解消されるわけです。
思えば、父の政次郎氏も、生前に「自分は仏教を知らなかったら三井、三菱くらいの財産は作れただろう」と言っていたということです。これも、常人には言えないような物凄い自信の表現であるとともに、仏教がそのような自我を抑制したということを明らかにしています。賢治と似ていますね。
賢治については上記のように思うのですが、本文で書いてみたのは、「制御しない=他力」という志向性も、一般に人間は持っているだろうという考えが、興味深かったからです。人間は(あるいは一部の人間は)、自分が独裁者になりたいと思っている反面、(また一部の人間は)独裁者に現れてほしいと願っている面も、なきにしもあらずと思うからです。少なくとも歴史を見ると、そう思えます。
最後は説明的な蛇足でした。
このたびは、ありがとうございました。今後とも、よろしくお願い申し上げます。