先日函館へ行く際に、私は村上春樹の短篇集『神の子どもたちはみな踊る』(新潮文庫)を、何気なくバッグに放り込んで出かけました。実際、往復の機内では、6つの短篇をじっくりと読むことができたのですが、それにしても今回の小旅行にあたって、なぜ私は本棚の片隅から他ならぬこの本を選び取ったのか、不覚にも帰宅してしばらくたってから、やっと私は自分の無意識的な動機に思い当たりました。
すなわち先週来、中国四川省の大地震の報道が、連日TVや新聞をにぎわしていたのです。
すでに読まれた方はご存じのように、『神の子どもたちはみな踊る』は、阪神大震災をモチーフにした連作短篇集です。各篇において震災がどのような意味を持って現れるかということは様々ですが、すべてに共通するのは、どの作品においても震災は主要な題材ではなくて、小説の片隅に、「遠景」のように小さく置かれていること、しかし実は、潜在的には重要な意味を帯びていることです。
震災は、物語の「外部」にあるように見えながら、いつしか物語や登場人物と「共振」をはじめます。
この辺の距離感と重みは、村上春樹氏が阪神地区(西宮市夙川)の出身でありながら、阪神大震災の当時にはアメリカで生活していて、現場から遠く離れていたこととも関係しているのかもしれません。
そして現在の私も、四川省の大地震のニュースを毎日見ていろいろなことを感じながらも、自分自身がその圧倒的な惨事の「外部」にいることを、日々思い知らされていたのです。
実は私は13年前の阪神大震災の際、地震から10日あまり経った1月29日から30日にかけて、1泊2日で現地の支援活動に行ったことがありました。同行者とともに、京都から車で長時間かけて神戸市の中心部に着いてみると、あの美しかった神戸の街の、変わり果てた姿がありました。その衝撃は、いまだに言葉で表現することができません。
それから2日間、地元の人たちと一緒に、私はそれなりの仕事をしました。しかし2日目が終わって気がついてみると、私は次にやって来るメンバーと交代して、もう京都へ帰ってしまう人間だったのです。毎日、避難所やライフラインの途絶えた住居と往復する地元の人とは異なって、私は、電気も水道も通い、風呂に入ってこの2日の疲れを癒やすこともできる場所へと、当たり前のように帰ることのできる人間だったのです。
この時、私は自分がいくら何かの援助活動に携わろうとも、やはりこの災害に関して、「外部」にいるのだということを痛感しました。そして瓦礫となった神戸の街の映像とともに、言いようのない自責の念が心に残りました。
ところで、このような大災害の被災者においては、「生存者の罪責感(サヴァイヴァーズ・ギルト)」と呼ばれる心理が問題になることが、しばしばあります。自らも被災しながら生き残った人にとっては、肉親や親しい人を喪った悲しみに加えて、「なぜこの人が死んで私が生き残ってしまったのか」「私が何とかしておれば、この人を救えたのではないか」「この人のかわりに私こそ死ぬべきだったのではないのか」などの気持ちが渦巻き、自分が生きていることへの罪悪感ともなってしまうのです。このような心理は、PTSDの重要な構成要素であり、外部にいるの者の安易な慰めが届くものでもありません。
典型的な「生存者の罪責感」を扱った文学作品として、広島の原爆被災を舞台とした井上ひさし氏の戯曲、「父と暮せば」がありました。
さて、災害の「外部」にある者が、その事態に対して感じる気持ちの中には、素直な「同情」、自分が役に立てないという「無力感」などとともに、このような「生存者の罪責感」の薄められたものも、確かに混じっているのでしょう。
遠くアメリカにいて、故郷の阪神大震災の報道に接した村上春樹氏も、そのような気持ちのいくばくかを感じたのかもしれません。ただ、さすがにすぐれた小説家は、私などのように苦い「無力感」を噛みしめることに終わらずに、「外部」にありながら何か新たな「力」を呼び覚ますかのような、一連の連作短篇を生み出したわけです。
ところで宮澤賢治の作品において、当時の大災害=関東大震災に言及したものとしては、1923年9月16日の日付を持つ「宗教風の恋」と「昴」(いずれも『春と修羅』所収)とがあります。
震災から10日あまりがたった時点で、やはり災害のはるか「外部」にあった賢治ですが、前者「宗教風の恋」では、次のように震災に触れます。
風はどうどう空で鳴つてるし
東京の避難者たちは半分脳膜炎になつて
いまでもまいにち遁げて来るのに
どうしておまへはそんな医される筈のないかなしみを
わざとあかるいそらからとるか
いまはもうさうしてゐるときでない
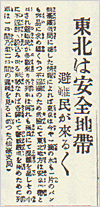 「東京の避難者」というのが、当時東京から東北地方へも避難してきていた地震の被災者のことです。「半分脳膜炎になつて・・・」という表現は、現代ならばあまり適切ではないと言われてしまいそうですが、今で言えば「急性ストレス反応」や種々の喪失体験など、精神的にも大変な状態で避難してきている人々が、多数あったのでしょう。対馬美香著『宮沢賢治新聞を読む』に引用された「岩手日報」大正12年9月7日版(右写真)によれば、「東北地方は安全地帯と目され避難民が多数来り各列車は何れも満員にて混雑を呈し・・・」とあります。
「東京の避難者」というのが、当時東京から東北地方へも避難してきていた地震の被災者のことです。「半分脳膜炎になつて・・・」という表現は、現代ならばあまり適切ではないと言われてしまいそうですが、今で言えば「急性ストレス反応」や種々の喪失体験など、精神的にも大変な状態で避難してきている人々が、多数あったのでしょう。対馬美香著『宮沢賢治新聞を読む』に引用された「岩手日報」大正12年9月7日版(右写真)によれば、「東北地方は安全地帯と目され避難民が多数来り各列車は何れも満員にて混雑を呈し・・・」とあります。
賢治は、このような被災者のことを思い、当時の自分を戒め、その心の有り様を責めています。
また、同じ日付の「昴」では、
市民諸君よ
おおきやうだい、これはおまへの感情だな
市民諸君よなんてふざけたものの云ひやうをするな
東京はいま生きるか死ぬかの堺なのだ
見たまへこの電車だつて
軌道から青い火花をあげ
もう蝎かドラゴかもわからず
一心に走つてゐるのだ
として出てきます。ここでも、賢治は被災した東京のことを考え、「東京はいま生きるか死ぬかの堺なのだ」として、自らの語り口を自重しています。そして気がつくと、自分が乗っている電車さえも、「生きるか死ぬかの堺」にある東京に共振するかのように、必死に走っているのです。
「昴」の最後は、そして「1923年9月16日」の日付を持つ4つの作品の最後は、次のように終わります。
どうしてもこの貨物車の壁はあぶない
わたくしが壁といつしよにここらあたりで
投げだされて死ぬことはあり得過ぎる
金をもつてゐるひとは金があてにならない
からだの丈夫なひとはごろつとやられる
あたまのいいものはあたまが弱い
あてにするものはみんなあてにならない
たゞもろもろの徳ばかりこの巨きな旅の資糧で
そしてそれらもろもろの徳性は
善逝(スガタ)から来て善逝(スガタ)に至る
遠い東京の震災ですが、すぐさまそこに感情移入できる賢治は、自らの死さえも身近に感じてしまいます。それまで「あてにされてきたもの」が脆くも崩壊した世界の現実に直面して、「あてにするものはみんなあてにならない」とあらためて自戒し、そして「たゞもろもろの徳ばかりこの巨きな旅の資糧で・・・」と、自身の宗教的立場からの観照を述べます。
やっぱり賢治も、遠い「外部」にありながら、震災を単なる他人事と見過ごしたり、無力感だけを覚えて終わったりするわけではなかったのです。
ところで上記「昴」の引用は、村上春樹の短篇「神の子どもたちはみな踊る」の終わり近くで、「善也」がある人に伝えようとした次のような言葉にも通ずるところがあるような気がしたのですが、どうでしょうか。
僕らの心は石ではないのです。石はいつか崩れ落ちるかもしれない。姿かたちを失うかもしれない。でも心は崩れません。僕らはそのかたちなきものを、善きものであれ悪しきものであれ、どこまでも伝えあうことができるのです。神の子どもたちはみな踊るのです。
・・・四川省の大地震から、やはり10日あまりが経った今日この頃です。
 |
神の子どもたちはみな踊る (新潮文庫) 村上 春樹 (著) Amazonで詳しく見る |
あっぷる すくらっふ
hamagakiさんの記事を読み、いろいろと考えさせられました。
最近読んだ「夕凪の街、桜の国」(こうの史代・株式会社双葉社)という広島の原爆を描いた本(漫画ですが)にも「生存者の罪責感」が出てきます。体験した人と同じにはなれなくても、少しでも理解しようという気持ちが大切なのかもしれません。
「神の子供たちはみな踊る」も読んでみます。
hamagaki
あっぷる すくらっふ様、コメントをありがとうございます。
喪失を体験した人が、その「悲しみ」を思うぞんぶん表出できるためには、「悲しみ」を受けとめてくれる人間が必要です。
大きく深い悲しみの場合には、それを長期間にわたって受けとめ続けるのも容易なことではありませんが、「外部」にあった者でも、覚悟を決めて本気になれば、やれるかもしれないことの一つかな、と思ったりします。
雲
なかなか、受けとめてくださる人間が、いてくださるだけで、「悲しみ」の受けとめ方も、ずいぶん、違うと思います。
HAMAGAKIさん、えらいです。
片岡昌哉
明けましておめでとうございます。年末に福田村の本を読み、元旦にたまたま宗教風の恋を読み、震災との関連を検索したらこのページがぱっと出てきてびっくりしました。またお話しする機会があるよう願って新年の挨拶とさせていただきます。本年もよろしくお願いします。
hamagaki
明けましておめでとうございます。
もう16年も前の記事でしたので、内容も忘れていたような話ですが、新年のご縁となって幸いでした。
今ちょうど香川県の田舎に帰省しているところですので、福田事件は他人事でないような切実さです。
昨今また排外主義が蔓延する世相で、100年前のこととは思えません。
本年もどうぞよろしくお願いします。