西崎専一著『ジョバンニの耳 宮沢賢治の音楽世界』という本を読みました。
 |
ジョバンニの耳―宮沢賢治の音楽世界 西崎 専一 (著) 風媒社 2008-01 Amazonで詳しく見る |
著者は、音楽美学やサウンドスケープ論を専門とする大学の先生で、その学問的立場から、宮澤賢治その人や作品について、考察したものです。
内容は、次のような章立てになっています。
プロローグ
かっこう鳥と「星めぐりの歌」
ジョバンニの耳
ゴーシュの音楽美学
賢治の蓄音機への旅
エピローグ
それぞれの章は、独立した論考になっていますが、著者みずから「あとがき」において、「本書は序奏とコーダ(終結部)が四つのパート(楽章)をはさむ、さらに序奏と最初の楽章に全体を導くモチーフが仕込まれているという、まるでロマン派の交響曲のような構成となりました」と述べているように、一冊の本全体としての構造にも工夫がこらされています。
著者の言うところの本書の「全体を導くモチーフ」とは、「プロローグ」から引用すれば、
賢治にとって音楽はまさに、「灰色の労働を燃やす」芸術的エネルギーの源だったのです。
という認識です。
この基本的なモチーフが、「ジョバンニの耳」の章においては、「銀河鉄道の夜」の分析を通して、「銀河鉄道」という賢治独特の仕掛けが、いかに音楽的な装置であるのかということを明らかにすることによって、また「ゴーシュの音楽美学」の章においては、一人の下手な「職業音楽家」が、ほんとうに「音楽する」ということに目覚めていく過程をたどることによって、浮き彫りにされていくのです。
まず最初の「かっこう鳥と「星めぐりの歌」」の章では、「「文語詩篇」ノート」の、「岩手山ニ独リ登山ス 夕暮、かくこう鳥、空線、風、すゞらん、柏林、」というメモや、「かくこうのまねしてひとり行きたれば、人は恐れて道を避けたり。」という短歌(312)や、文語詩「丘」の「かくこうはめぐりてどよみ」を引用しつつ、若き日の賢治にとって、かっこうの鳴き声は、特別な感傷を誘うものだったらしいと推測します。このあたりには、「サウンドスケープ論」の考え方も取り入れられているのでしょう。
また、生涯の最初期と最晩期の作品である「双子の星」と「銀河鉄道の夜」に、「星めぐりの歌」が登場することを紹介し、この歌の特徴であるような「はっきりとしたリズム」が、賢治の音楽的な好みを表しているのだろうと推測します。
後の「ゴーシュの音楽美学」の章においては、ゴーシュがかっこうと出会う第二夜が、ゴーシュの音楽的成長において最も重要であったと著者は考え、また「ジョバンニの耳」の章においては、「星めぐりの歌」がジョバンニにとって幻想世界と現実世界を結ぶ役割を果たしていると著者は考えておられますので、この第一章は、それらの章への伏線の役目を担っています。
先に紹介した著者の比喩によれば、「交響曲」の第一楽章に相当するはずのこの章ですが、実体としてはごく短く、古典的なソナタ形式ならば、ちょうど2つの主題が示される「呈示部」のような感じです。しかし「ロマン派の交響曲」であれば、こういう第一楽章もありえるのでしょう。
次章「ジョバンニの耳」は、本全体の題名にもされています。その結論をひとことで言えば、「銀河鉄道そのものが、音楽である。」ということになるでしょうか。
この一文だけを見ても何のことかわかりにくいでしょうが、実際に本書を読んでみると、わかったような気持ちになるから不思議です。ここでは、「そしてそのころなら汽車は新世界交響楽のやうに鳴りました。」という作品中の記述と、そもそも銀河鉄道とは死者の乗り物であり、いかなる文化においても死者の葬送には音楽が付随している、という著者の指摘のみ引用しておきます。
この章の考察でユニークなのは、あの悪名高い(?)岩波文庫版の「銀河鉄道の夜」の最後の部分を、作品分析の出発点にしているところです。私も、久しぶりにこの部分を読みましたが、やっぱりこれはいいものですね。この部分の草稿は紛失したと考えられており、現在は他の版で読むことはできないので、ちょっと長いですが、ここに引用しておきます(表記は文圃堂版全集による)。
けれどもまたその中にジョバンニの目には涙が一杯になって来ました。
街燈や飾り窓や色々のあかりがぼんやりと夢のやうに見えるだけになって、いったいじぶんがどこを走ってゐるのか、どこへ行くのかすらわからなくなって走り続けました。
そしていつかひとりでにさっきの牧場のうしろを通って、また丘の頂に来て天気輪の柱や天の川をうるんだ目でぼんやり見つめながら座ってしまひました。
汽車の音が遠くからきこえて来て、だんだん高くなりまた低くなって行きました。
その音をきいてゐるうちに、汽車と同じ調子のセロのやうな声でだれかゞ歌ってゐるやうな気持ちがしてきました。
それはなつかしい星めぐりの歌を、くりかへしくりかへし歌ってゐるにちがひありませんでした。
ジョバンニはそれにうっとりきゝ入ってをりました。
入沢康夫監修・解説による『宮沢賢治「銀河鉄道の夜」のすべて』では、この箇所について、次のように説明されています。
筑摩書房昭和四十二年版全集では、第79葉~第83葉の内容を作品末尾に移すにあたって、右の「けれども」~「きゝ入ってをりました。」の文を本文から削除し、その代わりに「後記」の中で、「なお、昭和三十一年版では、この部分の後に、さらに次の文章がつづいているが、これは作者によって抹消されている個所なので、本巻では削除した。」と述べて、掲出している。この内容を持つ草稿は現存していないが、宮沢清六氏の記憶によれば、全体が削除の大きな×印を付されたものであった由。用紙や使用インクについては、いっさい不明であり、どういう種類の草稿なのかも判定できない。
本書の著者の西崎専一氏は、「その草稿の紛失は結果として、「銀河鉄道」の車内やそれが走行する銀河空間に響いていた、豊かな音響的、音楽的イメージを読み解く鍵を奪い、また「星めぐりの歌」によって処女作「双子の星」と晩年の「銀河鉄道の夜」を結んでいるもの、いわば賢治の物語創作を支えた音楽的音響的イメージのひとつが「銀河鉄道」の世界から奪われることにもなってしまうという結果を招きます。」と残念がっておられます。そして、「その(=宮沢清六氏の)記憶がほぼ絶対視され、賢治自身が削除を意図したものであったという推測がまるで確かなものであるかのような扱いを受けて「銀河鉄道の夜」の世界から完全に排除されてしまった」ことに不満を表明しておられます。
しかしいずれにせよ、今回の西崎氏の論考によって、「銀河鉄道の夜」の音響的・音楽的(あるいはサウンドスケープ的)側面について、新たに鮮やかな光が照射されたことは、確かだと思います。
次の章「ゴーシュの音楽美学」は、「セロ弾きのゴーシュ」という作品について、音楽美学的に、考察したものです。「音楽美学」というと、哲学的な難しい議論を連想してしまいますが、要はこれは、「音楽は、なぜ・どのように、人間を感動させうるのか」ということを考える学問なのですから、音楽することが苦しみにさえなっていたゴーシュが、動物たちとの出会いを通じて、いかにして人を感動させるような音楽を奏でられるようになったのか、という問題にアプローチする上で、格好の足場を提供してくれるということなのでしょう。そして著者は最後に、「「セロ弾きのゴーシュ」は、音楽美学のためのかけがえのないテクストであり続ける」とまで述べます。
賢治は、「農民芸術概論綱要」の中で、「職業芸術家は一度亡びねばならぬ」と述べましたが、著者は、「セロ弾きのゴーシュ」とは、ゴーシュという「職業音楽家」が「一度亡び」、また再生する物語であると指摘します。
この章が本全体の中で最も長く、文章の読みごたえもありました。
「第四楽章」に相当する「賢治の蓄音機への旅」は、理論的な前二章とは雰囲気が変わって、賢治が愛用した(?)蓄音機を訪ね、さまざまな関係者からの聴き取りを行うフィールドワークの報告です。ただここでも、関係者の「証言」に依拠することの多い「賢治研究」のあり方について、著者としての考え方が詳しく述べられているのが特徴です。
農学校時代の賢治の教え子で羅須地人協会創立当時からのメンバーだった故・伊藤清氏は、昭和2年に結婚した際、お祝いとして賢治から蓄音機を贈られことを生前語っておられたとのことです。その蓄音機が、現在も伊藤家にあるということで、著者が訪ねて、対面を果たしてきます。
伊藤清氏の子息の孝氏の認識では、その贈られた蓄音機は賢治が使用していたものではなくて、お祝いのための新品だったということでしたが、著者の考察の結論は、これは羅須地人協会時代に、二階に置かれていた(小型の方の)蓄音機で、さらにその前は、賢治が農学校にしばしば持っ て行き、宿直室や職員室で生徒やその他の人々にレコードを聴かせた蓄音機だったであろうということです。
て行き、宿直室や職員室で生徒やその他の人々にレコードを聴かせた蓄音機だったであろうということです。
右の写真が、その伊藤家の蓄音機です(本書より引用)。卓上型のもので、いわゆる「ラッパ」はありません。木製のキャビネット部分には、「IWATEPHON」および「盛岡村定販売」と書かれたプレートが付いていて、「盛岡村定」とは、現在も盛岡市材木町で営業している「村定楽器店」です。
ところでちょっと本書からは離れますが、斎藤宗次郎著『二荊自叙伝』の大正13年8月24日の項には、「郊外なる農学校に立ち寄り宮沢賢治先生の篤き好意により職員室に於て蓄音機によれる大家の傑作を聴いた」との記述があり、下のような挿絵が添えられています。机の上にあるのが「蓄音機」のようで、この絵からは詳しいことはわかりませんが、卓上型で「ラッパ」は付いておらず、やはり伊藤家に保存されていたものと形は似ていますね。
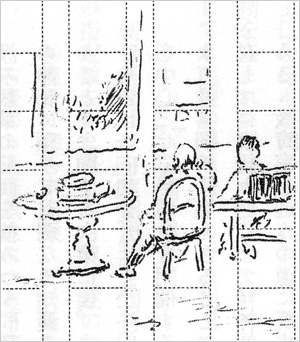
それから最後に、著者は本書の「あとがき」において、『【新】校本宮澤賢治全集』における賢治の歌曲の扱いについて、次のように書いておられます。
個々の研究者個人の解釈や見解表明はともかく、賢治に由来する原資料の提示が目標とされたはずの『新校本宮澤賢治全集』(筑摩書房)でも、「第六巻の歌曲の部」では、賢治自身が歌曲の楽譜を遺しているわけではないので、記憶に基づく採譜(?)といった極めて不安定な資料が「原資料」として扱われることになり、そこに編纂者による恣意的な改編やさらに後の時代のいっそう不確かな記憶に頼った変更が加えられたものが、その必然性の説明もなく資料として提示されることになり、その杜撰さのために賢治がその歌曲に託した音楽的イメージとそれに関わる活動の実態はますます捉えにくくなるといった現象を呈しています。
音楽学者としての立場からの意見なのでしょうが、かなり辛口ですね。私自身も、この問題については自分なりに思うところはあって、以前に「「【新】校本全集」における歌曲の校訂について」というエントリを書いてみたことがありますが、では実際にどうすればよいかとなると、なかなか難しい問題です・・・。
ともあれ、このような率直な表明も含めて、本書はとても魅力的な本でした。賢治とその音楽に関心のある方には、ぜひご一読をお薦めします。
ご参考までに、西崎専一氏はご自身で Webサイトを作成しておられて、それは「みみをすます」というサイトです。
豊田
『【新】校本宮澤賢治全集』における賢治の歌曲の扱いについては、読み物としては面白く読みましたが、幾つかの疑問もわきました。オリジナルをなるべく示すのが『【新】校本宮澤賢治全集』の役割と思いますが、編纂者個人の解釈面がきわだち、少し疑問に思っていました。
西崎氏の本、早速注文しました。早く読んでみたいですね。
雲
先日、偶然、ゴーシュの人形劇を、テレビで、観ました。
疑問は、どうして、「インドの虎狩り」なのか。
かっこうを、怒ってはいなかったと、ゴーシュさんは、自分で思うけど、怒った様子にしか、いつも、思えない。
かっこうを怒っていたわけでは、なく、自分に怒っていたわけだが、かっこうに、当たり散らしたのかな?と、思うのですが、はっきりしませんので、すっきりもしません。
最近、介護のことで、話しをする機会に、いつも、悩まされるので、ゴーシュさんに、おききしたいです。
かっこうのように、飛んで逃げるわけにも、いかないので。
文章を読んでいると、こんな事を、思い出しました。
hamagaki
>豊田 様、コメントをありがとうございます。
実際に賢治本人による記録(オリジナル)が残っていない「音楽」の領域において、「全集」を編纂するとなるとどういう基本的立場をとればよいのだろうと、私もわからずにいましたが、その後、西崎専一氏自身のお考えを知る機会に恵まれました。
西崎氏のお考えは、賢治の歌曲の場合には音楽学的意味における本来の基礎資料は存在しないので、それに準ずるものとして、「藤原嘉藤治による採譜記録楽譜」と、「鏡をつるし」(昭和8年10月21日・宮沢清六編集発行)の2つを、まずは重視すべきであるということで、これには私も心から納得できる感じがしました。
賢治全集も、賢治の草稿のように、今後も絶え間なく変化を続けていくのだろうと思います。
>雲 様
「印度の虎狩り」がどうして出てくるのかは、確かに不思議ですね。
それから、ゴーシュがかっこうに「怒ったんぢゃなかった」のかどうか・・・。この本の著者の西崎氏によれば、「ゴーシュはこのとき音楽的感動のただ中にいたのです。」ということです(p.125)。
かっこうの切実な歌にひたすら合わせているうちに、ゴーシュの感覚は、かっこうそのものに一体化するほど接近します。この時、ゴーシュはそれまでの自分の音楽の殻をまさに破ろうとしていたのでしょうが、しかしその極点において、それまでの音楽家としてのゴーシュの自意識が、警告を発します。「えいこんなばかなことをしてゐたらおれは鳥になってしまふんぢゃないか。」 そして、かっこうを追い出してしまいます。
この時は、自分が何か変化しようとしているという不安も、あったのかもしれません。
しかし、この夜の体験はゴーシュにやはり大きな影響を与え、ゴーシュは変わることができました。
それを、後から冷静になってみれば、ゴーシュも「怒ったんぢゃなかった」と自覚できたのかもしれません。
雲
ご説明ありがとうございます。
だいぶ、わかりましたが、まだ、なんとなく、わかりません。
すみません。
絵本の「あおくんときいろちゃん」みたいに、仲良しになったり、また、元通り離れたり。でも、その一歩手前で、離れてたんかなあ?と、思ったりします。