 |
新記号論 脳とメディアが出会うとき (ゲンロン叢書) 石田 英敬 (著), 東 浩紀 (著) ゲンロン (2019/3/4) Amazonで詳しく見る |
最近出た、『新記号論 脳とメディアが出会うとき』という本をたまたま読んでいましたら、賢治の『春と修羅』の「序」に関する、面白い言及がありました。
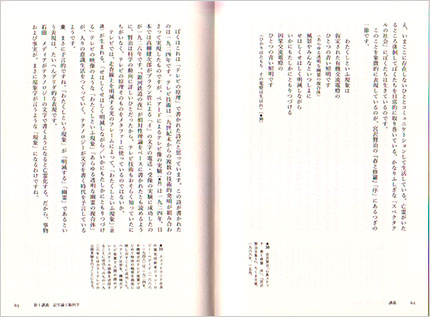
少し長くなって恐縮ですが、この「序」に対する新たな一つの解釈と思いますので、以下に引用させていただきます。
石田 人間は機械の文字を読み書きすることができないが、その認知のギャップこそが人間の知覚を総合し、人間の意識をつくり出すという話をしました。ぼくたちはこの「技術的無意識の時代」において見えないもの見て、意識の成立以前に聞こえるものを聞いて生活しているわけです。テレビであれ、インターネットの動画であれ、iPod の音楽であれ、ぼくたちは音・イメージや言葉など「記号」だけを取り出し、あたかもそれが現前しているように見なして生活しています。
現代は音・イメージを伝搬する電波に満ちた時代ですが、フランス語の「スペクトル spectre」(英語の spectrum)には光や音の波長分布像という意味のほかに、「亡霊」という意味もあります。それは、「スペクタクル spectacle(見世物)」という言葉とも結びつく。われわれは音・イメージがつくり出す見世物(亡霊)を存在と見なし、日々暮らしています。これこそヴァルター・ベンヤミンが言うところの「複製技術の時代」にほかなりません。いまここに存在しないひとが話し、存在しない事物の像や光景が見え、いまここに存在しないひととコミュニケーションして生活している。亡霊がいたるところ徘徊してぼくたちを日常的に取り巻いている、かなりふしぎな「スペクタクルの社会」にぼくたちは生きているのです。
このことを象徴的に表現しているのが、宮沢賢治の『春と修羅』「序」にあるつぎの一節です。わたくしといふ現象は
仮定された有機交流電燈の
ひとつの青い照明です
(あらゆる透明な幽霊の複合体)
風景やみんなといつしよに
せはしくせはしく明滅しながら
いかにもたしかにともりつづける
因果交流電燈の
ひとつの青い照明です
(ひかりはたもち、その電燈は失はれ)ぼくはこれは「テレビの原理」で書かれた詩だと思っています。この詩が書かれたのは1924年です。テレビ技術は19世紀末からの複数の技術的発明が組み合わさって実現したものですが、ベアードによるテレビ像の実験は1924年、日本では高柳健次郎がブラウン管による「イ」の文字の電送・受像の実験に成功したのが1926年です。『銀河鉄道の夜』が相対性理論をベースに書かれたとも読めるように、賢治は科学の動向に詳しいひとだったから、テレビ技術もおそらく知っていたにちがいなく、テレビの原理そのものをメタファーに使っているのではないか。
テレビでは、走査線上を明滅する光のフレームによって、「わたくしといふ現象」(意識)が生まれる。「せはしくせはしく明滅しながら/いかにもたしかにともりつづける」テレビの映像のような「わたくしといふ現象」「あらゆる透明な幽霊の複合体」が、人々の意識生活をつくっていく。テクノロジーが文字を書く時代を予言しているようです。
東 まさに予言的ですね。「わたくしという現象」が「明滅する」「幽霊」であるという表現は、たいへんデリダ的な表現です。
石田 メディアがテクノロジーの文字で書くようになると亡霊化する。だから、事物および事実が、まさに現象学が言うような「現象」になるわけですね。(『新記号論』p.61-63)
というわけで、賢治の『春と修羅』の「序」に登場する、「幽霊」や「明滅」する「照明」というイメージは、テレビジョンという当時世界最先端のテクノロジーのメタファーではないかという解釈が、ここで提示されているわけです。
映画好きで、弟を連れて頻繁に映画館に通っていたという賢治のことですから、もしもテレビの原理やその可能性について知っていたら、並々ならぬ興味を抱いて当然ですし、この「序」を書いた時点でそのような知識を持っていたのならば、それがここに反映されたという可能性も、十分に考えられそうです。
ただ、実際に賢治がテレビ技術について言及している記録は何一つ残っていないと思いますので、彼が「序」の執筆時点でそのような技術について知っていたか否かを判断するためには、まずはそれが「時間的に可能だったのか」ということから、調べてみる必要があります。
ご存じのように、賢治の『春と修羅』「序」には、「大正13年(1924年)1月20日」という日付が付されていますが、はたしてこの時点で、賢治がテレビジョンというものを知りうる可能性があったのでしょうか。上記の石田氏の発言には、「ベアードによるテレビ像の実験は1924年」という、まさにピンポイントの年号が書かれていますが、より細かい時間的な前後関係はどうなっていたのでしょうか。
そこでまず、Wikipedia の「ジョン・ロジー・ベアード」の項を見ると、「1924年2月、Radio Times 誌に半機械式のテレビシステムを公開し動く影(物体の輪郭)の映像を披露した」とあります。しかし、これだけではまだ十分に明らかではないので、ベアードのテレビ発明の記録として現時点で最も詳しそうな、“John Logie Baird: Television pioneer”という本を Google books で拾い読みしてみると、彼の1924年前後の研究活動は、次のようなものでした。
 |
John Logie Baird: Television pioneer (History and Management of Technology) Russell W. Burns The Institution of Engineering and Technology (2001/2/21) Amazonで詳しく見る |
- ベアードが、自らのテレビジョン研究について最初に出版物で報告したのは、1923年11月号の Chambers Journal 誌であり、ここでは、自作の装置が直径20インチで毎秒20回転の走査ディスクを用い、画面は2×2インチであること等を述べている。
- 1924年1月、研究のための資金集めに迫られていたベアードは、報道向けの実演を行い、同年1月15日付けの Daily News 紙と、1月19日付けの Hastings and St Leonard's Observer 紙に記事が掲載され、実際これを見たベアードの父親の友人から、50ポンドの資金援助を受けた。この時点では、ベアードの装置はまだ単一の文字や記号の「影絵」を転送できるだけで、集光レンズの前に置かれた十字架形の厚紙の輪郭を、数フィート離れた暗い部屋で見ることができたという。
- 1924年2月15日付けの Radio Times 紙には、「テレビジョンが実現すれば、肘掛け椅子から世界が見られる」と題された匿名記事が掲載され、無線放送や電波について説明をした後、もしもこれが実現すれば、たとえばアルバートホールに座ったままで、競馬ダービーや、オクスフォード・ケンブリッジ対抗ボートレースや、海軍観艦式や、アメリカのボクシング試合や、あるいは戦争さえ見られる、10年後には地球の反対側で起こる出来事さえ見ることができるだろう、と述べられていた。
- 1924年1月の新聞記事による資金援助を受けて、ベアードは4月までにより大きなアパートの研究室に引っ越し、4月10日に行った実験の電波が、イギリス南岸部でパリのラジオを聴取していた人々の耳に高音の雑音として聞こえたと、Glasgow Herald ほか数紙が報道した。
- 1924年3月17日に、ベアードは撮像機と受像機の同期に関する新たな技術の特許を申請した。
- 1924年4月の Radio Times 紙に、ベアードの支援者である作家のル・キューが「テレビジョン:一つの事実」と題した論文を掲載し、ベアードが撮像機と受像機を正確に同期させるという難題を克服して、完全に切断された装置の間での画像送信を成功させたこと、送信レンズの前で指を上下に動かすと、受像ディスクにおいて上下する指をはっきりと見ることができたことを述べている。
- 1924年5月に、ベアードはそれまでの実験成果をまとめた最初の技術論文を刊行した。
- 1924年7月26日付けの Hastings and St Leonard's Observer 紙に、「テレビジョンの発明者と名乗るベアード氏」の実験室で電流がショートして爆発事故が起こり、ベアードは爆風で部屋の端まで飛ばされたという記事が掲載された。
- この後、ベアードは1925年10月2日に、初めてグレースケールの画像の送受信に成功し、この装置が「最初のテレビジョン」と言われることとなった。1926年1月26日には公開実験においてこれを示した。
ということで、賢治が『春と修羅』の「序」を書いたと推測される1924年1月20日までの時点では、ベアードによるテレビジョン装置は、まだその前段階の開発実験が、イギリスの地方新聞や専門雑誌で細々と紹介されていたにすぎず、さらにその実験装置を実際に見ることができたのは、1924年1月の報道発表に招かれた一部の記者や、ベアードのために金銭的支援をする人だけだったというのが、実情のようです。彼が自らの装置について初めての論文を発表したのも1924年5月で、これも時期的に「序」には間に合いません。
そして、ベアードが現実に「最初のテレビジョン」と呼びうる性能の装置を製作できたのは、1925年10月のことだったのです。
つまり、賢治が日本にいながらにして、1924年1月までに当時のイギリスにおけるテレビジョンの開発状況――しかもそれはまだ非常に未熟で、隣の部屋に影絵を送れる程度であり、現地の人々にもあまり知られていなかった、実験室の中の試作機という段階――について、具体的に知りえた可能性は、まずないと言わざるをえません。

なお上の写真は、“John Logie Baird: Television pioneer”に掲載されている1924年初期におけるテレビジョン実験の様子で、中央の人物がベアードで、左側が支援者のル・キューです。さらに左には大きな円盤が写っていますが、当時はこのような円盤に螺旋状に多数の穴をあけておき、円盤を高速で回転させてその穴を透過してくる光を、撮像機および受像機で走査線として用いていたということです。
※
以上、実際に確認してみると、賢治が『春と修羅』の「序」を書いた時点では、テレビジョンの受像機において「せはしくせはしく明滅しながら/いかにもたしかにともりつづける」「幽霊の複合体」を想像しえたということはありえず、これが「テレビの原理」で書かれた詩だという解釈も、成り立たないということになります。
それはそれで、ちょっと魅力的な解釈だったのにまあ残念だった、というだけのことで、ここで今回の記事を終わってもよいのかもしれませんが、しかしそれにしても宮澤賢治という人は、この東大のメディア学の教授をしても、なぜかここまでの期待というか思い入れをさせてしまう、何か不思議な吸引力を持った人であることは確かです。
現代の我々は、たとえば賢治が「エコロジー思想の先駆者」であったとか、彼の書いたものやその行動を、ついつい贔屓目に持ち上げたくなる傾向があります。多くの場合、それはある程度までは事実に基づいているのでしょうが、しかし賢治が「有機農業の先駆者だった」とまで言い出すと、これは事実の真逆になってしまいます。また自然科学的分野でも、たとえばある高名な賢治研究者のように、短篇「柳沢」に描かれた岩手山頂の雪の白光を、「超高層空間における発光現象の予覚」であるとか論じてしまうと、やはり独りよがりな思いこみになってしまいます。
上のような問題は、勝手な読者の側に原因があるわけですが、ただ我々読者がそういうことを考えたくなってしまう理由の一つは、賢治の方も確かに当時の作家としては異例なほどに自然科学知識が豊富で、その最新の進歩にも通じていたということにあるでしょう。
冒頭の本で石田英敬氏が言っているように、「『銀河鉄道の夜』が相対性理論をベースに書かれたとも読めるように、賢治は科学の動向に詳しいひとだった」わけで、これも「相対性理論をベースに書かれた」とまで言ってしまうとちょっと言いすぎで、「相対性理論の前提である『真空は光の媒質である』という認識が踏まえられている」と表現した方が正確ではあるでしょうが、しかしやはり賢治という作家の印象は、まさにこのとおりなのです。
近代日本の作家で、我々がこういうイメージや思い入れを投影する人というのは、ほかにはちょっと思い浮かばず、森鴎外などはずっと現役の医師でしたから、当時最先端の科学にもきっと通じていたと思うのですが、読者としては鴎外の作品に、賢治のごとく何か「未来への先見性」を期待するという感じには、なぜかなりません。
そしてさらに、上記のように賢治が実際に自然科学に詳しかったということに加えて、彼は当時まだ知りえなかったはずの事柄まで、現在から見ると「当時なぜこんなことが書けたんだろう」と不思議になるような、信じられない想像力を示していることも、よくあるのです。
以前の記事「銀河、ワームホール、りんご」で書いたように、銀河を「りんご」に喩えてそこを走る鉄道を考えるというイメージは、空間の歪みをワープする「ワームホール」の着想そのものですし、また「現象としての真空」で書いたように、「この世界」と「異界」が「真空」という対象を媒介として繋がっているという発想も、現代物理学を先取りしていました。
これらはいずれも、「賢治の洞察力が凄かった」とまで言ってしまうと言いすぎで、まあ偶然に符合したにすぎないと考えるしかないのですが、しかしたとえ偶然にしても、数十年後に驚かされるようなこういう素晴らしいイメージを独自に生み出すことができる想像力というのは、やはり賢治ならではなのだと思います。
思えば、記事「現象としての真空」のコメント欄で吉田さんが、「賢治は、アインシュタインら、独創的な思考ができた科学者たちにも負けない豊かな想像力の持ち主だった」との意見を下さいましたが、まさにそういうことなのかなあと、あらためて感じざるをえません。
そして人は、やはり賢治のそういうところについつい惹かれて、冒頭のようにちょっと先走りした解釈を生み出してしまうこともあるのだろうかと思うのです。
しかし賢治作品のこういう「読み」もまた楽しいもので、ただそれにあまりとらわれると「トンデモ」になってしまって危ういのですが、その境目がわからないあたりを彷徨ってみるのは、私などは大好きです。まあ同時に、客観的で大局的な視点というものを、忘れないようにしなければなりませんね。
コバヤシトシコ
「春と修羅」序が、「テレビの原理」で書かれた詩であるというお話には、一瞬眼から鱗の思いがしましたが、タッチの差で賢治にはそのとき「テレビの原理」を伝わっていなかった、ということ、ちょっとホッとしました。
やはり、賢治の心が捉えた、現象を表す言葉であってほしい気がします。これも思い込みでしょうか。
アトリエ・エム
賢治は地元花巻の地層にも詳しく、『かつてはここに恐竜がいた』と予言していたと聞きます。(没後、実際に化石が発見されたことはご存知かと思います)
科学者としての先駆的な勘で、テレビジョンの出現を予見していたとしても、不思議ではない気がします。
大変興味深い考察を、有難うございました。
hamagaki
>コバヤシトシコ様
いつもありがとうございます。
私もこの本を最初に読んだ時、確かに「目から鱗」の感じがしました。言われてみればテレビにぴったりの表現でもありますね。
ただ同時に、「有機交流電燈」とか「透明な幽霊の複合体」などという賢治独自のイメージが、あまりに特定のテクノロジーに具象化され限定されてしまっても、読者によるそれ以上の空想の余地がなくなってしまうようで、それも確かに残念ですね。
>アトリエ・エム様
コメントをいただきまして、ありがとうございます。
賢治が地質学的な知識をもとに、おそらくその地層の年代と当時の環境から、恐竜の存在を想定していたというのは、確かに科学者としてすごいことだと感嘆します。
よく映画も見ていて、各種メディアには強い興味を抱いていた賢治のことですから、確かにテレビジョンの技術も想像することができた可能性はあるでしょうが、それにしても現代の私たちは、彼以外のいったいどんな作家になら、テレビジョンの出現を予見しえたと期待するでしょう。
つくづく、不思議な魅力を持った人だと思います。
どうか今後とも、よろしくお願い申し上げます。
佐々木伸行
随分前の事ですが、京都佛立ミュージアムで聞いた、宮澤和樹さんの話を思い出しました。
宇宙飛行士の毛利さんが来て、祖父清六さんに尋ねたそうです。自分が見た宇宙を賢治は何故正確に書けたのでしょう? 世六さんは「兄には見えたのでしょう」と答えたそうです。 随分前の事で記憶の精度はあやしいのですが、賢治の持つインスピレーションは不思議ですごいと思います。
hamagaki
佐々木伸行さま、お久しぶりです。
コメントをありがとうございます。
ほんとうに、賢治の想像力というか感性は、すごいですよね。
彼の17歳の頃の短歌に、次のようなものがあります。
これらはまるで、宇宙空間に一人で漂いつつ書いているようで、後世のSF小説も思わせます。
清六さんのおっしゃるように、賢治はこれらを頭で考えて書いたのではなく、ふっと「見えて」しまったのかもしれません。