先日の「文語詩「硫黄」の舞台(1)」の続きです。前回は、いったんは定説となったかに見えた「鶯沢鉱山」説に対して、細田嘉吉氏が「大噴鉱山」説という有力な新説を提唱し、細田氏は「硫黄(下書稿(一))」に出てくる「大森山」の候補として、葛丸川上流の割沢集落の北方3kmにある「大森山(d)」も考えられると指摘していることを、ご紹介しました。
今回は、賢治の書簡等をもとにして、賢治がこの文語詩「硫黄」のもととなった体験をしたのがいつのことだったのか、そして「下書稿(一)」にある「大森山の右肩に/二十日の月ののぼる」という現象が見られる時間や場所について、考えてみます。
3.書簡から推測する土性調査行の時期
まず、賢治が土性調査において、鶯沢鉱山やその北方の大噴鉱山あたりを踏査したと思われる記載を、彼の書簡から抜き出してみます。
書簡53 1918年(大正7年)4月16日付 鉛より宮澤政次郎あて
昨日も本日も調査甚進行仕り候。明日は豊沢伊藤豊左エ門方泊、十八日は鉛、十九日は台の釜田二十日夜帰り申すべく候。(後略)書簡60 1918年(大正7年)5月2日付 大瀬川より宮澤政次郎あて
昨日は雨天に御座候処予定の調査を終へ昨夜は当小学校長の宅に泊り衣類も全く乾かし貰ひ候
本日は晴れさうにも見え候へども割沢迄川沿ひに調査致し明日晴天ならば割沢より山地を経て当所に出で帰花仕るべく候書簡79 1918年(大正7年)7月17日付 盛岡より宮澤政次郎あて
(前略)
私は明後十九日迄当地にて分析に従事し二十日朝林学科小泉助教授と共に花巻へ参り直ちに当日は鉛温泉に至る途中の林相を調査致し鉛に泊仕るべく候
二十一日、鉛より豊沢、幕舘、桂沢―鉛帰泊
二十二日、鉛―割沢(或は割沢を経て台温泉)
二十三日、割沢―台(又は台―志度平)
二十四日、台より志度平又は(志度平―三ツ沢川北の又―二ツ堰―花巻)
二十五日、志度平、―三ツ沢川、花巻
(後略)書簡81 1918年(大正7年)7月22日付 鉛より宮澤政次郎あて
昨日志度平より叔母上に御托し上げたる手紙御了承のことと奉存候 扨て昨夜は大沢温泉にとまり本日は幕舘の少しく向迄参りて当地に泊仕り候 明後日は或は花巻に帰るかとも存じ候 遅くとも明々後日には帰り申すべく候 地質と森林との関係は実に明瞭なるものに御座候 今後は造林の立地等も充分の結果を見る様定め得べく候 明日は台温泉に割沢を経て参り申すべく候 毎日少しづゝの旅行に有之候間決して御心配無之様奉願候 先は以上
書簡79、81には、鉛温泉→割沢→台温泉→志度平と、鶯沢鉱山や大噴鉱山の近くを調査する予定が書かれていますが、「下書稿(一)」には「をちこち春の鳥なきて」とあることからすると、7月というのは季節がずれてしまいます。また、この年の7月というのは、鶯沢鉱山が休山した月であり、すでに鉱石の輸送は行われていなかった可能性が高いと思われることを注記しておきます。
細田嘉吉氏は、この書簡53、60をもとにして、「「楢ノ木大学士の野宿」を構想した葛丸川・豊沢川流域地質調査行程図」という地図を作成されました。下の図が、『石で読み解く宮沢賢治』(蒼丘書林)に掲載されているその労作です。ここでは、本来は右左につながる図を、上下に分けて掲載しているので、やや見にくくて申しわけありませんが、下の方の図で「T.7.4.16コース」「T.7.4.17コース」「T.7.4.18コース」「T.7.4.19コース」とあるのが、書簡53にもとづいた推定コース、上の方と下の方の図で「T.7.5.2コース」、下の方の図で「T.7.5.3コース」とあるのが、書簡60にもとづいた推定コースです。
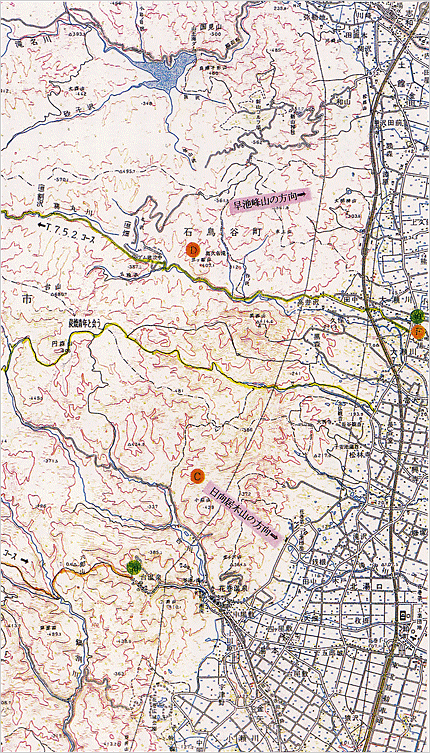
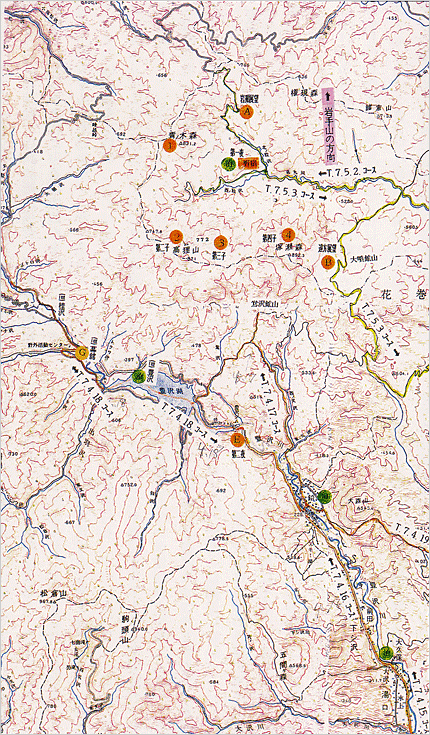
4.短歌642,643の検討
さて、このような資料を参考に、文語詩「硫黄」の舞台を考えてみたいのですが、まずは、この文語詩の原型となった、短歌642,643について検討します。
642 夜はあけて
馬はほのぼの汗したり
うす青ぞらの
電柱の下。643 夜をこめて
硫黄つみこし馬はいま
あさひにふかく
ものをおもへり。
この短歌の内容だけからは、馬が硫黄を積んできて、夜明けに目的地に到着したこと、その場所には電柱があること、ということがわかるにすぎません。しかし、「歌稿〔A〕〔B〕」におけるこの二首の次の作品、644は次のようなものです。
644 これはこれ
夜の間にたれかたびだちの
かばんに入れし薄荷糖なり。
賢治が土性調査に出て、かばんの中に薄荷糖を発見するエピソードは、工藤又治あての次の書簡に書かれています。
書簡54 1918年(大正7年)4月18日 鉛温泉より工藤又治あて
(前略)
私モ又ニギリ飯ヲ出サウト背嚢ニ手ヲ入レタラ[注:「ミツワ人参錠」の箱の絵]ノ様ナモノガ入ッテヰマシタ。コンナモノハ変ダト思ッテ中ヲ見タラ薬ハ入ッテヰナイデ、薄荷糖ガ一杯ニツマッテヰマシタ。コレハ私ノ父ガ入レテオイタノデス。私ハ後ニ兵隊ニデモ行ッテ戦ニデモ出タラコンナ事ヲ思ヒ出スダラウト思ヒマス。(後略)
つまり、短歌644に詠まれている薄荷糖のエピソードは、1918年4月15日~19日の、豊沢川遡上→鉛→豊沢集落→鉛→台という調査行の際のことだったと推定されるのです。
そこで、賢治の「歌稿」における短歌の配列と体験の時間的順序、ということを考えてみると、「歌稿」に並べられている短歌は、ごくごく一部の例外を除いて、賢治がその体験をした時系列の順に沿って配列されていると言えます。そして、このルールを適用するならば、642,643の短歌に詠まれている観察を賢治がしたのは、4月15日~19日の豊沢川流域調査行においてであった、ということになります。
5月2日~3日の葛丸川流域調査行は、上記の調査からいったん盛岡の下宿に戻って、それから出直したものですから、その時の体験が、644より前の642,643として並べられるはずはないのです。
つまり、643に出てくる「硫黄」は、この時は賢治は豊沢川流域にしか行っていないのですから、鶯沢鉱山から豊沢川に沿って輸送されてきた硫黄鉱石であると考えざるをえません。
642,643が、硫黄運搬の荷役から解放された馬の疲労感や安堵感を詠んでいるとすれば、馬がそのような状況を味わえるのは、当時は西鉛―志度平の間を運行していた馬車鉄道の終点志度平においてだろうと思われます。
前回、細田嘉吉氏が硫黄の搬出が鶯沢鉱山からであるとした場合の問題点として、
- 西鉛から志度平までの8kmの馬車鉄道は、所要時間も2時間足らずで、「二十日月ののぼるころ」つまり真夜中に出発し「夜をこめて」運搬する必要はなかった
- 馬車鉄道の終点・志度平温泉は山間の温泉で、ここまでには「東しらみて野に入れば」といった情景に合致するところも見あたらない
- 鶯沢鉱山の硫黄輸送は元山から花巻駅まで一貫体制で、西鉛から志度平まで馬力で運ばれた硫黄は、ここで積み替えられることなく、同じ貨車のまま電気機関車に切り替えられ運ばれることになるので、志度平で「か黒き貨車に移さるゝ」ということはなかった
という点を挙げておられることをご紹介しました。しかし上記の記述は、「夜をこめて」を除き、いずれも文語詩「硫黄」になってから現れるもので、短歌に詠まれている内容だけならば、これが志度平であると考えて、何ら矛盾することはありません。642には「電柱」が出てきますが、志度平からは電車が走っていましたから、「電柱」もあったはずです。
また、「夜をこめて」とは、一般に「夜を通して」という意味ではなく「夜明け前に」という意味です。賢治の短歌の用例でも、
523 天の川しらしらひかり夜をこめてかしはばやしを過ぎ行きし鳥
などがありますが、これも「一晩をかけて柏林を通過した」のではなく、「夜明け前に柏林を通過した」ということでしょう。
すなわち、短歌643は、「夜明け前から硫黄を積んできた馬は、今・・・」ということですから、所要時間が2時間足らずの行程でも、朝日が出る頃に目的地に到着するということは、あっておかしくないのです。
5.文語詩「硫黄」の検討
文語詩「硫黄(下書稿(一))」では、あたかも鉱山から硫黄を運搬する馬とともに作者も歩んでいるかのように情景描写が推移しますが、4月15日~17日にかけて実際に賢治がたどったコースは、豊沢川をさかのぼって、鶯沢鉱山方面を目ざすという、作品とは逆の方向です。
したがって、この詩の内容が4月の15日~17日の調査行にもとづいているとすると、すべて賢治の観察によっていたということはありえず、作者による虚構化がかなり入っているということになります。これは、一般に文学作品としては当然のことですが、賢治の作品ではかなり作者の実体験どおりという場合もありますので、少なくともこの作品に関しては、実体験どおりではない可能性があることを、確認しておきます。
ただし「実体験どおりではない」としても、この調査行で賢治は志度平を通った後、鉛温泉に行き、細田氏の推測では鶯沢鉱山にも行っているのですから、「硫黄(下書稿(一))」にあるように、「大森山の右肩に/二十日の月ののぼる」ところを賢治は目にして、それが文語詩に織り込まれたのだろうか、ということも考えたくなります。
そこで、「Stella Theater Pro」という天文ソフトを使って、1918年4月17日の宵の月齢を算出してみると、残念ながら'6.2'と出ました。
つまり、この調査行において賢治は、「大森山の右肩に/二十日の月ののぼる」様子を見ることはなかったということになります。
では、なぜ賢治はわざわざ「二十日の月」というものをここに出してきたのか・・・。
試しに、この後5月2日~3日に賢治は葛丸川流域調査行をしていることから、同様に1918年5月2日の月の出の時点の月齢を算出してみると、'20.4'となりました。すなわち、まさに「二十日の月」なのです。
ならば次に、この調査行で賢治が訪れたと思われる大噴鉱山のあたりから、「大森山の右肩に/二十日の月ののぼる」様子を見ることができるのか、ということが気になります。
まず、細田嘉吉氏の挙げておられる、葛丸川上流の割沢集落の北方3kmにある「大森山(d)」は、大噴鉱山から見て北東の方向にあり、二十日月の月の出は東南東ですから、この山の「右肩に月がのぼる」ということはありえません。
では、鉛温泉の東方にある「大森山(a)」を、大噴鉱山から見ることはできるのか・・・。
大噴鉱山から「大森山(a)」は、ほぼ真南に5kmほどの場所になります。私は実地に行って確認したわけではありませんが、地図を見ると大噴鉱山のすぐ南には601mの山もあり、そのさらに南には533.6mと521mの山も並んでおり、543.6mの大森山を直接見るのは無理なのではないかと、地形的には予想されます。さらに「カシミール3D」という地図ソフトに組み込まれている「カシバード」という3D鳥瞰機能を用いてシミュレーションしてみても、大噴鉱山の位置から大森山(a)は見えませんでした。
すなわち、賢治が大噴鉱山を訪ねたと思われる1918年(大正7年)5月2日~3日の土性調査において、野宿をした2日の晩に「二十日の月」がどこかの山から顔を出すところを賢治が見た可能性はありますが、その山は「大森山」ではなかったと考えられるのです。
あと、書簡81によれば、この年の7月22日にも賢治は鉛温泉に宿泊したことがわかります。この時にも賢治は「大森山(a)」は見たはずですので、念のためこの日の月齢を算出すると、'14.0'でした。これも「二十日の月」には該当しません。
文語詩「硫黄」に描写されている内容を検討すると、大噴鉱山から割沢、大瀬川集落を通って、石鳥谷駅に硫黄鉱石を運ぶ情景と共通点が多いことは、前回細田嘉吉氏の説に沿ってご紹介したとおりです。月齢が、「二十日の月」だったことも、さらに賢治が大噴鉱山を訪れた時の体験を思わせます。ただ、この月が「大森山の右肩に」のぼるというところは、上記のようにフィクションと考えざるをえません。
また、5月2日に賢治は葛丸川をさかのぼって、その上流で童話「楢ノ木大学士の野宿」の題材となる野宿をし、5月3日に大噴鉱山を通って、葛丸川沿いではなく台温泉の方に下りてきたと推定されます。5月2日に、硫黄鉱石を運んでくる馬とすれ違った可能性はありますが、文語詩「硫黄」に描かれているように、その運搬と同方向に道を歩んだわけではありませんので、ここにも虚構化が行われていると言えます。
6.まとめ
以上をまとめると、短歌642,643から、文語詩「硫黄」に至る作品系列を、どこか一つの「作品舞台」における、作者のある一回の体験にもとづいたものとして一元的にとらえることはできない、ということになります。
短歌642,643は、その創作時期からすると、4月16日あたりの早朝に志度平で、「鶯沢鉱山」から硫黄鉱石を運んできた馬車鉄道の馬を見て、詠まれたものかと思われます。
一方、文語詩「硫黄」の方は、その内容からすると、細田嘉吉氏が指摘したように「大噴鉱山」からの硫黄鉱石輸送をモデルにしている可能性が高いと思われます。「下書稿(一)」に出てくる「二十日の月」という月齢も、賢治が5月2日に葛丸川上流で野宿をした時に実際に見た月の様子を反映していると思われます。
しかし、その「二十日の月」が顔を出す「大森山」は、大噴鉱山ではなく鶯沢鉱山からの輸送ルートにある「大森山(a)」に由来しているのではないかと、私は考えます。上で見たように、1918年(大正7年)の土性調査では、賢治がここで「大森山の右肩に/二十日の月ののぼる」情景を見たわけではなかったようですが、賢治が何度も泊まった西鉛温泉から見れば、「大森山の右肩」は東南東の方角にあり、これは二十日月の際の月の出の方角と一致するのです。
「大森山の右肩に/二十日の月ののぼる」という言葉は、1918年の土性調査の折ではない別の時の、おそらく西鉛温泉から見えた月の記憶が織り込まれたものだろうと、私は考えます。
以上、短歌642,643から文語詩「硫黄」に至る系列は、2回の土性調査と、さらに他の記憶も合わせられて作品化されたものだろうというのが、とりあえず私としての結論です。
さてその場合、「経埋ムベキ山」としての「大森山」をどう考えるべきかということが問題です。私の関心も、そもそもそこから出発していました。
これに関しては、上述のように西鉛温泉から見た大森山(543.6m)が、いったんは「下書稿(一)」に取り入れられていたのではないかというのが私の考えで、その場合はこの山と月の記憶が、文語詩を推敲する晩年まで、賢治の心の中に存在しつづけていたことになります。賢治が家族ぐるみで長年親しんでいた西鉛温泉ですから、そのように強く印象が残ることも、ありえるのではないでしょうか。
すなわち、小倉豊文氏の言う「大森山(a)」が、賢治が選んだ「経埋ムベキ山」だったろうと、私は思うのです。

鉛温泉から望む大森山(a)
コメント