先日、「佐藤通雅著『賢治短歌へ』(1)」においてご紹介したように、著者の佐藤氏は賢治の短歌の特異性を、一般の短歌の前提である<一人称詩>としての性格からの「ふみはずし」としてとらえ、「<超一人称>の方向」として、論じておられます。
しかし、私としてはこの本を読んでいて、「問題の本質は<人称>なのか?」という疑問をいだかざるをえませんでした。
前回から繰り返しの引用になりますが、たとえば佐藤氏は、
32 黒板は赤き傷受け雲垂れてうすくらき日をすすり泣くなり。
にという作品に対して、
赤い傷に痛みをおぼえたのは、なによりも賢治自身だったはずだ。しかし、ほとんど同時に黒板に感情移入してしまっている。その結果、自分と対象との境界はほとんど霧消してしまう。作者が主軸となって成立する、一人称としての文学からは、あきらかなふみはずしだ。(p.89)
と述べ、ここにも「一人称としての文学からのふみはずし」を指摘されます。しかし私としては、上の短歌にはたしかに独特なところはあるものの、それでも立派な「一人称文学」ではないかと思うのです。
最後の「すすり泣くなり」の「なり」は、文法的に言えば、中世以前の「伝聞・推定の「なり」」が近世以降には「詠嘆」の意味に用いられるようになったものだろうと思いますが(間違っていたらすみません)、いずれにしてもこの「なり」という助動詞にこそ、作者賢治の主観的な認識と感情、「ああ、黒板がすすり泣いている!」という思いが込められているはずです。
「黒板に感情移入」することや、「自分と対象との境界はほとんど霧消してしまう」ことは、「人称」とはまた別の次元の問題なのではないでしょうか。この作品においても、作者は、作者自身の感じたことを、作者の立場から表現しているわけですから、「一人称としての文学」であることには、何ら変わりはないと私には思えるのです。
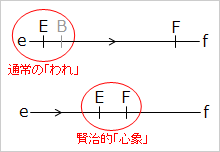 前回、「「心象」の体験線モデル」において、私は右のような図を書いてみましたが、左端に位置する「e=自極」から体験が出発しているところにおいて、やはり賢治のいうところの「心象」も、一人称的な経験であると、私は考えます。
前回、「「心象」の体験線モデル」において、私は右のような図を書いてみましたが、左端に位置する「e=自極」から体験が出発しているところにおいて、やはり賢治のいうところの「心象」も、一人称的な経験であると、私は考えます。
賢治の短歌も、後の時代の「心象スケッチ」と同じように、「自分と対象との境界はほとんど霧消してしまう」という特性があることを明確に示してくれた点において、佐藤氏のこの著書は私の蒙を啓いてくれるものでしたが、しかしその特性の本質は、「人称」にあるのではなくて、「体験様式」にあるのではないかというのが、この点に関する私の感想です。
まあそれはさておき、読みを先に進めると、佐藤通雅氏の『賢治短歌へ』の後半の4割ほどは、「賢治短歌」がいかにして徐々に「終焉」へと向かっていったかという軌跡をたどり、その運命を内在的に明らかにしていく論考になっています。
盛岡高等農林学校2年となった賢治は、『アザリア』同人に参加して、意欲的な作品を発表していきます。その「第一号」に発表したのが、「みふゆのひのき」および「ちゃんがちゃがうまこ」連作でしたが、これ以降の賢治は、「青びとのながれ」連作、「アンデルゼン氏白鳥の歌」連作、「北上川」連作など、「連作」形式に力を注ぐようになります。
この傾向について佐藤氏は、次のように述べておられます。
連作への傾斜をどうみるかも、大きな問題である。一首ごとの凝縮が短歌表現の基本だから、連作はその生理に反する。しかしつくり手の内部には、一首のわくにはおさまりきれない表現欲求が生じ、その結果として連作をまねきよせる。内部と形式のせめぎあいの結果としての連作とみてもよい。賢治におけるおさまりきれなさは、他分野の表現へ目ざめはじめたことと、同時に生じている。その意味では、連作は過渡的形態でもある。(p.241)
すなわち、童話や詩という、次の表現形式への移行への前触れが、少なくともここに現れているという指摘です。さらに、あらためて本書の半ばあたりまで戻って振り返ってみると、著者はすでに、次のように述べておられました。
初めにいわなかったが「大正三年四月」歌稿には、前半と後半の切れ目がある。入院、退院、帰花の日々の懊悩期間を前半とするなら、上級学校への受験許可がおりて平静をとりもどした期間が後半である。歌番号でいえば、192のあたりからだ。いままでの腐肉をひっかくようなおぞましさが、目にみえて後退しているので、それと知ることができる。代わって登場するのが物語性や詩性をおびた連作だ。「ガドルフの百合」や「めくらぶだうと虹」へ転生されていく作品群もある。(p.110)
というわけで、賢治の内の「物語性や詩性」への志向性は、盛岡高等農林学校入学前、賢治18歳の頃までさかのぼることができるというのが、作品の綿密な分析にもとづいた佐藤氏の指摘でした。
そして、最初は目立たなかったこの小さな「芽」が、しだいに成長していき、ついには短歌という形式を突き破ってしまうまでに至る過程が、たどられていきます。
賢治が短歌連作に大胆な構造性を取り入れた意欲作「みふゆのひのき」連作は、佐藤氏の評価によれば「壮大な失敗作」ということですが、その要因に関する佐藤氏の分析は、次のようなものです。
「ひのきの歌」失敗の因は、かなり根源的である。<われ>を主軸とする短歌形式にたいして、賢治は<われ>を脱色させた物語をつむぎあげようとした。短歌表現としての過重性はそこに結果される。しかし、この期になって、なぜ物語性をもちだすようになったのかといえば、賢治内部が急速にひろがりはじめたからである。
ここで著者は、「<われ>を主軸とする短歌形式にたいして、賢治は<われ>を脱色させた物語をつむぎあげようとした」という問題を、この記事の冒頭に述べた「<一人称詩>からの「ふみはずし」」の延長線上に考えておられるように思われますが、私自身は、これらは別に分けて考えた方がよいのではないかと感じました。
著者の言われる「<一人称詩>からの「ふみはずし」」とは、前述のように賢治独自の「体験様式」の特異性として考えるべきと思われるのに対して、「物語性」を追求していこうとするとどうしても「主観性」は後退せざるをえず、客観的な叙述の形式に近づくというのは、賢治に限らず普遍的な現象だろうと思うからです。
しかしそれにしても、賢治が短歌制作時代後半の一部の作品において、「<われ>を脱色させた物語をつむぎあげようとした」という佐藤氏の指摘は、私にとって個人的にも非常に興味深いものでした。
というのは、私は少し前に、「賢治詩の変容」というエントリで、「春と修羅 第三集」において出現してくる不思議な作品群を、かりに「無私架空物語的」と呼んで、晩年の文語詩の「人称超越構成的」な作品世界に、潜在的につながっているのではないかということを書いてみました。もしもここで、短歌の時代にも「<われ>を脱色させた物語」を表現しようとした作品群があったとすれば、上記の系譜は、さらに早い時代にまでさかのぼらせることができるかもしれないからです。
もちろん、それぞれの時期の作品の性格に、かなりのへだたりがあるのも事実ですが。
以上、途中にいろいろ勝手な私見を差しはさんだりしてしまいましたが、佐藤通雅氏の『賢治短歌へ』は、非常に読みごたえのある、これまで私が知る中で最高の賢治短歌研究書であると思います。賢治のディープな世界に興味をお持ちの方には、ぜひともご一読をお勧めする次第です。
最後に、本書の結末に置かれた含蓄のある言葉を引用させていただいて、ご紹介を終わります。
短歌をつくりはじめ、やがて唯一の表現手段としていくとき、賢治はまだ自分の心性には気づいていなかった。無意識のうちに、短歌として表現していただけだ。そこで、外面的には、青年期の短歌制作期をつうじて、定型感覚・韻律感覚を血肉化させていったと映るが、じつはその奥の原始心性への感応と二重になっていた。短歌の韻律感覚を手に入れながら、同時に内なる原始心性をよびさましていく、それが賢治にとっての短歌制作だった。
歌稿〔B〕をもって、ひとまず賢治短歌は終焉する。しかしこの終焉は、つぎの賢治世界をひらいていくための起点にほかならなかった。
 |
賢治短歌へ 佐藤 通雅(著) 洋々社 2007-05 Amazonで詳しく見る |
コメント