賢治の文語詩定稿における詩句配置形が、親鸞の「和讃」の引用形のそれと関わっているのではないかなどという変な話のつづきに、あと少しだけお付き合いください。
「文語詩稿 五十篇」「文語詩稿 一百篇」の定稿では、ほとんどは1行に「七・五」または「五・七」の句を縦に2つ配置しています。しかし、ごく少数だけですが、1行に3つの句を並べている作品もあります。「〔林の中の柴小屋に〕」、「山躑躅」、「氷上」がそれです。
これらはすべて、[七+五]×3で1行になっていますから、詩としては1行が非常に長いものです。近代以降の詩では、このような形式のものを私は他にあまり見たことがないのですが、初期の「和讃」の中には、先日引用した「極楽国弥陀和讃」や、「栴檀瑞像和讃」というもののように、1行が[七+五]×3となっているものが散見されます。
もっとも、これらを賢治が見知っていたかどうかはわかりませんが。
あと、「双四聯」という言葉の意味するところについて、です。
先日の記事でも触れたように、賢治はある文語詩草稿用紙の裏に、下記のような「メモ」を残していました。
文語詩双四聯に関する考察
一、概説文語詩定型詩、双四聯、沿革、今様、藤村、夜雨、白秋、
二、双四聯に於る起承転結
三、格律、単句構成法、
四、韻脚、
ここに出てくる「双四聯」という言葉は、文語詩の形式の名称のようですが、この聞き慣れない語の出典については、これまでの研究でもまだわかっていません。栗原敦さんは、その著書『宮沢賢治 透明な軌道の上から』(新宿書房)において、「宮沢賢治独自の造語であろうか、という判断に傾いている」と記しておられます。
また、この「双四聯」が具体的にどのような形式を指しているのかということについても、現在のところ定説はありません。
ただ、私が目にしたかぎりでは、これまでに下記のような示唆がなされています。
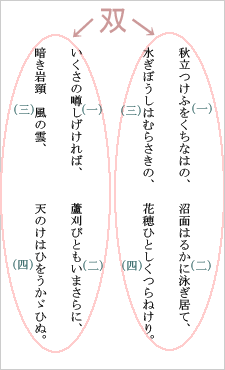 まず、栗原敦さんは上掲書において、次のように述べておられます。
まず、栗原敦さんは上掲書において、次のように述べておられます。
宮沢賢治の「双四聯」という用語は、あるいは(中略)、彼の「文語詩」に最も典型的な、四句で前後双つの聯にまとめられて連結されている型式を称するものとして造り出されたのかもしれない。
これを図示すれば、右図のようになります。「文語詩稿 五十篇」の「上流」という作品を例にとってあります。
この考え方では、作品全体を前半の2行と後半の2行に分けて「双」ととらえ(ピンクの楕円)、各々の内部に、「七・五」ずつの(一)~(四)を下位分節するわけです。
一方、歌人の岡井隆さんは、著書『文語詩人 宮沢賢治』(筑摩書房)において、次のように書いておられます。
「双四聯」の中身は、わたしにはわからないが、実作から察すると、中国詩の五言律詩や七言律詩が、「二句を一聯とした四聯から成る」というのに、よく似ている。「上流」でいえば、一行が一聯に相当する。<秋立つけふをくちなはの、>と<沼面はるかに泳ぎ居て、>が、一つの≪双≫を成すととれば、その≪双≫句を四つつらねた「双四聯」という命名も、考えられなくはない。
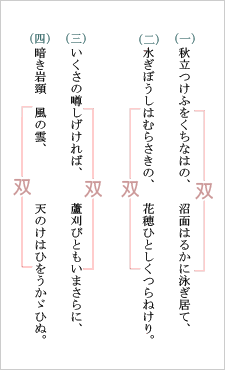 これを図示すれば、右のようになります。まず一行のうちの、上の「七・五」と下の「七・五」を「双」としてとらえ、これが(一)から(四)まで、「四聯」ならんでいると考えるのです。
これを図示すれば、右のようになります。まず一行のうちの、上の「七・五」と下の「七・五」を「双」としてとらえ、これが(一)から(四)まで、「四聯」ならんでいると考えるのです。
ただしお二人とも、これらを自説として「主張」するというスタンスではなく、あくまで一つ考え方として示唆するにとどめておられます。
さて、この二つの解釈のうち、実際に賢治はどちらの意味で「双四聯」という言葉を使っていたのでしょうか。
岡井隆さんが述べておられるとおり、漢詩における「聯」という語の原義から考えると、下図の解釈の方がもっともらしく思えます。
「律詩」というのも、この例と同じく全体で八行ありますが、一行目と二行目を合わせて「第一聯」、三行目と四行目を合わせて「第二聯」と言うのです。
しかし、先日からここに書いているように、賢治の文語詩定型を、「短和讃」、すなわち [七+五]×4 が、いくつか連ねられた形として理解するとすれば、また見方は変わってきます。
この「上流」という作品は、いわば「短和讃」を2首連ねたものですから、全体を何らかの形で分節するとすれば、まず上方の図のように、前半と後半の2つの部分に分けるのが、妥当に思われるのです。ここで、ピンクの楕円で囲まれた単位が、「短和讃」=「今様」の1首にあたるわけです。
というわけで、私自身はやや、上方の図の「栗原案」の方に傾いているところです。ただ命名法に関しては、「四句で前後双つの聯」と解釈するよりも、「聯」を「つらなり」という一般的な意味にとって、「四つの聯なりが双つ」と読む方が自然かな、と思ったりもしています。
コメント