大島紀行 詩群
1.対象作品
『三原三部』
「補遺詩篇 II」
「文語詩未定稿」

元町港と三原山 (2002.5.3)
![]()
2.賢治の状況
宮澤賢治は、友人の伊藤七雄の招待で、1928年6月に伊豆大島を訪れました。その日付は、作者が作品に付けたものでは上記のように6月13日~15日となっていますが、「【新】校本全集」の年譜では、当時の天候や賢治の書簡をもとに、実際には6月12日~14日であった可能性が高いと推定しています。
この大島行きの隠された意味については、歌曲「火の島」の項でも触れました。
伊藤兄妹は、この少し前、おそらく同じ年の春に、花巻に賢治を訪ねたようですが、きっとこの時三人は、ほんとうに親しく楽しいひとときを過ごしたのだと思います。賢治は伊藤の妹チヱに、優しくかつユーモアを持って接したでしょうし、チヱの方のも、そんな賢治に好感をもったのでしょう。
そこから、「お見合い」という話がでてきたかと思われますが、兄の伊藤七雄の方には、自分が大島に計画している「農芸学校」のスタッフに、将来的には賢治も身内として加わってほしいという思いもあったのかもしれません。
おそらく賢治のことですから、事前に「お見合い」などと聞いていたら、大島には行かなかったでしょう。しかし一方で賢治の方も、この兄妹から寄せられている好意が、たんなる友情という範囲を越えた特別なものになっていることを、きっと何となく感じとって、わかっていたはずだと思います。
この旅行中に書いた諸作品には、この兄妹に対して賢治の側からも意識していた、特別な感情が表れているように思うのです。
さて、賢治はこの大島の旅行中に、上に掲げたような作品の下書きをしています。『三原』三部作と、三篇の文語詩ですが、後者の三篇は、実は二曲の歌曲の歌詞として作られたものでした。
まず「三原 第一部」では、東京霊岸島から汽船に乗って、大島に向かうところが描写されています。船は、午前8時発で、大島の元村港には午後2時に着いたと推定されています。
作品の中には、おもに東京の港から離れて間もないうちの、船からの景色が記されていますが、「なまめかしい」「甘ずっぱい」など、官能的な形容詞が目を引きます。賢治とて、これから自分に好意を寄せてくれている若い女性に会いにいくのですから、胸にそんな思いがあって当然だと思います。
有名な、「…南の海の/南の海の/はげしい熱気とけむりのなかから/ひらかぬまゝにさえざえ芳り/つひにひらかず水にこぼれる/巨きな花の蕾がある…」という一節は、明らかにチヱのことを象徴していると思われますが、すでに賢治は大島に着く前から、自分とチヱが結ばれることはないのだということを、意識していたのでしょうか。
大島で二日目の「三原 第二部」では、農学者および芸術家としての賢治が、まさにその真骨頂を発揮します。
おそらく兄妹二人を前にして、裸足で土の上を行き来しつつ、土壌や環境の分析、種子の蒔き方、造園法などについて、躁的なほど饒舌にしゃべりまくります。かつて自ら「気圏オペラの役者」(「東岩手火山」)と名乗ったように、賢治のこういう立ち居振る舞いには、何か演劇的な才能も感じてしまいます。
チヱもあっけにとられたのではないかと思いますが、後に「何かしらとても巨きなものに憑かれてゐらっしゃる御様子」と回顧したのは、こういう賢治のことだったのではないでしょうか。
「三原 第三部」では、賢治はすでに大島を離れて、東京に帰る船上にいます。
最初の部分に少しだけ、「島」の描写もありますが、一眠りして目覚めると、もはや大島は影もなく、賢治は「なぜわたくしは離れて来るその島を/じっと見つめて来なかったでせう」と悔やみます。一人になってみると、兄妹の前ではたくさんしゃべったり動いたりして高揚していた気分も否応なくおさまり、「たうたうわたくしは/いそがしくあなた方を離れてしまったのです」という現実に直面します。そこで彼は、切実な愛惜の情にとらわれます。
それから後の賢治は、ひたすら空に浮かぶ雲を見ながら、とりわけチヱのいる大島の上空の雲に、思いを託します。
その方角の空は、いったんは「まばゆく光る横ぐもが/あたかも三十三天の/パノラマの図のやうにかゝってゐる」ように見えますが、日暮れとともに「もうあのかゞやく三十三天の図式も消えて/墨いろのさびしい雲の縞ばかり」となってしまいます。
しかし全篇の最後に、沈む夕日が空を染めて、「そらはいちめん/かゞやくかゞやく/猩々緋です」となって、作品はしめくくられます。賢治はこの美しい夕焼けに、二人の幸せを祈る気持ちをこめたのでしょう。
さて、次の文語詩「〔島わにあらき潮騒を〕」と「〔しののめ春の鴇の火を〕」とは、前者が後者の改稿形という関係にあります。下に参考のために、「【新】校本全集」第七巻校異篇から、草稿関係図を引用しておきます。(クリッカブルマップになっていますので、草稿名をクリックすると、テキストが表示されます。)
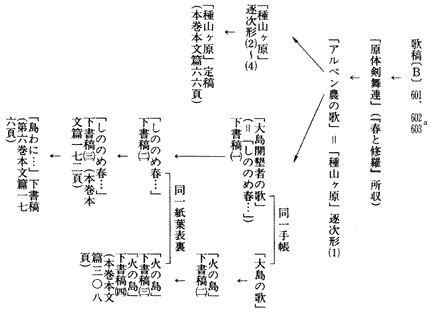
「大島開墾者の歌」から、「〔しののめ春の鴇の火を〕」を経て、「〔島わに荒き潮騒を〕」に至る系列は、そもそも歌曲「種山ヶ原」の「替え歌」の歌詞として、構想されたものでした。「種山ヶ原」は、故郷岩手の農業発展への願いをこめた讃歌でしたが、こちらの方はいわば、大島の農業への応援歌です。やはり、「種山ヶ原」のメロディーで歌うことができます。
前述したように、賢治はこの旅のあいだに、二曲の歌曲を作ろうとしていますが、この「島わに…」の方の歌は、大島の地に農芸学校を開こうとしている、兄の伊藤七雄のために捧げる歌と言えるでしょう。
これに対して、もう一曲の「火の島」の方は、きわめて個人的な感情を歌っていて、これは言わば、賢治が妹の伊藤チヱのために捧げようとした歌なのではないでしょうか。
「下書稿(一)」や「下書稿(二)」に出てくる、「わが胸の火ぞ燃ゆる」などの表現は、やはり賢治自身がチヱに対していだいていた気持ちを指しているのだと思います。
この感情は、ふつうの人だったら「恋愛感情」と呼ぶところのものかもしれませんが、賢治は結局、迷う様子も見せずに、チヱの傍らを通りすぎて行きました。このような対人的距離の取り方は、賢治らしいと思います。
そして伊藤七雄は、3年後の1931年に、念願の「大島農芸学校」の開校にこぎつけたのですが、その直後に、結核で亡くなります。宙に浮いてしまった農芸学校は、翌年の1月で廃校となりました。
兄の看病を続けていたチヱも、その後大島を離れ、東京で保母をしたということです。
それにしても、結核にむしばまれた自分の死期が遠くないことを悟っていたであろう伊藤七雄は、将来は賢治に大島農芸学校を託したいという願望をひそかにいだいていたのではないでしょうか。自分の妹チヱと賢治の結婚を望んでいたという気持ちの奥には、そんな期待があったのかもしれないと思ったりもします。
しかし結局、その思いはかなわず、薄倖の兄妹は大島から姿を消しました。
![]()
私は2002年5月、伊藤七雄がその夢を託した「大島農芸学校」の建っていた場所を見てみたくて、伊豆大島を訪ねました。
事前には、その場所について詳しくはわからなかったのですが、現地に着いてからあれこれ調べて、だいたいの見当がついたので、元町港から自転車で行ってみました。
こちらは、大島町観光協会でコピーさせていただいた住宅地図です。これで左上隅のあたりの、「野地655番地」という所が、伊藤七雄の旧宅があった場所です。現在は、藤平氏という方の宅地になっています。
またこちらは、萩原昌好氏が推定して作製した地図を、「賢治の事務所」の加倉井さんが撮影して送ってくださったものです。大島農芸学校の敷地跡も、示されています。
以下に、1928年6月に伊藤兄妹と賢治の三人が、楽しくかけがえのない二泊三日を過ごした場所、伊藤七雄旧宅跡付近の写真を掲げておきます。

伊藤家のあった場所に現在建っている民家

かなりの部分は、鬱蒼とした林になっている

一部は、畑になっている

「かういふ土ははだしがちゃうどいゝのです」

伊藤旧宅方向へ入る道
![]()