 今年はコロナのために、人が集まる様々なイベントが軒並み中止になり、賢治関係のセミナーなども開かれず寂しい日々が続いていますが、そんな中で立正大学文学部が、「賢治の世界を旅する」と題したオンライン公開講座を開催すると聞き、申し込んでみました。
今年はコロナのために、人が集まる様々なイベントが軒並み中止になり、賢治関係のセミナーなども開かれず寂しい日々が続いていますが、そんな中で立正大学文学部が、「賢治の世界を旅する」と題したオンライン公開講座を開催すると聞き、申し込んでみました。
去る10月14日(水)に、限定公開の YouTube でその第1回の講座があり、講師は哲学者の野矢茂樹さん、聞き手は文学部准教授の葉名尻竜一さんのお二人で、お題は「『風の又三郎』を読む―哲学と文学の対話」でした。
野矢茂樹さんというと、ウィトゲンシュタインの研究者であり、論理学のテクストも何冊も書いておられることからして、非常に厳格な議論をなさるのかと思ってしまうかもしれませんが、最近出された『心という難問―空間・身体・意味』という本では、私たちの素朴な実感に根ざした「しなやかな」哲学を構築され、また書評集の『そっとページをめくる』では、賢治の「土神ときつね」に関して、胸にじんと来るような文章も書いておられましたので、とりわけ楽しみにしていたのです。
野矢さんのお話をお聞きするのは初めてだったのですが、YouTube の画面に登場したお姿は、私のイメージどおりのソフトな紳士でいらっしゃいました。しかしそのお話は、優しくにこやかな雰囲気の奥底から、「風の又三郎」という作品に対する野矢さんの長年の熱い思いが、ほとばしり出てくるようなものでした。聞き手の葉名尻竜一さんのツッコミもほとんど的確で、風に乗って飛翔するような野矢さんのお話に、賢治研究からの知見などをうまくはさみこんでくれました。
私はだいたい動画をじっと視聴するというのは苦手なたちで、同じ内容なら文章で読ませてもらう方がよほどありがたいのですが、今回のお二人の生き生きとした話には、1時間があっという間に過ぎていました。
野矢さんのお話の中心は、「風の又三郎」に描かれている「異界」のあり方、というところにあったと思います。
賢治の作品の中で、一般にはもっとポピュラーな「銀河鉄道の夜」よりも、とにかく野矢さんは「風の又三郎」が大好きなのだと熱く語られ、二つの童話を対比して、「銀河鉄道の夜」は「空想」の物語であるのに対して、「風の又三郎」は「幻想」の物語だとおっしゃっていたのが、印象的でした。
野矢さんの言う「空想」においては、現実の世界と離れた別なところに非現実の「異界」が存在するのに対して、「幻想」とは、この現実の世界に「裂け目」ができて、そこに「異界」が顔を覗かせるのだ、ということでした。
この分類は、他の作家に当てはめてみることもできるでしょうが、とりわけ宮澤賢治という人は、後者の「現実世界の中にふと顔を覗かせる異界」の様子を描くことにおいては、類い稀な能力を持っていたと言えるでしょう。そしてその典型例が、まさに「風の又三郎」です。
おそらく賢治は、何気ない日常生活の中においても、この世ならぬものの姿を見たり、不思議な声を聴いたり、様々な幻覚体験をしていたと思われますので、生涯にわたってそういう異界の魅惑にも恐怖にも、深く親しんでいたのではないでしょうか。童話「インドラの網」に出てくる、「天の空間は私の感覚のすぐ隣りに居るらしい」という主人公の独白は、まさに彼自身の実感だったのだと思います。
「異界」の中でも、死者のいる場所を特に「他界」と言いますが、この他界に関する古今東西の様々な観念にも、上記と共通するものがあると思います。
キリスト教や仏教では、他界はこの世とは隔絶された超越的な場所とされるのに対して、柳田国男らが明らかにした日本の固有信仰では、死者の魂のいる場所は、人々が暮らす里を見下ろす山の上であったり、海の彼方の島であったりして、私たちの日常世界から少し離れてはいるけれども、いつも見渡せる範囲の中なのです。また柳田は「先祖の話」の中で、「お互いの眼にこそ見えないが、君と自分とのこの空間も
私は以前に、賢治が亡き妹トシの行方を探し求める過程の作品において、彼は上のような「超越他界観」「山上他界観」「海上他界観」「隣接他界観」を遍歴し、次第に遠くから自分の身近に、トシを感じるようになっていったのではないかと考えて、下のような図にしてみたこともありました(「賢治の他界観の変遷図」)。
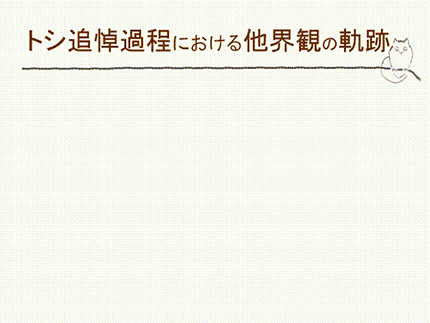
今回の講座で野矢さんが用いられた「空想」と「幻想」という言葉は、新たな独自の用語法ではありますが、このような賢治の「異界観」や「他界観」にも、つながるように感じました。
ところで、野矢さんがこの二つの概念を提示された際に、聞き役の葉名尻竜一さんは、「銀河鉄道の夜」はジョバンニが現実世界から異界に行ってまた帰って来る物語で、「浦島太郎」と同型であるのに対して、「風の又三郎」は、異界から来訪者が来てその後また帰って行ってしまう物語であることから、「竹取物語」と同じ構造をしているという指摘をされました。これはこれで興味深い対比で、賢治の作品の中でも「銀河鉄道の夜」や「ひかりの素足」は「行きて帰りし物語」の形であるのに対して、「風の又三郎」や「雁の童子」は、折口信夫の言う「マレビト」がこの世を訪れて、また去って行くという構図です。
ただしこの対比は、野矢さんのおっしゃるところの「空想」と「幻想」、すなわち「異界がこの現実世界と離れた別の場所にあるのか/それともすぐ隣にあってふと顔を出してくるのか」という問題意識とはまた別の話で、ここで少し論旨が拡散してしまった感がありました。
あと、「風の又三郎」に関しては、「九月八日」の章の最後で「雨はざっこざっこ雨三郎/風はどっこどっこ又三郎」と最初に叫んだのは、いったい誰だったのかという、これまでもよく論じられてきた「謎」があります。これについて野矢さんは、この声は異界から又三郎を呼び戻すものだったのだという考えを示されたのが、心に残りました。
そして実際、物語ではこの場面が高田三郎の登場する最後となり、次の「九月十二日」の章では、三郎はすでに転校して不在になっているのです。
一方、天沢退二郎さんは『宮澤賢治の彼方へ』所収の「風の又三郎は誰か」の中で、この箇所について、次のように述べておられます。
では最初に叫んだのは誰か。その答を賢治は書いていない。というより、その問を賢治はさりげなく蔽いかくして、やりすごしている。すなわち、叫んだのは「誰でもなかった」と作者は云いたがっているのである。全体的に非常にリアルな一種の生活童話であり、賢治の他の作品に頻出するごとき幻想や超自然的驚異が顔を出さない作品と考えられがちな『風の又三郎』であるが、ここの一箇所はまさしく賢治一流の、幻覚的な怪異の露出といわねばならない。
では最初に叫んだのは誰か。答はかんたんだ。あまりに明らかだ。それこそ風の又三郎 である。その叫びは、気のつかぬ間にまったく薄くなった作品世界のすぐ向うがわの、沈黙と死の国、存在の世界の声の、時ならぬ闖入にほかならない。
この叫び声が、「異界」からのものだと考える点では、天沢さんも野矢さんも共通しているのですが、天沢さんの説に従えば、「高田三郎と風の又三郎は別の存在である」ことが明らかになり、全ての子供たちがこの世の現実の存在としてきちんと整理がつくとともに、それでも最後に異界から響いた声の幻想性が、ことさら際立ちます。
これに対して野矢さんの解釈では、最後になって「やはり高田三郎は風の又三郎だった」ということになり、あらためて現実世界と異界の境目がどこにあったのかわからなくなって、読者は不思議な混沌の中に投げ込まれます。この解釈に立てば、三郎が「雨はざっこざっこ雨三郎/風はどっこどっこ又三郎」という声を聞いて動揺を隠せず、「何だい。」と言いながらも体が震えていたのは、月に帰る時が来たことを知ったかぐや姫のように、仲良くなった者たちとの突然の別れを意識し、悲しみ動転していたのだということになります。
これは、どちらが正解というような問題ではなくて、こういう多面的な読みが楽しめるところが、また賢治の作品の奥の深さなのでしょう。
これからもコロナ禍がおそらくまだ年の単位で続く以上、全国の賢治研究者を擁する「宮沢賢治学会イーハトーブセンター」などでも、今後こういったウェブ企画が順次行われていけば、ありがたいものだと思います。
コメント