ナポレオン・ボナパルトがクーデターによりフランス第一共和政を葬り去った半世紀後に、その甥のルイ・ナポレオンがやはりクーデターによって、第二共和制を崩壊させたという「歴史の繰り返し」を評して、マルクスが著書『ルイ・ボナパルトのブリュメール18日』の冒頭で述べた次の言葉は、広く知られています。
世界史上の大事件と大人物は二度現れると、かつてヘーゲルは書いた。だがヘーゲルは、次の言葉を付け加える事を忘れていた。その一度目は悲劇として、二度目は喜劇として、ということである。
これを最近の日本の政治で見ると、いえ無論それは「世界史上の大事件」などでは到底ありませんが、まず第一次安倍内閣の時にも閣僚の不祥事が相次いで、佐田特命大臣の辞任に続き、松岡農林水産大臣は政治資金問題を追及された結果、議員宿舎において自殺するという「悲劇」に至りました。これに続き、久間防衛大臣、赤城農林水産大臣、遠藤農林水産大臣も辞職する事態に及び、安倍首相自身も、まもなく辞任に追い込まれたのです。
一方今年の秋、第二次安倍内閣でも改造後に閣僚の不祥事が続き、2人の大臣が同時に辞任する運びとなりました。しかし今回の事態は、「これは“うちわ”か否か」などという珍妙な論争が国会で行われた挙げ句の結末であり、こちらは「喜劇」としか言いようがありません。
ということで、「一度目は悲劇として、二度目は喜劇として」という歴史の繰り返しは、やはり実際にあるものですね。
 |
ルイ・ボナパルトのブリュメール18日―初版 (平凡社ライブラリー) カール マルクス Karl Marx 平凡社 2008-09 Amazonで詳しく見る |
※
…と、話がえらく下世話な感じになってしまいましたが、実のところ本日述べたかったのは、もう少し神妙な事柄です。
喜劇王チャーリー・チャップリンが述べたとされる言葉として、次のようなものがあります。
人生とは、クローズアップで見ると悲劇だが、遠景で見ると喜劇である。
(Life is a tragedy when seen in close-up, but a comedy in long-shot.)
この含蓄のある言葉の出典がどこにあるのか、ネットであれこれ検索してみてもはっきりとはしないのですが、すでにこれはチャップリンの遺した箴言として、世界的に広く浸透しています。
生粋の映画人であったチャップリンらしく、ここでは人生というものへの視点が、'close-up'と'long-shot'という映画の撮影手法に喩えて表現されています。これは、ドタバタ喜劇の中でも、つねに庶民の悲哀とペーソスを描きつづけた、いかにも彼らしい言葉と感じられます。
先に挙げたマルクスの言葉が、時間的な順序に従って「悲劇」と「喜劇」が生じると言っているのに対して、こちらの言葉は、空間的な距離に伴って、「悲劇」となったり「喜劇」となったりしているというわけですね。
ここでチャップリンのこんな言葉をご紹介した理由は、これがまさに、宮澤賢治の口語詩と文語詩との関係にも当てはまるように、私には思われるからです。
『春と修羅』に始まる賢治の口語詩においては、激しいパッションをもって人間存在の修羅性や死の痛切な悲しみを描いた作品が、何と言っても印象的です。
これに対して、晩年に書かれた文語詩においては、人生における何気ないような各場面を、「三人称的に」「客観的に」「無私の視点から」、淡々とそしてしばしばユーモアをまじえつつ叙述しているのが特徴です。そこでは、当事者たちに渦巻く生々しい感情は稀薄となって、「自然の風景」と「人間の営み」とが、微笑みを誘うようにまるで一幅の絵のごとく溶け合っているのです。
賢治の創作態度がこのように変化した理由は、いろいろあるでしょう。私が思うところのその一つの大きな要因は、口語詩を書いていた頃の賢治は、身をもって人生や現世の苦難に直面していたのに対して、文語詩を書くに至った頃の賢治は、社会生活からは離れほとんど病床で過ごしつつ、昔の自分の詩稿に想を得たり、自らの人生をノートに整理して回顧したりしながら、自分や他の人々の人生を、観想的に眺めていたというところにあるのではないでしょうか。
上のチャップリンの言葉に倣えば、前者においては賢治は人生を「クローズアップ」で目にしていたのに対して、後者においては、遠くから「ロングショット」で眺めていた、ということになります。
それが、あるものを「悲劇」として表現するか、「喜劇」として表現するか、という違いを生んでいるのではないかと思うのです。
※
具体的な例を挙げてみましょう。
たとえば、「春と修羅 第三集」に属する「〔何をやっても間に合はない〕」という口語詩は、後に改作されて、「副業」という文語詩になります。
「〔何をやっても間に合はない〕」は、まず「詩ノート」に書き付けられた後、黄罫詩稿用紙に改稿されているのですが、ここではより臨場感をもって「クローズアップ」された姿を見ていただくために、その「詩ノート」上の形態を下に掲げます。
一〇九〇
何をやっても間に合はない
世界ぜんたい間に合はない
その親愛な仲間のひとり
また稲びかり
雑誌を読んで兎を飼って
その兎の眼が赤くうるんで
草もたべれば小鳥みたいに啼きもする
何といふ北の暗さだ
また一ぺんに叩くのだらう
さうしてそれも間に合はない
貧しい小屋の軒下に
自分で作った巣箱に入れて
兎が十もならんでゐた
もうここまででも
みちは倒れた稲の中だの
陰気なひばやすぎの影だの
まがってまがって来たのだが
あっちもこっちも気狂みたいに
ごろごろまはる水車の中を
まがってまがって来たのだが
外套のかたちした
オリーブいろの縮のシャツに
長靴をはき
頬のあかるいその青年が
裏の方から走って来て
はげしい雨にぬれながら
わたくしの訪ねる家を教へた
わたくしが訪ねるその人と
縮れた髪も眼も物云ひもそっくりな
その人が
わたくしを知ってるやうにわらひながら
詳しくみちを教へてくれた
ああ家の中は暗くて藁を打つ気持にもなれず
雨のなかを表に出れば兎はなかず
所在ない所在ないそのひとよ
きっとわたくしの訪ねる者が
笑っていふにちがひない
「あゝ 従兄すか。
さっぱり仕事稼がなぃで
のらくらもので。」
世界ぜんたい何をやっても間に合はない
その親愛な近代文明と新な文化の過渡期のひとよ。
この作品が書かれたのは、豪雨によって賢治が肥料設計した稲に甚大な被害が出た1927年8月20日のことで、その様子はやはり同日の「〔もうはたらくな〕」にも描かれています。人の力ではどうしようもない天災に直面して、賢治は必死の思いで、とある農家を訪ねようとしています。
途中たまた道を尋ねた農家では、副業として兎を飼っていました。激しい雷雨と、つつましい兎の巣箱の様子が、対照的です。しかしこの日の豪雨は、個々の農家によるこういう健気な工夫と努力をも、根こそぎ台無しにしてしまうほどの被害を、まさに引き起こしつつあるのです。
「何をやっても間に合はない」「世界ぜんたい間に合はない」と繰り返される言葉には、この現実に打ちひしがれた賢治の焦燥感や絶望感がこめられており、ここに描かれている情景は、まさに「悲劇」と言わざるをえません。
一方、この口語詩を賢治が晩年に文語詩化した「副業」では、情景は次のようになっています。
副業
雨降りしぶくひるすぎを、 青きさゝげの籠とりて、
巨利を獲るてふ副業の、 銀毛兎に餌すなり。兎はついにつくのはね、 ひとは頬あかく美しければ、
べっ甲ゴムの長靴や、 緑のシャツも着くるなり。
作品の舞台装置は、激しい雨、副業の兎、長靴、緑のシャツと、先の口語詩と共通しています。しかしここには、前作にあったような深刻な悲劇性はうかがえません。
「兎はついにつくのはね」(「つくのはね」は、償わない=採算が合わないこと)とやはり書かれていて、この副業が生活の「間に合はない」ことに変わりはないのですが、賢治はこの兎を飼い主の思惑を、「巨利を獲るてふ副業」と表現することで、あたかも「一攫千金を夢見るお人好し」のように造型しています。
さらにその飼い主は、「頬あかく美し」き人で、当時流行の「べっ甲ゴムの長靴」や「緑のシャツ」を身につけるという、なかなかのお洒落もしているのです。
すなわち、この文語詩の作品世界では、農家の厳しい境遇や運命の悲惨さなどではなく、一人の紅顔の農民の魅力、ユーモラスでもあるその無垢な純真さが、まるでミレーの絵のように、描かれているのです。
これは「喜劇」というほどではないにしても、読む者をふっと微笑ませてくれるものでしょう。
同じ題材を扱いながら、口語詩と文語詩とのこのような相違は、「出来事」と「書き手」との間に存在ある、時間的な距離が生み出しているのではないでしょうか。すなわち、豪雨災害の危機感の只中で書かれた口語詩と、それから遙か何年も経って賢治にもいろいろあって、病床の中で多少とも懐かみつつ回想しながら書かれた文語詩との間の違いです。
ついでにもう一つ、例を挙げておきます。
まずは、やはり「春と修羅 第三集」の、「〔同心町の夜あけがた〕」です。
一〇四二
一九二七、四、二一、
同心町の夜あけがた
一列の淡い電燈
春めいた浅葱いろしたもやのなかから
ぼんやりけぶる東のそらの
海泡石のこっちの方を
馬をひいてわたくしにならび
町をさしてあるきながら
程吉はまた横眼でみる
わたくしのレアカーのなかの
青い雪菜が原因ならば
それは一種の嫉視であるが
乾いて軽く明日は消える
切りとってきた六本の
ヒアシンスの穂が原因ならば
それもなかばは嫉視であって
わたくしはそれを作らなければそれで済む
どんな奇怪な考が
わたくしにあるかをはかりかねて
さういふふうに見るならば
それは懼れて見るといふ
わたくしはもっと明らかに物を云ひ
あたり前にしばらく行動すれば
間もなくそれは消えるであらう
われわれ学校を出て来たもの
われわれ町に育ったもの
われわれ月給をとったことのあるもの
それ全体への疑ひや
漠然とした反感ならば
容易にこれは抜き得ない
向ふの坂の下り口で
犬が三疋じゃれてゐる
子供が一人ぽろっと出る
あすこまで行けば
あのこどもが
わたくしのヒアシンスの花を
呉れ呉れといって叫ぶのは
いつもの朝の恒例である
見給へ新らしい伯林青を
じぶんでこてこて塗りあげて
置きすてられたその屋台店の主人は
あの胡桃の木の枝をひろげる
裏の小さな石屋根の下で
これからねむるのでないか
賢治は、自分で作った野菜や花をリヤカーに積んで町へ売りに行くところですが、近所の農民(程吉)の冷たい視線に遭います。それが、作物に対する「嫉視」であるのならまだ根は浅いが、町に育ち、学校を出て、月給をとったことのあるものへの疑いや反感ならば、もっと根は深いと嘆じています。
道中の情景には心温まる部分もありますが、賢治の心の中は、苦々しく重たいものです。
一方、これが後に文語詩に改作された、「短夜」という作品を次に掲げます。
短夜
屋台を引きて帰りくる、 目あかし町の夜なかすぎ、
うつは数ふるそのひまに、 もやは浅葱とかはりけり。みづから塗れる伯林青の、 むらをさびしく苦笑ひ、
胡桃覆へる石屋根に、 いまぞねむれと入り行きぬ。
ここでは、作者の心に当時あった重苦しい思いは消し去られ、ロングショットのカメラが代わりにとらえるのは、口語詩では最後に登場していた「屋台店の主人」です。
屋台に自分で施した塗装のその塗りむらに苦笑しつつ、仕事を終えてさあ寝ようと家に入るその主人…。ここにもやはり人生のペーソスが、ふと垣間見えています。
賢治は詩稿用紙の上で文語詩を推敲しつつ、当時の自分の個人的な思いよりも、こういった人間のふとした仕草を思い出しつつ愛おしみつつ、書き付けていったのだろうと思います。
チャップリンが、映像表現において「クローズアップ」と「ロングショット」で対比したのは、カメラと被写体との間の「空間的な距離」でしたが、賢治にそのような視点を与えてくれたのは、対象との「時間的な距離」だったと言えるでしょう。
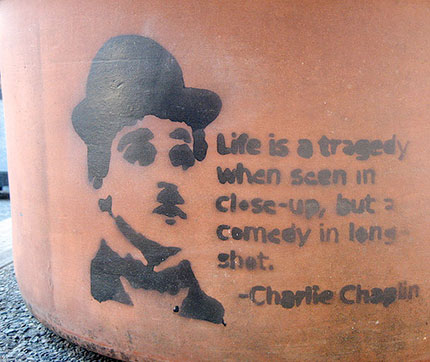
ガハク
書くという行為が既にその瞬間の感情から一歩引いた場所に自分を置くと漱石は虞美人草でしたっけ書いてました。あれは感情的距離を言っていますね。
賢治も書き続けながらその距離をとっていたかもしれないとも思います。感情のはけ口や昇華というような。そして時間をおいてさらに当時の心境を過去においた感懐の中で言葉を練り直すという作業が確かにあったでしょうね。それから推敲する時に長文から短文、自由律から定型というような形式の違いなんかも感情表現に反省を加える大きな要素でもあったでしょうか。
読んでパッと思い出したのは15世紀?ヨーロッパのマニエリスムです。
神話や聖書に由来したテーマで描きながらその主題そのものは風景の隅に追いやられその気になって探さないと全体の構図に埋没してしまうというやつです。あれは映画でいう「引いて撮る」手法ですね。そしてクローズアップでは悲劇が喜劇とまではいかないまでも日常の一情景にまで換骨奪胎されています。誰でもが知っている事をどう画家が面白く表現してくれているかを楽しむと。
こうして新旧の作品を比べて眺めさせて頂いていると距離をとって見るという態度の空間的又は時間的推移もさることながら賢治自身が自己の作品を推敲しながら同時に読む側に立ってその面白さを楽しんでる遊んでるようで僕には愉快でもあります。
hamagaki
ガハクさん、コメントをありがとうございます。
そうですね。一般には「書く」という行為自体が、体験を「対象化」して距離を置かせる営みであるのは確かですね。
賢治とて、つねにそういう立場に身を置きつつも、彼が特に「心象スケッチ」という方法論を標榜しつつ、「一刻一刻、心の中で生起する現象を、ありのままに書き取ろう」という試みを行ったことの目的は、そのように「対象化」する手前にあるナマの現実を、捉えようとすることにあったのかとも思います。
たとえば長詩「小岩井農場」などにおいては、普通の文学作品に見られるような主客が分離した作者と対象との関係は見えず、読む者はまるで混沌とした世界に連れ込まれてしまいます。
賢治の口語詩は、こういう特異な性質のために普通とはちょっと変わっているのに対して、また逆に文語詩の方では反対の極端に行ってしまって、ほとんど「自我」というものが姿を消して、完全に「引いて撮る」という感じの画面になっています。
そういう両極端なところが、チャップリンの言葉の「クローズアップ」と「ロングショット」に、典型的に当てはまるように感じた次第です。
また、絵画史におけるマニエリスムの例を挙げていただいて、ありがとうございます。
「主題そのものは風景の隅に追いやられ」ているという状況は、まさに賢治の文語詩にも通底するように思います。
あるいは、賢治が若い頃は短歌を作っていて、晩年には俳句を作るようになったというのも、同じようなスタンスの変化と言えるかもしれませんね。
岡本康兒
「管理人あてメール」webmaster@ihatov.ccにメッセージをお送りしたのですが、跳ね返ってきます。賢治の楽曲の音源の使用許可を頂きたく連絡差し上げたいことがありますので、okamoo@gmail.comまで返信いただけたら幸いです。
hamagaki
管理人ですが、お手数をおかけしてすみません。
メールはちゃんと届いておりましたので、先ほど返信させていただきました。
素晴らしいお話を、ありがとうございます。