童話「ひかりの素足」と「銀河鉄道の夜」は、二人の子どもが図らずも死後の世界へ行って、うち一人はそのまま死の側に残り、一人だけが帰ってくるというお話です。作品世界の設定は、一方は岩手の方言が話される山村、他方は星祭りの行われる異国(?)ということで、雰囲気は対照的に異なっていますが、物語の骨組みは同じなのです。
さらに骨組みだけではなくて、その「死後の世界」の描写の細部にも、よく似たところがあります。
例えば、まず「ひかりの素足」に出てくるボール投げの話。
一人が云ひました。
「こゝの運動場なら何でも出来るなあ、ボールだって投げたってきっとどこまでも行くんだ。」
一方、「銀河鉄道の夜」では・・・。
〔以下原稿一枚?なし〕
「ボール投げなら僕決してはづさない。」
男の子が大威張りで云ひました。
次には、「ひかりの素足」に出てくる「巨きな人」が言及する不思議な本。
その巨きな人はしづかに答へました。
「本はこゝにはいくらでもある。一冊の本の中に小さな本がたくさんはいってゐるやうなのもある。小さな小さな形の本にあらゆる本のみな入ってゐるやうなのもある。お前たちはよく読むがいい。」
これに対し、「銀河鉄道の夜」(初期形第三次稿)における「青白い顔の瘠せた大人」が見せてくれる地歴の本。
ちょっとこの本をごらん、いいかい、これは地理と歴史の辞典だよ。この本のこの頁はね、紀元前二千二百年の地理と歴史が書いてある。よくごらん紀元前二千二百年のことでないよ、紀元前二千二百年のころにみんなが考へてゐた地理と歴史といふものが書いてある。だからこの頁一つが一冊の地歴の本にあたるんだ。
三つめには、「光の素足」に出てくるチョコレート。
「チョコレートもある。こゝのチョコレートは大へんにいゝのだ。あげやう。」その大きな人は一寸空の方を見ました。一人の天人が黄いろな三角を組みたてた模様のついた立派な鉢を捧げてまっすぐに下りて参りました。そして青い地面に降りて虔しくその大きな人の前にひざまづき鉢を捧げました。
「さあたべてごらん。」その大きな人は一つを楢夫にやりながらみんなに云ひました。みんなはいつか一つづつその立派な菓子を持ってゐたのです。それは一寸嘗めたときからだ中すうっと涼しくなりました。舌のさきで青い螢のやうな色や橙いろの火やらきれいな花の図案になってチラチラ見えるのでした。たべてしまったときからだがピンとなりました。しばらくたってからだ中から何とも云へないいゝ匂がぼうっと立つのでした。
そして、「銀河鉄道の夜」におけるチョコレート(?)。
「こっちはすぐ喰べられます。どうです、少しおあがりなさい。」鳥捕りは、黄いろな雁の足を、軽くひっぱりました。するとそれは、チョコレートででもできてゐるやうに、すっときれいにはなれました 。
「どうです。すこしたべてごらんなさい。」鳥捕りは、それを二つにちぎってわたしました。ジョバンニは、ちょっと喰べてみて、(なんだ、やっぱりこいつはお菓子だ。チョコレートよりも、もっとおいしいけれども、こんな雁が飛んでゐるもんか。
これらは、物語の大筋には関係のない小さな事柄なのですが、しかしこういう何気ない細部に類似があるところが、よけいに二つの作品の密接な関係を示している気がします。大塚常樹氏は、「ひかりの素足」のことを、「「銀河鉄道の夜」と双子関係にあると言ってもよい」と評していますが(『宮沢賢治 心象の宇宙論』p.278)、たしかにそうだなあという感じがします。
◇ ◇
ところで、今回考えてみたいのは、上のような共通点とは逆に、「ひかりの素足」と「銀河鉄道の夜」の相違点、についてです。
もちろん、前述のように二つの作品はその舞台設定も大きく異なりますし、「ひかりの素足」が仏教それも法華経の功徳を物語の中心に据えているのに対して、「銀河鉄道の夜」の方はいわば「汎宗教的」な要素を色濃く持ちます。いろいろ違いを挙げていけばきりがありません。
ただ私としては、こういった物語の設定などよりももっと奥深くの、物語としての「意味」の部分に、何か本質的な違いがあるのではないか、ということが気になったのです。
思いつくままに、いくつか挙げてみます。
1.死を自覚しつつ共に行くこと
「ひかりの素足」においては、一郎と楢夫という主人公の二人は、猛吹雪の中で気を失った後に「うすあかりの国」にやって来た時、自分たちが死んでしまったのだということを覚ります。
「楢夫、僕たちどこへ来たらうね。」一郎はまるで夢の中のやうに泣いて楢夫の頭をなでてやりながら云ひました。その声も自分が云ってゐるのか誰かの声を夢で聞いてゐるのかわからないやうでした。
「死んだんだ。」と楢夫は云ってまたはげしく泣きました。
じつは物語にはここに至るまでにも、死へと向かう伏線が周到に張り巡らされていました。
冒頭から、楢夫は自分が死装束を着せられ野辺送りをされる夢を見たことを語り、父や兄に(そして読者にも)不吉な予感を与えます。
そして二人が道行きを始めてしばらくすると、あの「象のやうな形の丘」にやって来ます。天沢退二郎氏は、この印象的なモチーフについて、次のように書き記しています(『≪宮澤賢治≫鑑』所収「峠を登る者」より)。
みちはいつか谷川からはなれて大きな象のやうな形の丘の中腹をまはりはじめました。(強調は天沢氏)
この≪まはりはじめました≫という表現はいかにもその“みち”が避けがたく宿命の鞍部へついに引きよせられて行くかを示すと同時に、宿命の大きな輪自体がゆっくりとカタストロフへと回転を開始したさまをも示していて、再読三読するときは息をのむばかりであるが、それというのも―そのような≪表現≫ではからずもあり得た根拠は―いうまでもなく≪象のやうな形の丘の中腹を≫という目的格の力によるのである。
すでに入沢康夫氏によって指摘されているように、この丘は、吹雪をえがいたもうひとつの賢治童話にも見出される―二疋の雪狼が、ぺろぺろとまつ赤な舌を吐きながら、象の頭のかたちをした、雪丘の上の方をあるいてゐました。(「水仙月の四日」)
そしてこの「水仙月の四日」でも、この丘の山裾の≪峠の雪の中≫で子どもが吹雪に遭って、埋もれる。
これ以外にも二人の運命を暗示するモチーフがいくつも配されているのは、天沢氏が上掲書において指摘しておられるとおりですが、とにかくこの物語において一郎と楢夫は、自分たちがまさに死のうとしていることを知りつつ吹雪に閉ざされ、まもなく死後の世界に自らを見出します。
これに対して、「銀河鉄道の夜」という物語において、ジョバンニは自分が銀河鉄道に乗りながらそこが「死後の世界」(あるいは生と死の境界領域)であることを、まったく自覚していません。彼は大好きなカムパネルラと一緒に列車の旅ができる嬉しさいっぱいで、死者と思しき人々が乗り合わせてきても、自分やカムパネルラの生死については無頓着です。
そして物語の終わり近く、現実世界に戻ったジョバンニはそこで初めて、じつはカムパネルラが死んでしまったこと、そして自分もさっきまでその親友と一緒に死後の世界を旅していたのだということを、知るのです。
私は先月、「死ぬことの向ふ側まで」という記事において、トシの死が近づきつつあった1922年夏頃の賢治が、できることならトシと運命をともにして、「死ぬことの向ふ側まで一諸について行ってやらう」と思っていたのではないか、そしてその気持ちを、当時「イギリス海岸」という短篇にも忍ばせたのではないか、ということを書きました。
上に挙げた「ひかりの素足」と「銀河鉄道の夜」の相違点は、このような賢治の思いに関わっているのかもしれません。
すなわち、「ひかりの素足」において一郎は、はっきりと自覚しつつ楢夫とともに、「死ぬことの向ふ側まで一諸について行ってやらう」と思っています。
これに対して「銀河鉄道の夜」においてジョバンニは、結果的には「死ぬことの向ふ側まで」カムパネルラに同行したことになりましたが、それはまったく本人の自覚的な行動ではありませんでした。ジョバンニは、自分がなぜ銀河鉄道に乗っているのかわからず、ポケットに「切符」を発見してからも、それについて尋ねられると「何だかわかりません」と答えるしかありませんでした。
「初期形第三次稿」においては、このジョバンニの体験はブルカニロ博士が行った「実験」だったということが最後に明かされます。しかし「第四次稿」においては、これはジョバンニの夢だったという形に改められました。
つまり、「ひかりの素足」の一郎が楢夫とともに死後の世界へ行ったのは、(不可避だったとは言え)本人にとって自覚的な行動だったわけですが、「銀河鉄道の夜」でジョバンニがカムパネルラとともに死後の世界へ行ったのは、本人にとっては意味不明な出来事であり、しいて言うならばそれは偶然に見た夢だったか、あるいは自分の与り知らない何か超越的な力によって起こった現象だったということになります。
2.兄弟であること
「ひかりの素足」と「銀河鉄道の夜」のもう一つの相違点は、前者は一郎と楢夫という「兄弟」の物語であるのに対して、後者はジョバンニとカムパネルラという「親友」の話であることです。
これは大して本質的な違いには見えないかもしれませんが、賢治の生涯を念頭に置いて考えてみると、主人公が「兄弟」であることは、賢治とトシという「兄妹」を否応なく連想させます。これに対して「親友」となると、保阪嘉内という存在のことも意識せざるをえません。
物語の中でも、ジョバンニはあたかも賢治が嘉内に対してそうだったように、カムパネルラに嫉妬したり拗ねたりしますが、一方「ひかりの素足」には、兄の一郎が弟の楢夫を献身的にいたわり守ろうとする姿が、何度も繰り返し印象的に描かれます。
例えば、まだ朝起きてまもない頃に顔を洗った後に一郎は、
その時楢夫も一郎のとほりまねをしてやってゐましたが、たうたうつめたくてやめてしまひました。まったく楢夫の手は霜やけで赤くふくれてゐました。一郎はいきなり走って行って
「冷だぁが」と云ひながらそのぬれた小さな赤い手を両手で包んで暖めてやりました。
と、弟への優しさを見せます。
吹雪に遭遇してからも、一郎は何度も何度も小さな弟に声をかけて、勇気づけようとします。
- 「あんまり急ぐな。大丈夫だはんて なあにあど一里も無ぃも。」
- 「さあもう一あしだ。歩べ。上まで行げば雪も降ってなぃしみぢも平らになる。歩べ。怖っかなぐなぃはんて歩べ。あどからあの人も馬ひで来るしそれ、泣がなぃで、今度ぁゆっくり歩べ。」
- 「来た来た。さあ、あどぁ平らだぞ 楢夫。」
- 「さあ 歩べ。あど三十分で下りるにい。」
- 「大丈夫だ。楢夫、泣ぐな。」
- 「さあも少しだ。歩げるが。」
そして、ついに二人が猛吹雪の中で立ち往生してしまう場面。
「泣ぐな。雪はれるうぢ此処に居るべし泣ぐな。」一郎はしっかりと楢夫を抱いて岩の下に立って云ひました。
風がもうまるできちがひのやうに吹いて来ました。いきもつけず二人はどんどん雪をかぶりました。
「わがなぃ。わがなぃ。」楢夫が泣いて云ひました。その声もまるでちぎるやうに風が持って行ってしまひました。一郎は毛布をひろげてマントのまゝ楢夫を抱きしめました。
一郎はこのときはもうほんたうに二人とも雪と風で死んでしまふのだと考えてしまひました。いろいろなことがまるでまはり燈籠のやうに見えて来ました。正月に二人は本家に呼ばれて行ってみんながみかんをたべたとき楢夫がすばやく一つたべてしまっても一つを取ったので一郎はいけないといふやうにひどく目で叱ったのでした、そのときの楢夫の霜やけの小さな赤い手などがはっきり一郎に見えて来ました。いきが苦しくてまるでえらえらする毒をのんでいるやうでした。一郎はいつか雪の中に座ってしまってゐました。そして一さう強く楢夫を抱きしめました。
一郎の弟に対する献身的な愛情は、「うすあかりの国」に入ってさらに胸に迫ります。
- 「さあ、兄さんにしっかりつかまるんだよ。走って行くから。」一郎は歯を喰ひしばって痛みをこらへながら楢夫を肩にかけました。そして向ふのぼんやりした白光をめがけてまるでからだもちぎれるばかり痛いのを堪えて走りました。それでももうとてもたまらなくなって何べんも倒れました。倒れてもまた一生懸命に起きあがりました。
- 「楢夫、しっかりおし、楢夫、兄さんがわからないかい。楢夫。」と一生けん命呼びました。
楢夫はかすかにかすかに眼をひらくやうにはしましたけれどもその眼には黒い色も見えなかったのです。一郎はもうあらんかぎりの力を出してそこら中いちめんちらちらちらちら白い火になって燃えるやうに思ひながら楢夫を肩にしてさっきめざした方へ走りました。足がうごいてゐるかどうかもわからずからだは何か重い巌に砕かれて青びかりの粉になってちらけるやう何べんも何べんも倒れては又楢夫を抱き起して泣きながらしっかりとかゝへ夢のやうに又走り出したのでした。- そのとき楢夫がたうたう一つの赤い稜のある石につまづいて倒れました。鬼のむちがその小さなからだを切るやうに落ちました。一郎はぐるぐるしながらその鬼の手にすがりました。
「私を代りに打って下さい。楢夫はなんにも悪いことがないのです。」- 楢夫がいきなり思ひ出したやうに一郎にすがりついて泣きました。
「歩け。」鬼が叫びました。鞭が楢夫を抱いた一郎の腕をうちました。一郎の腕はしびれてわからなくなってただびくびくうごきました。楢夫がまだすがりついてゐたので鬼が又鞭をあげました。
「楢夫は許して下さい、楢夫は許して下さい。」一郎は泣いて叫びました。
「歩け。」鞭が又鳴りましたので一郎は両腕であらん限り楢夫をかばひました。
まだ子どもである一郎が、これほどまでに自分の身を投げ打って、弟を守ろうとするのです。
私は、このような兄一郎の行動こそが、賢治が妹の死を前にして、「死ぬことの向ふ側まで一諸について行ってやらう」と思っていた気持ちの表現ではなかったのかと思うのです。
死んでいくトシの先には、どんな苦難が待ち受けているのか、賢治にもわかりません。賢治は、愛する妹を知らない世界に一人で往かせるのがあまりにも不憫で、できることなら自分が一緒について行って、一郎が楢夫にしたように、我が身を賭してでも守ってやりたいと願ったのではないでしょうか。
それからあともう一つ私としては、一郎と楢夫という兄弟が、賢治とトシという兄妹を投影したキャラクターだったのではないかと感じる理由が、あります。
下記は、物語の冒頭で目を覚ました一郎が、まだ眠っている楢夫の方を見やる場面です。
「ほう、すっかり夜ぁ明げだ。」一郎はひとりごとを云ひながら弟の楢夫の方に向き直りました。楢夫の顔はりんごのやうに赤く口をすこしあいてまだすやすや睡って居ました。白い歯が少しばかり見えてゐましたので一郎はいきなり指でカチンとその歯をはじきました。
楢夫は目をつぶったまゝ一寸顔をしかめましたがまたすうすう息をしてねむりました。
小さな子ども同士の、ささやかな微笑ましい情景です。賢治の作品の細部には、しばしばこういった絶妙とも言える描写が出てきて、いったい作者はどうやってこのようなディーテイルを思いついたのだろうと感心することがよくあるのですが、ただこの箇所に関しては、この悪戯は賢治がトシに実際にしてみたことなのではないかと、私は思うのです。
 ご存じのように、トシはとても美しい女性でしたが、唇の間から前歯が少しだけ顔を覗かせることがあったようです。
ご存じのように、トシはとても美しい女性でしたが、唇の間から前歯が少しだけ顔を覗かせることがあったようです。
右の有名な写真は、日本女子大学の卒業アルバムのために撮られたと言われているものですが(1918年?)、左の前歯がちょっと見えているようでもあり、そうでないようでもあります(ちくま学芸文庫『図説 宮澤賢治』より・部分)。
花巻高 等女学校の教諭時代、1921年2月の卒業式におけると言われている右の写真では、かわいい前歯の様子が、よりはっきりとわかります(ちくま学芸文庫『図説 宮澤賢治』より・部分)。
等女学校の教諭時代、1921年2月の卒業式におけると言われている右の写真では、かわいい前歯の様子が、よりはっきりとわかります(ちくま学芸文庫『図説 宮澤賢治』より・部分)。
賢治は「松の針」という作品において、トシを栗鼠に喩えていますが、ひょっとしたら彼女のこんな表情から、栗鼠をイメージしたのではないだろうかとも思ったりします。
そして、このようなトシの口もとの様子からすると、二人がまだもっと幼かった頃には、眠っているトシの唇の間から「白い歯が少しばかり見えて」いることもきっとあったのではないでしょうか。そして、賢治は思わず「指でカチンとその歯をはじき」たくなったのではないかと、私はひそかに想像するのです。
賢治は後年になってその記憶を、一郎が楢夫にした他愛もない仕草として織り込んだのではないか・・・。
すなわち、「ひかりの素足」に描かれている一郎と楢夫の兄弟の様子は、やはり賢治のトシに対する思いを大きく反映したものではなかったか、もっと具体的に言うならば、「死ぬことの向ふ側まで一諸について行って」やりたいという賢治の切なる願いを一つの物語として造形したものが、この「ひかりの素足」という作品だと言えるのではないかと、私は考えるのです。
この問題に関してはあとまだもう少し、「ひかりの素足」と「銀河鉄道の夜」が草稿が書かれた時期の比較を行うとともに、一郎とジョバンニがそれぞれ死後の世界に行くことになったのはなぜなのか、そしてそこから帰還することになったのはなぜなのか、ということについて考えてみたく思いますが、続きは稿を改めさせていただきます。
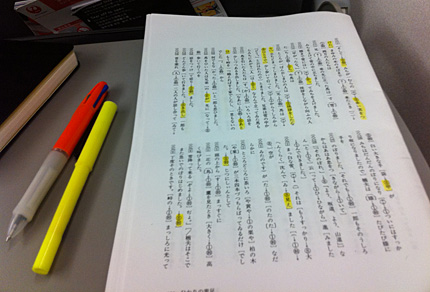
(6月5日、伊丹ー花巻間の機内にて。「ひかりの素足」草稿において、トシの死後に手入れがなされた部分。)
ガハク
確かに一郎の楢夫への愛情の深さ美しさこそが「光の素足」の中心になってると思えますね。「お前はいい子だ弟を身をていして鬼からかばった」と褒められてもいるし。
トシさんの写真を見せて頂いたら、楢夫の可愛らしさがここから見えて来る感じが確かにします。賢治さんの妹への愛が感覚的に伝わって来ました。リスは間違いないですね。
「銀河…」ではそのこちらから一方的でもある出て来る愛の発露が完全には受け止められていない。言われてみればジョバンニの、特にカンパネルラへの愛は最期にはスルーされているように僕には思えて、いつもその点は口惜しいような残念な気持ちが残ったままw。
それにしても機内でも草稿をチェックする「売れっ子作家」!
健康にはくれぐれもお気をつけ下さい。
竹崎
ちょっと核心とは外れてしまいますが・・・
最近ずっと、「トシ子の前歯」のことを考えていたのでびっくりしました。この2枚目の写真は、最近あまり見なくなったなあと思っていましたが、『図説・・・』でみつけてちょっとうれしかったです。
子どものころの賢治が、トシ子の口元から覗いたかわいい歯をみて、「かちん」とやらならなかったわけはないと思います(笑)そう思わせるほどに、この一郎と楢男の朝の描写はリアルな感覚を感じさせるものでした。
僕は、兎も、トシ子をイメージさせるものとして作品のどこかに登場しているのではないかと考えているのですが(ホモイは違うと思います)
「ゆきてかえりしものかえらぬものそしてのこされたもののこったもの―」について、後半も楽しみにしております。
hamagaki
ガハクさん、竹崎さん、こんにちは。
「ひかりの素足」において、一郎が健気に楢夫に対して注ぐ愛情、その献身的な振る舞いは、本当に胸が切なくなるほどですね。思わず、上にもたくさん引用してしまいました。
山の朝の情景と兄弟や父子のやりとり、吹雪の描写、上記のような一郎の楢夫への優しさ、それから「うすあかりの国」で迫り来る恐ろしさと情けなさ、これらの絶妙の描写が、「ひかりの素足」の尽きせぬ魅力かと思います。
それに比べたら、「如来寿量品」の不思議な功徳や「巨きな人」の立派な姿など、本当は作品の眼目なのでしょうが、とって付けたようにさえ感じられてしまいます。(とまでいうと、言いすぎかな?)
そして、「ひかりの素足」のリアルな情感に並べると、「銀河鉄道の夜」は、おそらくもっと広大な射程があり、宗教的・思想的にはより深いものなのかもしれませんが、たしかにやや抽象的になっている感は否めませんね。
これは、「トシの死」という深刻な喪失体験を、賢治がどのように乗り越えていったのか、ということとも関わってくる問題でしょうが、いずれ本稿の続きで考えてみることができれば、と思っています。
(しかし、これはなかなか難題で、きちんとまとまるかどうかわかりませんが・・・。)
それから竹崎さん、「トシ子の前歯」の件、私以外にも同じことを考えている方がいらっしゃったとは、心強いかぎりです。(^_^)
こういうことは、プロの研究者の方はあまり言っておられないようで、もちろんテクストはテクストとして読むべきであって作者の伝記的事項から解釈するのは邪道かもしれませんが、それでもこういう風に考えてみれば、「賢治:トシ → 一郎:楢夫」という相似関係がより具体的に感じられたりもします。
「兎」についても、ご示唆ありがとうございました。
「ゆきてかえりしものかえらぬものそしてのこされたもののこったもの―」ですね・・・。
mishimahiroshi
「ひかりの素足」は「水仙月の四日」と並ぶ雪を描いた日本を代表する傑作だと確信しているのですが、まさに浜垣さんのおっしゃる以下の部分
「如来寿量品」の不思議な功徳や「巨きな人」の立派な姿など、本当は作品の眼目なのでしょうが、とって付けたようにさえ感じられてしまいます。(とまでいうと、言いすぎかな?)
大いに賛同いたします。
この部分がなかったら、いわゆる童話あるいは少年小説としてもっと人に勧めやすい作品になったことでしょうね。
中所さんはそこを「光の素足」として一般化することで能として見事に成立されました。
いずれにしても後半を期待しています。ガハク先生同様
それにしても機内でも草稿をチェックする「売れっ子作家」!
健康にはくれぐれもお気をつけ下さい。
と付記させていただいて・・・。
hamagaki
mishimahiroshi さん、ありがとうございます。
物語終了時点において、「ひかりの素足」の一郎と、「銀河鉄道の夜」のジョバンニを比べると、大切な人を失ってしまったことは共通しながらも、一郎の方がはるかに大きな喪失感を抱えているだろうと感じざるをえません。
楢夫の死をどう受けとめたかも明らかにされずに幕切れとなる一郎と違って、ジョバンニは前向きに喪失体験を昇華しようとしているように見えます。
それが、「ひかりの素足」を書いた頃の賢治と、「銀河鉄道の夜」を書いた賢治との違いなのかもしれません。
そして、そこにこそ、中所宜夫さんが「ジョバンニの後日譚」ではなくて、「一郎の後日譚」を能に作り上げられた所以があるのだろうと思います。
命がけの献身の甲斐もなく、弟を喪って自分だけが生き残ってしまった一郎の魂が救われるためには、まだもう一つの物語が必要とされていたのだろうと感じます。