先日来、「公衆食堂(須田町)」について記事を書いていた時期に、「賢治の事務所」の加倉井さんが、賢治と高村光太郎が生涯に一度だけ面会して、「鍋をつついた」とされる店の存在について、疑問を提起しておられました(2月16日付の「緑いろの通信」参照)。
1926年12月に、賢治と光太郎と詩人の手塚武が3人で、上野駅近くの「聚楽の二階」で食事をしたという記載が旧『校本全集』にはあったのですが、この「聚楽」というのは、実は先日から話題にしていた「須田町食堂」の、系列店にあたるのです。
まず、『【新】校本全集』の年譜篇における、この問題に関わる「注」を、下記に引用します(読みやすくするため、途中に改行を入れました)。
*71 校本全集年譜では
「一二月一八日(土)または二〇日(月) 本郷区駒込千駄木林町一五五番地に高村光太郎を訪う。先客に「銅鑼」の同人手塚武がいた。手塚は第八号に「新しい盗人」というエッセイを発表しているので、賢治も名前は知っていた。手塚の記憶によると、高村光太郎はふだんとちっとも変わらぬ態度で、賢治にいつごろ出てきたか、何を勉強しているか、岩手ではどのような生活をしているかを問い、賢治はエスペラントを習っている、音楽の勉強もしたいといったり、何か弟さんに気がねをしているような言葉の節があったという。
夕方になり、一緒にめしを喰おうと高村光太郎がさそいだし、三人は林町の家を出て坂を下り、池の端から上野駅近くまで歩き、当時はまだ小さかった聚楽の二階の一部屋でいっぱいやりながら鍋をつついた。一時間半ぐらい話しあったという、賢治はマント、高村光太郎はインバネスであったか、と手塚は言う。(後略)」
と記述していた。この記述内容は、校本全集年譜編纂時に堀尾青史のもとに手塚からもたらされたという。ただし、具体的根拠が再確認できない。
手塚自身『宮沢賢治追悼』(昭和九年一月二八日、次郎社)に収録された「宮沢賢治君の霊に」の中で、「僕の東京住まい中、たつた一度出て来た宮沢君と、余りに突然だつたので、僕はその機会を失した。今にして非常に残念に思ふ。高村さんだけは逢つた。」と記している。
つまり手塚武氏は、昭和9年には、「自分は賢治には会えなかった」という意味のことを書き、その後校本全集編纂時には、上記のようにかなり具体的な面会の記述を、堀尾青史氏に提供しているわけです。
堀尾氏にもたらされたという情報には、実際に面会したとしか思えないような具体的で臨場感あふれる描写があるのに、この矛盾は本当に不思議です。
この「謎」に関連して、上記のページで加倉井さんは、次のように指摘しておられます。
須田町食堂の創始者加藤清二郎が株式会社「聚楽」を設立したのが、1934(昭和9)年のことです。とすれば、上記の出来事があったとされる1926(昭和2)年12月には「聚楽」が存在していなかったことになります。
また、「当時はまだ小さかった」というのも少々疑問で、須田町食堂の流れにある聚楽の店舗(現ヨドバシカメラ近く)の方は小さなものでした。この店は数年前に撤退してしまい、現在はガード下に2店舗(ファミリーレストランと居酒屋)が営業されています。上野公園の下にある「聚楽台」は大型の店舗ですが1959(昭和34)年の開店です。
この面会は実際にあったのでしょうか。
歴史学などにおける「史料批判」の原則から言えば、史料Aと史料Bの間に矛盾があって、いずれかの正誤を判断するための第三の史料も存在しない場合、事件から時間的・空間的に近い史料の方が、また間接情報よりも直接情報の方が、信頼性が高いと見なすのが一般的です。その観点からは、校本全集編纂の1970年代よりも昭和9年の言説の方が、また堀尾青史氏を介した話よりも手塚氏が直接執筆した文章の方が、信頼性が高いと期待されることになります。
とりあえずこの原則に従って、手塚武氏が『宮沢賢治追悼』に執筆した内容の方を採用すれば、「手塚氏と賢治は面会しなかったが、高村光太郎と賢治は、東京において面会した」と、推測してみることができます。実際、『【新】校本全集』年譜篇も、この12月に賢治と光太郎の二人は会ったと〔推定〕しています。
ただここで、上記で信頼性が劣ると判断した「校本全集編纂時に手塚氏から堀尾氏にもたらされた情報」に関しても、その中に一片の真実も含まれていないなどと断定することはできません。長い年月がたつうちに、手塚氏の記憶に錯誤が生じたとしても、その中の一部には、事実が含まれている可能性があります。
例えば、「エスペラントを習っている、音楽の勉強もしたい」という賢治が語ったとされる言葉は、実際に他の伝記的資料と対照しても、まさに賢治の1926年の上京時の行動にぴたりと一致していますが、手塚氏は当時のこのような賢治の活動内容を、いったいどうやって知ったのでしょうか。
手塚氏が、それまでに賢治の伝記などを読んでいて、賢治の東京における行動についてある程度知識を持っていた可能性は、十分にあります。しかしそれでも、賢治の上京は全部で9回もありますから、その中で、唯一自分が面会できた可能性のあった1926年上京時の活動内容だけを、無意識のうちに伝記から適確に抽出して記憶の錯誤の中に潜り込ませていたというのは、ちょっと考えにくいことです。
そこで考えられる一つの推測として、高村光太郎が、賢治との面会時の様子や話した内容を、後から手塚氏に話していたのではないか、ということが想定されます。
高村光太郎と手塚武氏の関係は、手塚氏の創刊した詩誌に光太郎が作品を載せるほどの間柄で、同じ東京に在住していたわけですから、会う機会は十分にあったはずですし、もしも賢治と光太郎の面会後に手塚氏が光太郎に会えば、その面会時のことが話題に上るのも、自然なことです。(ちなみに、賢治は『銅鑼』に計11作品もの詩を掲載していますが、「面会」直前の1926年12月1日発行の「九号」は、編集者・草野心平、発行者・手塚武となっていて、賢治はこの号に「永訣の朝」を載せています。)
ですから、「エスペラントを習っている、音楽の勉強もしたい」という賢治の「言葉」は、賢治が実際に1926年に光太郎に語り、それを後で手塚氏が光太郎から聴いて、手塚氏の記憶の底に沈んでいた内容だったのではないかというのが、私としては最も自然な仮説に思えるのです。
そこでさらにもう一歩進めて、「上野駅近く」の「聚楽の二階でいっぱいやりながら鍋をつついた」という陳述に関しては、どうでしょうか。
これも、賢治と光太郎の二人が実際に食事に行ったエピソードとして、光太郎が手塚氏に語ったことなのでしょうか。それともこの部分は、例えば手塚氏が、光太郎ともう一人は賢治ではない誰か別の人と一緒に、「聚楽の二階でいっぱいやりながら鍋をつついた」際の記憶が、誤って紛れ込んでいるのでしょうか。
これについては、何ともわからないとしか言いようがありません。正直言うと、この部分に関しては、後者の可能性が結構あるのではないかと、私も思います。1926年の時点では、「聚楽」という店はまだ存在していなかったのではないかという、加倉井さんによる上記の指摘もあります。
ただ、私としては、宮澤賢治と高村光太郎の二人が、「いっぱいやりながら鍋をつついている」情景が、何とも理屈抜きに魅力的に思えてしまうのです。そこで、ひょっとしてこのようなことが実際にありえた可能性は本当にないのか、どうしても考えてみたくなったのです。
というわけで、私は今日、『聚楽50年のあゆみ』(1974)という本を閲覧しに、龍谷大学の図書館まで行ってきました。
すでに長くなってしまいましたので、その結果については、次回またご報告したいと思います。
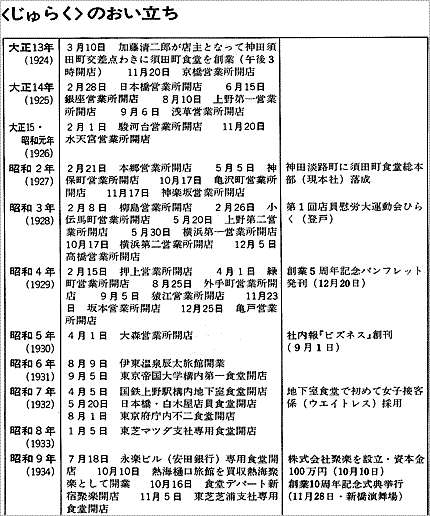
『聚楽50年のあゆみ』より
長嶺俊一
前略。たまたまこのサイトを見ました。
私は沖縄県在住の作曲家長嶺俊一と申します。
私は1967年から2005年までの38年間宇都宮に住んでいまして詩人の手塚武氏と10年ほど彼が1986年に亡くなるまで交流していました。
手塚氏は、宮沢賢治に会って彼から「ガリ刷りの詩集」と原稿をもらったといっていました。ですので宮沢賢治と会っているはずです。
私は手塚武氏の通作詩と有節詩に1978~1979年頃の間に5曲の歌曲を作曲しています。
https://www.youtube.com/results?search_query=SchrzoForte1
以上
hamagaki
長嶺俊一さま、貴重な情報を書き込みいただきまして、ありがとうございます。
手塚武氏が、『校本宮澤賢治全集』編者の堀尾青史氏以外に対しても、「宮沢賢治に会った」と語っていたという事実があったのですね。
しかも、賢治自身から「「ガリ刷りの詩集」と原稿をもらった」とは、すごいお話だと思います。
「ガリ刷りの詩集」とは、賢治が生前に「春と修羅 第二集」について、「夏には騰写版で次のスケッチを拵へますから…」と1925年12月の森佐一あて書簡215に書いていたことを、連想させずにはおきません。
そのような「ガリ刷りの詩集」が、実際に作成されたという証拠は(岩波茂雄あて書簡214aに同封した「鳥の遷移」の謄写版稿以外には)現存していないのですが、もしも賢治が自ら「詩集」として作成したものが存在していたとすれば、画期的な事柄です。
そのテキストを分析するだけでも、宮沢賢治研究の世界に、大きな動きが起こるに違いありません。
それにしても、結局のところ「謎」として残されるのは、上の記事にも書きましたように、手塚武氏は昭和9年の段階では「宮沢賢治に逢えなかった」と書いているのに、晩年になると堀尾青史に対しても今回の長嶺俊一様に対しても、「賢治に会った」と言っているという、証言の矛盾です。
賢治は昭和8年に亡くなっていますので、手塚氏が最初の証言以降に賢治に会ったということはありえませんから、どちらかが「間違い」だということになります。
常識的に考えれば、賢治が亡くなった直後の記憶よりも、何十年も経ってからの記憶の方が曖昧になってくるでしょうから、「賢治に会った」という話の方が間違いだと推測するのが自然ですが、しかし賢治愛好家としては、もしかして「ガリ刷りの詩集」がどこかに残されていたら・・・ということも、思わず夢想してしまいます。
いずれにしましても、このたびは直接に手塚武氏からお聞きになった貴重なお話をご教示いただきまして、本当にありがとうございました。
今後とも、よろしくお願い申し上げます。
長嶺俊一
作曲家の長嶺俊一です。
私は宮沢賢治については、ほんの常識的な知識しか持っていません。ですので、賢治の作品全般につきましても有名な「雨ニモマケズ」「チェロ弾きのゴーシュ」以外ほとんど読んだことはありません。
ただ、手塚武氏と宮沢賢治氏の前投稿の件は、私の宇都宮の自宅にお越しいただいたり、私が彼の自宅に伺ったりした時に、多分その話をしたと思います。しかし、賢治については多くは語りませんでしたし、私もあまり興味を持っていませんでしたので、自ら率先してお伺いをしたこともありません。
手塚氏は、昭和48年9月29日に下野新聞社から詩集「月夜の傘(こうもり)」と言う詩集を限定300部を発行されましたが、なんと「限定300部の内 第1冊」を私に贈呈してくださいました。署名入りのその詩集を現在でも所有しています。彼の詩に私が何曲か作曲しましたので、ことのほか喜んでくださいましたので、その気持ちからだと思います。その中でも「やまぼうし」という曲は現在でも全音楽譜出版社より「日本名歌選集 中声用 右近義徳 編」楽譜に掲載されています。現在は何刷りになっているかわかりませんが、多分版を重ねていると思います。
以上、このサイトへの投稿はここで止めおきます。
特別何かご用件がございました時には、私のアドレス宛お尋ね戴きますれば、知っている範囲のことはお答えいたします。それでは失礼いたします。ありがとうございました。
hamagaki
長嶺俊一様、ご丁寧なお言葉をありがとうございます。
もしも本当に手塚武氏が宮沢賢治から「ガリ刷りの詩集」をもらっていたのだとしたら、それは何処へ行ったのだろう、ご遺族の方に尋ねたら何か分からないだろうか・・・などということもつい考えてしまいましたが、残念ながら今となっては霧の彼方のことと思います。
あと、YouTubeにて、長嶺様作曲の「やまぼうし」や沖縄旋法による器楽曲を拝聴させていただき、詩情あふれる響きに感銘を受けました。
とりわけ、交響詩のフルートアンサンブル版の実演は、私自身が昔フルートをやっていたこともあって、その活き活きとした演奏に心惹かれました。
また何かお尋ねしたいことができましたら、メールをさせていただくことがあるかもしれませんが、その節はよろしくお願い申し上げます。
長嶺様のご健康をお祈り申し上げます。
長嶺俊一
返信ありがとうございます。
宮沢賢治の件につきまして、手塚先生は1982年に亡くなられていますので、今となってはやはり「霧の彼方」でしょう。と申しますのは、確か手塚先生にはお子様もおいでにならならなかったですし、奥様もすでに亡くなられたと聞いております。私が30代のころ彼はすでに80歳を超えて居られましたし、あれから更に30年以上も経ていますので、やはり今となっては・・・ということです。私が賢治についてもっと興味を持っていたなら、色々と聞き出せていたかもしれませんが、それも残念というしかありませんね。
ただ、手塚先生の同人の方で手塚先生と共に親しくしていられた方、また私の歌曲「紫陽花」の作詩者でも居られる野澤俊雄さんは、まだご健在で多分御年80歳は優に超えていられますが、もしかしてお会いするチャンスもあるかもしれませんので、万が一ご健在中に邂逅が果たせました場合には、賢治の件も尋ねてみたいところです。
また、私の拙作をお聴きくださいましてありがとうございました。
ついでに申しますが「やまぼうし」ほか多くの作品は詩人たちの臨在するステージで、私の伴奏とレコードで独唱している堀純子さんとの共演で初演を果たしています。
演奏の前に詩作者ご本人が「朗読」をしたのち、演奏するというスタイルを取りました。30年以上前の話です。
長くなりました、これで投稿を終了いたしますがご用件の節は前投稿の通りといたします。
重ねてお世話になりありがとうございました。今後のご発展をお祈りいたします。
長嶺俊一
作曲家の長嶺俊一です。
「これで投稿を終了いたします。」と、前投稿で申し伝えましたが、新しい情報がわずかに得られましたので何かに役立つかもしれないと思い、再度投稿いたします。
また、前投稿で「手塚先生は1982年に亡くなられています」と申しましたが、正確には初めの投稿で申し上げました「1986年没」が正しいです、錯誤失礼いたしました。
さて、宇都宮にもしも行くことがありましたら、手塚武との深い交流のありました宇都宮市在住の野澤俊雄氏にお会いするチャンスを持ちたいと申しましたが、実は5月に宇都宮に行くことができ、お会いできましたので、お知らせしておこうと思いました。
私の友人の詩人、綾部健二氏(栃木県文芸家協会理事、日本現代詩人会会員)と二人で5月19日に野澤氏の自宅へお伺いしましてお会いしました。久方ぶりの、多分14~5年ぶりかの邂逅でした。野澤氏は御年87歳で今なお矍鑠となされて現在、詩誌「橋」主宰、日本詩人クラブ会員、栃木県文芸家協会顧問、栃木県現代詩人会会長の任にいられます。
野澤氏は、高村光太郎が友人の推薦の為の、和紙に書いた筆書きの候文書簡の原本をお持ちで、私たちに見せて下さいました。それは桐の箱に入れられて「巻物」としてきれいに保存されていまして、いかにも大切にいていられるという感じでした。高名な方の直筆候文は「古文書」のようで、スムーズには読めませんでしたね。
そうこうしているうちに「手塚武と宮沢賢治の邂逅の件」が気になりましたので、やはり私が野澤氏に「手塚武と宮沢賢治は会ったことがあると思いますか?」と質問しましたら、彼の答えは「当然会っているはず」との答えでした。賢治は銅鑼に何篇もの詩を掲載しているわけなので、一度も会ったことがないはずはない、とのご回答です。野澤氏の説明によると、銅鑼は、編集人住所が手塚武の「兄」の住所になっているとも、申していました。
さらに野澤氏は宮沢賢治が品種改良した「陸羽132号」と言う米を、栃木県真岡市在住の高松さんと言う方が、その銘柄米を今でも栽培していて、野澤氏の教え子で宇都宮市在住のある方が送ってくれて、野澤氏は「陸羽132号」をご賞味されたそうです。味は「そこそこ」と言う感じだった、とのご感想でした。
野澤氏は賢治詩集の中のその「陸羽132号」のことがかかれている「あすこの田はねぇ」と言う「詩」を私に見せてくれて、綾部健二氏がその場で朗読してくれました。
勿論、素人の私はその詩の存在すら知る由もありませんでしたが、賢治らしさはあったような印象です。以上、ちょっとした情報でしたが投稿してお知らせしておきます。
hamagaki
長嶺俊一 様、また書き込みをありがとうございます。
このたび、手塚武氏と直接にご親交もあった野澤俊雄様にお会いになり、その際にわざわざ賢治と手塚武の面会の可能性についてお尋ねをいただけましたことは、本当に有り難く存じます。
野澤様の個人的なご推測としては、賢治と手塚武氏は直接会っていたのではないかということでしたが、おかげさまで今回私としては、「生前の手塚武氏は、少なくとも野澤様に対して『自分は宮澤賢治と会ったことがある』と語ったことはなかった」ということを、知ることができました。
今回のお話では、野澤様は賢治についても相当にお詳しいようですから、もしも手塚武氏が生前の賢治と会っておれば、野澤様との間で何かのきっかけで賢治の話が出た可能性もありえたわけですが、実際そのようなことはなかった、というわけですね。
だからと言って、二人が会っていなかったという証拠になるわけでもありませんが、しかしこれも一つの貴重な証言かと存じます。
それから、「あすこの田はねえ」という賢治の詩に関しては、たまたま最近その作品を刻んだ詩碑の写真を、説明を付けて拙サイトに掲載したばかりでしたので、不思議なご縁を感じました。
ご指摘のとおり、とても「賢治らしい」詩で、私も大好きな作品の一つです。
花巻の羅須地人協会跡近くにあるその詩碑の写真を下記に載せていますので、ご覧いただけましたら幸いです。
https://ihatov.cc/monument/141.htm
御地では、もう梅雨も只中でしょうか。こちら京都でも、そろそろ入梅が近づいてきた感のある今日この頃です。
どうかお体にお気を付けてお過ごし下さい。