6.「手宮文字」について
前回は、「雲とはんのき」(『春と修羅』)に登場する「手宮文字=おまへが刻んだその線」の内容とはどういうものだったのだろうかということについて、考えてみました。
今回は、その「線」とはどんな形をしていたのかということについて、私の想像するところを書いてみます。
最初にもう一度、作品の該当箇所を抜粋しておきます。
感官のさびしい盈虚のなかで
貨物車輪の裏の秋の明るさ
(ひのきひらめく六月に
おまへが刻んだその線は
やがてどんな重荷になつて
おまへに男らしい償ひを強ひるかわからない)
手宮文字です 手宮文字です
こんなにそらがくもつて来て
山も大へん尖つて青くくらくなり
豆畑だつてほんたうにかなしいのに
先日も書いたように、賢治は1923年6月に、どこかに線刻文字のようなものを刻んだのではないかと私は考えているのですが、作品中に「手宮文字です 手宮文字です」という「合いの手」が入ってくるのは、賢治がこの時に刻んだ「線」には、当時の呼び方で「手宮文字」(=手宮洞窟の線刻画)を連想させるようなところがあったのではないかと思います。
その手宮洞窟の線刻画とは、下のようなものです(イギリスの地質学者ジョン・ミルンによる1880年の模写)。
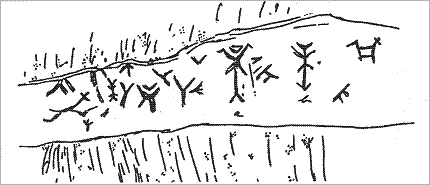
これが「古代文字」であるという説は、発見当初からあったようですが、1913年(大正2年)に、考古学者・人類学者である鳥居龍蔵が、これは「突厥文字」(古代トルコ文字)であるという説を発表しました。突厥文字というのは、「世界の文字」というサイトの該当ページで見ることができますが、たしかに形は似た感じはします。
1918年(大正7年)には、広島高等師範教授の中目覚という人が、突厥文字との立場から、これを「我は部下を率ゐ大海を渡り・・・闘ひ・・・此洞穴に入りたり」と「解読」し、また1944年には、地元小樽の小学校校長だった朝枝文裕という人が、これは支那古代文字であるとして、「舟を並べて来たり、この地にいたり、本営を置く。帝この下に入る。変あり、血祭す」と、新たな「解読」をしたりしています。
しかし、学界においては、すでに1920年頃にこれは文字ではなく「壁画」であるとの説が有力となり、戦後1950年に隣の余市町でフゴッペ洞窟が発見され、その中にこの手宮のものと類似した壁画が発見されるに至って、さらに考古学的な価値が再認識されています。
ただ、このような「学界の定説」にもかかわらず、それと並行する形で、これが「文字」であるという理解は世間には根強く続いていたようで、1922年(大正11年)の「皇太子殿下行啓記念写真帖」にも、手宮洞窟訪問時の写真には「手宮洞窟古代文字ニ向ハセラル」とタイトルが付けられていますし、賢治自身も現に1923年の時点において、「手宮文字」と書いているわけです。
ちなみに、「鶴岡雅義と東京ロマンチカ」の1968年のヒット曲「小樽の女」の二番の歌詞には、「偲べば懐かし 古代の文字よ・・・」という一節が出てきますし、今も小樽には、「古代文字ラーメン」というラーメン屋さえ存在しています。(^_^;;
7.賢治の「暗号文字」
ちょっと話がそれてしまいましたが、問題は、宮澤賢治自身が、「手宮文字」に似た「線」を刻んだとすれば、それはどのようなものだったのか、ということです。
賢治が、そのような奇妙な「文字」を実際に書いたという点で、私に思いあたるのは、賢治が盛岡高等農林学校2年だった1916年8月に、東京から盛岡にいる親友の高橋秀松あてに出した、一枚の葉書です。『【新】校本全集』第十五巻に収められている[書簡18]を見ると、の中に、次のような箇所があるのです(『【新】校本全集』よりコピー)。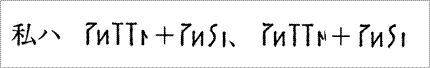
これは、まさに「暗号文字」ですが、葉書の最初に鉛筆で書き込まれているということです。「校異篇」を見ると、『昭和四十二年筑摩書房版全集』においてなされたその「解読」は、![]()
ということだそうです。
つまり、上の文は、「私ハ 待ッテヰマス、待ッテヰマス」となるのです。東京に出てドイツ語の勉強を始めた賢治は、秘かに親友に上京を誘いかけているわけで、実際これを受けとった高橋秀松は、すぐに東京まで来て賢治と同宿し、「東京独逸学院」に一緒に通いました。
「校異篇」は、これにつづいて≪備考≫として、「暗号文字」に関して次のように説明をしてくれています。
暗号文字は賢治と高橋だけの間で使用されたもの。高橋の記憶によれば、この文字は前年の一学期の終り頃から使用しはじめたもので、案出の動機は次のような事情によるものという。
賢治は当時、毎日一、二首(時には更に多く)の短歌や詩を作り、暗号文字によりいわば日記代りのノートに書きつけていた。また時折は大学ノートの一頁に短歌を一首ずつ書いて、自啓寮(高等農林学校寄宿舎)の同室者五人(高橋を含む)に披露するのを常としていたが、ある日上級の室友に「これが歌か詩なもんか」と冷やかされた。それ以来、彼は作品を高橋だけに見せることとし、ついには鍵を与えないまま暗号のノートを高橋に渡し、高橋は独力で解読した。
すなわち、賢治はこの暗号文字を、1915年から日常的に、日記や短歌の表記に使用していたようなのです。そうすると、アルファベットは上の7つだけではなくて、ローマ字表記に必要な文字は、すべて存在していたのでしょう。
そして、私は思うのですが、この縦線が多く線刻っぽい字体は、上に載せた手宮洞窟の壁画の線に、どこか似ていないでしょうか。
じつは私は、1923年6月に賢治が、「トシとの通信がかなうならば、私は死んでもよい」という内容のことをどこかに「線で刻んだ」際には、8年前に自ら発明したこの「暗号文字」を用いたのではないか、と考えているのです。呪術的な意味を込めて「暗号文字」を用いたとも思えますが、何よりもその形に注目した時、「手宮文字です 手宮文字です」という作品中の言葉は、私にとって最もすっきりと納得できるのです。
賢治が具体的にどうやってこの暗号化されたアルファベットを作りだしたのかということはわかりませんが、それを使い始めた1915年というと、鳥居龍蔵氏の「北海道手宮の彫刻文字に就いて」という講演録はすでに発表されており、世間も「古代文字」について関心を高めていた頃です。
もしも当時、暗号文字を見せられた高橋秀松と賢治との間で、「これはまるで、手宮文字みたいだな」などという会話がかわされていたならば、「手宮文字です 手宮文字です」という言葉が、記憶の奥底から甦ってくるというのも、十分にありそうなことに思えるのです。
8.おわりに
繰り返しになりますが、賢治は1923年6月に、自分が学生時代に使っていた(手宮文字に似た)暗号文字によって、「トシとの通信がかなうならば、私は死んでもよい」という内容のことを、呪術的な意味を込めてどこかに刻みつけたのではないか、というのが今回私の考えてみたことでした。
この秘かな「賭け」を実行に移してみたのが、「オホーツク挽歌」の旅行、とりわけ宗谷海峡で賢治がとった行動だったのだと思います。そして、旅行から帰って少ししてから、それをあらためて思い出したところが、「雲とはんのき」に出てくる「ひのきひらめく六月に/おまへが刻んだその線」の正体なのではないかと、私は思うのです。
ところで、この「線を刻んだ」ことは、彼がおそれたように、その後「重荷になつて」「男らしい償ひ」を彼に強いたでしょうか。
夜の宗谷海峡で、トシが賢治を「呼ぶ」ということは結局なく、彼は死なずにすみました。彼が「オホーツク挽歌」の旅行に懸けていた、「愛する妹に、死後の世界までも一緒について行ってやりたい」という願いは、結局かなわなかったわけですが、しかしこのテーマは、その後の賢治にとってずっと「重荷」のように、ついてまわります。「手紙 四」も「ひかりの素足」も「銀河鉄道の夜」も、結局は同じテーマを扱ったものです。
「銀河鉄道の夜」においてジョバンニは、死んだカムパネルラにいったんは「呼ばれ」て銀河鉄道に同乗しました。しかし、やはり「どこまでも一緒に」行くことはできず、現実の世界に戻ったのでした。
また逆に、「春と修羅 第二集」の「序」では、「わたくしはどこまでも孤独を愛し/熱く湿った感情を嫌ひますので」と書き、また小笠原(高瀬)露あての書簡[252a]には、「私は一人一人について特別な愛というやうなものは持ちませんし持ちたくもありません。さういふ愛をもつものは結局じぶんの子どもだけが大切といふあたり前のことになりますから。」と書いたように、ある時期からの賢治は、人との過度の親密さを避けるようになった節があります。
これは、究極の目的としては「世界ぜんたい」の幸福のためなのかもしれませんが、現実の生活において「一人一人について特別な愛」を持たないように自らを仕向けるということが、賢治がこの一連の苦闘の後にとった、彼なりの「償ひ」なのかもしれません。
それはちょっと、寂しすぎる感じもしますが。
つめくさ
北海道への調査旅行お疲れ様でした。
今回も興味深い推論を楽しませていただきました。
「”踊る人形”だよ、ワトソン君」みたいにワクワクします。
♪変わらぬものは~古代文字ィ~ は、「オホーツク挽歌」ならぬ「石狩挽歌」(北原ミレイ)ですね。
hamagaki
つめくさ様、コメントありがとうございます。
今回の「手宮文字」に関するお話は、私としてもちょっとキワモノっぽいかなと思っているところですが、わずかなりとも興味をお感じいただければ幸いです。
「シャーロック・ホームズ」シリーズの「踊る人形」は、謎解きと不気味さの共存した素敵な作品でしたね。あの人形たちの姿は、夢にまで出てきそうな感じです。
さて、北原ミレイの「石狩挽歌」(1975)に「古代文字」が登場していたのは、ご指摘によって再認識しました(昔は、よく聴いた歌だったはずなのですが…)。
ちょっと調べてみると、この曲を作詞した なかにし礼 氏の自伝的小説『兄弟』によれば、なかにし礼 氏の兄は、戦後小樽に引き揚げて、ニシン漁でいったんは大儲けしたものの、その後多大な借金を作って一家離散、弟の なかにし礼 氏の生活を苦しめ続けたとのこと、その時の思いも、あの「石狩挽歌」にはこめられているのでしょう。
やはり、「小樽」と「古代文字」は、一つながりなのですね。