ピーター・クレイン著『イチョウ 奇跡の二億年史』(河出書房新社)という本を読みました。著者は、植物の系統・進化史を専門とするイギリス人生物学者で、昨年の国際生物学賞も受賞された方です。
 |
イチョウ 奇跡の2億年史: 生き残った最古の樹木の物語 ピーター クレイン Peter Crane 河出書房新社 2014-09-17 Amazonで詳しく見る |
実にこの本を読むまで私は、いつも当たり前のように眺めているあのイチョウの木が、地球上でこれほど数奇な運命をたどってきたのだとは、思いもよりませんでした。
イチョウは、現生の樹木の中でも最も古い形質を持ち、2億年も昔から各大陸で繁栄を続けていたということですが、白亜紀末からは徐々に減少を続け、人類が地球上に登場する頃には、わずかに中国の山間部に残るだけになっていたということです。しかし、人間がその種子を食用にし、また宗教的にも尊んだことから、まずは中国各地に、その後は朝鮮半島および日本へと、分布を広げていきました。
そして江戸時代に、日本の出島に居留していたオランダ人がこの美しい樹木に興味を持ったことから、この木は海を渡ってヨーロッパで人気を博し、その後は瞬く間に世界各地に広がっていったのです。
これまでに人類は、たくさんの生物種を絶滅に追いやってきたことでしょうが、図らずもその逆に、絶滅から救うことになった種もあったのだというわけです。
その波乱の歴史の一コマにおいては、日本が多少の貢献をしているというのも、嬉しいところです。イチョウの英独仏語'ginkgo'は、江戸時代の日本で「銀杏」を「ギンキョウ」とも読んでいたのを、出島に来ていたドイツ人医師ケンペルが、'y'音を'g'で表すという北ドイツ式の表記法によって伝えたことに由来するということです。
また近代日本となって以降にも、賢治の生年である1896年(明治29年)には、小石川植物園の平瀬作五郎が世界で初めて、イチョウの受精の際に繊毛で泳ぐ精子を観察することに成功しました。この仕事は欧米の研究者を驚嘆させるとともに、「日本人科学者の名が国際舞台にのぼる最初の研究成果」になったということです。
2億年もにわたりこの地球上で長く生きのびて、「生きた化石」とも呼ばれる生物が、地質学的には「ほんの一瞬」とも言えるわずか1000年ほどの間に、ヒトを介して東アジアに広まり、また300年ほどで全地球に分布するようになったというその壮大な時間の対照が、何とも不思議な感動を誘います。
そしてこの本によれば、イチョウがその生存を「一瞬」に賭けているのは、このような歴史の偶然性においてだけではなくて、実は毎年のことなのです。
雌雄異株、すなわち雄木と雌木が別株であるイチョウの生殖は、先に触れた泳ぐ精子の存在にとどまらず、全てが非常に精妙に行われます。
暖かい春の数日間に、雄木の短枝には「花粉錐」が形成されて伸長し、その先に付いた「花粉袋」が裂けると、2-3日のうちに1本あたり1兆個もの花粉が飛び散ります。途方もない数の花粉ですが、どこか離れたところの雌木にたどり着いて受精を成し遂げるためには、それくらいが必要なのです。
花粉が風に乗って漂っているまさにそのとき、(雌木の)若い胚珠はその先端に珠孔液という液体をつけてきらきらと輝く。この液体は空中を漂う花粉を捕らえるためのもので、ここで捕らえられた粒子を何であれ内部にとりこむ。珠孔液は花粉粒を胚珠に引きこむまで、一日に何度も吸収と再生をくり返す。
自ら動いて伴侶さがしができない植物にとって、受粉は生殖における最もリスキーな部分だ。中でもイチョウのような雌雄異株の植物の場合、雌木と雄木で珠孔液と花粉の産生をぴったり同じタイミングに合わせなければならない。これを同期させられるかどうかですべてが決まる。受粉に成功した花粉粒の中で精子細胞が育ち、それが数か月後に胚珠の中にある卵に受精させると胚ができ、それが育つと種子になる。しかし、タイミングが少しでもずれれば成果はゼロだ。種子はできず、次世代の子孫を残せない。雄木と雌木の絶妙の同期作業が自然淘汰によって調整し尽くされてきたことは想像に難くない。(『イチョウ 奇跡の2億年史』p.82)
このように、いっせいに花粉が舞い散り、風に乗ってすぐさま胚珠に取りこまれるという見事な斉一性は、秋のその落葉においても、際立っています。
イチョウがその黄金色の葉を、晩秋のある日いっせいに落としてしまうことについて、アメリカの桂冠詩人ハワード・ネメロフは次のような詩を書きました。(同書p.55)
合意
十一月下旬のたった一日の
まだ凍えるほど寒くない夜に
イチョウの木々はいっせいに葉を落とす
雨でも風でもなく、時だけに合わせるように
きょう、芝の上に散乱する黄金の葉は
きのうは枝の上ではためく光の扇であったのに星からどんな合図が来るのだろう
木は何をもって決断を下すのだろう
葉を襲い、葉を落とせという合図に
反抗すべきか降伏すべきかという決断を
だが、それが定めなら、免れることなどできようか
時が教えてくれることを知って何になる
さ、いまだ、と星が命じてくれるなら
かくして一挙に敢行されるイチョウの落葉の鮮やかさから、私はさらに宮澤賢治の童話「いてふの実」も連想しました。
賢治初期のこの短篇は、東の空に「優しい桔梗の花びらのやうにあやしい底光り」が現れてから、「突然光の束が黄金の矢のやうに一度に飛んで来る」までの、夜明けの短時間を描いたお話です。イチョウの雌木に生まれた千の種子たちは、母なる木とお互いの別れを惜しみつつ、しかし時が来ればやはりいっせいに、未知の世界へと旅立つのです。
突然光の束が黄金の矢のやうに一度に飛んで来ました。子供らはまるで飛びあがる位輝やきました。
北から氷のやうに冷たい透きとほった風がゴーッと吹いて来ました。
「さよなら、おっかさん。」「さよなら、おっかさん。」 子供らはみんな一度に雨のやうに枝から飛び下りました。(「いてふの実」)
いったいイチョウの木が、何をもって種子を落とす「決断を下す」のか、果たしてネメロフが想像したような「星からの合図」によるのかわかりませんが、賢治の童話に出てくる若い種子たちも、それを「定め」として巣立っていくのです。
この本は、一つの生物種の2億年の歴史が、上のような命がけの一瞬の積み重ねによって形作られていることを、教えてくれました。
イチョウに関する生物学、古生物学の知見、イチョウをめぐる古今東西の文化や人間との関わり、そして地球における生物多様性の意味についても、包括的に記された一冊です。
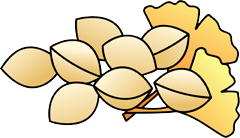
ゆき
こんにちは。
今年の秋~お正月も「さよなら、おっかさん」と旅立った銀杏の実を美味しくいただきました。少し前までレトルトパウチ食品の銀杏を買っていましたが、この頃は毎年殻付きです。殻を割るのに、くるみ割り人形が欲しくなるのですが、きれいに割れた殻の中から、翡翠色の実が美しく、少し眺めてから味わいます。
こんなふうに食用ばかりでなく、一面の黄葉も、また黄葉した葉も好きです。しおりとして本に挟むと防虫効果があると聞き、願いを込めたい本に挟んでみたりします。
あと、私は飲んだことないのですが、イチョウ葉エキスの薬?サプリメント?もあるとか。肺がんのお薬イレッサと合せて飲んでいるとポツリお話してくださった方がありました。
宗教的なつながりというと、本願寺のイチョウはお西さんもお東さんも、また、別院などでもすばらしいですね。どういう意味合いで寺院にイチョウの木が植えられているのか知りたいです。
あと、青森県にあるイチョウの巨木にも一度会いに行きたいです。
素敵な本をご紹介くださりありがとうございました。
少々お高い本のようなのですが、なんとか手に取ってみたいです。
hamagaki
ゆき様、コメントをありがとうございます。
お返事が遅くなってすみませんでした。
銀杏の実は私も大好きです。
お金のなかった学生時代に、大学のイチョウ並木から落ちたたくさんの銀杏を拾い集め、しばらく土に埋めておいてから洗い、下宿で煎って食べたことを思い出します。
欧米では、街路樹や庭木としてのイチョウは人気があるのに、その実は「苦い」とか「渋い」とかいってほとんど食べられないのだそうで、不思議ですね。
この本の著者が来日した際に、銀杏を食べた時の繊細な描写が、面白かったです。
青森県の大イチョウとは、十和田市にある樹齢800年~1200年の「法量イチョウ」ですね。私もまだ見たことはなく、ぜひ一度訪ねたいと思っています。
この本によれば、日本で一番古いと考えられているイチョウは、富山県の上日寺のもので、それに匹敵すると言われているのが、宮城県の姥神社のイチョウだそうです。
人間にはとても及ばない悠久の歳月を生き抜いてきた木には、何か言いようのない神秘を感じます。