去る4月20日に行われた「宮沢賢治学会京都セミナー2014」は、この種の地方セミナーとしてはかなり多い113名もの方々がご参集下さり、熱気にあふれた会となりました。
はるばる遠方から、あるいは地元京都からお越しいただいた皆様に、あらためて御礼申し上げます。
◇ ◇
セミナーの演目中、君野隆久さんは「宮沢賢治とジャータカ」と題した講演において、「ジャータカ(本生譚)」と称される一群の仏教説話が、いかに賢治の作品に影響を与えたかということを、具体的な例を挙げながらわかりやすく説き明かして下さいました。

「宮沢賢治とジャータカ」などというタイトルを見ると、何となく超マニアックなお話なのかなと思って、はたして私自身の興味がついて行けるかと事前に心配していたのですが、実際にお聴きしてみると、これはある一つの角度から賢治の精神性の本質にも迫る非常に面白いお話で、君野さんの賢治に対する思いも、そこここに垣間見えました。
「ジャータカ」とは、釈迦の前世(過去世)における様々な伝説を集めた説話集、あるいはその個々の説話のことだそうですが、賢治は「手紙 一」や「学者アラムハラドの見た着物」においては有名なジャータカを再話あるいは引用し、「オツベルと象」や「四又の百合」においてはジャータカの中のモチーフ(白象、供花など)を作品に生かし、さらに「二十六夜」においては、新たなジャータカを創作しようとしたのだということです。
様々なジャータカを読んでいたと推測される賢治ですが、中でも特に強い関心を抱いていたと思われるのが、「ヴェッサンタラ王」という特異な人物が登場する説話です。賢治はこの「ヴェッサンタラ・ジャータカ」の一部を、1918年(大正7年)12月の保阪嘉内あて書簡94において引用し、1923年(大正12年)頃の執筆とされる童話「学者アラムハラドの見た着物」においても引用し、1927年の日付を持つ詩「ドラビダ風」においても引用しているのです。
賢治がどのようにしてこの「ヴェッサンタラ・ジャータカ」を知ったのかという問題について、伊藤雅子氏は、1918年(大正7年)6月15日に発行された『国訳大蔵経』第十三帙に収められている「ヱ゛ッサンタラ所行品」で読んだのではないかと推定しておられますが(宮沢賢治研究Annual Vol.14所収「ベッサンタラ王渉典」,2004)、その原典の伊藤雅子氏による要約は、以下のとおりです。
ヱ゛ッサンタラの父母はヂェーツッタラの都で結ばれた。母が布施のための巡行を終えて、吠舎種の街路の中央に来た時に出産したためヱ゛ッサンタラと名づけられた。八才のとき乞う者の願いに従って何物をも、たとえ我が身であろうとも、求められれば与えようと考えた。彼が自分の身体に思いをいたしたとき大地が震え動いた。月に三回布施した。
あるときカーリンガ国の婆羅門が来て、雨が降らず大飢饉になったので吉徳ある白象を下さいと願った。あえて布施行を貫くために与えた。そのとき大地が震えた。シヰ゛国民は怒ってワ゛ンカの山へ入れと言った。都を去るときシヰ゛人に耳鼓を打たせて大施を行い、象・馬・車・奴・婢・牛・財を施した。大地が震えた。
赤蓮・白蓮のようにマッヂー妃は娘カンハーヂナー(妹)を抱き、ヱ゛ッサンタラは息子ヂャーリー(兄)を金像のように携えた。森林を通りかかったとき子らが高い木になる果実を見て泣くと、その木が自ら曲がって近づくという不可思議が起きた。
ワ゛ンカ山の林中で茅舎に住み果実を拾って暮らした。旅の婆羅門が二子を与えよと乞うたので、喜んで与えたところ、大地が震えた。次に帝釈天が婆羅門に姿を変えて妃を求めたので喜んで与えた。大地が震えた。ひたすら一切智を求めるために愛する妻子をも与えたのであった。
のちにヱ゛ッサンタラが父母と再会したとき大地が震えた。親族とともに林を去りヂェーツッタラに戻ったとき、天より七宝が降り大雨が注ぎ大地が震えた。ヱ゛ッサンタラの施与の力によって計七回大地が震えた。(伊藤雅子「ベッサンタラ王渉典」より)
そして以下には、賢治によるこのジャータカの引用を、順に挙げてみます。
まず、1918年(大正7年)12月の、保阪嘉内あて書簡94より。
ベッサンタラ王が施しをした為に民の怒りを買ひ王宮を逐はれ二人の子をつれて妃と山へ入りました。密林の中には多くの果実が実り子等はこれを求めて泣き叫びました。
木は自ら枝を垂れ下して果実を与へました。身毛為に堅つべきこの現象よ。これは王の過去に積んだ徳行によるのでせう。
次に、「学者アラムハラドの見た着物」より。アラムハラドが子供たちに教え聞かせているところです。
「あの木は高くてとゞかない。私どもはその実をとることができないのだ。けれどもおまへたちは名高いヴェーッサンタラ大王のはなしを知ってゐるだらう。ヴェーッサンタラ大王は檀波羅蜜の行と云ってほしいと云はれるものは何でもやった。宝石でも着物でも喰べ物でもそのほか家でもけらいでも何でもみんな乞はれるまゝに施された。そしておしまひたうたう国の宝の白い象をもお与へなされたのだ。けらいや人民ははじめは堪えてゐたけれどもついには国も亡びさうになったので大王を山へ追ひ申したのだ。大王はお后と王子王女とただ四人で山へ行かれた。大きな林にはいったとき王子立ちは林の中の高い樹の実を見てああほしいなあと云はれたのだ。そのとき大王の徳には林の樹も又感じてゐた。樹の枝はみは生物のやうに垂れてその美しい果物を王子たちに奉った。
これを見たものみな身の毛もよだち大地も感じて三べんふるえたと云ふのだ。いま私らはこの実をとることができない。けれどももしヴェッサンタラ大王のやうに大へんに徳のある人ならばそしてその人がひどく飢えてゐるならば木の枝はやっぱりひとりでに垂れて来るにちがひない。それどころでない、その人は樹をちょっと見あげてよろこんだだけでもう食べたとおんなじことになるのだ。」
そして、「ドラビダ風」(詩ノート)より。
(前略)
風は白い砂を吹く吹く
もういくつの小さな砂丘が
畑のなかにできたことか
汗と戦慄
牛糞に集るものは
迦須弥から来た緑青いろの蠅である
ヴェッサンタラ王婆羅門に王子を施したとき
紺いろをした山の稜さへふるえたのだ
右へまはれ
左へまはれ
汗も酸えて風が吹く吹く
もし摩尼の珠を得たらば
まづすべての耕者と工作者から
日に二時間の負ひ目を買はう
伊藤雅子氏が挙げた『国訳大蔵経』第十三帙は、1918年(大正7年)6月15日に刊行されているので、時期的に見ても、1918年(大正7年)12月の保阪嘉内あて書簡94には間に合います。また、賢治が書簡中で「身毛為に堅つべき」と表現している箇所が、『国訳大蔵経』では「身毛ために堅起すべき哉」と記されているなど、その表現の類似からも、賢治がこれを読んでいた可能性は高そうです。
ただ、賢治は「ベッサンタラ王」「ヴェーッサンタラ大王」「ヴェッサンタラ王」と、いずれの引用においても「王」または「大王」の称号を付けているのに、上に引用したように『国訳大蔵経』第十三帙においては、このような称号はなく「ヱ゛ッサンタラ」とのみ記されているのが、両者の大きな違いです。
これについて伊藤雅子氏は、賢治はさらに1918年(大正7年)2月28日に発行された『国訳大蔵経』第十二帙に収められている「国訳弥蘭陀(ミリンダ)王問経」の記述が念頭にあったのだろうと推測しておられます。すなわち、この経典中では、「吠三多羅(ヱ゛ーツサンタラ)大王」「吠三多羅(ヱ゛ーツサンタラ)王」として、「大王」や「王」の称号を伴って登場するのです。
ところで、この「国訳弥蘭陀(ミリンダ)王問経」の中の「吠三多羅(ヱ゛ーツサンタラ)王の布施に就て」という文章において、王が二人の子供を布施してしまう箇所の記述があまりに印象的ですので、伊藤雅子氏の要約を下記に引用させていただきます。
菩薩(=ヴェッサンタラ王:引用者注)はあえて最愛の子らを婆羅門に奴僕として布施した。子らは縄で黒あざができるほどきつく縛られてひきずられていった。子が縄を解いて戻ってきたとき、再び縛って婆羅門に与えた。子らが泣いて「お父さま、此鬼が私共を喰ひに連れ去ります」と叫んだのを、「怖はがりなさるな」と言って慰めた。王子闇梨(ヂャーリ)が父の足下に打ち倒れ「お父さま、〔我が妹〕カンハーギナーだけは許して下さい、私が彼の鬼と一緒に参ります、私は彼に喰べられませう」と嘆願しても、婆羅門の求めが二子であったために許すことができなかった。(伊藤雅子「ベッサンタラ王渉典」より)
ここで、「〔我が妹〕カンハーギナーだけは許して下さい、私が彼の鬼と一緒に参ります」と兄のヂャーリが言うところを読むと、賢治の童話「ひかりの素足」において、鬼の鞭に打たれる弟をかばって兄の一郎が言った、「楢夫は許して下さい、楢夫は許して下さい」という言葉を、私は思い起こさずにはいられません。
◇ ◇
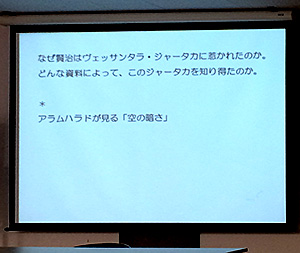
さて、君野隆久氏はこの講演において、(1)なぜ賢治はヴェッサンタラ・ジャータカに惹かれたのか、(2)どんな資料によって、このジャータカを知り得たのか、という二つの疑問を提出されました。
このうち(2)については、上に引用させていただいたように、伊藤雅子氏が一つの(かなり確からしそうな)説を提唱しておられます。
今日はここで(1)について、すなわち「なぜ賢治はヴェッサンタラ・ジャータカに惹かれたのか」という問題に関して、私なりの考えを記してみたいと思います。
このヴェッサンタラ王の話において、読む者に最も強い印象を与えるのは、やはり王が最愛の子供2人と妻を、人の求めに応じて「布施」してしまうところです。王が様々な財宝を人に施したという話など、たとえそれが国の宝と言われる白象であったとしても、「肉親を捨てる」というこの衝撃的な布施の前では、全くかすんでしまいます。
一方、様々なジャータカの中には、いわゆる「捨身」=自己犠牲の説話も、たくさん出てきます。自分の皮を猟師に与え、自分の肉を虫たちに与えたという竜の話もそうですし、あの「捨身飼虎」の話もそうです。賢治は、もちろんこの種の自己犠牲の話にも偏愛を示し、上記の竜のジャータカは「手紙 一」として翻案していますし、「我が身を犠牲にして人を助ける」という話は、種々の童話に登場します。
これらに比してヴェッサンタラ王の話の特異性は、「我が身」ではなく、ある意味で「我が身以上に大切な」子供や妻を、他人のために与えてしまうところです。ある人々は、これを「冷酷非情な行い」と感じるでしょうが、真の家族の情愛を知る者にとっては、これは恐ろしいほどに深く強靱な、「喜捨の心」とも受け取れます。
そして、家族愛の深い家庭に育った賢治にとっても、やはりこれは我が身を捧げる布施以上に、衝撃的な話だったのではないでしょうか。
父母+兄+妹という家族構成は、ある時期までの宮澤家と同じであり、父は自ら病気になってまで息子を看病するほどの人であり、母もまたこの上なく優しい人であったと言われています。そして、兄と妹の仲の良さも、皆様ご存じのとおりです。
賢治にとっての「家族」がこのようなものであってみれば、その父親が自分たちいたいけない子供を、他人の求めに応じて、奴婢として与えてしまうという行動が意味するところは、身を切るほどに痛く、ありありと感じられたことでしょう。
これは確かに、賢治がヴェッサンタラ・ジャータカに強い感銘を受けた理由の一部を構成しているでしょう。
しかし、賢治が生涯にわたってこの説話を三度も引用した理由について、このように解釈してみただけでは、何かとても皮相にとどまっている感を禁じ得ません。
賢治がヴェッサンタラ王の行いに惹かれた背景には、何かもっと深いものが潜んでいるのではないでしょうか。
これについてより深く考えてみるためには、上記のように賢治がもう一方では、「捨身=自己犠牲」というテーマにも非常に強く惹かれていた、その背景にある要因を見てみることが、参考になるでしょう。
賢治が、「自己犠牲」をモチーフとして様々な作品を書いた理由は、「我が身を捨ててまで他者を助ける」という行為が、それだけ強固な利他心を、直截に表現しているからでもあるでしょう。しかし、このような単純な見方にとどまらず、その奥にある心理を想定してみることもできます。
それは、「賢治は、(他者を助けるという)その行為自体の目的とは別に、とにかく我が身を捨てたいという衝動を、心の奥底に抱えていた」という、深層心理学的解釈です。
見田宗介氏は、『宮沢賢治―存在の祭りの中へ』において、賢治には「存在の罪」というようなやむにやまれぬ意識があって、この「罪」を消滅させるために、「我が身を焼き尽くす」という「焼身幻想」を抱いていたと、分析しています。そしてこの「焼身幻想」が「自己犠牲」と結びつくことによって、一つの「合理化」がなされ、「捨身」は単に自己満足のためになされるのではなく、「他者のために」なされるという意味が付与されるのです。
この立場から見れば、「よだかの星」も、「蠍の火」の話も、あるいは「グスコーブドリの伝記」も、そのような形で「合理化された焼身幻想」であるという側面を持ちます。
これを同様に敷衍すれば、ヴェッサンタラ王が我が子を布施してしまうという話に賢治が惹かれているその背後の闇には、「実は賢治は、父親から放逐されたいという無意識的な願望を抱いていた」という仮定を、置いてみることができます。
私がこういうことを考えてみる理由は、1918年(大正7年)当時の賢治という若者は、家父長たる父親が、その人格的・社会的偉大さと、「イエ」の論理と、家族に対する深い愛情によって、完璧に作り上げた「牢獄」の中に、まさに囚われの身になっていたと感じるからです。
もともと商人には学問は必要ないということで、中学までしか行かせてもらえなかったところを、父親の特別の「慈悲」によって高等農林学校に進学させてもらい、晴れてその学校を卒業したからには、長男として家業を継ぐという宿命からは、もはや何をやっても逃れることはできず、しかしどうしてもその家業には嫌悪感しか抱けないという状況に、当時の賢治はありました。
それまでの賢治は、東京で起業をしたいとか、アメリカに行きたいとか、いろいろなことを言って逃げ道を模索してきましたが、どれも父親によって、赤子の手をひねるように却下されてしまいます。
そして1918年(大正7年)2月になると賢治は、自分は徴兵検査を受けてシベリアに行くのだと言い出します。当時、第一次世界大戦は終結していましたが、ちょうどロシア革命の混乱に乗じて日本もシベリア出兵を準備している時期で、そうなると東北地方の第八師団などは、出征する可能性も高かったのです。
父親は息子の身を案じて、高等農林学校の研究生ということにして徴兵検査を延期するよう強く勧めますが、賢治は言うことを聞きません。父の勧めに反抗して、徴兵を忌避することは「放縦なる心」「懈怠の心」を生むと主張したり、愛国心の大切さを述べたりもしますが、なぜ今すぐに検査を受けなければならないのか、賢治が持ち出す理屈には、あまり説得力はありません。
結局さすがの父も、息子のあまりの強引さに押し切られ、賢治は1918年(大正7年)4月に、晴れて徴兵検査を受けました。しかし結果は、「体格や能力が劣る」という「第二乙種」となり、当面は賢治が徴兵される可能性は消滅します。
つまり、「兵役によって家業から逃れる」という賢治の作戦は、失敗に終わったのです。きっと彼にとって、我が身が囚われている牢獄の塀は、一段と高くなったように感じられたことでしょう。
そこに1918年(大正7年)6月、『国訳大蔵経』第十三帙が出版され、おそらく賢治はその中で、仲の良い家族の絆を断ち切り、愛する我が子を他人のもとへ「布施」してしまうという、衝撃的なヴェッサンタラ王の話を読んだのです。
賢治から見れば、もしも自分の父親がヴェッサンタラ王と同じ行為をしてくれたならば、それは三者それぞれにとって、「一石三鳥」の結果を生みます。
その「鳥」の一羽目は、布施をされる相手にとっての直接的利益。二羽目は、そのような尊い犠牲を払うことが父親にとっての善根となるという功徳。そして三羽目は、賢治にとって家という牢獄から解放されるという運命の転換。
賢治は、このヴェッサンタラ王の行跡を読んだ時に、あのお気に入りの「捨身」の説話が醸し出す、一種の甘美さにも似た言い知れぬ魅力を、どこかに一抹感じたのではないかと、私は秘かに思っているのです。
ガハク
おお!これはなんという鋭く穿った説でしょう。
「父親から放逐されたいという無意識的な願望」←これは凄いですね。賢治の心証を理解してないと出て来ない推論。きっとそうですよ。
今までヴェッサンタラ王なんて意識してませんでしたが喜捨といえばキリスト教史にある聖フランチェスコを僕なんかはすぐ思い出してしまうんですがそれを遥かに超える喜捨物語があったんですね。なるほど賢治がこれに惹き付けられてなおかつ自己投入したと。その理由が痛い程分る気がして来ました。
signaless
私の場合は、賢治がヴェッサンダラ王かと思ってしまいました。
何でも布施してしまって国が滅びそうになり父である国王に追放されるというところに、価値のない質草に大金を渡してしまう賢治が、父から放たれたいという願望を潜ませ自分に重ねていたのかも、と。
肋膜炎と診断され結核の影に怯え、(恐らく)自分は結婚を断念し子孫を持たないという思いにかられた頃でもあり、妻や子供を捨てるということは、はじめからそれを持つ願いを捨てるということではないか、なんてことも考えたりしたのですが…。
賢治の願いの根の深さには心痛みます。
hamagaki
コメントをありがとうございます。
>ガハク様
そうですね、確かにかなり「穿った」見方です。
まるで賢治さんの代弁をしているかのような口ぶりで、思わずいろいろと書いてしまいましたが、もちろんこれは私の勝手な思いにすぎません。
それを「面白い」と思っていただける方がおられれば、それだけでも私としては十分ですし、「きっとそうだ」と感じていただけるのならば、嬉しいです。
ところで、この「ヴェッサンタラ王」の話などというのは、私も今回のセミナーを聴くまで、ほとんど意識したことはありませんでした。今回の講演のおかげであらためて詳しく理解して、賢治が特にこの話に惹かれていたというのは、とても興味深いと思った次第です。
>signaless 様
なるほど、ヴェッサンタラ王は賢治自身と考えてみることもできますね。
まさにご指摘のように、賢治が「肋膜のおそれ?」と診断されたのも、おそらく彼がヴェッサンタラ・ジャータカを読んだと推定されるこの1918年のことであり、そして保阪嘉内あて書簡において「但し今後の繋累は断じて作らざる決心に御座候」と書き、妻子を持たない宣言をしたのも、この年の9月でしたね。
とにかく賢治の内面では、いろいろ複雑な葛藤が渦巻いていた、疾風怒濤の時代だったんですね。
コバヤシトシコ
賢治は、深く「捨身」に心を寄せながら、科学者として「捨身」の不可能さを知っていたのではないかと感じています。大切な人が失われようとしたとき、身代りになりたいという思いはあっても、ほとんどの場合不可能です。それを確実にしたのは、トシの死ではないでしょうか。
〈かなしみ〉という言葉は、〈叶わぬこと〉から発生したといわれます。賢治の作品全般に〈かなしみ〉が漂うのは、〈叶わぬこと〉―自分の力ではどうすることもできないこと―死・天災・父との関係など―を知りながら、なおも他者への想いを持ち続けたためではないでしょうか。
3月31日の「なぜ往き、なぜ還ってきたのか。2」のお話も眼から鱗の思いでした。
賢治が〈あゝいとしくおもふものが/そのまゝどこへ行ってしまったか/わからないことが/なんといふいゝことだらう〉という思いに至って、救われていたとしたら、私も心安らぎます。
hamagaki
コバヤシトシコ様、コメントをありがとうございます。
ご指摘のように、賢治自身は「捨身」に心惹かれながらも、それを肯定しきれない気持ちも抱いていたのかと、私も思います。
そして、上でご紹介した君野隆久さんも、講演の中で同様のことを指摘しておられました。
君野さんによる上の2枚目のスライド写真に、「アラムハラドが見る『空の暗さ』」と書かれています。
これについて、本文中では触れる余裕がありませんでしたが、「学者アラムハラドの見た着物」において、アラムハラドがヴェーッサンタラ大王の話を子供たちに語り聞かせた直後に、「さっきまでまっ青で光ってゐたその空がいつかまるで鼠いろに濁って大へん暗く見えたのです」というところがあります。
あるいは、「銀河鉄道の夜」においても、ジョバンニが「僕はもうあのさそりのやうにほんたうにみんなの幸のためならば僕のからだなんか百ぺん灼いてもかまはない」と言った後に、あの不吉な「石炭袋」が現れます。
君野さんはこの二点を挙げて、「自己犠牲の話のすぐ後に、このような対照的な暗さが配置されているのは、賢治自身が自己犠牲ということに対して抱いていた気持ちの反映ではないか」と述べられました。
このご指摘を聴いた時、私も何か深く感じるものがあったのです。
コバヤシ様のコメントのおかげで、この日のお話を思い起こして、また少し考えてみることができました。
今後とも、よろしくお願い申し上げます。
コバヤシトシコ
コメントをいただき有難うございます。
漠然と考えていたことが、作品にも表わされていること、大変うれしいと思います。
これからは私もできるだけ作品に拠って考えるように
してみたいと思います。
よろしくお願いいたします。