「ではみなさんは、さういふふうに川だと云はれたり、乳の流れたあとだと云はれたりしてゐたこのぼんやりと白いものがほんたうは何かご承知ですか。」 先生は、黒板に吊した大きな黒い星座の図の、上から下へ白くけぶった銀河帯のやうなところを指しながら、みんなに問をかけました。
カムパネルラが手をあげました。それから四五人手をあげました。ジョバンニも手をあげやうとして、急いでそのまゝやめました。たしかにあれがみんな星だと、いつか雑誌で読んだのでしたが、このごろはジョバンニはまるで毎日教室でもねむく、本を読むひまも読む本もないので、なんだかどんなこともよくわからないといふ気持ちがするのでした。
(中略)
「大きな望遠鏡で銀河をよっく調べると銀河は大体何でせう。」
やっぱり星だとジョバンニは思ひましたがこんどもすぐに答へることができませんでした。
物理的な空間を超越した壮大なファンタジーである「銀河鉄道の夜」が、このような科学的な授業の風景で開始されることは、逆説的なようでありながら実は象徴的です。
「ぼんやりと白いものがほんたうは何か」と問いかける先生の言葉は、物語の後半で「ほんたうの神さま」について、ジョバンニたちが議論をする場面を、何となく予感させます。
もちろん一般的には、「科学的真理」と「宗教的真理」という風に同じ「真理」という言葉を使っても、その意味は異なった次元に属すると考えるのが普通です。しかし賢治の世界では、この二つは同じ次元で不思議な共生をしているように見えます。あるいは、科学と宗教が互いに尊敬を払いつつ相補っているような世界を、作品によって創造しようとした、と言うか……。
私はつい最近、ツイッターで「神秘」と「科学」との関係について話し合う機会がありましたが、人間においてこの二つは分かち難く支え合っていることを、いろんな方の示唆によってあらためて感じました。
ただ一般的には、「科学」と「神秘」は対立関係にあるように思われている節もあって、そのような見方によれば、現代では世界のほとんどは科学で解明されているけれども、まだ一部にはわかっていない所もあり、それが「神秘」として残されている、という理屈になります。
しかし、「科学」がこの世から「神秘」をだんだんと駆逐していっているわけではないことは、少し考えただけでもわかります。
銀河は、昔は「川」だと言われたり「乳の流れたあと」だと言われたりしたということですが、望遠鏡という科学技術のおかでで、少しでもその神秘性は損なわれたでしょうか? カムパネルラの家に遊びに行ったジョバンニは、カムパネルラがお父さんの書斎から持ってきた巨きな本の「ぎんが」というところを広げ、「まっ黒な頁いっぱいに白い点々のある美しい写真を二人でいつまでも見たのでした。……」
ここで二人は、望遠鏡が開いてくれた扉の向こうに広がるさらに大きな「神秘」に、時を忘れるほど感動していたわけです。科学は世界の神秘を減らすどころか、ますます深めてくれると私は思います。地上で木から落ちる苹果と、太陽の周りを楕円軌道で運行する惑星が、簡単な数式で記述できる同じ法則に従っているとは、何と美しく神秘的なことでしょう。
ただ現実には、世の中には「科学万能主義」というような風潮もあって、そのような立場からは「神秘」など無用のものであり、科学と神秘は対立するものとして演出されるきらいもあります。
上記ツイッター上の議論では、「科学はまだ神秘に対する反抗期にある」という面白い意見もお聴きしましたが、このように捉えるとすれば、科学によるそのような「反抗」が始まった時代の最も象徴的な人物は、イタリアのガリレオ・ガリレイ(1564-1642)だったと言えるでしょう。(下写真は、ウィキメディア・コモンズより)
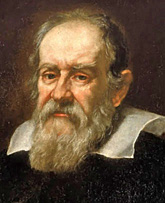 周知のようにガリレオは、著書『天文対話』でコペルニクスの地動説を支持することを間接的に表明したために、聖書の記述に反する異端の説を流布した罪で1633年に異端審問を受け、有罪を宣告されて地動説を撤回します。その際に「それでも地球は動く」と呟いたかどうかはさておき、教会にとってはその神聖な教義に挑戦しようとする、許し難い異端者・反抗者だったわでです。
周知のようにガリレオは、著書『天文対話』でコペルニクスの地動説を支持することを間接的に表明したために、聖書の記述に反する異端の説を流布した罪で1633年に異端審問を受け、有罪を宣告されて地動説を撤回します。その際に「それでも地球は動く」と呟いたかどうかはさておき、教会にとってはその神聖な教義に挑戦しようとする、許し難い異端者・反抗者だったわでです。
宗教と科学が対立・敵対するという構図は、最初はこのようにまず宗教の側が仕掛けたものであったことは、歴史的事実です。先立つ1600年、地動説を最後まで主張したジョルダーノ・ブルーノに至っては、火あぶりの刑に処せられたのですから……。
さてその受難によって、晩年は軟禁状態で不遇に過ごしたガリレオですが、そもそも彼の輝かしい業績は、「パドヴァ公立数学院の哲学者兼天文学者」であった1610年に刊行した、『星界の報告』というパンフレットのような小さな冊子から始まりました。
 |
星界の報告 他一編 (岩波文庫) ガリレオ ガリレイ (著), 山田 慶児 (翻訳), 谷 泰 (翻訳) 岩波書店 (1976/10/18) Amazonで詳しく見る |
オランダで発明された望遠鏡の噂を聞いたガリレオは、その原理を理解して自作し、それまでは航海や軍事目的での応用を期待されていたこの道具を、初めて夜空に向けたのです。そして、次々に驚くべき事実を発見し、興奮も醒めやらぬままに書いたのが、この『星界の報告』でした。
わたしたちが三番目に観測したのは、天の川の本質、すなわち、実体である。わたしたちは、筒眼鏡によってそれを詳細に調べることができた。こうして、この眼で確かめることによって、数世紀のあいだ哲学者たちを悩ませてきたすべての論争に、終止符をうった。わたしたちは、果てしのない議論から解放された。銀河は、実際は、重なりあって分布した無数の星の集合にほかならない。だから、どの領域に筒眼鏡をむけても、星の大群が視野に入ってくる。そのなかには、十分大きくはっきりと目立った星もいくつかあるが、大部分の小さな星は、ほとんど見分けがつかない。
つまり、「銀河鉄道の夜」の冒頭「午后の授業」においてテーマとなっていた「銀河の正体」を発見したのは、この時のガリレオだったのです。
そして上では、「三番目に観測した」のが銀河だったと書いてありますが、ガリレオが最初に観測し、この小冊子でも巻頭で報告していたのは、望遠鏡で見た月面の様子でした(下図は、同書に掲載されたガリレオによる月の表面のスケッチ)。
くりかえし調べた結果、つぎの確信に達した。月の表面は、多くの哲学者たちが月や他の天体について主張しているような、滑らかで一様な、完全な球体なのではない。逆に、起伏にとんでいて粗く、いたるところにくぼみや隆起がある。山脈や深い谷によって刻まれた地面となんの変りもない。
このような月の表面の科学的観測結果についても、実は賢治は書いていました。「雨ニモマケズ手帳」に記していた「月天子」がそれです。
月天子
私はこどものときから
いろいろな雑誌や新聞で
幾つもの月の写真を見た
その表面はでこぼこの火口で覆はれ
またそこに日が射してゐるのもはっきり見た
后そこが大へんつめたいこと
空気のないことなども習った
また私は三度かそれの蝕を見た
地球の影がそこに映って
滑り去るのをはっきり見た
次にはそれがたぶんは地球をはなれたもので
最后に稲作の気候のことで知り合ひになった
盛岡測候所の私の友だちは
--ミリ径の小さな望遠鏡で
その天体を見せてくれた
亦その軌道や運転が
簡単な公式に従ふことを教へてくれた
しかもおゝ
わたくしがその天体を月天子と称しうやまふことに
遂に何等の障りもない
もしそれ人とは人のからだのことであると
さういふならば誤りであるやうに
さりとて人は
からだと心であるといふならば
これも誤りであるやうに
さりとて人は心であるといふならば
また誤りであるやうにしかればわたくしが月を月天子と称するとも
これは単なる擬人でない
ここには、賢治が自然科学の成果を積極的に受け入れつつ、なおまったく同時に、この世の神秘を敬い尊ぶ気持ちが、鮮やかに表明されています。ここでは、「神秘」と「科学」が、対立するものとしてあるのではなく、幸福な結婚を果たしているとも言えるでしょう。
ということで、無類の天文好きだった賢治が作品中に引用している二つの発見が、どちらもガリレオ・ガリレイが刊行した一冊の小さな本で報告されているという偶然があったというわけです。
ところで、賢治が上の「月天子」の最後の方で、「もしそれ人とは人のからだのことであると/さういふならば誤りであるやうに/さりとて人は/からだと心であるといふならば/これも誤りであるやうに/さりとて人は心であるといふならば/また誤りであるやうに・・・」と書いているのは、具体的には何が言いたかったのでしょうか?
ここは、「しかればわたくしが月を月天子と称するとも/これは単なる擬人でない」という最後の結論を導くための論拠として述べている箇所で、この作品においてとても重要な意味を持つのでしょうが、かならずしもわかりやすい論法とは言えません。
記事の残りでは、この箇所について考えてみます。
◇ ◇
「自然科学の父」と呼ばれたガリレオに対して、「近代哲学の父」と呼ばれるのは、フランスのルネ・デカルトです。
デカルトは1596年に生まれ、10歳の時に「ラ・フレーシュ学院」というイエズス会の学校に入学します。くしくもガリレオが『星界の報告』を刊行した1610年、学院の創立者アンリ4世の命日を記念して学生たちが作成した詩集の中に、「アンリ大王の死をめぐる、また二三の新しい惑星あるいは未知の遊星がその年ガリレオ・ガリレイ(フィレンツェ大公の名高い数学者)によって発見されたことをめぐるソネット」という非常に長たらしい題名の14行詩が収められているのですが、デカルトの研究者たちによれば、これが当時14歳のデカルトの作であるという説が、非常に有力なのだそうです(ロディス=レヴィス著『デカルト伝』未来社より)。
この詩は、ガリレオが『星界の報告』で明らかにしたもう一つの大きな業績、すなわち木星の衛星の発見を讃える内容なのですが、おそらく少年デカルトは、『星界の報告』が刊行されたその年にこれを読み、その意義を理解していたということになります。
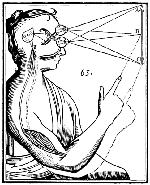 それはさておき。後に壮年期のデカルトが、「我思う、ゆえに我あり」から出発して築き上げた哲学は、「実体二元論」と呼ばれています。この世界は、「思惟」を属性とする「精神」と、「延長」を属性とする「物質」から成り立っており、この二種の実体は本質的に独立しているというのです。しかし独立しているなら、人間の精神が身体を動かすことができるのはどうしてかという問題が出てきますが、デカルトは脳の中の「松果体」という部位において、精神と身体が相互作用すると考えました。(右図は『省察』より、「松果体」における心身の相互作用)
それはさておき。後に壮年期のデカルトが、「我思う、ゆえに我あり」から出発して築き上げた哲学は、「実体二元論」と呼ばれています。この世界は、「思惟」を属性とする「精神」と、「延長」を属性とする「物質」から成り立っており、この二種の実体は本質的に独立しているというのです。しかし独立しているなら、人間の精神が身体を動かすことができるのはどうしてかという問題が出てきますが、デカルトは脳の中の「松果体」という部位において、精神と身体が相互作用すると考えました。(右図は『省察』より、「松果体」における心身の相互作用)
デカルトは、それまでの哲学がアリストテレスなど古典に準拠して物事を考えるだけだったのに対して、独力で一から哲学大系を打ち立てたことにおいて画期的でしたが、その「二元論」は折衷的な印象もあり、評判は芳しくありませんでした。そしてその後の主要な哲学の流れは、もともとキリスト教が「霊」を「肉」よりも優位に位置づけてきたことも反映してか、カント以降ヘーゲルに至る壮大な「観念論」の系譜を形作ります。
「観念論」とは大まかに言えば、事物の存在と存り方は、当の事物についての「観念(イデア)」によって規定される、ということになると思いますが、この立場を突き詰めていくと「唯心論」になります。アイルランドのジョージ・バークリーは、物質を否定して、知覚する精神と神のみが「実体」であると考えました。
ヘーゲルにおいて近代哲学における「観念論」が一種の完成を見ると、そこでまさに弁証法的に、対立物への転化が起こります。若い頃は「ヘーゲル左派」に属したマルクスは、「弁証法は、ヘーゲルにあっては逆立ちしている。神秘的な外皮のなかに合理的な核心を発見するためには、それをひっくりかえさなければならない」(『資本論』第二版あとがき)と述べ、「唯物論」の立場を宣言します。「ヘーゲルにとっては、彼が理念の名のもとに一つの自立的な主体に転化しさえした思考過程が、現実的なものの創造者であって、現実的なものはただその外的現象にすぎない。私にとっては反対に、観念的なものは、人間の頭脳のなかで置き換えられ、翻訳された物質的なものにほかならない」として、観念とは人間の脳における物質の反映にすぎず、物質のみが実体であるとするのです。
以上、突然に西洋近代哲学の流れを述べたのは、賢治の「月天子」の終わりの方の部分は、この「二元論」「観念論(唯心論)」「唯物論」という三つの立場を、賢治がそれぞれ却下しているところだろうと、私は思うからです。
すなわち、
- 「人とは人のからだのことであるとさういふならば誤りである」というのは、「唯物論」の否定
- 「人はからだと心であるといふならばこれも誤りである」というのは、「二元論」の否定
- 「人は心であるといふならばまた誤りである」というのは、「観念論(唯心論)」の否定
という主張になっているのだろうと思うのです。
しかし、近代哲学の主な三つの立場を全て否定してしまって、それではいったい賢治は、「人とは」何であると言いたいのでしょうか。
ここで参照すべきは、『春と修羅』の「序」であると私は思います。
わたくしといふ現象は
仮定された有機交流電燈の
ひとつの青い照明です
(あらゆる透明な幽霊の複合体)
風景やみんなといつしよに
せはしくせはしく明滅しながら
いかにもたしかにともりつづける
因果交流電燈の
ひとつの青い照明です
(ひかりはたもち、その電燈は失はれ)
賢治は、「わたくし」というのは「現象」であると言い、それを電燈の「照明」に喩えれば、その「ひかり」はたもちながらも電燈という「実体」は失われた状態である、と言います。このように「実体」がないという考えは、仏教の「空」の思想に基づいているのでしょう。
そして少し後の箇所では、
これらについて人や銀河や修羅や海胆は
宇宙塵をたべ、または空気や塩水を呼吸しながら
それぞれ新鮮な本体論もかんがへませうが
それらも畢竟こゝろのひとつの風物です
と書いていて、様々に考えられている「本体論」は、結局は「こゝろのひとつの風物」だと言うのです。西洋近代哲学における「二元論」「観念論」「唯物論」は、いずれも何らかの「実体」を想定し、それが「本体」であるという立場であることにおいて「本体論」になるわけですが、賢治はそれも本当は「空」であるところの現象にすぎないと言うわけです。
そして「月天子」において、このように「本体論」をいずれも否定した上で賢治が言いたかったのは、「月」も「わたくし」も、どちらも「現象」であることにおいては何ら違いはない、ということだったのだろうと思います。月を(人のように)天子として敬ったとしても、それは「擬人」ではなく、人も月も同列の現象として扱っただけである、ということになるのでしょう。
思えば、「銀河鉄道の夜」初期形第三次稿ではブルカニロ博士が、ジョバンニがたったいま旅をしてきた「天の川」さえも、心の現象にすぎないことを示していました。
「……変な顔をしてはいけない。ぼくたちはぼくたちのからだだって考だって天の川だって汽車だってたゞさう感じてゐるのなんだから、そらごらん、ぼくといっしょにすこしこゝろもちをしづかにしてごらん。いゝか。」
そのひとは指を一本あげてしづかにそれをおろしました。するとジョバンニは自分といふものがじぶんの考といへものが、汽車やその学者や天の川やみんないっしょにぽかっと光ってしぃんとなくなってぽかっとともってまたなくなってそしてその一つがぽかっとともるとあらゆる広い世界ががらんとひらけあらゆる歴史がそなわりすっと消えるともうがらんとしたたゞもうそれっきりになってしまふのを見ました。だんだんそれが早くなってまもなくすっかりもとのとほりになりました。
「さあいゝか。だからおまへの実験はこのきれぎれの考のはじめから終りすべてにわたるやうでなければいけない。それがむづかしいことなのだ。けれどももちろんそのときだけのものでもいゝのだ。あゝごらん、あすこにプレシオスが見える。おまへはあのプレシオスの鎖を解かなければならない。」
「ぽかっと光ってしぃんとなくなってぽかっとともってまたなくなって……」というのは、まさに人も銀河も「せはしくせはしく明滅」しているわけですね。
最後に、ここで博士からジョバンニに課題として託された、「プレシオスの鎖を解くこと」……。それはまた不思議なことに、ガリレオ・ガリレイが『星界の報告』において、銀河の観測の前に「筒眼鏡」を向けてその詳細を明らかにしてスケッチした、もう一つの天体でした。
ガリレオなりに解いた「プレシオス(プレアデス)の鎖」が、ここにあります。
第二例として、プレイアデスを描いた。これは天空のきわめて狭い区域にとじこめられている牡牛座の六つの星(六つというのは、七番目の星が殆どみえないから)である。その附近には肉眼にみえない40以上の星が密集している。そのいずれも、上述の六つの星のいずれかからも、半度とは離れていない。そのうちの36個だけを記しておいた……。

『星界の報告』に載せられたガリレオによるプレアデス星団のスケッチ
signaless
「月天子」にこれだけのことが詰まっていたなんて…と絶句しています。
賢治も凄いけど、それを読み解き、判りやすく解説して下さるhamagakiさんも凄い…。
賢治が、わかりやすい言葉を使って非常に深いことを書いていることに改めて感動しています。賢治が読み飽きず、どれだけでも追いかけたくなるのはそういう美しく楽しい仕掛け(?)がいっぱい潜んでいるからかもしれません。
賢治をあまり知らなくても、よく知っていても、それぞれの位置からいろんな発見や見方ができる。
ますます、宮沢賢治というひとは何という人なんだろうと感じています。
NakashoNobuo
この文章は私の長年の疑問「賢治は何故マルクス主義から自由でいられたのか?」に答えてくれています。およそ当時の知識人が多かれ少なかれ影響を受けていたマルクス主義。賢治は全く異なる物差しの中で生きていた。それは本質論ではなく、因果論だったのですね。
「因果」について、実は数カ月前に南直哉著「『正法眼蔵』を読む」を読みかけて、今まで自分が親しんできた哲学指向との余りの違いに愕然とし、むしろ敬して遠ざけてしまっていたのです。これは腰を据えて読まなければ・・・のまま。
しかし、賢治は法華経に親しむ思考の中で、自ずから本質論を遠ざけていたために、マルクス主義とは全く共鳴しなかった。しかもその答えは「春と修羅」の序に明確に示されていたとは!ツイッターで「月天使」を示されていたときには、あまりにストンと抵抗なく受け入れていて、賢治ならそう言うだろうと思っていました。しかしその中にここまで伸びるベクトルが含まれていることには気が付きませんでした。有難うございます。
ところで、私が取り組んでいるもう一人の詩人、尹東柱(ユンドンジュ)(ご存知でしょうか?)もマルクス主義と無縁の人なのです。キリスト者である彼が因果論者(乱暴な言い方ですが・・・)だったとは思えません。二人に共通しているのは、言語意識のありようのような気がします。今は明確な言葉では表現できませんが、そこに何か共通しているものを感じます。
ガハク
プレアデスは地球から最も近い僕らの銀河とは別の星団だと聞かされて双眼鏡で観察した事があります。
その謎を解く事がブルカニロ博士から命じられたことでそれはガリレオもどうやら「気にしていたらしい」って事で良いですか?
そこに未知の神秘があり科学はその開かずの扉に挑戦すべしと。
それにしても『月天子』の思想性は僕らに美しく深く浸透してどれだけ勇気を与えてくれたか分からない。本当に僕はこのことだけでも賢治に感謝している位なものです。
それからガリレオという人も面白そうな人ですね!w。がぜん興味湧いてきました。
さて今回は(残念な事に)触れられてませんでしたが、この『月天子』の詩に納得できるか否かで、その人の中にウォーコップの「神秘≧科学」のパターンが成り立つかどうかも決まるのでは?と思いました。
kyoちゃん
この長く正しく美しい文脈で展開された『ガリレオの筒眼鏡』という織物は、
横糸が宮澤賢治の『銀河鉄道の夜』と『月天子』で、
縦糸にはガリレオの神秘と科学を縒り合わせた絹糸が使われているようです。
青や黄色の模様のデカルトヘーゲルマルクスも、賢治の金色の糸で輝いて見えます。
この織物の中にはウィリアム・ブレイクの詩も仕込まれていて、ほんとうに楽しく読ませていただきました。
hamagaki
皆様コメントをありがとうございます。
> signaless 様、
「賢治がわかりやすい言葉を使って非常に深いことを書いている」、本当にそのとおりですね。
それで私たちは時として、深読みの「しすぎ」をしそうにもなってしまいます。特に、こんなブログを書くネタをひねりだそうと頭をかきむしっていると・・・w。
つねづね自戒はしているつもりなのですが、時に自分の過去の記事を見ると、いくら何でもこれは「こじつけ」だろう、というのもあったりして、赤面します。
> NakashoNobuo 様
生まれた時から仏教が骨身にまでしみこんでいただろう賢治にとっては、(労農党のシンパとなっていたように)マルクス主義の目ざす何かに共感するところはあっても、その思想そのものに一体化することは、困難だったのでしょうね。
尹東柱(ユンドンジュ)という詩人については、不勉強にも、まったく知りませんでした。「言語意識のありようが賢治と共通している」とは、とても興味が湧きました。ご教示ありがとうございました。
> ガハク様
はい、ガリレオもブルカニロ博士には、どこかで出会っていたんじゃないでしょうか。何せ、ジョバンニもカムパネルラもブルカニロも、みんな彼と同じイタリア人っぽいですからねw。
ウォーコップについては、話を持ち出そうとすると全体がまた倍くらいの字数になってしまいそうでしたので、今回は触れることができませんでした。
しかしウォーコップの哲学は、、上に述べたような「二元論」「観念論」「唯物論」というような世界観の対立を、軽々と乗り越えた地点からすべてを見渡せるようなところに、私としては最大の魅力を感じます。
> kyo 様
美しすぎるコメントをありがとうございます。
目ざすところとしては、一本の線のように伸びるお話であるだけでなく、上に理想的に描いていただいたような、二次元に織物のごとく広がる世界が書けたらもう言うことないのですが、実際はとてもそうは行きません・・・。
もし、少しでもそれに近いものができるとしたら、題材としてとりあげた賢治の作品が、そういう様々な方向に広がっていく深さを持ってくれているおかげですよね。
fujino
「月天使」の解釈をとても刺激されるように拝見しました。最近、賢治さんの「まことのことば」とか「まことのいのち」という言葉が頭の片隅をうろうろしているのですが、賢治さんはそのことをおそらく科学と宗教の合一の中にきっととらえていたのだろうと思いますがよくわかりません。
表現できないのですが、hamagakiさんの「月天使」解釈がそのことを教えてくれているように読みました。
hamagaki
fujino 様、コメントをありがとうございます。
そうですね。賢治が、自分の存在以前のすべての根底に置いていたのは、法華経を中心とした仏教だったでしょうし、科学に対しても時には「冷たく暗い」なんて不満を表明しながらも、じつは不満は期待の裏返しであり、心底からずっと科学を愛していたと思います。
そのような科学に対する思いと、心に備わった宗教的感覚とを素朴に表現したのが、この「月天子」という作品ですよね。
以前は、これはちょっとナイーブすぎるように感じたこともあったのですが、やっぱり賢治らしい、愛らしい作品だと思います。
今後とも、よろしくお願い申し上げます。