「小岩井農場」の「パート九」の終わり近くに、次のような有名な箇所があります。
ちいさな自分を劃ることのできない
この不可思議な大きな心象宙宇のなかで
もしも正しいねがひに燃えて
じぶんとひとと万象といつしよに
至上福しにいたらうとする
それをある宗教情操とするならば
そのねがひから砕けまたは疲れ
じぶんとそれからたつたもひとつのたましひと
完全そして永久にどこまでもいつしよに行かうとする
この変態を恋愛といふ
そしてどこまでもその方向では
決して求め得られないその恋愛の本質的な部分を
むりにもごまかし求め得やうとする
この傾向を性慾といふ
すべてこれら漸移のなかのさまざまな過程に従つて
さまざまな眼に見えまた見えない生物の種類がある
この命題は可逆的にもまた正しく
わたくしにはあんまり恐ろしいことだ
けれどもいくら恐ろしいといつても
それがほんたうならしかたない
さあはつきり眼をあいてたれにも見え
明確に物理学の法則にしたがふ
これら実在の現象のなかから
あたらしくまつすぐに起て
賢治の典型的な世界観、そして世界に対する己の態度を表現したものとして、しばしば引用され論じられることも多い部分です。見田宗介氏は『宮沢賢治―存在の祭りの中へ』において、これを「長詩のおわりの、思想的な結語のごとき個所」と呼んでおられます。
それだけ重要と考えられてきた箇所ですが、今日ここで考えてみたいのは、下から3分の1あたりにある「この命題は可逆的にもまた正しく」という言葉の意味するところです。
私は以前に、「《ヘッケル博士!》への呼びかけに関する私見」という記事において、この「可逆的」という言葉の意味を、「ほんらい生物学的には、種は自然選択によって適者生存の方向へ変化(=進化)し、個体は発生過程で未熟な段階から成熟した段階へと変化(=発生)していくが、賢治はその変化に「逆方向」もありうる、と言っている」のだと解してみましたが、その後もう少し詳しく考えてみると、上記の解釈は間違っていたのではないかと思うようになりました。
そこで、あらためてきちんと考えてみようというのが、本日の趣旨です。
まず問題は、「可逆的にも正しい」という言葉の意味です。これは圧縮した表現でやや寸詰まりになっていると思いますが、これをくだいて言い換えれば、(1)「この命題は可逆的(reversible)である」すなわち「この命題の[逆]も、一つの命題として成立する」という主張と、(2)「その[逆の命題]なるものも、また正しい」という主張と、二つのことを同時に言っているのだと思われます。
そこで、この[逆の命題]とは何なのか、ということが次の問題になります。いくつかの考え方がありえます。
1.形式論理学的な「逆」
論理学においては、「PならばQである(P⇒Q)」という命題があるとすると、「QならばPである(Q⇒P)」という命題のことを「逆命題」と呼びます。ちなみに、「PでないならばQでない(¬P⇒¬Q)」のことを「裏命題」、「QでないならばPでない(¬Q⇒¬P)」のことを「対偶命題」と呼びます。元の命題が真ならば、その対偶は必ず真になりますが、逆や裏は真とは限りません(「逆は必ずしも真ならず」)。
たとえば、「地球は丸い」という命題は真ですが、その逆の「丸いものは地球である」という命題は偽です。ここで「地球は丸い」という命題の「逆命題」は何であるかということを考える際に、「地球は丸い」という元の命題を、「(物体xは地球である)ならば(物体xは丸い)」という形に、変項xを含んだ表現に分解してみるとわかりやすくなります。この形式ならば、その逆命題は「(物体xは丸い)ならば(物体xは地球である)」となることは明らかであり、それは「丸いものは地球である」と言い換えられます。
以上を前置きとして、このような形式論理学によって、賢治が提出した命題の「逆」を考えてみます。
ここで「元の命題」は、上の引用において「この命題は可逆的にもまた正しく」の前行までの部分になります。その内容を要約すれば、「ある宗教情操→恋愛→性慾」という、さまざまな「個体間相互作用」とでも言うべき活動の「漸移」があって、その漸移のなかの種々の過程に対応して、「さまざまな眼に見えまた見えない生物の種類がある」のだ、ということになるでしょうか。
ここで想定されている「さまざまな生物の種類」とは、賢治にとっては仏教的な「十界」だったと思われますから、図示すると、下のようになります。とりあえず、「ある宗教情操」には「菩薩」、「恋愛」には「人」、「性慾」には「畜生」を対応させています。
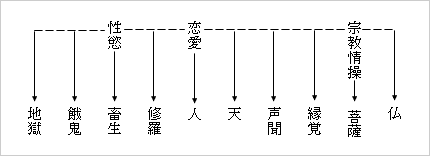
さて、これは複雑な命題なので、やはり上の「地球は丸い」のように、変項を含んだ命題に書き直してみると、次のようになります。
(個体xが、Aという個体間相互作用を示す)ならば、(個体xは、Bという生物種に属する)
ここで、「個体間相互作用」と呼んでいるものの内容としては、恋愛と性慾の中間的な形態や、恋愛に少しだけ宗教情操の混じったものなど、さまざまな段階のものがありえるでしょうが、系列の中のどの段階にあるかによって、生物の種類が決まるというのです。
元の命題が上記であれば、その逆命題は、次のようになります。
(個体xが、Bという生物種に属する)ならば、(個体xは、Aという個体間相互作用を示す)
生物種の方から、個体間相互作用が一意的に決定するというのです。これを図示すれば、下のようになります。
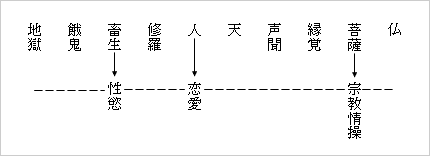
さてこれが、はたして賢治の言いたかったことでしょうか。ちょっと私にはそうは思えません。
上記の「元の命題」と「逆命題」がどちらも正しいということは、生物種と個体間相互作用の間には、固定した「一対一対応」の関係があることを意味します。たとえば、人間には「恋愛関係」しかありえないし、逆に「恋愛関係」を持つ生物は人間だけである、ということになります。これでは、現実にも合いませんし、これを賢治が「わたくしにはあんまり恐ろしいことだ」と言うとも思えません。
実際、「恋愛」はかなり人間的な営みではあるでしょうが、人はもっと即物的な「性慾」にとらわれた行動をすることもありえますし、また一方で時には凡夫も「正しいねがひに燃えて/じぶんとひとと万象といっしょに/至上福祉にいたらうとする」こともあるでしょう。また、動物のカップルが、性慾のためだけでなく相手のことを思いやる行動をとる(ように見える)こともあるでしょう。このように、どの「界」にも他の「界」の特性が一部備わっているという考えが、賢治も信じていたはずの「十界互具」という思想です。
結局ここで考えてみた事柄は、常識的な観念とも、賢治の思想とも異なっています。すなわち、形式論理学的な解釈では、この箇所は理解できないようです。
2.唯物論的解釈としての「逆」
ちなみに、「小岩井農場」のこの箇所について、吉本隆明氏は、次のように述べておられます(「喩法・段階・原型」:『宮沢賢治』所収)。
宗教から恋愛へ、そして性慾へと連続して流れてゆく情操と願望のうつりかわり(変態)という理念は、宮沢賢治の生涯の理念であるとともに、生涯によってじっさいに演じられたドラマだった。この考え方はふつう倒さだ。人間の身体の生理的なうつりゆきの必然的な過程で、性慾がきざし、さかんになり、思春期にはいって、ひとりの異性をもとめる願望に結晶してゆく。この願望がうまく遂げられず、そのあげく宗教的な自己救済や人間救済の願いを持つようになる。そんな過程はありうる。だがこの逆はない。宮沢賢治がスケッチャーとしてここで展開している考え方は、逆だった。これはただの詩的修辞とみなさないとすれば、宮沢賢治の生涯の謎を理念化したものだといえる。
吉本氏が賢治の考えに対して、「この考え方はふつう倒さだ」「宮沢賢治がスケッチャーとしてここで展開している考え方は、逆だった」と評する時、そのはるか背後には、マルクスが「ヘーゲルの弁証法は倒さに立っている」と断じたことが、かすかに連想されていたのではないかと、私は勝手に想像します。いずれにしても、吉本氏が指摘するとおり、一般には、性慾が昇華されて恋愛感情になり、「愛」の感情がより普遍化される時、一つの宗教情操が生まれるという方が、よくある考え方でしょう。
賢治の命題はその逆なわけですが、これをマルクスがヘーゲルを逆転させたように、もう一度倒さにすることで、「逆の命題」を得ることができます。それは、上にも述べたように、「性慾が昇華されて恋愛になり、愛が普遍化されて宗教情操になる」という命題であり、いわば唯物論的な立場からの宗教の解釈です。
これが、賢治の言う「この命題は可逆的にもまた正しく」ということの意味するところかもしれません。もしも、賢治が全存在をかけて信仰する宗教情操が、もとをたどれば性慾の昇華されたものにすぎないとすれば、それが「わたくしにはあんまり恐ろしいこと」と感じられるのも、無理もないでしょう。
これは一つの仮説として成立すると思いますが、しいて難点を挙げるとすれば、以下のようなことが考えられます。
その一つは、作品テクストでは上で論点となった「宗教情操→恋愛→性慾」という記述の後に、「すべてこれら漸移のなかのさまざまな過程に従つて/さまざまな眼に見えまた見えない生物の種類がある」という2行があり、その次に「この命題は可逆的にもまた正しく」という一節が来るという配列の順序です。ごく素直に読めば、「この命題」という言葉は、その直前の内容を指しているように感じられ、「宗教情操→恋愛→性慾」の部分であると解釈するためには、少しだけ飛躍しなければなりません。
もう一つの難点は、賢治の世界観との関係です。私が理解するところでは、当時も賢治が考えていたのは、「宗教と科学はいずれ一体化する」というようなことだと思うのですが、上記のような理解に立つと、宗教と科学は、融合するような関係ではなくて、「逆」すなわち対立関係になってしまいます。
したがって私としては、この仮説も棄却したい感じがします。
3.変態の起こる領域の「逆」
最後に考えてみるのは、1.の変形とも言えるもので、1.のように元の命題を論理的な「逆命題」にするのではなく、意味内容を生かして一部だけを入れ替えるものです。「逆にする」理屈として厳密さには劣りますが、より現実的ではあると思います。
これに関しては、図を見ていただくのが早いでしょう。まず、テクストにある「元の命題」が下記です。
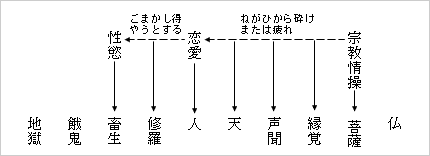
次に、上下を入れ替えた「逆」の命題が、下記です。
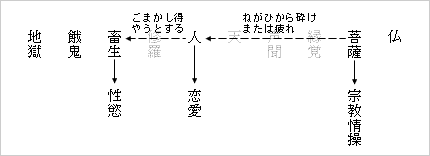
すなわち、すべての生き物は、その行動や心の持ちよう、あるいは信仰のあり方によっては、十界のうちの上位の段階から下位の段階に「堕ちて」しまうこともあるのだというのです。
この現象は、仏教における「輪廻転生」のことと解釈することができます。「ねがひから砕けまたは疲れ」たり、あるいは「むりにもごまかし得やうとする」と、生物は下位の段階に輪廻転生してしまうことになり、これは賢治にとって、「あんまり恐ろしいことだ」と感じられるのも当然でしょう。
もっともこの図にあるように、仏教的には「菩薩」の段階にある存在が本当に下に「堕ちて」しまうということはないのでしょうから、これは図式化することの限界に由来する誤差と言うべきかと思います。
ただし、「小岩井農場」とちょうど同じ1922年5月21日の日付を持つ作品「〔堅い瓔珞はまっすぐに下に垂れます〕」の中には、「ねがひから砕け」堕ちるのではなく、「願ひによって堕ち」る人のことが出てきます。
こんなことを今あなたに云ったのは
あなたが堕ちないためにでなく
堕ちるために又泳ぎ切るためにです。
誰でもみんな見るのですし また
いちばん強い人たちは願ひによって堕ち
次いで人人と一諸に飛騰しますから。
ここに登場する「いちばん強い人たち」とは、まさに「菩薩」のことなのでしょう。これより前の箇所では、「天人が堕ちる」ことについて記され、また上のように「あなたが堕ちる」ことについても書かれていて、この項の意味での「逆命題」が、生き物が「堕ちる」ことについて示唆していることとつながるようです。
というわけで、上記のように同日付作品との関連性からも、私としてはこの3.の解釈が、もっとも妥当なのではないかと思うところです。
と言うか、このように考えてみることによって、同日付に書かれた「小岩井農場」と「〔堅い瓔珞はまっすぐに下に垂れます〕」というかなり印象の違う二作品の関係が、浮かび上がってくるように思えるのです。

熊野観心十界曼陀羅
コメント