『春と修羅』所収の「マサニエロ」という作品は、冷たい秋の空にどこかしらさびしい雰囲気が感じられます。翌月のトシの死の予感も、漂ってくるようです。
この作品の中に、「(ロシアだよ チエホフだよ)/はこやなぎ しつかりゆれろゆれろ」という一節が不意に登場するのですが、これについて「新宮澤賢治語彙辞典」は、「チェホフに民話風の短篇『はこやなぎ』があるのを賢治は読んでいて連想したと思われる」と説明しています。ところが、いくらあちこちを探しても、チェーホフには「はこやなぎ」という題名の作品は見つからないのです。
「日本ロシア語情報図書館」というサイトにある「チェーホフ日本語翻訳作品一覧」というページは、翻訳された作品に関してはかなり網羅的なようですが、これにも「はこやなぎ」という作品は載っていませんし、国会図書館の蔵書から検索した1922年以前に出版されたチェーホフの訳書5冊の収録作品の中にも、そのような題名は見あたりません。
ちなみに、チェーホフの初期の短篇に、「ねこやなぎ」という作品ならあります。猫が箱に化けるなどということはないでしょうが(笑)、ひょっとして「新宮澤賢治語彙辞典」は、このよく似た作品名と取り違えたのでしょうか。
「マサニエロ」では、賢治はぼんやりと空を眺めながら、イタリア→ロシア→支那という風に自由に連想を浮遊させているのですから、たまたまそこにあった樹木とチェーホフの作品名との間に、とくに関連は存在しなくてもよいようにも思います。どなたか、チェーホフの「はこやなぎ」という作品についてご存じ方がおられましたら、ご教示いただければ幸いです。
さて、私としては、チェーホフと宮澤賢治を並べてみると、両者の作品に出てくる不思議な「音」のことが気になります。
まずチェーホフの「桜の園」の第二幕に、その音は登場します。(湯浅芳子訳)
(みんなすわって、じっと考えこむ。静けさ。フィールスがそっとつぶやいているのだけがきこえる。突然、まるで天から落ちたように、遙かな遠い音が鳴りひびく、ぷっつり切れた絃の、しだいに消えてゆくもの悲しい音)
リューボーフィ・アンドレーエヴナ あれは何?
ロパーヒン わかりません。どこか遠くの炭坑で釣瓶が切れたんでしょう。
しかしどこか非常に遠くだ。
ガーエフ がもしや鳥かもしれん。何か……鷺のような。
トロフィーモフ それとも大みみずくか……
リューボーフィ・アンドレーエヴナ (身ぶるいする)気持ちがわるいわど
うしてか。(間)
この音は、第四幕のいちばん最後の幕切れにも現れます。四幕ではすでに桜の園の桜は伐り倒され始めていますが、その斧の音は別に聴こえていますから、これは得体の知れない「謎の音」です。それがはたして何を象徴しているのかということについては、様々な議論があるようですね。
具体的にどんな音をイメージするかとなると、人によっていろいろでしょうが、「演劇の舞台音響 =「桜の園」の音=」というページでは、その一つの実例を聴くことができます。
一方、賢治の「林学生」(「春と修羅 第二集」)には、次のような部分があります。
東の青い山地の上で
何か巨きなかけがねをかふ音がした
それは騎兵の演習だらう
いやさうでない盛岡駅の機関庫さ
そんなもんではぜんぜんない
すべてかういふ高みでは
かならずなにかあゝいふふうの、
会体のしれない音をきく
それは一箇の神秘だよ
ここでも、登場人物があれこれと詮索していますが、結局この「巨きなかけがねをかふ音」は、「一箇の神秘」ということになっています。
私には、何となく二つの音の由来が似ているように感じられ、「桜の園」でも「林学生」でも、これはきっと「この世の音」ではなくて、世界の裏側かどこかから響いてきているのではないかと思えるのです。
音楽において、これらに相当する「音」を考えてみると、私は、マーラーの交響曲第六番の第四楽章で、二度にわたって撃ち下ろされる巨大なハンマーの音を連想します。
ところで、チェーホフと賢治には、このような「謎の音」、それからどちらも結核で亡くなったことに加えて、さらにもう一つ共通点がありました。
二人とも、その生涯における魂の危機に際して、サハリンを訪ねていたのです。
チェーホフは、30歳の1890年にサハリンを目ざしますが、まだシベリア鉄道も開通していない時代に、大半を馬車で、モスクワから1万km離れた極東のさい果ての地へ行くのは並大抵のことではなく、実に片道に3ヵ月を費やしています。そしてサハリンでは、苛酷な環境で強制労働をさせられている流刑囚の実態を3ヵ月にわたって調査し、その結果を後に『サハリン島』という厖大な報告書にまとめます。
賢治の旅行は、これに比べるとはるかに穏やかなもので、自分自身「オホーツク挽歌」で 'Casual observer! Superficial traveler!' と自嘲したように、わずか数日間の滞在にすぎませんでした。
しかし、チェーホフの旅行が「仮死と再生の旅」と呼ばれるのと同様に、賢治のサハリン行はやはり彼自身にとっては死を賭けた試みであり、これらの旅の体験が彼らのその後の創作に対して大きな影響を与えたことも、共通しています。
チェーホフが亡くなったのは1904年で、これは日露戦争が始まった年でした。この戦争にかろうじて勝利をおさめた日本は、1905年のポーツマス条約によってサハリンの南半分の領有権を獲得し、1907年に「樺太庁」を設置します。
1918年、日本はロシア革命に乗じてシベリア出兵を行い、さらに北方への足場を固めようと、陸海の交通網を整備していきます。1922年11月、旭川~稚内間の宗谷線が開通したのに続いて、1923年5月には、稚内港とサハリンの大泊港を結ぶ稚泊連絡船が就航しました。これによって、東京からサハリンまでの経路が、鉄道および連絡船によって、一本に貫通したわけです。
まるでこれを待っていたかのように、賢治がサハリンへ旅立ったのは、その年の夏のことでした。
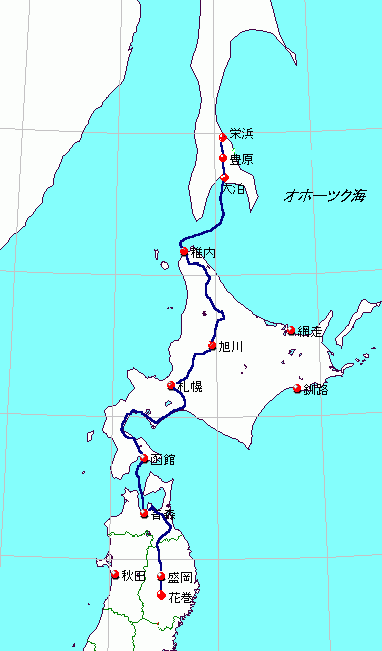
コメント