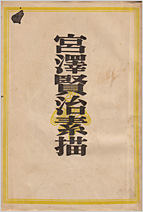 関徳弥氏(筆名:関登久也)は、賢治からすると「従叔父(いとこおじ);父方祖母の腹違いの弟の息子」にあたりますが、年齢は賢治の3歳下で、賢治の影響で短歌を作り、賢治と時を同じくして「国柱会」に入るなど、生前の賢治を兄のように慕っていたということです。その関登久也が賢治に関するさまざまなエピソードをつづった『宮澤賢治素描』という本の中に、次のような文章があります。
関徳弥氏(筆名:関登久也)は、賢治からすると「従叔父(いとこおじ);父方祖母の腹違いの弟の息子」にあたりますが、年齢は賢治の3歳下で、賢治の影響で短歌を作り、賢治と時を同じくして「国柱会」に入るなど、生前の賢治を兄のように慕っていたということです。その関登久也が賢治に関するさまざまなエピソードをつづった『宮澤賢治素描』という本の中に、次のような文章があります。
花束
昭和二年頃でありましたか、東京から声楽の立松房子夫人が花巻に参りました。夫君の立松判事が職務上の事件から、世間的に問題を捲き起こし、たいへん同情されて居りました。随つて立松夫人の独唱会もそれらの原因もあつてか人気を呼び起し、当日の朝日座に於ける会は、大入でなかなかの盛会でした。その頃賢治は羅須地人協会を開設し、音楽に多大の関心を持つて居られましたので、オルガンやギターを買つて勉強してゐると云ふ話が私達の耳にも這入つて居りました。さて当夜の独唱会には私も参り、立松夫人の奇麗な、しかも精神的なソプラノに感激して耳を傾けて居りましたが、プログラムもだんだん終りに近づいた頃、可愛い尋常一年位の女の子が舞台に出て来て、手にあまる美しい花束を、立松夫人に渡しました。花束は実に水々しく真紅の花、淡紅色の花、それに白や水色など、或ひはほやほやした毛のアスパラガスなど交へたものでした。その少女は町の宮金といふ砂糖問屋の可愛い百合子さんといふ少女でした。立松夫人は夫君を助ける為に一人児を家に置いて、地方廻りの独唱会を開いてゐるといふことなど、大分人々の同情を買つてゐましたが、花束を捧げた少女と、立松夫人のとり合せは大変涙ぐましい情景で、しかも美しい大きな花束は一層、その場面の気分を引立たせたので、満堂は酔へるが如く拍手の嵐を送りました。その時あの花束は一体誰が送ったのだらうと考へてみましたが、少したつてそれは賢治が手作りの花を少女へ頼んで渡したのだといふことがわかりました。それまでは賢治といふ人はそんなことをする人だとは思つて居りませんでしたので、意外な感興を吾々は呼びおこしたものです。
立松夫人と大きな花束と賢治といふ取合せは今も美しい一つの詩となつて、吾々の脳裡に消ゆることなく残つてゐます。
「ひそかに贈る」というところが賢治らしい感じがしますが、それにしてもここに出てくる「声楽家と少女」という取り合わせは、賢治の童話「マリヴロンと少女」を、おのずと連想させます。
賢治は、別に童話のイメージを再現しようとして少女に花束を贈らせたわけではないのでしょうし、あるいは舞台上の情景を見て、「めくらぶだうと虹」から「マリヴロンと少女」への改作を思いついたわけでもないのでしょうが、これは「美しい一つの詩」と表現するにふさわしい、印象的なエピソードに思えます。
ところで、童話に出てくる歌手「マ リヴロン」は、『新宮澤賢治語彙辞典』によれば、19世紀を代表するフランスのオペラ歌手 Marie Malibran の名前から由来しているということです。賢治が中学5年時に習った英語のリーダーの中に、'Malibran and the Young Musician' という話が出てくるので、これが賢治の記憶に残っていたのだろうという推定です。
リヴロン」は、『新宮澤賢治語彙辞典』によれば、19世紀を代表するフランスのオペラ歌手 Marie Malibran の名前から由来しているということです。賢治が中学5年時に習った英語のリーダーの中に、'Malibran and the Young Musician' という話が出てくるので、これが賢治の記憶に残っていたのだろうという推定です。
実際の歌手マリー・マリブランは本当に美しかったということで、右のように当時に描かれたいくつかの肖像画が残っています。
Wikipedia(英語版)によれば、マリーは父の主宰する一座とともにニューヨークで公演中に、28歳も年上の銀行家フランソワ・マリブランと電撃結婚をしたということですが、これはマリブラン氏がマリーの父親に、結婚させてくれれば10万フランを贈ると約束したため、父に無理強いされたのだという説もあるということです。ところが、結婚後わずか数ヵ月で夫の銀行は破産してしまい、マリーは歌手活動によって夫を経済的に支えざるをえなくなるという不運に見舞われています。
そしてこの、「夫を支えるために歌う」というところが、最初に引用した立松房子女史に通じるところがあるのです。「夫君の立松判事が職務上の事件から、世間的に問題を捲き起こし」とか、「立松夫人は夫君を助ける為に一人児を家に置いて、地方廻りの独唱会を開いてゐる」という箇所にほのめかされていますが、その「事件」とは、次のようなものでした。
1925年(大正14年)、無政府主義者の朴烈とその(内縁の)妻の金子文子が、皇太子に対する襲撃を計画していたとして、大逆罪で起訴されました(朴烈大逆事件)。この事件の予審判事として二人の取り調べを担当したのが、立松房子の夫である立松懐清氏で、朴と金子は、1926年(大正15年)5月に大審院で死刑を宣告されます。まもなく二人は恩赦により無期懲役に減刑されるも、両人ともそれを拒否し、金子は7月に刑務所内で縊首自殺を遂げてしまいました。 ところが金子の死の7日後、予審取調中に金子が朴の膝の上に座り、仲睦まじくくつろいでいるような写真(右)が世間に出回り、「怪写真」として問題になります。予審判事だった立松懐清が、自白を得るために二人に「特別待遇」を与えていたとして非難され、野党や右翼は司法の綱紀紊乱を言い立て、当時の若槻礼次郎内閣の不信任案が国会に提出されるまでに至ります。事件の責任を問われた立松懐清判事は免官され、その後1938年(昭和13年)に結核で世を去ります。
ところが金子の死の7日後、予審取調中に金子が朴の膝の上に座り、仲睦まじくくつろいでいるような写真(右)が世間に出回り、「怪写真」として問題になります。予審判事だった立松懐清が、自白を得るために二人に「特別待遇」を与えていたとして非難され、野党や右翼は司法の綱紀紊乱を言い立て、当時の若槻礼次郎内閣の不信任案が国会に提出されるまでに至ります。事件の責任を問われた立松懐清判事は免官され、その後1938年(昭和13年)に結核で世を去ります。
この「怪写真事件」において、確かに写真を撮影したのが立松懐清判事であったことは事実のようですが、なぜ取調官がそのようなことをしたのかということについては、諸説があります。
上に引用した Wikipedia の解説にも、「『大逆事件を告発した司法官』としての出世を望む立松」という表現が出てきて、とにかく立松懐清が取り調べを都合よく進めるために二人をつけ上がらせてしまったという見方がある一方、本田靖晴著『不当逮捕』(講談社文庫)では、かの立松房子女史にも取材し、「立松懐清が二人の境遇に真に同情して、死刑になる二人へのはなむけとして写真を撮ってやった」という話が紹介されています。朴烈は死刑を覚悟していましたから、朝鮮に住む家族に自分の最後の姿を届けようと、写真を受刑者の仲間に托したところ、それが巡りめぐってあの北一輝の手元に渡り、体制攻撃の道具として使われてしまうことになるのです。
 |
不当逮捕 (講談社文庫) 本田 靖春 (著) 講談社 1986-09 Amazonで詳しく見る |
この『不当逮捕』という本は、立松懐清・房子夫妻の次男である立松和博・元読売新聞記者の不当逮捕を描いたノンフィクションなのですが、同じように政争の犠牲になったと言える父・立松懐清の巻き込まれた事件にも触れているのです。
この本の中でも、立松懐清・房子夫妻が、金子文子の獄中自殺を知った時のいきさつが、とりわけ印象的です。
大正十五年七月二十二日の午前二時ごろ、房子は人の訪う気配にふと目覚めた。暗闇の中でじっと耳をすましていると、隣で眠っているはずの懐清が声を掛けてよこした。
「おい、だれか来たようだよ」
「ええ、それで私もいまさっきから目が覚めていたの」
「じゃあ、おれの空耳じゃなかったんだ」
「あなたちょっと表を見て来て下さらない?」
見回って戻った懐清が「だれもいない」といい、二人はまた眠りに落ちた。
翌朝、懐清は宇都宮刑務所栃木支所の西茂からの電話を受けた。彼は懐清の父方のいとこにあたる。支所では所長に次ぐ地位にいた。
「金子文子が死んだぞ」
「えっ、いつ?」
「時刻はまだはっきりしないが、朝の見回りで発見された」
「自殺だろうか」
「首を吊っていた」
懐清は房子にすぐ身仕度をさせ、一緒に車で現地に向かった。
「でも不思議なことがあるものですわね。死ぬ前にお別れに来たのかしら」
車中で未明の出来事を口にする房子に、懐清は答えなかった。文子に向かっての「説教」が実を結ばずにこの日の結末を迎えてしまったのが、ひどくこたえているようであった。
房子は西茂に特別の許しを得て、文子が縊死した独房を清掃し、途中で買った花束を一隅に供えて、用意の線香を手向けた。それから、西茂が栃木支所に勤務するあいだ、毎月二十二日の命日がくると、房子は文子の供養に足を運んだ。このことはこれまで世間にまったく知られていない。
ソプラノ歌手として当時の日本の第一人者だった立松房子女史が、大逆罪の囚人の独房を清掃し、また供養のために栃木まで毎月訪れていたというのは、まったく驚くべきことです。立松懐清判事が、自分の出世のために大逆事件を利用しようとしたというのは間違いだったのではないか、実際は被疑者に本当に同情していたのではないかということを、感じさせるエピソードです。
一方、ソプラノ歌手・立松房子は、「怪写真事件」の渦中の1926年(大正15年)秋にも、新潟で独唱会を開く予定がありました。新潟市は佐渡出身の北一輝の地元に近いということで、混乱を恐れる当局は、彼女に中止を勧告しましたが、「自分は世間から後ろ指をさされるようなことは何もしていない」と言う立松房子は、独唱会を敢行しました。当日は、制服の警官がステージの周囲を固めるという物々しい様子で、それがまた新聞記事をにぎわしたということです。
こちらのブログには、「天下の視聴を聚めた立松氏夫妻」と題した『歴史写真』(大正15年12月号)の写真が掲載されています。「ヨーロッパ系の血を引いているかと見紛うほどに整った目鼻立ち」(『不当逮捕』より)と言われた立松房子女史の写真は、ネット上で探してもここぐらいでしか見られませんでした。
花巻で立松房子の独唱会が開かれたのが、関登久也氏の記憶どおり昭和2年(1927年)ならばこの翌年ですから、話題になるのも当然だったでしょう。そして賢治も、「夫を支える」そのけなげな活動に、花束を贈ろうという気持ちになったのかもしれません。
その後の立松房子女史は、90歳代になってもまだ弟子たちに声楽のレッスンを行っていたとのことで、1992年、101歳の年に大往生を遂げられています。
一方の歌手マリブランは、ニューヨークで夫を支えていたのは1年にしかすぎず、その後ヨーロッパに戻ってベルギー人のヴァイオリニストとの間に一子をもうけ、このカップルのためにメンデルスゾーンもヴァイオリンの入ったソプラノのためのアリアを作曲しているということです。
ただ、マリブランは立松房子とは対照的に、28歳の若さで伝説のうちに生涯を終えてしまいます。
停車場の方で、鋭い笛がピーと鳴り、もずはみな、一ぺんに飛び立って、気違ひになったばらばらの楽譜のやうに、やかましく鳴きながら、東の方へ飛んで行く。
「先生。私をつれて行って下さい。どうか私を教へてください。」
うつくしくけだかいマリヴロンはかすかにわらったやうにも見えた。また当惑してかしらをふったやうにも見えた。
そしてあたりはくらくなり空だけ銀の光を増せば、あんまり、もずがやかましいので、しまひのひばりも仕方なく、もいちど空へのぼって行って、少うしばかり調子はづれの歌をうたった。(「マリヴロンと少女」末尾)
本倉雅子