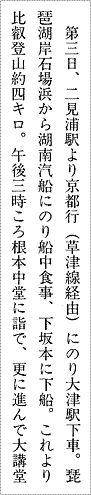 1921年(大正10年)に賢治が家出上京していた間の4月上旬、父政次郎氏は賢治を誘って、二人で伊勢~比叡山~奈良をめぐる関西旅行を行いました。右のテクストは、『【新】校本全集』年譜篇p.222に記載されている、その「第三日」の初めの部分をコピーしたものです。
1921年(大正10年)に賢治が家出上京していた間の4月上旬、父政次郎氏は賢治を誘って、二人で伊勢~比叡山~奈良をめぐる関西旅行を行いました。右のテクストは、『【新】校本全集』年譜篇p.222に記載されている、その「第三日」の初めの部分をコピーしたものです。
ここに書かれている旅行中の事実経過は、政次郎氏が後年、おそらく賢治の没後に語った内容にもとづいているのだと思いますが、本日検討してみたいのは、この中の「大津駅下車。琵琶湖岸石場浜から湖南汽船にのり・・・」という部分です。
当時の賢治父子の足どりをたどってみようと調べているうちに、この時期の「湖南汽船」が、大津の「石場」の港に発着していたのかどうか、不確かな感じがしてきたのです。
歴史的にみると、石場港は、琵琶湖の舟運において重要な役割を果たしてきた港でした。
「急がば回れ」という諺がありますが、その由来は、
もののふの矢橋の船は速けれど
急がば回れ瀬田の長橋
という、室町時代の連歌師・柴屋軒宗長の歌から来ているのだそうです(「語源由来辞典」参照)。
東海道を旅する際には、大津宿石場港から草津の矢橋を結ぶ「矢橋の渡し」を利用する方が距離的に近く、たいていの場合は速いのだけれど、舟というものは天候に左右されて危ないので、大きく南を回って「瀬田の長橋(=瀬田の唐橋)」を渡る方が安全確実である、ということを、この歌は意味しているのだそうです。
また、「近江八景」の一つである「矢橋の帰帆」も、この石場港と矢橋港を往き交う帆舟を、比叡山と夕空を背景に眺めたものでした。
ということで、江戸時代から明治初期までは、大津のメイン・ポートとして栄えた石場港だったのですが、どうも明治後期以降は、次第に他の港にその座を譲って、衰退していったようです。
私が最初に「石場浜から湖南汽船にのり・・・」という記述に疑問を持ったのは、明治末期の大津市の様子を示す、下の図を見た時でした。
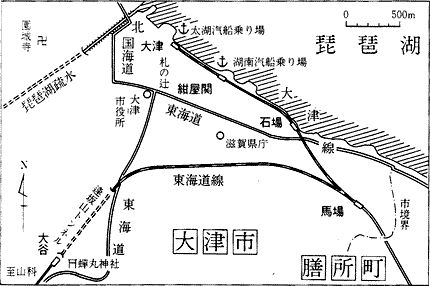
(『琵琶湖汽船100年史』より)
そもそもこの図は、明治末期までの国鉄大津駅は東海道本線の上にはなくて、スイッチバックの支線上の駅だったことを示すものですが、大津駅の湖岸には、「太湖汽船乗り場」があって、紺屋関駅の湖岸には、「湖南汽船乗り場」があるのに、石場駅の湖岸には、何もないのです。
同じような状況は、古い資料においても確認できます。下の図は、1895年(明治28年)に京都で「第4回内国勧業博覧会」が開かれた際に、滋賀県にも観光客を誘致しようと作られた「近江案内略記」という観光地図の一部です。
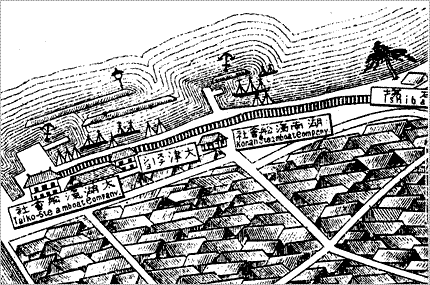
(『新修大津市史 第五巻』より)
ちょっと見にくいですが、ここでも、「大津ステーション」の左方には「太湖汽船會社」があって、湖岸には船の絵と錨の印があり、右方には「湖南汽船會社」があって、やはり湖岸には船の絵と錨の印があるのに、右端の「石場」の湖岸には、大きな木が一本描かれているだけです。
すでに明治時代後半の石場浜は、港としての機能はあまり果たしていなかったのではないかと、心配になってきます。
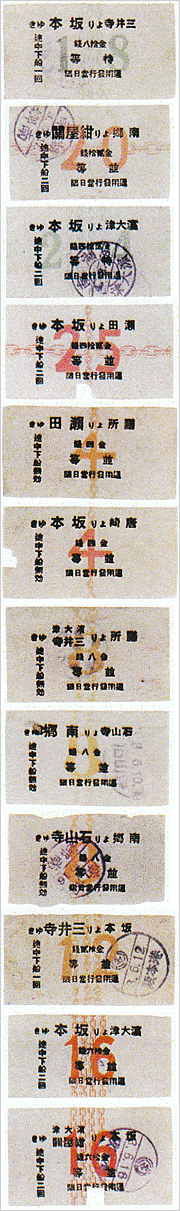 ところで、賢治たち父子が大津から坂本まで乗船した、湖南汽船の定期航路運航が始まったのは、1894年(明治27年)のことでした。以下に、『新修大津市史』の記述を引用します。
ところで、賢治たち父子が大津から坂本まで乗船した、湖南汽船の定期航路運航が始まったのは、1894年(明治27年)のことでした。以下に、『新修大津市史』の記述を引用します。
翌明治二十七年、湖南汽船は湖南の探勝を目的に、大津―石山、大津―坂本間の定期航路運航をもって、湖上遊覧船営業に乗り出したのである。湖南汽船の定期航路の開始は、琵琶湖遊覧汽船の始まりにあたるが、遊覧船の営業は、営業収益の下降的傾向にあった湖南汽船の歯止めとなり、以後順調な営業の発展をみていったのである。一方、太湖汽船も湖南汽船と相前後して遊覧船航路を開拓し、明治二十八年以降は収入・利益とも明治二十二年以前の状態に復すことができた。(中略)
遊覧汽船客誘致が成功してか、湖南汽船は明治三十六年以降収入・利益とも順調な発展をみた。なかでも第一次大戦後の好景気は湖上遊覧時代を出現させ、大正九年(1920)には京阪電気鉄道株式会社と提携して船車連帯運輸による「八景めぐり」を開始し、同十五年には同社の融資も得て遊覧船明治丸・大正丸・平安丸の鋼鉄船を建造し、さらに同年には南郷遊覧をさらに発展させるため、宇治川ラインの遊覧船就航を計画、モーターボート夕照号、秋月号の進水をみたのである。(強調は引用者)
琵琶湖の水上運送は、湖岸に東海道線が全通するなど陸上交通の発達によって、明治中頃に一時的な打撃を受けますが、ここで単なる貨客運送から遊覧・観光に重点を移すことによって、また勢いを盛り返していったというわけです。
賢治父子が琵琶湖で汽船に乗った1921年(大正10年)とは、まさに上述の「湖上遊覧時代」にあたり、2人が汽船の上で食事をとったのも、そんな時代の観光旅行の一コマだったわけですね。
それから、右の方にずらっと並べた写真は、『琵琶湖汽船100年史』という本に掲載されていた、「湖南汽船会社」の、「湖南航路」の切符です。
これらは、昭和初期のものということで、賢治たちの旅行の時のものと同一とは限りませんが、切符に記載されている港を、北から順に並べてみると、下のようになります。
- 坂本
- 唐崎
- 三井寺
- 浜大津
- 紺屋関
- 膳所
- 瀬田
- 石山寺
- 南郷
琵琶湖南部の観光地が並んでいますね。もちろん、これらの切符がすべての区間を網羅しているとはかぎりませんから、ここに「石場」が出ていないからといって、これも、湖南航路の寄港地に「石場」が含まれていなかったという証拠になるわけではありません。
しかし、上の二つの図や、この12枚の切符から浮かび上がる状況を合わせると、明治後期以降には「石場」という港があまり使われていなかったのではないか、そして湖南航路の停泊港になっていなかったのではないか、という危惧を生じさせます。
それでは、もしも賢治父子が乗船したのが「石場港」ではなかったとしたら、それはどこだったのでしょうか。
それを考えるためには、当時の「大津駅」の場所を再確認する必要があります。
最初に掲げた図においては、明治末の「大津駅」は、琵琶湖岸(現在の京阪浜大津駅の場所)にありました。しかし、賢治父子が旅行した1921年(大正10年)には、またこの時と状況が変わっていたのです。
1913年(大正2年)に、大津電車軌道(現在の京阪電車石山坂本線の前身)が旅客営業を開始すると、上の図で「大津線」と書かれている支線は旅客営業を廃止して貨物線にされてしまい、上記の「馬場駅」が、新たに「大津駅」と改称されたのです。
つまり、1921年に賢治父子が下車した「大津駅」は、上の図の「馬場駅」(現在のJR膳所駅)だったわけです。
となると、上にまとめた「湖南航路」の停泊港のうちで、その「大津駅」から最も近いのは、「膳所港」ということになります。その場所は現在の近江大橋の西のたもとのあたりで、当時の大津駅からは、道のりにして1.3kmほどになります。
次に近い港は、湖南汽船本社の傍で、湖南航路の中心でもある「紺屋関港」です。ここは、当時の大津駅から1.8kmの距離です。
どちらの港だったかは断定できませんが、距離的に近いこと、また政次郎氏が「石場浜」と勘違いした要因として、当時の大津の繁華街からは少し南東にはずれた港だったという意識があったかもしれないことから、「膳所港」だったのかもしれないと、私は思います。
1921年当時における、湖南航路の停泊港をはっきりと示してくれる資料があれば、事情は明確になったはずなのですが、そのような資料が見つけられなかったので、今回は間接的な資料による「推測」にとどまりました。
ところで、本題からは少しそれますが、冒頭に引用した図が示していたように、ある時期までの国鉄大津駅は、現在の位置ではなくて、今は京阪電車の浜大津駅がある場所にあり、馬場駅からスイッチバックで入るようになっていました。これは、(旧)逢坂山トンネルの滋賀県側出口はかなり高い位置にあって、湖岸の高さにある大津駅から直接列車が向かうことができなかったためだったということですが、さらに前述のように大正初期に、「大津駅」の名称はそれまでの「馬場駅」に移動させられて(=2代目「大津駅」)、表面上は、スイッチバックなどという非効率なことをしなくてよくなります。
しかし一方、当時の東海道線は、京都側においても、トンネル工事の事情でいったん「稲荷」(現在は奈良線)の駅まで南下してから、滋賀県側に抜けるというまわり道をしていました。こちらの非効率を改善するために、京都駅から真っ直ぐ東に抜けるルートで「新逢坂山トンネル」が掘削され、滋賀県側の東海道線のルートはそれまでより北側を走るように変更されて、大津駅もまたまた滋賀県庁の南西に移動し(3代目「大津駅」)、新たな東海道線が営業を開始したのが、1921年(大正10年)8月1日のことでした。そしてそれまでの大津駅(2代目)は「馬場駅」に名称が戻されるとともに、旅客営業はいったん廃止されます。
すなわち、賢治たち父子が訪れた1921年4月、大津駅(2代目)と旧東海道線は、くしくも廃止寸前の時期にあたっていたというわけなのです。
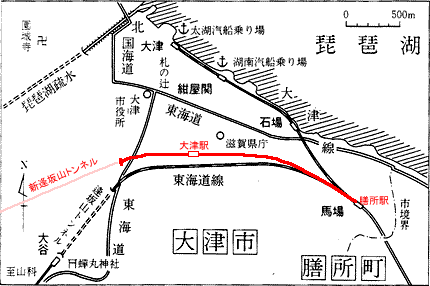
赤色は現在の東海道線
コメント