下写真は、賢治の「「文語詩篇」ノート」から、1913年1月の頁です。
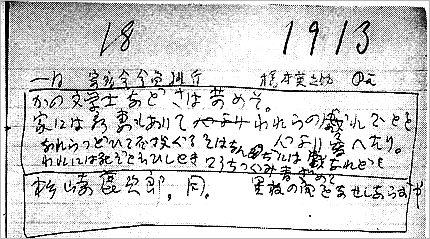
「18」は賢治の数えの年齢で、年号「1913」の下には、次のように書かれています。
一月 寄宿舎舎監排斥 橋本英之助 Pã
かの文学士などさは苛めそ。
家には新妻もありて心よりわれらの戯れごとを
心より憂へたり。
なれらつどひて石投ぐる そはなんぢには戯なれども
われには死ぞと云ひしとき 口うちつぐみ青ざめて
異様の面をなせしならずや。杉崎鹿次郎。 同。
これは、賢治が盛岡中学4年の1月、生徒たちが寄宿舎舎監の排斥運動を起こし、学校側はその処分として、4年・5年の寄宿生全員に退寮を命じたという事件に触れたものです。これによって賢治も処分を受け、以後は清養院という曹洞宗のお寺に下宿することになりました。
この舎監排斥運動においては、賢治もかなりの役割は果たしていたようで、詳細は不明のようですが、『【新】校本全集』年譜篇も、「指揮をとった黒幕参謀は賢治」という説を紹介しています。
その関わりの程度はともかく、賢治にとってこの事件の記憶がどのようなものであったかは、後年に書いたこの「「文語詩篇」ノート」の記載から、うかがい知ることができます。
すなわち、生徒から何らかの排斥的な仕打ちを受けた舎監の一人は、生徒たちの「戯れごと」を「心より憂へ」て、「なれらつどひて石投ぐる そはなんぢには戯なれどもわれには死ぞ」と言ったというのです。これは教師と生徒との関係とも思えないほど切実な言葉ですが、その時「口うちつぐみ青ざめて異様の面」をなしたのは、賢治自身だったのでしょうか。
「年譜篇」にも、この「文学士の言葉は賢治の胸を衝いたようである」と付記されています。
ところで、私は昨日たまたま賢治とは関係ない本を読んでいた時、この「なれらつどひて石投ぐる そはなんぢには戯なれどもわれには死ぞ」という言葉は、もとはあるイソップの寓話に由来していることを知りました。
それは「少年たちと蛙」という題名の寓話で、Charles Stikeney による英語版では、‘The Boys and the Frogs’として、こちらで読むことができます。日本語への抄訳は、こちらのページに「52.少年たちと蛙たち」として収められています(いずれも、「イソップ」の世界 The World of Aesop より)。
Charles Stikeney 版からちょっと訳してみると、下のような感じです。
少年たちと蛙
池のそばで遊んでいた少年たちが、水中にたくさんの蛙が泳いでいるのを見つけました。
一人の子が、「蛙に石を当てられるか、やってみよう」と言い、みんなで石を投げはじめました。
何匹かの蛙に石が当たって、とうとう一匹の蛙が水から頭を出して言いました。「みんな、どうかやめて下さい。私たちに石を投げるのは、あなたたちにしたらたいそう面白いことかもしれませんが、私たちにとっては、死なのです。私たちは、あなたたちに何も悪いことはしていないのに、ああ、あなたたちは私たちの家族を、もう三匹も殺しました。」
盛岡中学の悪童たちの被害にあった舎監は、このイソップの寓話の一節を引用して、生徒たちに自覚を促そうとしたのでしょう。そしてそれは、少なくとも賢治の心には、とても痛切に響いたのだと思います。
ところで、このように訴えて賢治に印象を与えた「文学士」とは、いったい誰だったのだろうか、ということが気になります。
『【新】校本全集』の「補遺・伝記資料篇」に収められている「岩手県立盛岡中学校学校行事」と、「年譜篇」をもとにリストアップすると、この当時に寄宿舎の「舎監」をしていた教師は、千田宮治(国語・漢文)、服部品吉(国語・漢文)、杉崎鹿次郎(英語)、矢口恵之助(博物)、そして「舎監補助」に、津田清三(英語)の5人が、少なくともいたようです(括弧内は担当科目)。
「文学士」ということで、「博物」担当教諭の矢口恵之助氏をまず除外すると、あとは「国語・漢文」と「英語」の教官が残りますが、上のようにイソップの寓話を引用しているところからは、「国語・漢文」ではなくて、「英語」の先生なのではないかという気がします。この寓話は、数あるイソップのお話の中では、さほど有名なものではなく、しかし英語の教材としてならば、当時の教師と生徒の間で共有されていた可能性があると思われるからです。
「英語」担当だとすると、候補は杉崎鹿次郎・津田清三の2人に絞られて、杉崎鹿次郎教諭は、ノートの下段で「杉崎鹿次郎。同。」として登場することからすれば、上段の「かの文学士」とは、津田清三教諭のことだったのではないかと、とりあえず私は推測してみます。
津田清三教諭は、舎監ではなく「舎監補助」ですが、生徒はそんな肩書など区別せずに悪戯を働いたでしょうし、津田氏はこの前年の1912年10月3日に盛岡中学に着任したばかりで、さらに12月21日に舎監補助に任命されたという「新入り」でしたから、生徒たちの格好の標的にされた可能性はあります。また「家には新妻もありて」というところも、この文学士が若かったことを推測させます。
ところで下の写真は、1913年頃に寮の仲間たちとともに撮った写真で、賢治は後列の左から二人目です。これは、中央の人物が「寮旗」を持っていること、皆が胸に花を飾っていることから、退寮処分を受けた面々が、寮との別れに際して撮った「記念写真」かと推測されている一枚です。
まあ、「青春の一コマ」ですね。

さて、「かの文学士」の詮索には限界もあるのでこの辺でやめておきますが、それよりも私がここでぜひとも注目しておきたいのは、「男の子が(残酷さの自覚なしに)蛙を石で傷つける」という、イソップ寓話のモチーフです。
これは、賢治が妹トシの死後、おそらくサハリン旅行から帰って作成・配布した「〔手紙 四〕」という文章に、まさにつながっています。
幼い妹ポーセを十一月に病気で亡くした少年チユンセは嘆き悲しみ、翌春には学校もやめて、働いていました。
チユンセはキヤベヂの床をつくつてゐました。そしたら土の中から一ぴきのうすい緑いろの小さな蛙が、よろよろと這つて出て来ました。
「かへるなんざ、潰れちまへ。」 チユンセは大きな稜石でいきなりそれを叩きました。
それからひるすぎ、枯れ草の中でチユンセがとろとろやすんでゐましたら、いつかチユンセはぼおつと黄いろな野原のやうなところを歩いて行くやうにおもひました。すると向ふにポーセがしもやけのある小さな手で眼をこすりながら立つてゐてぼんやりチユンセに云ひました。
「兄さんなぜあたいの青いおべべ裂いたの。」 チユンセはびつくりしてはね起きて、一生けん命そこらをさがしたり考へたりしてみましたがなんにもわからないのです。・・・
もちろん、「〔手紙 四〕」の中心的テーマは、妹トシの死でした。しかし、その話の中にことさら、無邪気な残酷さをもって「蛙を石で叩く」というエピソードが登場する背景には、寓話「少年たちと蛙」の記憶が、賢治にあったからなのではないかと、私には思えるのです。
「なれらつどひて石投ぐる そはなんぢには戯なれどもわれには死ぞ」という言葉とともに、賢治の胸中には昔の舎監排斥事件をめぐって、心に刺さったトゲのような罪責感が残っていたのではないでしょうか。そしてそれがここの箇所で、トシを救ってやれなかった悔恨に混ぜ入れられているような、そんな感じが私はします。
コメント