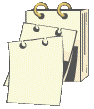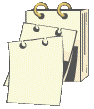賢治 日めくり ~7月1日~
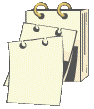
- 1912年7月1日(日)(賢治15歳)、博物の山県頼咸教諭が盛岡中学校を退職して、南満州工業専門学校に赴任することになり、後任の舎監は服部品吉教諭になった。山県頼咸教諭は生徒から「ライカン」と呼ばれて親しまれ、賢治が入学した時から寄宿舎の舎監長でもあった。
- 1917年7月1日(日)(賢治20歳)、盛岡高等農林学校学生による文芸同人雑誌「アザリア」一号が発刊された。和紙袋綴じ、48頁、ガリ版刷りで、同人各々が手綴じして、各自が一冊ずつ所持した。同人の中心になったのは、3年の賢治のほか、3年の小菅健吉、2年の保阪嘉内、河本義行で、これ以外にも3名が作品を寄稿している。
一号の巻頭に、「初夏の思ひ出に」と題して小菅健吉は次のような文章を寄せているが、アザリア会発足の意気込みとはこのようなものであったのだろう。
「…感受的詩人が限りなき涙を流すは、げにや此の晩春より初夏への移り目、はりつめたる琴線の見えざる刺戟にも尚ほ美妙なる音を発する時にあらずや、
吾がアザリア会はかゝる詩人(敢て吾曹一派を詩人と名つけん)多忙の初夏、乱れ易く傷みやすき心を育み、現在に対する不平を軽からしめ、自由てふ心を積極的に向上せしめしむべく年来各自の心に、はりつめたる琴線相触れて、こゝに第一歩を踏み出しぬ。…」
この号に賢治は、連作短歌「みふゆのひのき」12首、「ちゃんがちゃがうまこ」8首、短篇「「旅人のはなし」から」を発表した。ちなみに、当時の賢治の下宿跡には、「ちゃんがちゃがうまこ歌碑」が建っている。
- 1918年7月1日(月)(賢治21歳)、この日盛岡高等農林学校で関豊太郎教授に会い、前日に肋膜かと思って岩手病院を受診して薬をもらったこと、はっきりするまで学校を二三日休みたいということを話したところ、「それならば鈴木医学士に見て貰へ」と勧められ、さっそく医師宅を訪ねて診察を受けた。
その結果は、「只今は決して悪しと云ふことなきも殊によれば罹るやも知れず薬は矢張用ふる様、且つ山へ行く前には必らず見て貰ふ様、然らざるも毎週一回位は来る様にとの事にて只今の分析は差支なし」ということだった。
この経緯を手紙で父に知らせ、「今年一年は専心に分析と山の調査のみに従事し別段に身体を痛めざる様勉強は控へ申すべく候」と書いた(書簡77)。
「【新】校本全集」の年譜をはじめ多くの賢治の伝記では、この時をもって、宿痾となった結核の徴候が初めて賢治に現れたとしている。しかし、上記の賢治の書簡を見るかぎりでは、医師も賢治も「肋膜」(結核性胸膜炎)であったとは、言っていない。
医師は、「只今は決して悪しと云ふことなきも殊によれば罹るやもしれず…」と言っており、「(肋膜に)罹る」のは今後の一つの可能性としているわけであるから、この時点ではまだ罹患していないと診断したことになる。また、賢治自身も、「何分この様の事に一一神経を病みては却て病気を起す事とも存じ候間…」と書いており、やはり「病気を起す」のは未来の可能性と考えている。さらに、この時点で病んでいるのは「神経」であると、自分でも感じているのである。
すなわち、賢治の書簡から判断するかぎりでは、医師も賢治も、この時の症状を肋膜とは考えていなかったのである。
賢治はしばらく前から、研究生としての実験補助に嫌気がさし、学校をやめたいと父に申し出たものの、「忍耐力がない」と叱られて、意気消沈していた。そんな時に同宿の従弟が肋膜と診断されたので、「胃の近くが痛い」というだけの自覚症状でも、神経質になってしまったのではないかと思われる。
結果的には、これが契機となって父も賢治が学校をやめることを承認したわけで、賢治としてみれば当初の希望がかなったわけである。
ちなみに、結核性胸膜炎とは、結核の初感染による肺門リンパ節の炎症が肺葉間の胸膜に波及した場合に起こる炎症で、ほとんどは結核の初感染から数ヵ月以内に見られる。典型的な症状は、乾性咳、胸痛、38~39℃の発熱であり、この頃の賢治の様子とは明らかに異なっている。しかし、一部には、自覚症状を伴わないか日常生活に支障ない程度で治癒してしまう場合もあると言われているため、この時の賢治の病気が結核性胸膜炎だったか否かということを、症状のみから判断することはできない。
- 1926年7月1日(木)(賢治29歳)、本日付発行の詩誌「貌」7月号に、「春」が掲載された。この号の「編輯後記」で森佐一は、「吾々の運動は単に詩のみではない。勝れた童話作家としてタルホイナガキや佐藤春夫やと比肩しうる宮沢賢治氏を持つてゐる。」と賢治に触れている。
- 1927年7月1日(金)(賢治30歳)、「一〇七九 僚友」(「春と修羅 第三集」)を、スケッチした。
- 1928年7月1日(日)(賢治30歳)、本日付で発行された「天邪鬼」五の巻に掲載された「雨窓夜話」において、民俗学者の佐々木喜善が、賢治が雑誌「月曜」に発表した「ざしき童子のはなし」に言及した。
- 1931年7月1日(水)(賢治34歳)、この日と翌日、盛岡市内の米穀店をまわり、石灰搗粉の宣伝をして需要の調査を行った。またおそらく、この日、「北海道拓殖博覧会」に出展するための見本品を持って県庁を訪れ、県から北海道に送ってもらうよう託した。
県庁を出てから22軒の米穀商・精米場をめぐり、石灰搗粉の宣伝に努めたが成果はなく、疲れはてて仙北町の駅前の広場にたどり着き、水を飲もうとした。そこにいた青年がポンプの蛇管をとって勧めてくれたが、賢治が飲もうとした時に、それまで勢いよく出ていた水が、急に止まってしまった。この時、青年が心から慰めてくれたので、賢治の疲れは癒えて全身が洗われるような心地がしたという。
この日の状況は、「孔雀印手帳」に、「〔朝は北海道の拓植博覧会へ送るとて〕」(「補遺詩篇 II」)としてスケッチされている。
またこの日付で発行された詩誌「詩神」7月号に、草野心平が「宮沢賢治論」を発表した。また同号の「この人この本」アンケート「求めたい絶版本」「どんな本をどんな人は是非出して貰ひたい」に答えて、小森盛、石川善助が、賢治の名前と作品を挙げた。
- 1933年7月1日(土)(賢治36歳)、本日付で発行の詩誌「詩人時代」に、「葱嶺先生の散歩」が掲載された。
また、同号の「岩手詩鉱脈の光芒とその出発」の中で及川儀三が賢治に触れ、「御大宮沢賢治病躯をおして再びペンをとり始めた」と書いた。